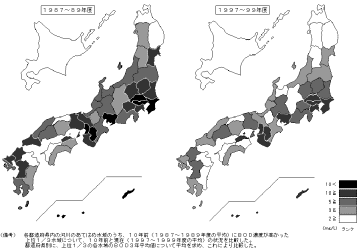- 参考資料一覧
- (参考1) 健康項目の達成状況
(参考2-1) 生活環境項目(BOD又はCOD)の達成率の推移
(参考2-2) 三海域の環境基準(COD)達成率の推移
(参考3) 指定湖沼の水質状況(COD年間平均値)
(参考4) 都道府県別の汚濁度の高い河川の10年間におおける水質変化(BOD)
(参考5) BOD/COD上位水域(ベスト5)
(参考6) BOD/COD高濃度水域(ワースト5)
(参考7) トリハロメタン生成能濃度(年間平均値)分布状況(地点数)
(参考1)健康項目の達成状況
| 測定項目 | 調査対象地点数 | 環境基準値を超える地点数 |
|---|---|---|
| カドミウム | 4,877 | 0( 0 ) |
| 全シアン | 4,308 | 0( 1 ) |
| 鉛 | 4,964 | 7( 7 ) |
| 六価クロム | 4,478 | 0( 0 ) |
| 砒素 | 4,883 | 22(18) |
| 総水銀 | 4,731 | 0( 0 ) |
| アルキル水銀 | 1,791 | 0( 0 ) |
| PCB | 2,464 | 0( 0 ) |
| ジクロロメタン | 3,770 | 3( 1 ) |
| 四塩化炭素 | 3,801 | 0( 0 ) |
| 1,2-ジクロロエタン | 3,754 | 1( 1 ) |
| 1,1-ジクロロエチレン | 3,742 | 0( 0 ) |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 3,742 | 0( 0 ) |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3,837 | 0( 0 ) |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 3,743 | 0( 0 ) |
| トリクロロエチレン | 3,954 | 0( 1 ) |
| テトラクロロエチレン | 3,949 | 0( 1 ) |
| 1,3-ジクロロプロペン | 3,804 | 0( 0 ) |
| チウラム | 3,718 | 0( 0 ) |
| シマジン | 3,734 | 0( 0 ) |
| チオベンカルブ | 3,730 | 0( 0 ) |
| ベンゼン | 3,713 | 0( 1 ) |
| セレン | 3,646 | 0( 0 ) |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 3,003 | 4(-) |
| ふっ素 | 2,259 | 11(-) |
| ほう素 | 1,861 | 1(-) |
| 合計(実地点数) | 5,889 | 47 |
| (うち新規3項目以外) | 5,458 (5,409) | 31(27) |
| 環境基準達成率(新規3項目を含む) | 99.2% | |
| 環境基準達成率(新規3項目を除く) | 99.4% | (99.5%) |
- 注1: ( )は平成10年度の数値
- 注2: 新規3項目とは硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素を指す。
- 注3: ふっ素及びほう素の測定地点数には、海域の測定地点のほか、河川又は湖沼の測定地点のうち海水の影響により環境基準を超えた地点は含まれていない。
- 注4: 合計欄の超過地点数は実数であり、同一地点において複数項目の環境基準を超えた場合には超過地点数を1として集計した。なお平成11年度は2地点において2項目が環境基準を超えている。
(参考2-1)生活環境項目(BOD又はCOD)の達成率の推移
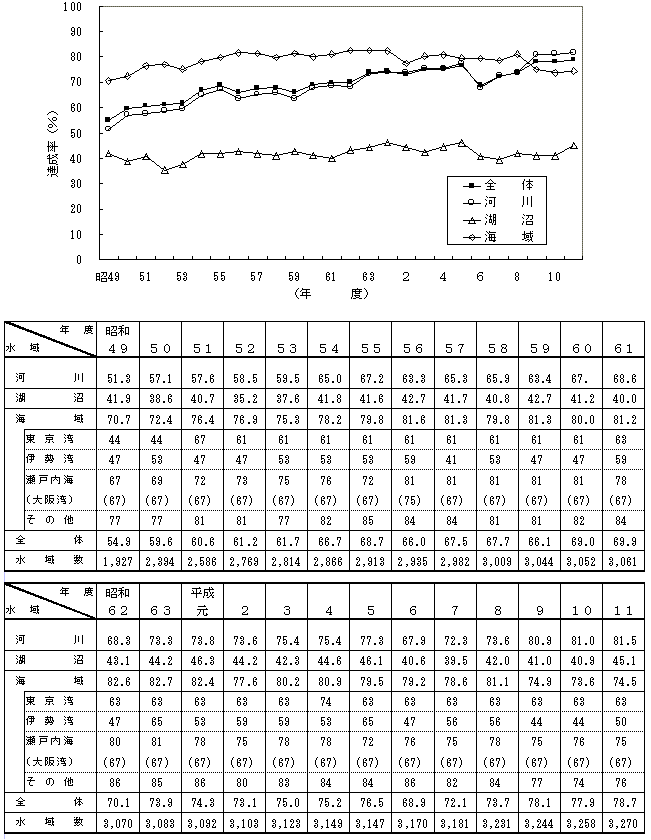
- (備考)
- 河川はBOD、湖沼及び海域はCOD
- 達成率(%)=(達成水域数/あてはめ水域数)×100
(参考2-2)三海域の環境基準(COD)達成率の推移
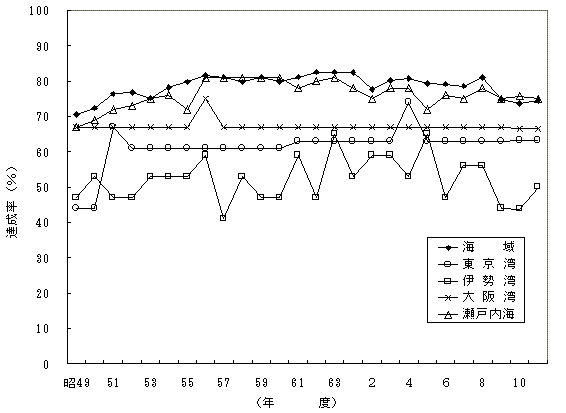
- (参考)総量規制制度について
- 昭和53年の水質汚濁防止法等の改正により、広域的な閉鎖性海域について、当該水域への汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制を制度化した。
総量規制制度は、排水の濃度規制では環境基準を維持達成することが困難な海域(指定水域)を対象としており、現在、CODを削減対象として東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を指定している。
総量規制の仕組みは、内閣総理大臣が総量削減基本方針で指定水域ごとに汚濁負荷量の削減目標量、目標年度等を定め、これに基づき都道府県知事が総量削減計画でその都道府県内の発生源別の削減目標量及びその達成の方途等の事項を定める。その計画に基づき、下水道の整備等各種生活排水処理施設の整備、工場・事業場に対する総量規制基準による規制、教育・啓発等の所要の対策を実施することとしている。
平成11年度を目標年度とする第4次総量規制の実施によって、CODの汚濁負荷量は平成6年度の概ね95%(東京湾92%、伊勢湾93%、瀬戸内海96%)程度に削減がなされる見通しとなっている。
(参考3)指定湖沼の水質状況(COD年間平均値)
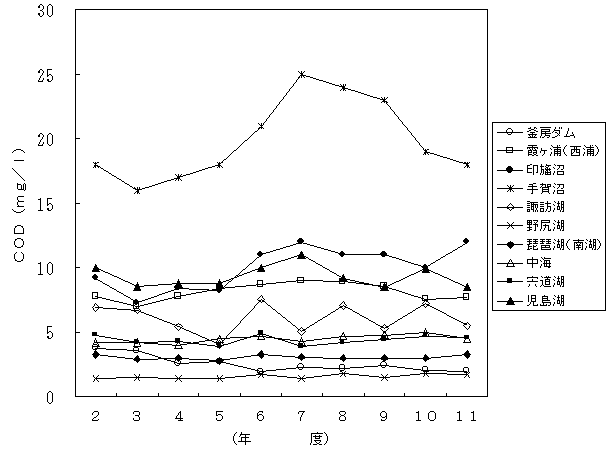
- (参考)指定湖沼について
- 湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川や海域に比べて環境基準の達成率が低い。また、富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。このような湖沼の水質汚濁の原因は、湖沼の集水域で営まれる諸産業の事業活動から、人々の日常生活に至るまで多岐にわたっている。湖沼水質保全のためには、従来からの水質汚濁防止法による規制だけでは十分でないこと等にかんがみ、昭和59年に湖沼水質保全特別措置法が制定され、昭和60年3月から施行されている。
同法に基づき、環境基準が達成されていない又は達成されないこととなるおそれが著しい湖沼であって、利水状況、汚濁の推移等から水質保全施策を総合的に講ずる必要があると認められる湖沼について、指定湖沼として指定することができるとされている。
これまでに、琵琶湖、霞ヶ浦等の10湖沼が指定湖沼として指定され、湖沼水質保全計画に基づく各種施策が実施されている。湖沼水質保全計画の内容は、[1]水質の保全に関する方針、[2]下水道の整備等水質の保全に資する事業、[3]工場排水、生活排水等各種汚濁源に対する規制その他の措置、[4]その他水質保全のために必要な措置等である。
(参考4)都道府県別の汚濁度の高い河川の10年間におおける水質変化(BOD)
(参考5)BOD/COD上位水域(ベスト5)
(1)河川(BOD、mg/l)
| 順位 | あてはめ水域名 | 都道府県名 | 年間平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小糸魚川(こいといがわ) | 北海道 | <0.5 |
| 〃 | 小荒川(こあらかわ)上流 | 青森県 | <0.5 |
| 3 | 別々川(べつべつがわ) | 北海道 | 0.5 |
| 〃 | 斜里川(しゃりがわ)上流 | 北海道 | 0.5 |
| 〃 | 覚生川(おぼっぷがわ) | 北海道 | 0.5 |
| 順位 | あてはめ水域名 | 都道府県名 | 年間平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樽前川(たるまえがわ) | 北海道 | 0.5 |
| 〃 | 白老川(しらおいがわ)下流 | 北海道 | 0.5 |
| 〃 | 広尾川(ひろおがわ)中流 | 北海道 | 0.5 |
| 〃 | トムラウシ川(がわ) | 北海道 | 0.5 |
| 〃 | 錦多峰川(にしたっぷがわ)上流 | 北海道 | 0.5 |
(2)湖沼(COD、mg/l)
| 順位 | あてはめ水域名 | 都道府県名 | 年間平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 支笏湖(しこつこ) | 北海道 | 0.7 |
| 2 | 倶多楽湖(くったらこ) | 北海道 | 0.8 |
| 3 | 猪名湖(いなこ) | 長野県 | 1.4 |
| 〃 | 猿谷(さるたに)ダム湖 | 奈良県 | 1.4 |
| 5 | 然別湖(しかりべつ) | 北海道 | 1.9 |
| 順位 | あてはめ水域名 | 都道府県名 | 年間平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倶多楽湖(くったらこ) | 北海道 | 0.7 |
| 2 | 支笏湖(しこつこ) | 北海道 | 0.8 |
| 3 | 然別湖(しかりべつこ) | 北海道 | 1.8 |
| 4 | 奥只見貯水池(おくただみちょすいち) | 福島県 | 2.1 |
※生活環境項目(全窒素及び全燐を除く)に係る環境基準をすべて満足している水域のうち、BOD/CODの年間平均値が低い水域から順位を付した。
(参考6)BOD/COD高濃度水域(ワースト5)
(1)河川(BOD、mg/l)
| 順位 | あてはめ水域名 | 都道府県名 | 年間平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弁天川(べんてんがわ) | 香川県 | 22 |
| 2 | 樫井川(かしいがわ)下流 | 大阪府 | 20 |
| 3 | 谷八木川(たにやぎがわ) | 兵庫県 | 18 |
| 〃 | 大門川(だいもんがわ) | 和歌山県 | 18 |
| 5 | 南浅川(みなみあさかわ) | 東京都 | 17 |
| 〃 | 東除川(ひがしよけがわ) | 大阪府 | 17 |
| 〃 | 報得川(むくえがわ) | 沖縄県 | 17 |
| 順位 | あてはめ水域名 | 都道府県名 | 年間平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樫井川下流(かしいがわ) | 大阪府 | 32 |
| 2 | 弁天川(べんてんがわ) | 香川県 | 24 |
| 3 | 谷八木川(たにやぎがわ) | 兵庫県 | 18 |
| 4 | 鴨川(かもがわ) | 埼玉県 | 17 |
| 5 | 国分川(こくぶがわ) | 千葉県 | 16 |
(2)湖沼(COD、mg/l)
| 順位 | あてはめ水域名 | 都道府県名 | 年間平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手賀沼(てがぬま) | 千葉県 | 18 |
| 2 | 印旛沼(いんばぬま) | 千葉県 | 12 |
| 3 | 牛久沼(うしくぬま) | 茨城県 | 11 |
| 〃 | 佐鳴湖(さなるこ) | 静岡県 | 11 |
| 5 | 油ヶ淵(あぶらがぶち) | 愛知県 | 9.5 |
| 順位 | あてはめ水域名 | 都道府県名 | 年間平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手賀沼(てがぬま) | 千葉県 | 19 |
| 2 | 印旛沼(いんばぬま) | 千葉県 | 10 |
| 3 | 児島湖(こじまこ) | 岡山県 | 9.9 |
| 4 | 佐鳴湖(さなるこ) | 静岡県 | 9.7 |
| 5 | 油ヶ淵(あぶらがぶち) | 愛知県 | 8.7 |
※BOD/CODの年間平均値が高い水域から順位を付した。
(参考7)トリハロメタン生成能濃度(年間平均値)分布状況(地点数)
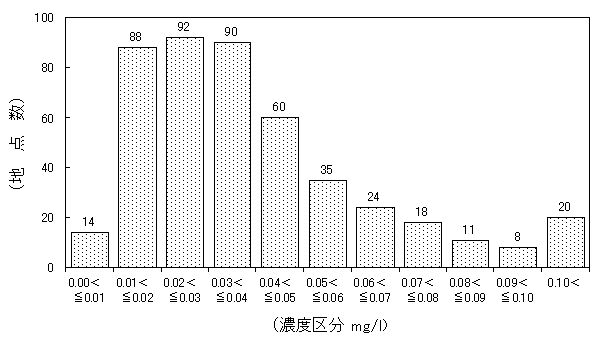
トリハロメタン生成能については、平成11年度は、全国460地点(河川420地点、湖沼40地点)で、1,999検体が測定された。
トリハロメタン生成能の分布状況をみると、0.01~0.06mg/lの範囲にある地点が全体の8割を占めている。
(注)トリハロメタン生成能については、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に基づき、特定水道利水障害を防止するため指定水域及び指定水域に指定された場合に、当該水域を水源とする浄水場の浄水処理方法、水温等を勘案して、当該水域の水質目標を定め、評価することとされているが、現在のところ指定がない。
トリハロメタンとは、メタン(CH4)の4つの水素原子のうち3個が塩素や臭素などのハロゲン原子で置き換わった化合物で発がん性物質である。具体的には、クロロホルム(CHCl3)、ブロモジクロロメタン(CHBrCl2)、ブロモホルム(CHBr3)、ジブロモクロロメタン(CHBr2Cl)の4物質が代表的な物質である。これらのトリハロメタンは、水道原水中に含まれるフミン質等の有機物質が、浄水処理の過程で注入される塩素と反応して生じる。
トリハロメタン生成能とは、一定の条件下でその水がもつトリハロメタンの潜在的な生成量をいい、具体的には一定のpH(7±0.2)及び温度(20℃)において、水に塩素を添加して一定時間(24時間)経過した場合に生成されるトリハロメタンの量で表される。