1 平成16年度夏期観察の実施
| (1) | 観察期間 | : | 平成16年8月6日(金)から8月19日(木)まで (この期間中に1日以上観察) |
| (2) | 観察方法 | : | [1] | 肉眼による観察 高度の異なる天の川の3部分(白鳥座、たて座、いて座)を観察する。 |
| [2] | 双眼鏡による観察 こと座のおりひめ星(ベガ)を含む三角形付近の星について、何等級の星まで見えたかを観察する。 |
|||
| [3] | 星空の写真撮影 平成13年度冬期観察を最後に取り止めていた一般参加団体による写真撮影を、今回より再開する。 一眼レフカメラを使用し、天頂部分の夜空をリバーサルフィルム(スライド用フィルム)に撮影する。 |
| ※ | 写真撮影のデジタル化への試行結果 | |
| 一般参加団体による写真撮影は、その測定にかかる労力が大きい等の理由から取りやめていたが、そこから得られたデータを基に公表してきた「全国星空ランキング」の復活を望む声が多くあることから、その復活に向けて、観察データのデジタル化による労力の軽減等を図るため、平成15年度冬季観察の際に、定点観察地23地点の観察団体の協力を得て下記の方法による試行を行った。 | ||
| [1] | 冷却CCDカメラによる観察 光量の少ない夜空でも高精度撮影が可能なデジタルカメラ(冷却CCDカメラ)により撮影を行い、コンピュータ解析により夜空の明るさを判定する。 |
|
| [2] | 一眼レフタイプデジタルカメラによる観察 一眼レフタイプデジタルカメラにより撮影を行い、上記同様の方法により夜空の明るさを判定する。 |
|
| [3] | スライドフィルム撮影による観察 夜空を撮影したスライドフィルム映像をデジタルスキャンし、上記同様に夜空の明るさを判定する。 この結果[3]のスライドフィルム撮影による観察が他の方法に比べ、安定した画像が得られ、比較的短時間で精度の高い判定が可能であった。したがって、今回の観察より、この方法により、一般参加団体の写真撮影を行うものである。 |
|
| (3) | 参加方法 | : |
都道府県・政令指定都市・中核市の大気環境行政担当部局へ参加申込みを行い、「観察の手引き」に基づき観察を実施し、その結果を大気環境行政担当部局まで報告する。 |
| (4) | 定点観察 | : | 別途依頼をしている全国23地点の定点観察地においての観察 一般参加団体による写真撮影の方法(上記(2)[3])と同様の方法で行い、引き続き、夜空の明るさを測定する。 |
2 星空継続観察シンボルマーク及びイメージキャラクターの決定
平成15年度冬期観察の実施に併せ募集した本事業のシンボルマーク及びイメージキャラクターは両部門あわせて391作品の応募があり、選考の結果、下記の作品に決定した。
| ○ | 環境大臣賞 | ||
| シンボルマーク部門 | : | 杜多 利香(兵庫県神戸市) | |
| イメージキャラクター部門 | : | 同上 | |
 シンボルマーク |
 キャラクター |
| ○ | 佳作 | ||
| シンボルマーク部門 | : | 高見澤 アカネ(埼玉県さいたま市) | |
| イメージキャラクター部門 | : | 川本 智(長野県大桑村) |
|
| ○ | 日本環境協会理事長賞(小~高校生対象作品) | ||
| シンボルマーク部門 | : | 森本 寛子(京都府福知山市) | |
| イメージキャラクター部門 | : | 森 加奈子(福岡県北九州市) | |
環境大臣賞に決定したシンボルマーク、イメージキャラクターは、今後、パンフレット、ポスター、星空観察ノート等、星空継続観察事業の顔として広く使用するものとしている。
なお、環境大臣賞及び日本環境協会理事長賞については、平成16年8月21日(土)京都府京丹後市で開催される第16回「星空の街・あおぞらの街」全国大会において表彰を行う予定である。
3 平成15年度冬期観察の結果概要
| (1) | 観察期間:平成16年1月11日から1月24日まで(1日以上観察) |
| (2) | 参加団体・参加者数:全国47都道府県の346団体、延べ3,491人(昨年度は344団体、延べ3,843人)が参加。(図1) |
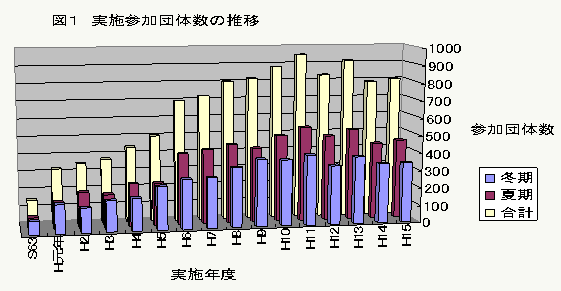
| (3) | 観察結果 | |
| [1] |
肉眼による天の川の観察 肉眼で天の川の高度の異なる3部分(ペルセウス座付近、ふたご座付近、いっかくじゅう座付近)の見え方を観察した。(図2) |
|
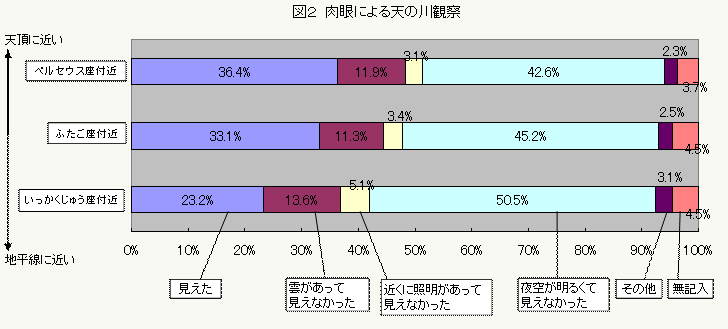
星座の高度に応じて見え方に違いがあり、総じて高度が高いほど星が見えやすいという回答の割合が高い。地上に近いほど人工光の影響を受けていることが確認できる。
| [2] | 双眼鏡による観察結果 双眼鏡を用い、すばる(プレアデス星団)のラケット形の中の星を観察し、何等級の星まで見えたのかを都市規模別にまとめた。(図3) |
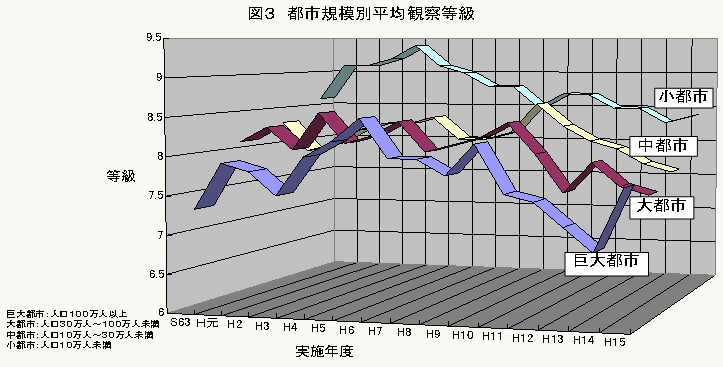
総じて、規模の小さな都市ほど暗い星まで見え、星がよく見えるという結果となっている。特に小都市は、中都市以上の都市と比べて顕著にその傾向が現れている。
| [3] | カラースライド写真から求めた「夜空の明るさ」 全国23地点の定点観察地で、アルデバランを中心とする夜空のカラースライド写真撮影を実施した結果をまとめた。なお、「夜空の明るさ」の値が大きいほどより暗い星が見えたことを表し、夜空が暗いことを示す。(図4) |
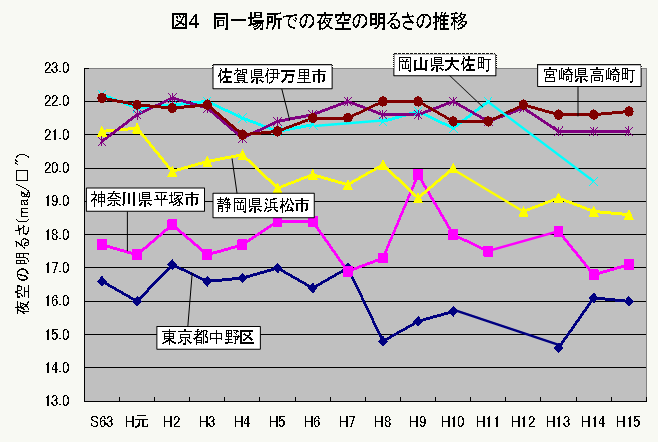
図4は、定点におけるスライド撮影による夜空の明るさ判定の結果を図化したものである。スライド撮影による明るさ判定は第3者が客観的に行うので、前記の肉眼や双眼鏡による観察と比べると観察者による差が出にくく、また、観察場所の移動がない分、経年的変動データとしての信頼度は高くなる。
観察結果は、総じて、各都市とも横ばい若しくは右下がり(夜空の明るさの増加)となっていることが見て取れる。
観察結果は、総じて、各都市とも横ばい若しくは右下がり(夜空の明るさの増加)となっていることが見て取れる。
なお、7ページ目に全国の定点観測の結果を示す。