

地球環境研究総合推進費は、地球環境問題が人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼすことに鑑み、様々な分野における研究者の総力を結集して学際的、国際的な観点から総合的に調査研究を推進し、もって地球環境の保全に資することを目的とした研究資金です。
制度の特徴と基本的なしくみ
地球環境政策を科学的に支えることを明確に指向した研究資金です
推進費は、オゾン層の破壊や地球温暖化など、数々の地球環境問題を解決に導くための政策(ここでは地球環境政策と呼びます)へ、研究活動による科学的知見の集積や科学的側面からの支援等を通じて、貢献・反映を図ることを目指しています。このため、地球環境政策への貢献について関連が不明確な研究は、採択対象課題となり得ませんので ご注意ください。
競争的研究資金です
推進費で実施する研究課題は、公募により研究者や研究者グループから提案のあった研究課題候補の中から、審査により選定されます(実施する課題を、公募により集めた研究提案の良し悪しにより競争的環境下で決めるため、競争的研究資金と呼ばれます)。
審査は、学識経験者等で構成される外部評価委員会の協力を得て行い、政策的又は科学的な価値や貢献の度合い、目標達成の可能性などの観点から、地球環境に関する国内外の動向に即して判断されます。
*外部専門家・有識者の名簿はこちらからご覧になれます。
研究の対象分野
(1)全球システム変動
地球規模のオゾン層破壊、温暖化、水循環
(2)越境汚染
大気、陸域、海域、国際河川等を通じた越境汚染
(3)広域的な生態系保全・再生
地域レベル(東アジアなど)で広範囲に見られる生態撹乱、生物多様性の減少、熱帯林の 減少、砂漠化
(4)持続可能な社会・政策研究
地球環境保全に係る環境と経済及び社会の統合的研究
研究区分
1.地球環境問題対応型研究領域
研究の要件
個別又は複数の地球環境問題の解決に資する研究で、国内の研究機関に所属する研究者による研究課題です。公募に当たって、重点的に募集したい研究分野などを記した公募方針を提示します。採択研究課題は、研究者から応募のあった研究課題の中から、学識研究者等による審査をもとに選定します。
産学民官を問わず、国内の研究機関に研究者として所属している者とします(国籍は問いません)。国外の研究機関への研究費の配分はできません。
研究課題代表者は、予定される研究期間について研究全般に責任を持って、研究者間の経費の配分、研究の進行管理、研究評価結果への対応などを行います。
研究期間
原則3年間とします。ただし、中間評価において、研究の発展可能性、進捗状況からみて研究の延長が妥当と認められた課題については、研究評価を実施した上で、2年間延長が可能です(計5年間)。
研究開始2年目に中間評価、研究終了の次年度に事後評価を行います。
2.戦略的研究開発領域
研究の要件
わが国が国際的に先駆けて、若しくは国際的な情勢を踏まえて、特に先導的に重点化して進めるべき大規模な研究プロジェクト、又は個別研究の統合化・シナリオ化を行うことによって、わが国が先導的な成果を上げることが期待される大規模な研究プロジェクトです。
本研究区分の場合は、研究概要(研究テーマや研究内容の基本的な構成、研究プロジェクトリーダー等)は環境省が設定します。その上で、研究プロジェクトを構成する具体的な研究内容や研究参画者(以下、「研究課題詳細」と呼びます)を公募し、学識経験者等による審査をもとに研究課題詳細を決定します。
研究への参加資格
研究全般に責任を持って、研究者間の経費の配分、研究の進行管理、研究評価結果への対応などを行う研究プロジェクトリーダーは、公募ではなく環境省が指名します。
研究プロジェクトへの参加者は、産学民官を問わず、国内の研究機関に研究者として所属している者とします(国籍は問いません)。国外の研究機関への研究費の配分はできません。
研究期間
原則5年間(第Ⅰ期3年間、第Ⅱ期2年間)ですが、研究評価(中間評価)において、研究の発展可能性、進捗状況等からみて、第Ⅱ期への移行が適切でないと認められた場合は、第Ⅰ期で終了します。
研究開始3年目に中間評価、研究終了の次年度に事後評価を行います。
3.課題検討調査研究
研究の要件
地球環境問題対応型研究領域の研究課題提案に先駆けて、実施の具体的方途が未分明で検討・分析を要する研究領域について、適切な課題の設定又は課題の見直しに反映させるために必要な調査研究です。ただし、課題検討調査研究の実施により提案を目指すこととなる研究課題は、地球環境問題対応型研究領域の要件を満たす必要があります。
※なお、当該研究区分は、平成18年度より「地球環境研究革新型研究領域」に移行したため、今後募集は行いません。
4.地球環境研究革新型研究領域
研究の要件
新規性・独創性・革新性に重点を置いた若手研究者向けの研究課題で、研究代表者及び研究参画者のすべてが研究開始初年度の4月1日時点で40歳以下を要件とします。
以下のような研究課題をはじめ、地球環境問題の解決に資する研究課題を広く公募します。
・地球環境に影響を及ぼす新規発見物質の発生と推移(fate)に関する研究、
・地球環境研究に関する新たな研究手法、観測・測定技術の開発、
・現時点で想定されていない新たな政策提言、国際的枠組みの構築につながる政策研究など
研究への参加資格と代表者
産学官を問わず、国内の研究機関に研究者として所属している者とします(国籍は問いません)。国外の研究機関への研究費の配分はできません。
研究課題代表者は、予定される研究期間について研究全般に責任を持って、研究者間の経費の配分、研究の進行管理、研究評価結果への対応などを行います。
研究期間
1年間又は2年間のいずれかとします。
5.国際交流研究
研究の要件
地球環境部門における外国の研究者(以下、「招へい研究者」と呼びます)をわが国に招へいし、国内の研究機関の研究者(以下、「受け入れ研究者」と呼びます)と共同研究を実施することにより、 地球環境研究の国際的な推進を図ることを目的とする研究です。
この研究は上記1、2のいずれかの研究課題(親課題と呼びます)の一部を分担・構成し、親課題に課せられた研究目的や達成目標などの要件を満たすものでなければなりません。
招へい研究者の要件
以下のすべてに該当することが必要です。
(1)日本国籍又は日本の永住権を有しない者。
(2)自然科学又は人文社会科学部門における博士号取得者又は同等の学位・資格を有するもの。ただし、先進国以外の国において当該学位・資格を得た場合は、先進国における研究活動歴が3年以上ある者又は同等の実力を有すると認められる者。
(3)研究活動に支障のない健康な者。
(4)日本語又は英語に堪能な者。
受け入れ研究者の要件
受け入れ研究者は、国立試験研究機関又は独立行政法人研究機関に、研究者として所属している者とします。
研究期間
研究期間は原則1年以内ですが、研究の発展可能性、進捗状況等のほか、招へい研究者及び受け入れ研究者の意見を聴いて、研究の継続が必要と認められるものについては、最大2回の延長(計3年間)が認められます。
公募と課題選定
公募時期
公募の予定は、推進費ホームページや、科学雑誌、一部の学会誌、環境・科学関係Webサイト等にてお知らせします。
例年、10月に公募要項を公表し、11月中旬頃までを期限として、課題提案を受け付けています。
*時期は変更する場合がありますのでご注意ください。
応募方法
課題提案に必要な資料の様式は、全て推進費ホームページからダウンロードして入手できるようにします。提出方法は、公募要項にてお知らせします。
課題の選定
提案課題は、書類の不備や満たすべき要件のチェック後、外部の学識経験者により構成される地球環境研究企画委員会、及び第1~第4研究分科会において審査を行います。審査の手順は、書面による第1次審査を経て課題を絞り、ヒアリング形式の第2次審査を行って、採択課題の選定を行います。
採択課題の内定は、例年3月頃です。講評などの審査結果は、審査の終了後、応募者へ送付します。
研究費の流れ
研究費は、財務省との協議及び予算承認を受け、関係各府省及び各機関に配分されます。
この際、国立試験研究機関以外の研究機関(独立行政法人研究機関、国公私立大学、民間機関等)の場合は、国から研究機関に対する委託研究として実施することになります。研究者個人との契約は行いません。
研究評価(研究課題評価成果と研究制度の評価)
推進費で実施している研究課題については、地球環境研究企画委員会及び第1~第4研究分科会において、研究の進捗度、地球環境保全への寄与度、成果の科学的・社会経済的価値等の観点から評価を行っています。評価結果は、研究課題毎の計画の見直しや研究予算の配分に活用されています。また、施策としての制度評価も実施されています。
評価結果は、推進費ホームページ
(http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/jpn/evaluation/evaluation_top.html)にて公表しています。
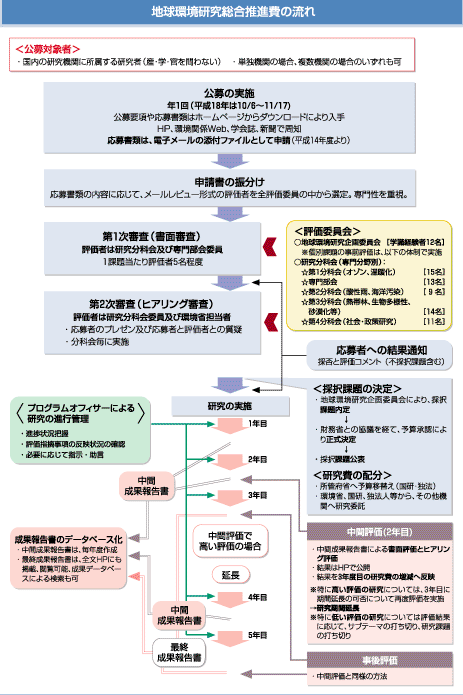
「平成21年度地球環境研究総合推進費」の内容は、こちらからご覧になれます(閲覧にはAdobeReaderが必要です)。
「平成21年度地球環境研究総合推進費」 [PDF 8,325KB]
1/8 [PDF 1,134KB] 2/8 [PDF 1,242KB] 3/8 [PDF 1,063KB]
4/8 [PDF 1,055KB] 5/8 [PDF 925KB] 6/8 [PDF 1,062KB]
7/8 [PDF 975KB] 8/8 [PDF 932KB]
Global Environment Research Fund FY2009 (in English) [PDF 8,707KB]
1/8 [PDF 1,358KB] 2/8 [PDF 1,297KB] 3/8 [PDF 874KB]
4/8 [PDF 1,149KB] 5/8 [PDF 1,162KB] 6/8 [PDF 1,112KB]
7/8 [PDF 1,192KB] 8/8 [PDF 673KB]