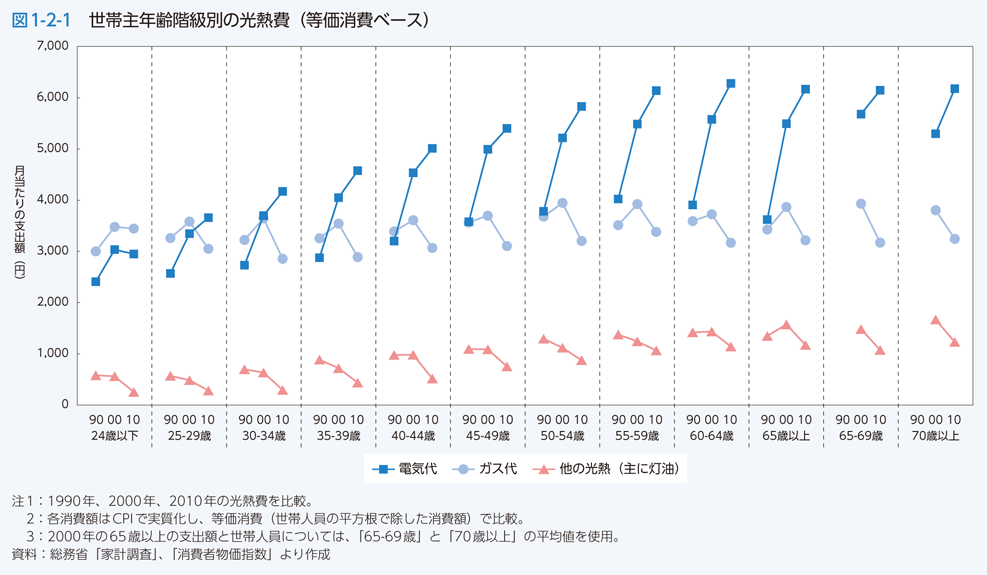
平成26年に世界の総人口は72億人を超え、国連の「世界人口展望2012」によれば、2100年(平成112年)には108億人に達すると推計されています。人間活動が環境に与える負荷を考えれば、こうした人口爆発による環境負荷は甚大なものになると考えられます。例えば、エコロジカル・フットプリントという考え方に基づくと、仮に全世界の人々が日本と同水準の生活を送った場合、約2.3個分の地球の資源が必要になるとされ、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムや生活様式は、持続可能とは言えません。
我が国においては、前節で述べたとおり人口減少が予想されており、エネルギー消費に伴う温室効果ガスの排出、廃棄物の排出など、環境負荷が減少することが予想されます。しかし、ライフスタイルの変化や高齢化等によって、主に家庭部門における一人当たりの環境負荷は増す可能性があります。例えば我が国では、核家族化等に伴い世帯数が増加しています。国民生活基礎調査によると、世帯数は昭和60年の約3,723万世帯から、平成25年には約5,011万世帯まで増加するとともに、平均世帯人員は3.22人から、2.51人まで減少しました。
国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(2013年(平成25年)1月推計)」によれば、今後も人口減少が予測されるにもかかわらず、世帯人数の少人数化も進むと考えられるため、平成22年の約5,184万世帯から、平成31年の約5,307万世帯まで世帯数は増加し、その後は減少に転じて平成47年には約4,956万世帯になると見込まれています。しかし世帯主が65歳以上である高齢世帯数は、一般世帯総数よりも増加率が高く、平成22年の約1,620万世帯から、平成47年には約2,022万世帯へ増加し、全世帯数に占める割合は30.7%から37.7%へ上昇すると見込まれています。世帯人数が少ないほど、一人当たりのエネルギー消費量は増加する傾向があるため(平成18年版環境白書を参照)、こうした世帯の少人数化と世帯数の増加が、環境負荷を高め、人口減少による環境負荷の低減を相殺していくと考えられます。
また、電化製品の普及や多様化等により、日常生活等にかかる電力消費が年々増加しています。さらに高齢世帯は、高齢化により体温調節機能が低下し、在宅時間が長くなる傾向が見られることから、空調等に必要な電力など、日常生活に係るエネルギー消費が増加する傾向にあると考えられます(図1-2-1)。
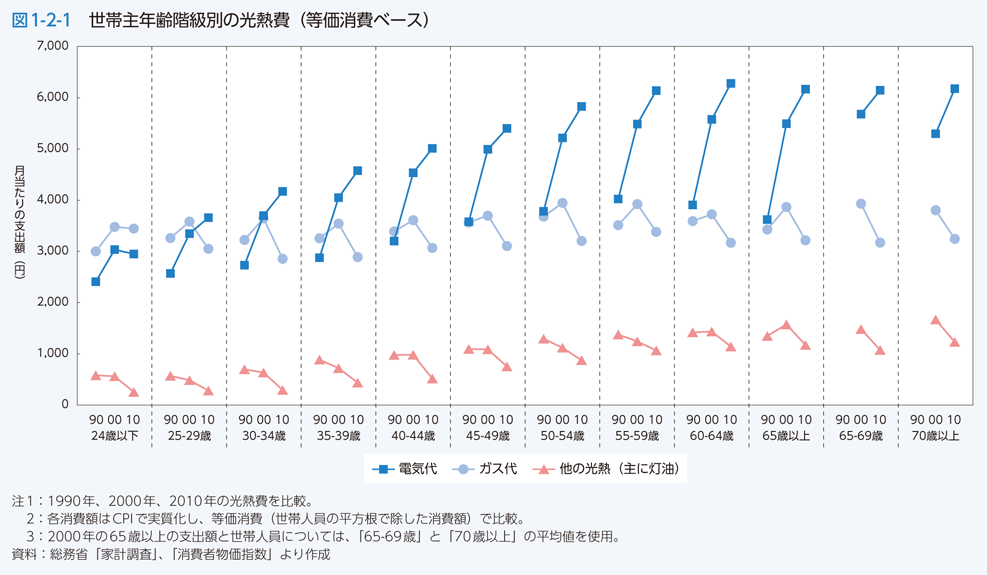
家庭ごみの排出量に関する北九州市の調査によれば、高齢単身・夫婦世帯と全世帯平均では大きな差が見られませんでしたが、世帯の少人数化と世帯数の増加に伴って、一人当たりの家庭ごみ排出量は増加する傾向があるため(平成18年版環境白書を参照)、高齢世帯を始めとする世帯の少人数化と世帯数の増加に伴い、家庭ごみ排出量の増加が懸念されます。
加えて、地方圏においては、人口減少や耕作放棄地の増加に伴い、従来地域住民の利用により維持されてきた里地里山の荒廃や、鳥獣被害の増加が問題となっています。
里地里山とは、原生的な自然と都市の中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林と人工林、農地、ため池等で構成される地域です。人間と自然の営みが調和した地域である里地里山は、国土の約4割を占めており、絶滅危惧種が集中している地域の約6割を占めています。また、我が国は、世界でも有数の「固有種の割合の高い国」であり、哺乳類の固有種率は30%(世界7位)、両生類は80%(世界11位)に上っています。固有種とは、特定の限られた地域にのみ生息する生物種のことであり、その豊かさは、我が国が誇る魅力の一つと言えます。
政府は、2050年(平成62年)までに、里地里山的環境を有する都市から離れた中山間地域や奥山周辺の約3~5割が、無居住地化すると予測しています(図1-2-2)。さらに、農林業における担い手の減少・高齢化に伴って、近年耕地面積が減少する一方で、耕作放棄地は増加しています(図1-2-3)。また、森林資源利用の減少(化石燃料の普及による薪・炭の需要減少や、化学肥料の普及による森林由来の堆肥需要の減少)等に伴い、二次林の管理放棄が進み、野生動植物の生息・生育環境の劣化が生じています。
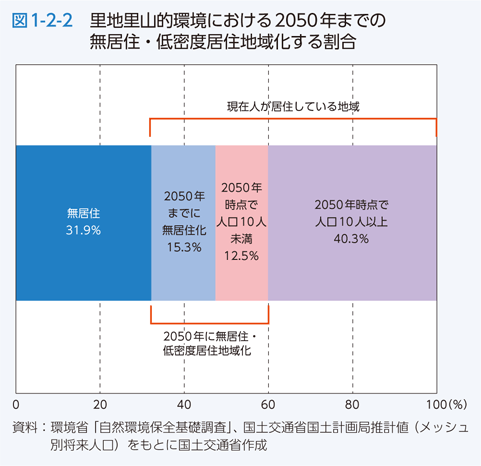
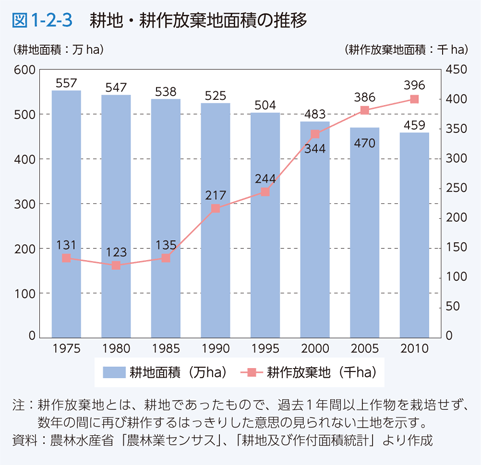
こうした里地里山の荒廃は、森林による水質浄化や洪水緩和、大気浄化などの生態系サービスの低下を招くことが懸念されます。この機能低下は、森から里、里から川、川から海という森里川海のつながり・循環の中で、大都市圏にも様々な悪影響を及ぼすこととなります。
鳥獣被害については、近年増加しているニホンジカ(以下「シカ」という。)やイノシシといった野生鳥獣が、我が国の自然環境や森林、農林業に大きな被害を与えています。具体的には、シカの食害により、絶滅のおそれがある希少植物が被害を受けているほか、樹木の剥皮による森林の劣化や、下層植生の食害等による土壌の流出が懸念されています。また、シカ、イノシシ等による農作物被害は、近年200億円前後で推移しています(図1-2-4)。これらの野生鳥獣による被害が深刻化している要因としては、鳥獣の生息域の拡大、個体数の増加等が考えられます。それらの主な原因として、農山漁村の過疎化、高齢化等により、里地里山等における人間活動が低下するとともに、鳥獣の隠れ家やえさ場となる耕作放棄地が増加したこと、地球温暖化に伴う少雪による自然死の減少、狩猟者の減少、高齢化等により、狩猟による捕獲圧が低下したことが指摘されています。狩猟や有害鳥獣捕獲による、シカ、イノシシ等の適切な個体数の管理は、生態系のバランス維持に貢献しますが、こうした活動は狩猟者が担ってきました。
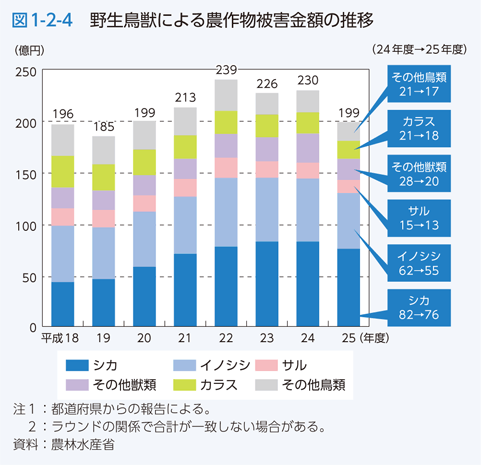
しかし、我が国の狩猟免許所持者は、昭和50年度の延べ約53万人と比べると、平成24年度は延べ約18万人へと大幅に減少しています。また、その年齢構成も85%が50歳代以上と高齢化が進んでおり、今後より一層狩猟者数が減少することが懸念されます(図1-2-5)。
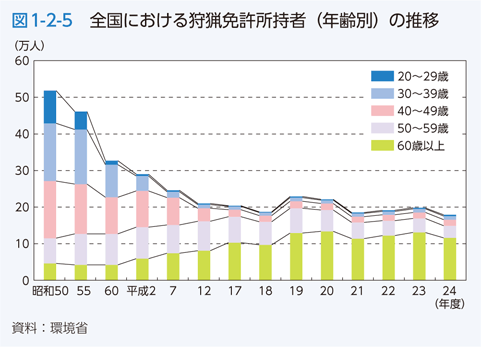
こうした鳥獣被害の増加は、営農意欲の低下を招き、結果として更なる耕作放棄地の増加と鳥獣被害の増加につながるという悪循環を生じさせています。
第1節で見てきたように、都市構造の拡散は、行政コストの増大や中心市街地の衰退、高齢者の移動手段の減少等、経済・社会の様々な側面に影響を及ぼします。同様に、都市構造は、環境問題とは密接な関係があり、特に運輸部門と業務部門のCO2排出量に影響を与えると考えられます。
拡散型の市街地を有する都市は、集約型の市街地を持つ都市と比べて、住民一人当たりの自動車からのCO2排出量が多い傾向にあります(図1-2-6)。このことは、公共交通の利便性が下がる地区が増えるなどにより自動車依存度が高まることによって、旅客、貨物共に住民一人当たりの自動車の走行距離が増加することに原因があると考えられます。第1節で、一人当たりの道路延長と市街地の拡散との関係について説明しましたが、一人当たりの道路延長が長い地域は、住民一人当たりの自動車CO2排出量が多い傾向にあります(図1-2-7)。道路が整備されることで、道路の沿道が開発される場合は自動車の利用を前提とした店舗等の立地が進んで住民の自動車の利用が増えるほか、目的地への移動時間が短縮されるなど相対的に公共交通より自動車が便利になって自動車分担率が高くなるなど、道路の整備に伴って、いわゆる誘発・転換交通が発生する可能性があると考えられます。
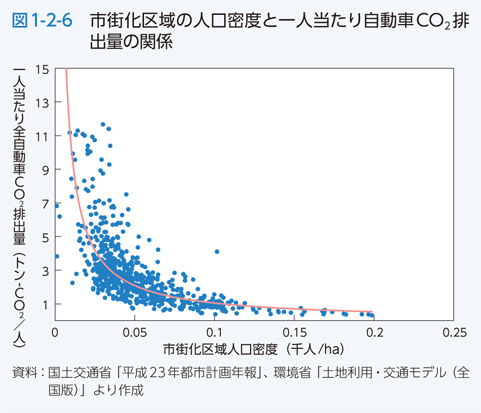
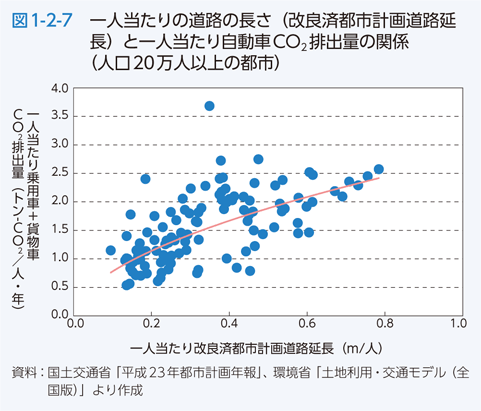
また、拡散型の都市構造を有する都市は、相対的に地価が安い地域での開発を可能とすることから、建築物において広い床面積を確保しやすく、従業者一人当たりの業務床面積を増大させ、それに連動して照明や空調等のエネルギー消費が増えることで、業務部門のCO2排出量に影響を与えると考えられます(図1-2-8)。我が国の平成25年度の業務その他部門の温室効果ガス排出量(速報値)は、1990年度(平成2年度)に比べて約7割増加していますが、その主な要因として業務床面積の伸びとの相関が考えられます(図1-2-10を参照)。
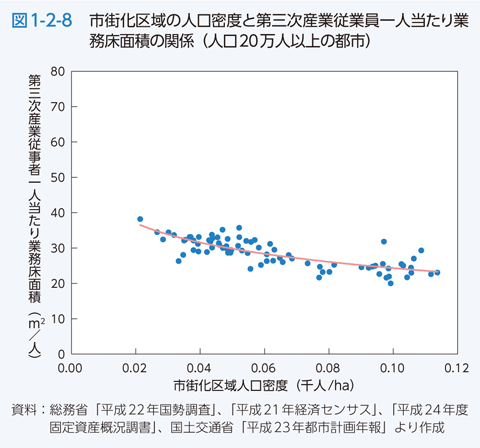
都市構造と小売業からのCO2排出量
ここでは、業務部門の平均よりも床面積の拡大の程度が大きい小売業について、そのCO2排出量と都市構造との関係を見てみます。
我が国の小売業では、売り場面積が増大している一方、売上は近年低下・横ばい傾向ですが、第1節でも見たように、特に中心市街地における売上が低下する一方で、郊外型店舗の売上は伸びています。
小売業の一人当たりの売り場面積は、地域によって大きく異なります。拡散型の市街地を有する地域は、市町村人口一人当たりの売り場面積が大きくなっています。しかし、小売業の売上は、主に消費者である地域住民の総所得によって大きく影響を受けるために、商圏の消費者の規模が変わらなければ、売り場面積を増やしても、地域全体の売上の増大には直結しないと考えられます。そのため、拡散型の市街地を有する地域は、集約型の市街地を有する地域に比べて、売上当たりの業務床面積が大きく、その結果、売上当たりのエネルギー消費量、CO2排出量が大きくなる傾向にあります。すなわち、地域の都市構造の違いによって、地域における小売業のエネルギー・CO2生産性に大きな違いが生じていると考えられます。
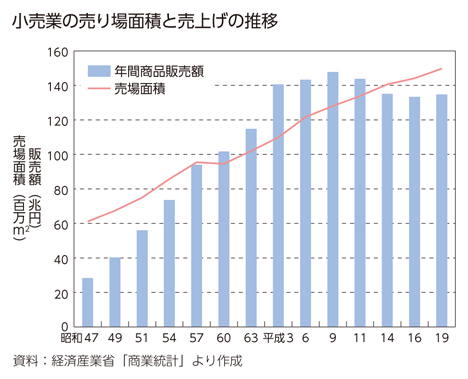
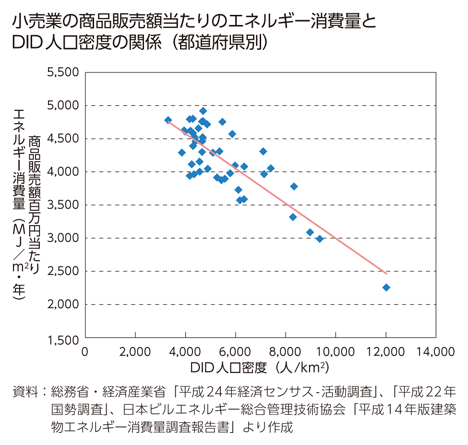
また、店舗などは立地場所によって、来場者の交通手段に由来するCO2排出量に大きな差異が生じると考えられます。店舗等への来場者から発生する自動車からのCO2排出量について、宇都宮市を例に挙げると、郊外の高速道路のインターチェンジ付近の店舗群は、鉄道駅付近の中心市街地の店舗群と比べて、自動車の利用割合が高いなどの理由により、CO2排出量が約6倍となっています。
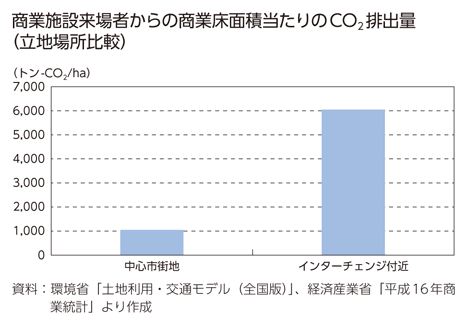
平成16年度をピークに、我が国の最終エネルギー消費量は減少傾向にありますが、第1節で示した第三次産業化も背景に、業務部門の最終エネルギー消費量は増加傾向にあります。2012年度(平成24年度)の業務部門の最終エネルギー消費量は、1990年度(平成2年度)に比べて41.9%増加しており、産業部門(-12.6%)や運輸部門(+3.1%)よりも伸びが大きくなっています。業務部門のエネルギー消費量は、「延床面積当たりエネルギー消費原単位(以下「エネルギー消費原単位」という。)×延床面積」で表すことができます。エネルギー消費原単位は1990年代後半から2000年代前半にかけて急激に悪化しましたが、2007~2009年度は原油価格高騰等により改善し、近年はまた増加傾向にあります(図1-2-9)。業務床面積は特に「事務所・ビル」及び「卸・小売業」を中心に一貫して増加しており、2012年度(平成24年度)の業務床面積は、1990年度(平成2年度)比で42.9%も増加しました(図1-2-10)。結果的に、2005年度(平成17年度)~2013年度(平成25年度)のエネルギー消費原単位の純減少分を、業務床面積の増加分が約8割相殺しています。近年は、エネルギー消費原単位も悪化しており、業務部門のCO2排出量の増加が懸念されます。
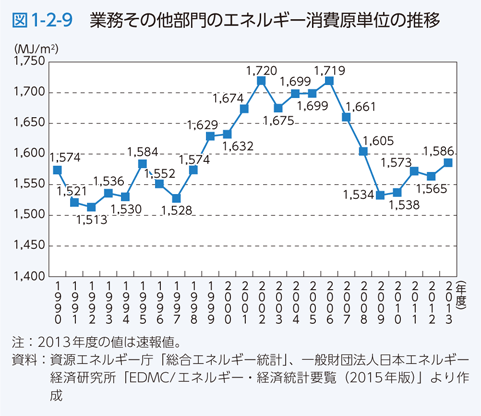
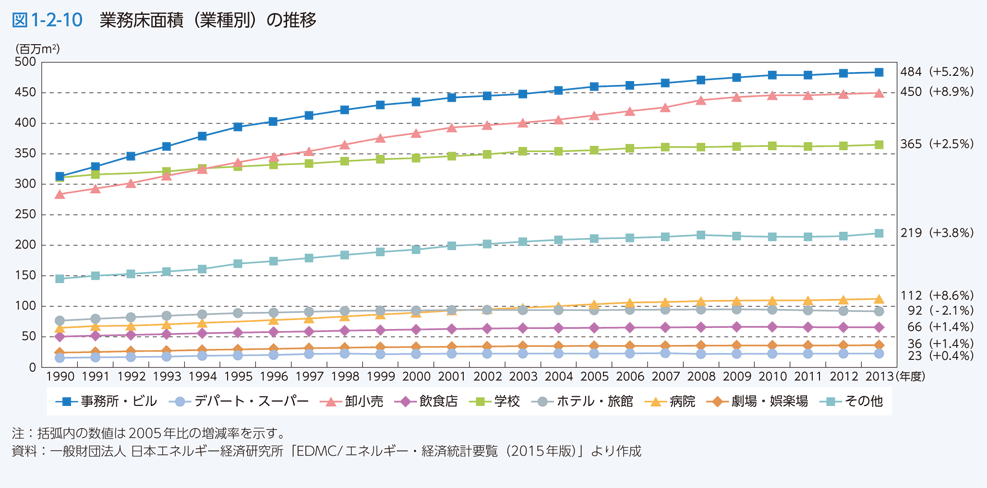
前述のとおり、我が国全体の最終エネルギー消費量は減少傾向にあるにもかかわらず、CO2排出量は増加傾向にあります。この主な要因として、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により、一般電気事業者の電源構成に占める火力発電の割合が、平成22年度の61.7%から平成25年度には88.3%へ高まっており、これに伴ってエネルギー起源CO2排出量が急増していることがあります(図1-2-11)。
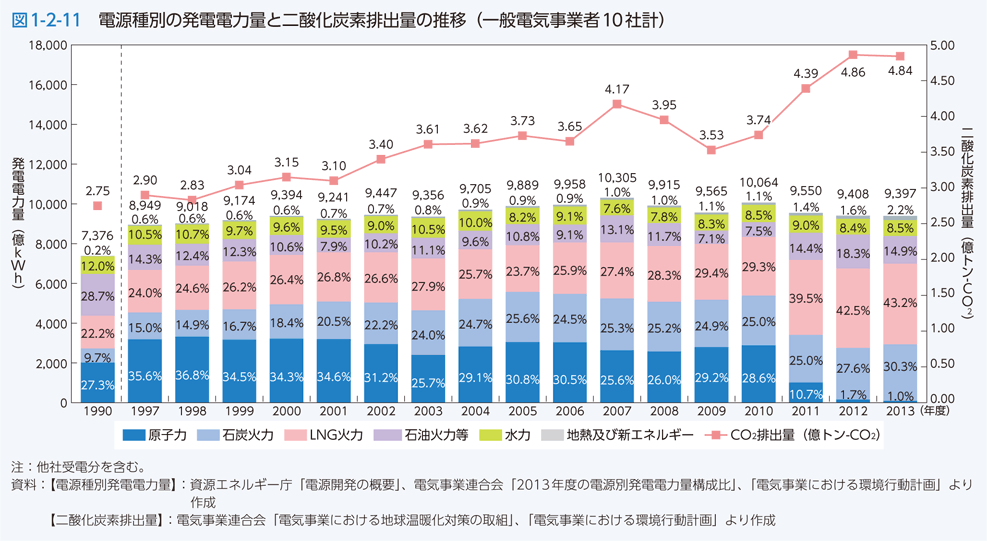
電気1kWhを発電する際に発生するCO2排出量を表す「CO2排出係数」を見ると、京都議定書第一約束期間の基準年である1990年(平成2年)以降、主要国がこれを減少させている一方で(図1-2-12)、我が国は横ばいとなっており、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故等の影響で原子力発電所の稼働が停止し、その供給不足分が火力発電により代替されるようになった2011年(平成23年)以降は急激に悪化しています。1990年度(平成2年度)以降の発電に伴うCO2排出量の推移を具体的な燃料種別で見ると、電源構成に占める石炭火力発電及び天然ガス火力発電(以下「LNG火力発電」という。)の割合が増加していることが分かります。具体的には、LNG火力発電からのCO2排出量が約2倍増加しているほか、石炭火力発電所からのCO2排出量は約3倍増加しています。また、火力発電に占める石炭火力発電の割合は、1990年度(平成2年度)の1/3弱から2013年度(平成25年度)の1/2弱まで増えているほか、LNG火力発電の割合は1/5から1/3に増加しています(図1-2-13)。1990年(平成2年)から2010年(平成22年)の間に、他国と同様にCO2排出係数が減少していないのは、CO2排出量が多い石炭火力発電の割合の増加が要因の一つであると理解できます。一方、国際エネルギー機関(IEA)の「Energy Balances of OECD countries 2014 edition」によれば、再生可能エネルギーが我が国の電源に占める割合は、他の主要国に比べて低くなっています(図1-2-14)。平成24年7月に固定価格買取制度(FIT)が導入されて以降、再生可能エネルギーの導入が進んでいますが、電気事業連合会「電源別発電電力量構成比」によれば、平成25年度に水力発電を除く再生可能エネルギーが発電電力量に占める割合は、2.2%にとどまっています(一般電気事業者10社計、他社受電分を含む)。
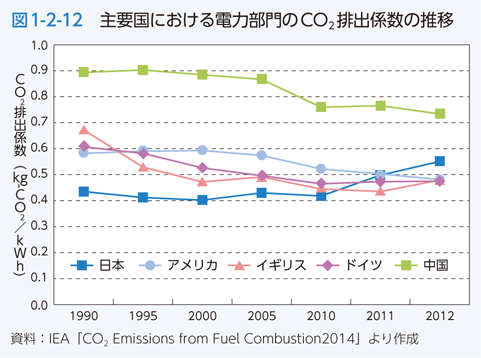
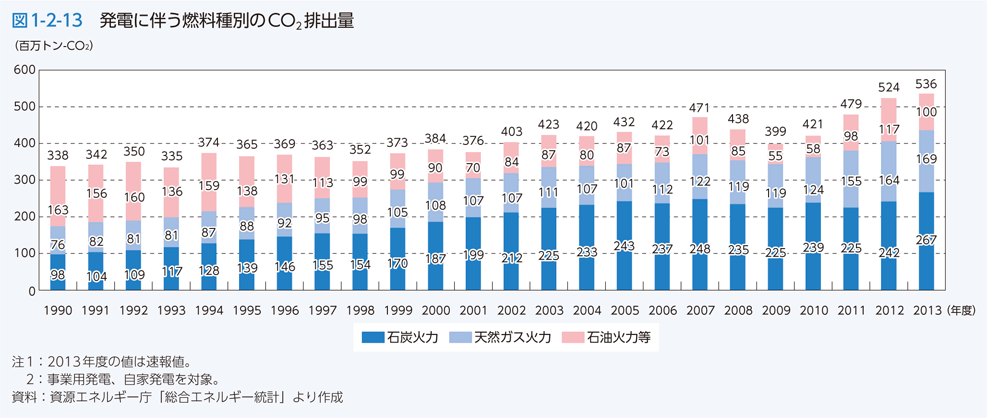
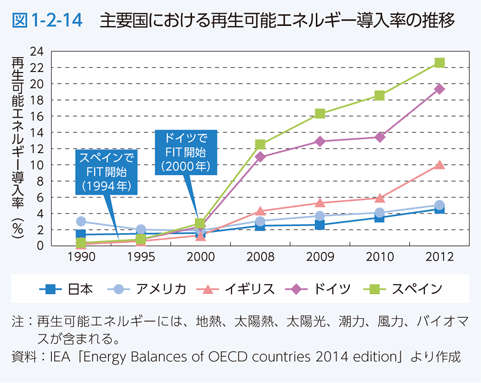
我が国は、先進超々臨界圧発電(A-USC)や石炭ガス化複合発電(IGCC)など、世界最高水準の石炭火力発電技術の開発を進めています。しかし、石炭は他の化石燃料に比べて、地政学的リスクが化石燃料の中で最も低く、安定供給性や経済性に優れていると考えられている一方で、CO2排出量が多く、現在用いられている技術の水準では最新型の石炭火力発電であっても、最新型のLNG火力発電に比べ、約2倍のCO2を排出します(図1-2-15)。このため、その経済性の評価に当たっては、CO2の排出に伴う地球温暖化により生じ得る様々な問題のコストが、適切に反映されていく必要があると考えられます。
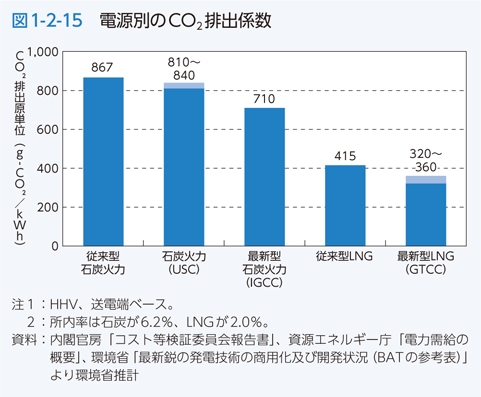
電気事業者の供給計画や報道発表によると、我が国では、環境影響評価法対象規模未満のものを含め、過去10年の立地・運開のペースを大きく上回る石炭火力発電の立地・運開が計画されています。これらの計画がすべて実施されるかは定かではなく、また、発電効率や利用率等によりCO2排出量は異なることから、CO2排出係数への定量的な影響を算出することは困難ですが、今後、このようなCO2排出量が多い石炭火力発電所の立地・運開が進んだ場合には、電力部門におけるCO2排出係数が相当程度増加することは否定できず、ひいては、企業や家庭における省エネの取組(電力消費量の削減)の削減効果に影響を与えることが懸念されます。
経済活動のうち、消費活動はGDPの約6割を占めており、消費者の選択は、生産活動を左右する側面があることから、消費支出や価値観の変化は社会経済全体に大きな影響を与えると考えられます。例えば、消費者が省エネに価値を置き、価格が高くとも省エネ製品・サービスを選ぶようになれば、エネルギー効率の悪い低価格製品・サービスは売れなくなり、自ずとそうした製品・サービスの生産・販売等は縮小することとなります。このため、消費の価値観の変化は環境政策を考える上で、重要な情報の一つであると言えます。
株式会社野村総合研究所が、1997年(平成9年)から3年おきに実施している「生活者1万人アンケート調査」によれば、近年の消費の価値観として、「安さよりも品質を重視する」傾向が見られます。特に10~20代の若年層においては、こだわりのあるモノ・サービスは高価であっても購入する傾向が強くなっています(図1-2-16)。また、株式会社ボストン・コンサルティング・グループによる「BCG世界消費者調査2013」によれば、「ワンランク上の消費を行う」と回答する割合は増加しており、特にレジャー旅行や住宅、娯楽などが「ワンランク上の消費」を行いたいものの上位を占めています。こうしたモノの消費以外の、形のない「体験」や「経験」等を消費する「コト消費」においては、特に高付加価値なモノ・サービス等を求める傾向が高いと考えられます。
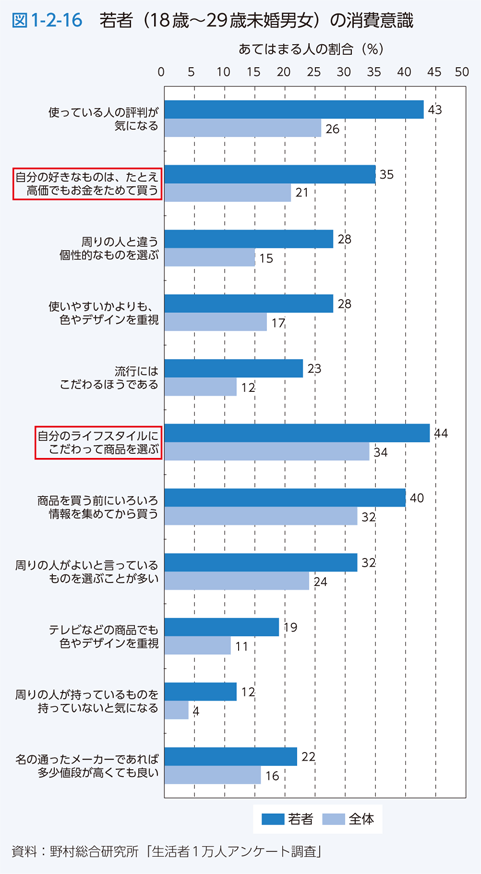
こうした消費の価値観の変化の中で、環境に配慮した消費行動を促すには、「環境配慮」自体に価値が置かれるとともに、「環境配慮」がモノ・サービスの高付加価値化につながるような工夫が必要であると考えられます。一般的に、環境配慮製品・サービスは、環境配慮を行っていない(環境負荷低減に対するコストを支払っていない)製品・サービスに比べ、価格が高い傾向があります。したがって、こうした消費の価値観の変化の中で、「環境配慮」にこだわりや価値が置かれない場合、「価格」が消費判断の基準となる可能性が高く、環境に配慮を行っていない製品・サービスが選択されていくことが懸念されます。環境省の調査によれば、環境に配慮した消費行動は、年齢が低いほど実施されておらず、実施する意欲も低くなっています(図1-2-17)。一方、高齢者は環境に配慮した消費を実施している割合が高くなっています。今後、消費者の中でも存在感を増すことになる高齢者の消費志向としては、健康や医療介護、旅行などが大きな割合を占めており、こういった分野では、環境配慮製品・サービスの選好が進む可能性があると言えます(図1-2-18)。
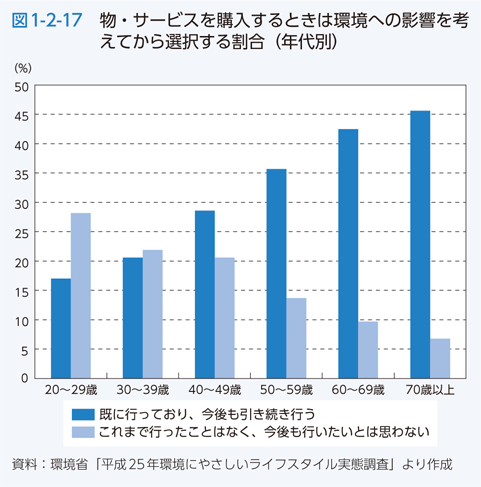
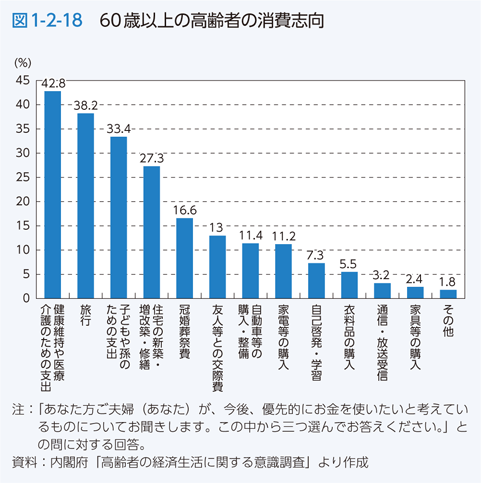
近年、増加している大雨や猛暑の背景には、地球温暖化による影響があると考えられており、今後は大雨の頻度と強度の増加、強い台風の増加などによる自然災害の増加が予想されています。また、気温の上昇、降水量の変化など様々な気候の変化、海面の上昇、海洋の酸性化などにより、自然災害だけでなく、食料、健康などの様々な面で影響が生じることも予想されています。
こうしたことから、平成27年夏頃をめどとした政府全体の適応計画策定に向けて取りまとめられた「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について(意見具申)」(中央環境審議会、平成27年3月)では、緩和の取組を着実に進めるとともに、既に現れている影響や、今後中長期的に避けることのできない影響への適応を計画的に進めることが必要とされています。
また、気候変動の影響は気候、地形、社会条件などによってその内容や程度が異なるとともに、適応は地域づくりにもつながることから、地域が主体となって適応に取り組むことが求められます。
自治会や町内会などの地縁型の地域コミュニティは、自然環境の劣化や廃棄物問題など、地域の環境問題に対応する主体も担ってきました。しかし、地域コミュニティの衰退に伴って、こうした地域の環境保全活動の減少が懸念されます。
地域共有の課題としての環境保全への取組を通じて、社会問題解決の基盤にもなる地域コミュニティが活性化することが期待できる一方、地域コミュニティに活力がある場合には、環境保全の取組も積極的に行われる傾向があり、地域コミュニティによる環境を保全する取組と社会問題解決能力の間に好循環を創り出す必要があります。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |