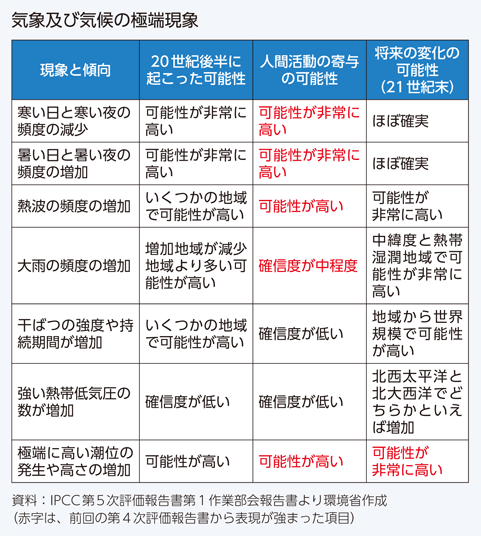
温室効果ガスによる気候変動の見通しや、自然や社会経済への影響、気候変動に対する対策など、2,500人以上の科学者が参加し、最新の研究成果に対して評価を行っている「気候変動に関する政府間パネル」(以下「IPCC」という。)において、第4次評価報告書から7年ぶりに公表される第5次評価報告書の作成が、現在進められています。IPCC評価報告書には3つの作業部会報告書がありますが、そのうち地球温暖化などの気候変動に関する自然科学的根拠を評価している第1作業部会報告書が、平成25年9月にIPCC総会にて採択されました。
ア 自然科学的知見に基づいた気候変動の状況(第1作業部会報告書)
第1作業部会報告書では、地球温暖化については疑う余地がないことを改めて指摘しました。観測事実としては、主に以下の4つがあります。[1] 世界の平均地上気温については、1880年(明治13年)から2012年(平成24年)までの期間で、0.85℃上昇したことが観測されています。[2]過去20年にわたってグリーンランド及び南極の氷床の質量が減少し、氷河はほぼ世界中で縮小し続けていると報告しています。[3]海面水位は上昇し続けており、1901年(明治34年)から2010年(平成22年)までの期間で、19cm上昇していると報告されています。[4]1971年(昭和46年)から2010年(平成22年)までの期間で、海洋の表層(0~700m)の水温が上昇したことはほぼ確実であるとともに、また、1992年(平成4年)から2005年(平成17年)の期間に、3,000m以深の海洋深層においても水温が上昇している可能性が高いことが初めて指摘されています。
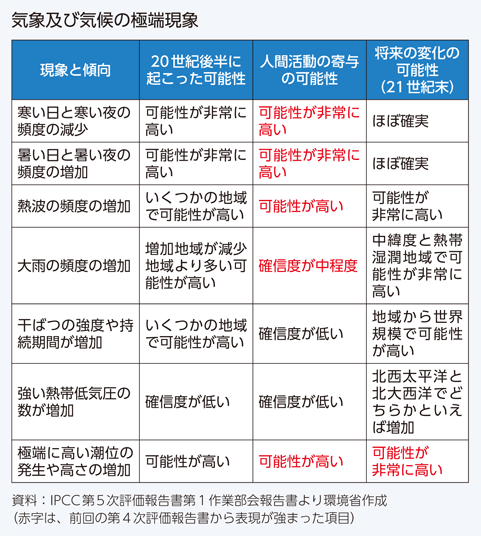
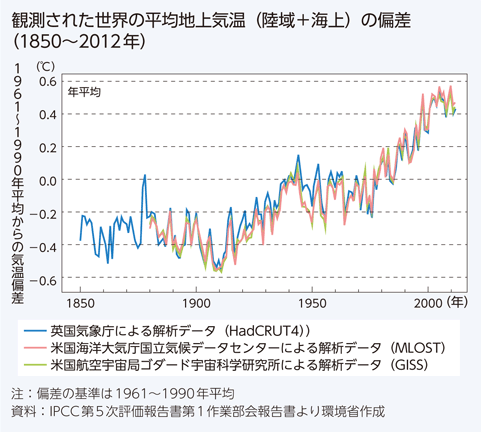
また、地球温暖化の原因としては、1951年(昭和26年)から2010年(平成22年)の間に観測された世界の平均地上気温の上昇の半分以上が、温室効果ガスの排出などの人間活動が気候に与えた影響によりもたらされた可能性が極めて高いと指摘しています。さらに、温室効果ガスの一つである二酸化炭素(以下「CO2」という。)の累積排出量と世界の平均地上気温の応答(変化)は、ほぼ比例関係にあり、最終的に気温が何℃上昇するかは累積総排出量によって決定づけられると、IPCC報告書において初めて指摘されました。
そして、地球温暖化の将来予測については、今回新たに代表的濃度経路(RCP)と呼ばれる4つのシナリオが作成されました。可能な限りの地球温暖化対策を前提としたシナリオであるRCP2.6では、2081年(平成93年)から2100年(平成112年)において、20世紀末頃と比べて世界の平均地上気温が0.3~1.7℃上昇し、世界の平均海面水位が26~55cm上昇する可能性が高いと予測されています。一方、かなり高い排出量が続くシナリオであるRCP8.5では、平均気温が2.6~4.8℃上昇し、平均海面の水位が45~82cm上昇する可能性が高いと予測されています。こうした気温の上昇に伴って、ほとんどの陸上で、今後極端な高温の頻度が増加する可能性が非常に高く、中緯度の大陸などにおいて、今世紀末までに極端な降雨がより強く、頻繁となる可能性が非常に高いと指摘されています。
イ 気候変動による社会経済や自然への影響、適応(第2作業部会報告書)
平成26年3月に横浜で開催されたIPCC総会において採択・公表された第2作業部会報告書は、気候変動に対する社会経済や自然への影響、適応について評価しています。
ここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋において、自然生態系及び人間社会に影響を与えており、気候変動の影響の証拠は、自然生態系に最も強くかつ包括的に現れていることが指摘されました。また、気候変動の将来の影響について、複数の分野や地域に及ぶ確信度の高い主要なリスクとして、海面上昇・沿岸での高潮被害、大都市部への洪水による被害、気温上昇・干ばつ等による食料安全保障、沿岸海域における生計に重要な海洋生態系並びに陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失など8つのリスクを挙げています。また、あらゆる分野及び地域にわたるこれらの主要なリスクについて、まとめるための枠組みを提供する包括的な「懸念の理由」(Reasons for concern)を5つ挙げています。これを現在(1986年(昭和61年)~2005年(平成17年)の平均)と比較した気温上昇の程度で見ると、以下のようにリスクが高まることが示されています。
[1]1℃の気温上昇により、深刻な影響のリスクに直面する「独特で脅威に曝されているシステム(生態系や文化など)」の数は増加し、熱波、極端な降水、沿岸洪水のような「極端な気象現象」のリスクも高くなる。
[2]2℃の気温上昇により、北極海氷システムやサンゴ礁など適応能力が限られている「独特で脅威に曝されているシステム」は非常に高いリスクにさらされる。
[3]3℃以上の気温上昇により、氷床の消失による大規模で不可逆的な海面水位の上昇の可能性があることから、「大規模な特異現象」が生じるリスクは高くなる(ある値を超える温度上昇が続くと、グリーンランド氷床が千年あるいはそれ以上かけて消失し、平均7mの海面水位の上昇を起こすだろう)。
さらに、経済的、社会的、技術的、政治的決定や行動の変革が、気候に対してレジリエント(強靱)な社会の実現を可能とすることが示されています。
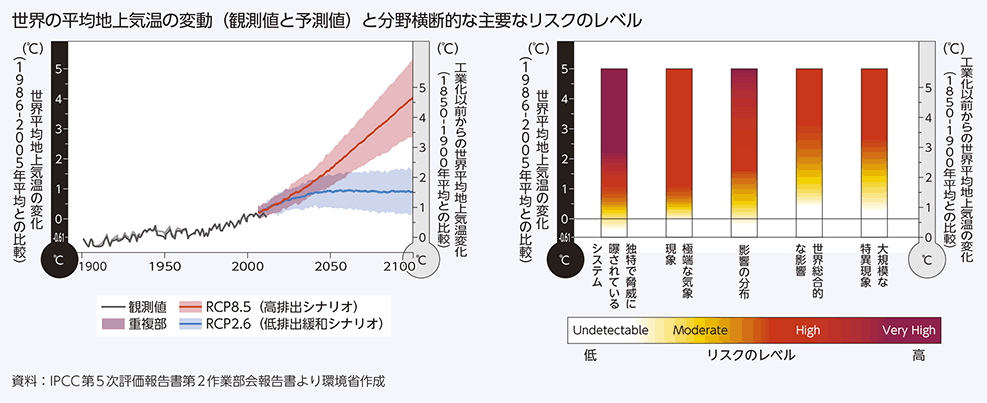
IPCC第3作業部会報告書について
平成26年4月に採択・公表された第3作業部会報告書は、温室効果ガスの排出削減(緩和策)に関する科学的な知見の評価を行っています。同報告書では、人為起源の温室効果ガス排出量は1970年(昭和45年)から2010年(平成22年)の間にかけて増え続け、この40年間に排出された人為起源のCO2累積排出量は、1750年から2010年(平成22年)までの累積排出量の約半分を占めていると指摘されています。
報告書では、900以上の将来の緩和シナリオについて収集・分析を行っており、気温上昇を産業革命前に比べて2℃未満に抑えられる可能性が高いシナリオ(2100年(平成112年)時点の温室効果ガス濃度:二酸化炭素換算で約450ppm)では、以下の特徴を有すると説明しています。
[1]2010年(平成22年)の世界の温室効果ガス排出量と比べて、2050年(平成62年)の世界の温室効果ガス排出量を40~70%削減し、さらに、2100年(平成112年)には世界の温室効果ガスの排出量がほぼゼロ又はそれ以下に削減する。
[2]エネルギー効率がより急速に改善され、再生可能エネルギー、原子力エネルギー、並びに二酸化炭素回収・貯留(CCS)を伴う化石エネルギー並びにCCSを伴うバイオエネルギー(BECCS)を採用したゼロカーボン及び低炭素エネルギーの一次エネルギーに占める割合が、2050年(平成62年)までに2010年(平成22年)の3倍から4倍近くになる。
[3]大規模な土地利用変化と森林減少の抑制。
さらに、2030年(平成42年)まで緩和の取組を遅延させると、気温上昇を産業革命前に比べて2℃未満に抑え続けるための選択肢の幅が狭まると算定しています。持続可能な開発を阻害せずにエネルギー効率性を向上させ、行動様式を変化させることが、鍵となる緩和戦略であるとしています。
また緩和政策では、温室効果ガスのキャップ・アンド・トレード制度を始めた国や地域が増加しているが、キャップが緩い又は義務的でなかったため、短期的な環境効果は限定されていること、炭素税が技術や他の政策と組み合わさり、国内総生産(GDP)と炭素排出の相関を弱めることに寄与したことなどが挙げられています。さらに、緩和のアプローチ方法として、国際協力の必要性を指摘しています。
ア 世界における異常気象と自然災害
世界気象機関(WMO)は、139か国に行った調査に基づき、2001年(平成13年)から2010年(平成22年)が前例のない異常気象に見舞われた10年間であったと述べています。異常気象による死者は37万人に上り、1991年(平成3年)から2000年(平成12年)に比べて20%増加していると指摘しています。死因別の内訳は、熱波による死亡が13万6,000人と急増しており、洪水など熱帯低気圧による災害が約17万人を占めており、経済的損失は3,800億ドルに達しています。さらに、対象国の94%近くが、2001年(平成13年)から2010年(平成22年)を観測史上最も気温の高い10年間であったと記録していることを報告しています。
例えば、平成25年に米国の中西部コロラド州で、豪雨により河川の氾濫やダムの決壊が生じ、1万8,000人以上が避難しました。非常事態宣言が発出された本災害による被害総額は、20億ドル(2,000億円)に達するという推計が出ています。また、フィリピンのレイテ島にハイエン(台風第30号)が直撃したことによって、被災者は1,410万人に上り、そのうちの死者・行方不明者は7,900人を超え、約410万人が家を失いました。被害総額は約5,711億ペソ(1兆3,000億円)に達し、復旧には相当な年数がかかると推測されています。

WMOは、気温上昇などの気候変動による海面上昇が、フィリピンに甚大な被害をもたらしたハイエン(台風第30号)のように、台風の被害を増大させていると指摘しています。地球温暖化と個別の暴風雨に直接の因果関係を認めることは難しいとしながらも、温室効果ガスの排出が続けば、一層の気温上昇と異常気象の増加は避けられないと警告しました。
他方、極端な低温も世界各地で生じています。平成26年には米国国内の広い範囲が、大寒波に見舞われました。米国の一部都市では体感温度が史上最低のマイナス53℃を記録し、寒波による死者は20人以上に上りました。米国における大寒波の原因の一つとして、北極上空の気流の渦である「極渦」が乱れ、通常閉じ込められている寒気が南下したことが挙げられていますが、この「極渦」が乱れた原因の一つとして、米国政府は地球温暖化を挙げています。
こうした世界各国で生じている気候変動による被害は、我が国に無関係とはいえません。例えば平成23年に、インドシナ半島で平年より長期間多雨が続いたことに伴って、タイで大規模な洪水が発生し、多くの現地日系企業に大きな被害が生じ、そこから部品等を輸入している日本国内の企業の生産にも影響が及びました。また、我が国は多くの食糧を海外から輸入しており、異常気象や自然災害による農作物の生産減少などによって、輸入食糧の価格高騰による影響を受ける可能性があります。
イ 日本における異常気象と自然災害
我が国は1898年(明治31年)から2013年(平成25年)に100年当たり1.14℃の割合で気温が上昇しており、世界平均の100年当たり0.69℃の割合を上回る上昇速度となっています。平成25年3月に環境省などがまとめた「日本の気候変動とその影響」によると、1931年(昭和6年)から2012年(平成24年)における最高気温が35℃以上(猛暑日)の日数及び最低気温が25℃以上(熱帯夜)の日数は、それぞれ10年当たり0.2日、1.4日の割合で増加しています。一方、最低気温が0℃未満(冬日)の日数は、10年当たり2.2日の割合で減少しています。
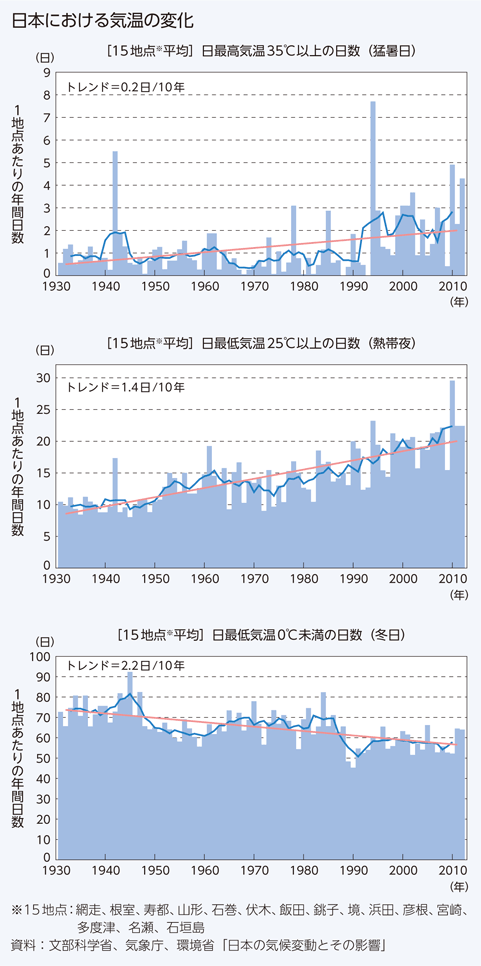
また、独立行政法人国立環境研究所などにより、世界最高水準のスーパーコンピューターである「地球シミュレータ」を用いて、将来の気候変化を予測した結果によると、20世紀末頃と比べて、2100年(平成112年)に日本の夏の日平均気温は4.2℃上昇し、真夏日の日数も約70日増加することが示されました。さらに、日本の夏の降水量は約20%増加し、大雨の頻度も増加すると予測されています。
平成25年度は、我が国でも多くの異常気象が発生し、特に夏季には記録的な猛暑と少雨、度重なる集中豪雨を記録しました。例えば、高知県の四万十市で最高気温が41.0℃を記録するとともに、九州南部・奄美地方の7月の降水量が統計開始以降最も少雨になる一方、山口県、島根県、秋田県、岩手県の一部地域で過去に経験したことのないような大雨が起こるなど、極端な天候が目立ちました。さらに、10月には大型の台風第26号の接近に伴い、記録的な豪雨となった伊豆大島では、大規模な土砂災害が発生し、36人の死者を出す大きな被害が生じました。災害救助のため自衛隊が2万人以上派遣され、被害総額は30億円に上ると推計されています。

地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出削減は、一国が取り組むだけでなく、世界各国も取り組まなければ実現することができません。地球温暖化に歯止めをかけるためには、国内の低炭素化の取組を加速させていくだけでなく、世界全体で取り組んでいくことが不可欠です。
1997年(平成9年)の国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3、以下締約国会議を「COP」という。)で採択された京都議定書では、先進国のみに対し、京都議定書第一約束期間(2008年(平成20年)から2012年(平成24年))における温室効果ガス排出削減の数値目標を定めています。しかし、京都議定書には当時最大の温室効果ガス排出国であった米国が参加せず、また、排出量が急増していた中国やインドなどの新興国や途上国には削減約束が課せられなかったため、途上国からの排出量についても措置を求める声が高まってきました。
これらを受け、2010年(平成22年)のCOP16では、「カンクン合意」が採択され、先進国と途上国の双方の削減目標や行動が気候変動枠組条約下で位置付けられました。2011年(平成23年)のCOP17では、将来の国際枠組みに関するプロセスとして「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」(以下「ADP」という。)を立ち上げ、2015年(平成27年)にすべての国が参加する新たな法的枠組みに合意し、2020年(平成32年)から発効させるとの道筋に合意しました。また、京都議定書については、第二約束期間が採択されましたが、すべての国が参加する公平かつ実効的な枠組みの構築に資さないとの判断から、我が国を含むいくつかの国は第二約束期間には参加しないこととしました。京都議定書は、先進国のみを削減義務の対象としていることから、第一約束期間で排出削減義務を負う国の排出量は、世界全体の排出量の約4分の1にとどまる枠組みとなってしまいました。削減約束を負っていない途上国による温室効果ガスの排出量は、人口増加や経済発展に伴って急増しており、2011年(平成23年)で世界全体の約6割を占め、今後も増え続けると予測されています。
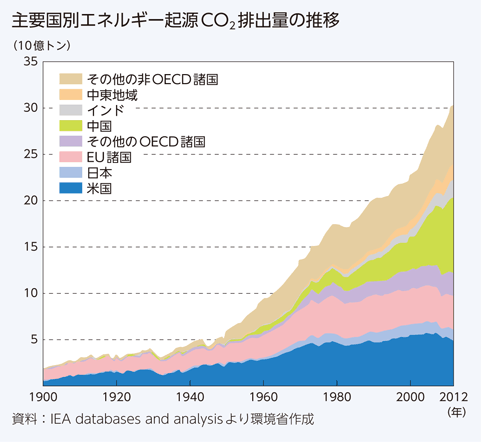
こうしたことから、世界の排出削減を実現するためには、すべての国が参加する公平かつ実効的な枠組みを構築することが急務となっています。
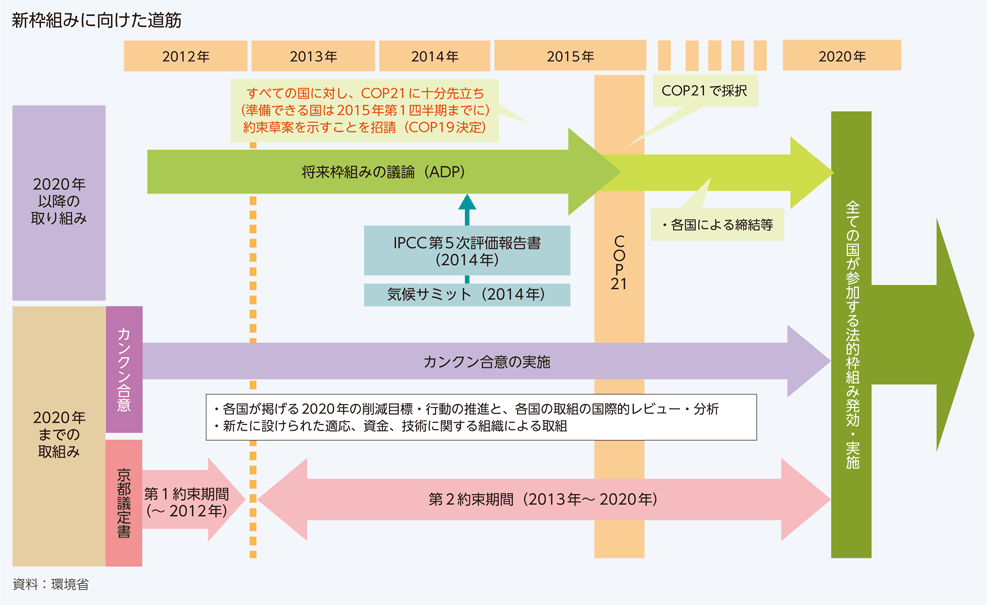
2013年(平成25年)11月11日から11月23日にポーランドで開催されたCOP19では、2020年(平成32年)以降の法的枠組みについて、締約国会議は、すべての国に対し、自主的に決定する約束草案のための国内準備を開始し、COP21に十分先立ち(準備できる国は2015年(平成27年)第1四半期までに)、約束草案を示すことを招請しました。また、ADPに対し、約束草案を提出する際に必要な「情報」を、COP20で特定することを求めることが決定されるなど、議論の前進につながる成果が得られ、COP21におけるすべての国が参加する新たな法的枠組みの合意に向けた準備を整えるという我が国の目標を達成することができました。
京都議定書において、我が国は2008年度(平成20年度)から2012年度(平成24年度)までの5か年平均で、1990年度(平成2年度)と比べて温室効果ガスの総排出量を6%削減することが義務づけられていました。2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量は13億4,300万トン(CO2換算)となり、前年比2.8%増となりました。これは東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、火力発電の増加に伴って化石燃料の消費量が増えたことが主な原因です。
京都議定書第一約束期間(2008~2012年度)の総排出量は5か年平均で12億7,800万トン(基準年比1.4%増)、目標達成に向けて算入可能な森林等吸収源による吸収量は5か年平均で4,870万トン(基準年比3.9%)となりました。この結果、京都メカニズムクレジットを加味すると、5か年平均で基準年比8.4%減となり、京都議定書の目標(基準年比6%減)を達成することとなりました。
我が国は、こうした京都議定書第一約束期間の目標達成について、COP19で報告するとともに、2020年度(平成32年度)の削減目標を、基準年を2005年度(平成17年度)にした上で、3.8%減とすることを説明しました。この新たな目標は、原子力発電の活用のあり方を含めたエネルギー政策及びエネルギーミックスが検討中であることを踏まえ、原子力発電による温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点での目標であり、今後、エネルギー政策の検討の進展を踏まえて見直し、確定的な目標を設定することとしています。また、本目標は、現政権が掲げる経済成長を遂げつつも、世界最高水準の省エネを更に進め、再エネ導入を含めた電力の排出原単位の改善、フロン対策の強化、二国間オフセット・クレジット制度の活用、森林吸収源対策の実施など、最大限の努力によって実現を目指す野心的な目標です。
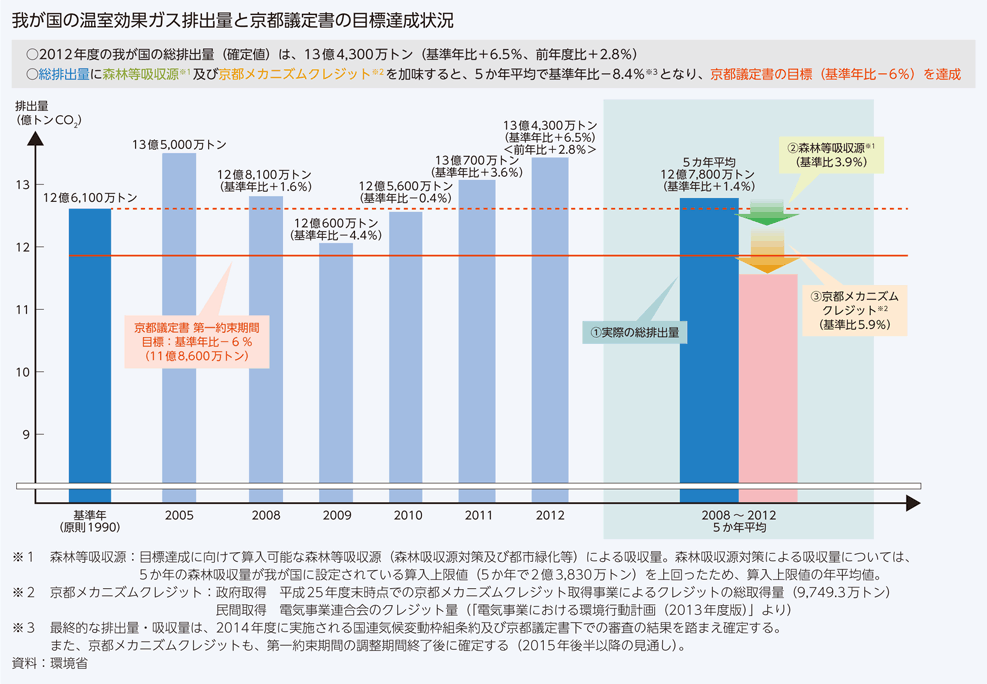
また我が国は、2013年(平成25年)11月に攻めの地球温暖化外交戦略「Actions for Cool Earth:ACE(エース)」を発表し、温室効果ガス排出量を2050年(平成62年)までに世界全体で半減、先進国全体で80%削減を目指すという目標を改めて掲げています。この目標を実現するために、イノベーション(技術革新)、アプリケーション(普及)、パートナーシップ(国際連携)という三本柱を立てて、「技術で世界の低炭素化に貢献していく、攻めの地球温暖化外交」を実行していきます。
具体的には、革新的環境エネルギー技術の開発を推進し、将来にわたって大幅な温室効果ガス排出削減を確実にするとともに、途上国のニーズに応える現地適応型の技術開発を進めることで、早急かつ効果的に途上国に寄り添った温室効果ガス排出削減に貢献します。具体的には、技術革新を推進するため、2020年度(平成32年度)までの国、地方の基礎的財政収支黒字化を前提としつつ、官民あわせて5年で1,100億ドルの国内投資を目指しています。これと同時に、我が国が誇る既存の低炭素技術を世界に展開させていくことで、温暖化対策と経済成長を同時に実現させていきます。さらに、2013年(平成25年)から2015年(平成27年)の3年間で、官民あわせて約1兆6,000億円の途上国支援を行うことにより、技術革新と技術普及の基礎を形づくります。これは今後3年間で先進国に期待されている、計約350億ドルの途上国支援のうち、3分の1を我が国が担うこととなります。このように、技術で世界に貢献する攻めの姿勢を示すことで、実効性のある対策に裏打ちされた地球温暖化の国際交渉を展開し、我が国の存在感を高めることが期待されます。
我が国は、長期的な目標として2050年(平成62年)までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指すとしています。
しかし前述のとおり、CO2などの温室効果ガスの排出量は増加の一途を辿っています。平成24年度のエネルギー起源CO2排出量の内訳は、産業部門が32.7%、業務その他部門(小売・サービス業などの産業・運輸部門に属さない企業・法人部門)が21.4%、家庭部門が16.0%、運輸部門が17.7%となっています。これを京都議定書の基準年比でみると、産業部門は13.4%減少していますが、業務その他部門は65.8%、家庭部門は59.7%と大幅に増加しています。業務その他部門におけるCO2排出量の増加の背景には、産業構造の転換、延床面積の増加やそれに伴う空調使用の増加、また家庭部門では、利便性や快適性を求めるライフスタイルへの変化や、世帯数の増加などの社会構造の変化があると考えられています。
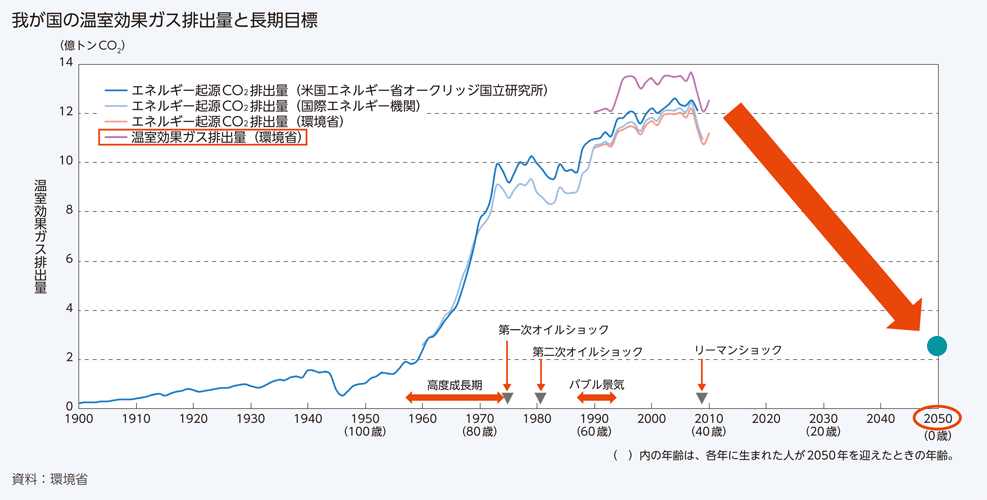
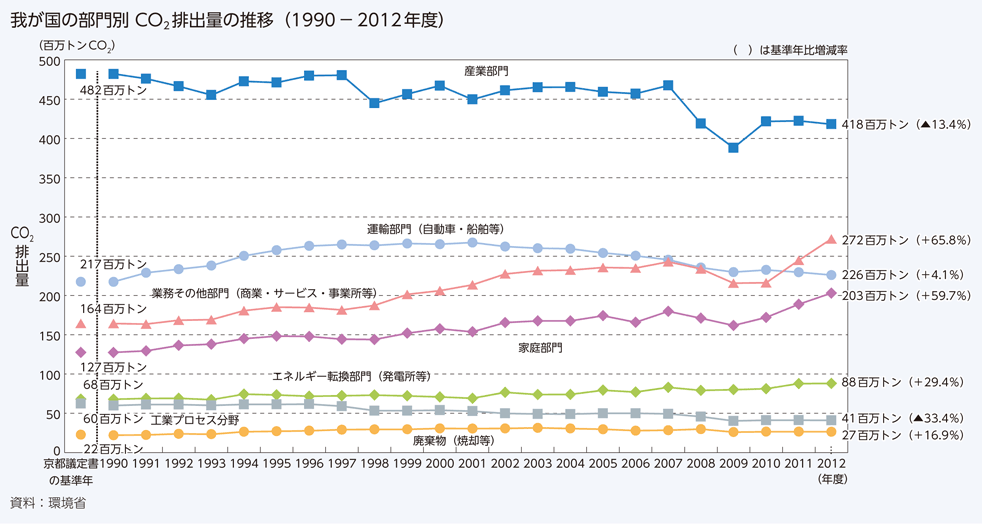
ア 代替フロンの削減に向けた取組
オゾン層を保護するための国際的な取り決めであるモントリオール議定書に基づいて、オゾン層を破壊する特定フロンについて製造が禁止されている一方で、オゾン層を破壊しない代替フロンが開発されました。代替フロンは、オゾン層は破壊しないものの、CO2の数百から1万倍以上という強力な温室効果を有しており、フロンの代替品としてエアコンや冷蔵庫などにおける使用が増加したことで、2010年(平成22年)の世界のフロン類(特定フロン及び代替フロン)の排出量は、2002年(平成14年)に比べて倍増しました。
こうした排出量の増加を受けて、代替フロンへの国際的な規制の動きがみられる中、我が国は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)を改正し、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「改正フロン類法」という。)を策定しました。改正フロン類法では、これまで規制されていなかった製造・輸入業者も対象となり、製品のノンフロン化や、より温室効果の低いフロン類への代替化を促進するなど、排出削減の対策を強化しており、温室効果ガスの削減が一層促進されることが期待されます。
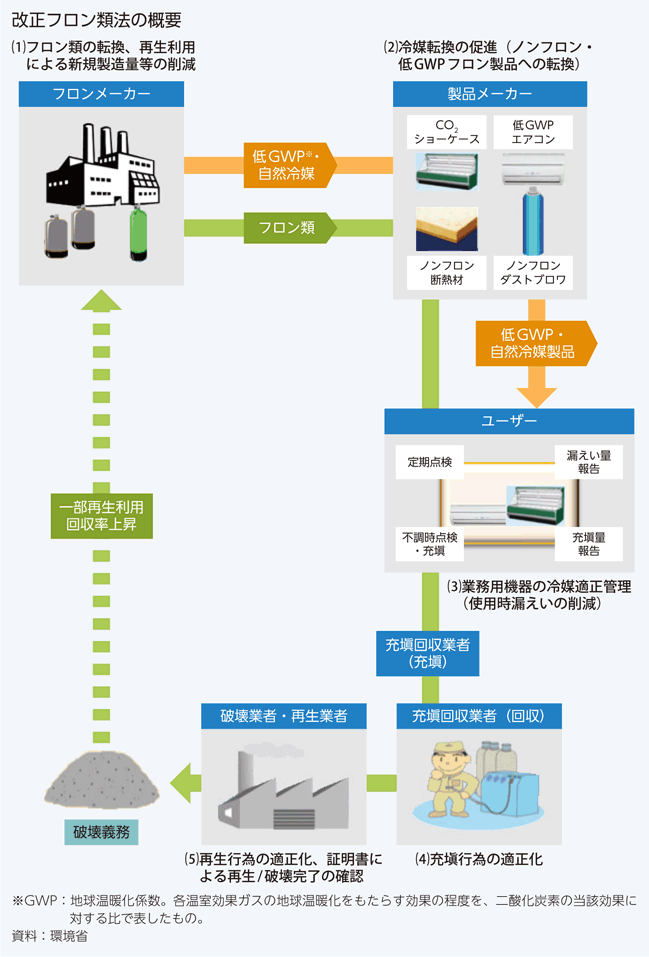
イ 低炭素な移動・輸送
一人が1km移動する時のCO2排出量は、マイカーでは170g、バスでは51g、鉄道では21g、自転車や徒歩は0gと、移動手段により大きく異なります。これからは状況に応じた最適な移動方法を選択することにより、環境負荷を削減する「スマートムーブ(smart move)」が重要です。例えば、公共交通機関が発達している地域では、公共交通機関や徒歩の積極的な利用、そうでない地域では自動車の利用方法の工夫(エコドライブの実践など)や、カーシェアリング、コミュニティサイクルなど、さまざまな手段からベストミックスで地球にやさしい移動を選ぶことが望ましいといえます。
こうした環境負荷の少ない「スマートムーブ」を促進させるため、我が国では平成22年よりウェブサイト上で、「スマートムーブ」の取組などを紹介しています。例えば公共交通機関について、富山市では、今後本格化する人口減少や超高齢社会に対応した持続可能なまちづくりを進めるため、「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を目指しており、鉄道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居住、商業、業務などの都市の諸機能を集積させることにより、車がなくても安心して生活ができる集約型都市構造へと改変を進めています。こうしたまちづくりの中軸として、平成18年に我が国で初めてLRT(Light Rail Transit)という次世代型路面電車を導入した富山ライトレール株式会社が開業しました。LRTは、電気バスや自動車に比べてCO2排出量が少なく、振動が少ないという快適性や、低床式車両の活用による乗降の容易性などの利点を備えているため、自動車からの転換が期待される交通システムです。富山ライトレールは、新駅の設置や運行本数の増加などによって利便性向上と利用者増を図ったことから、平日平均約5,000人の方に利用されており、平成24年には、累計の実利用者が1,000万人を超えました。

また、物流でも低炭素化の取組が進められています。政府は、JR博多駅構内などの消費者が利用しやすい場所に設置した宅配ボックスによる不在時荷物受け取りサービスや、宅配便を行う集配車への電気自動車導入などについて実証するとともに、それぞれのCO2削減の効果等を検証しました。こうした人や物の移動・輸送における低炭素化の取組が、一層進むことが期待されます。
ウ 低炭素な住宅・建築物
暮らしの場となる住宅についても、環境の面から見直そうとする視点が重要です。住宅が建設から建て替えで取り壊されるまでの平均経過年数(住宅の寿命)について日本と欧米を比べると、米国は約67年、英国は約81年であるのに対し、日本は約27年しかありません。これからの住宅は、「つくっては壊す」というフロー消費型から、「いいものをつくって、きちんと手入れして長く大切に使う」というストック型への転換が求められています。
低炭素な住宅・建築物の普及を加速させるため、我が国はエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく住宅・建築物の省エネルギー基準を改正するとともに、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)を制定し、低炭素建築物認定制度を創設しました。本制度により、認定を受けた低炭素建築物は、所得税等の特例が認められるほか、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35Sにより融資金利の引き下げを受けることができます。低炭素建築物に認定されるためには、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)の省エネ基準に比べて、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上になることなどが要件となっており、こうした建築物の低炭素化を誘導する基準を設定することにより、低炭素水準の高い住宅・建築物の普及・拡大が期待されます。
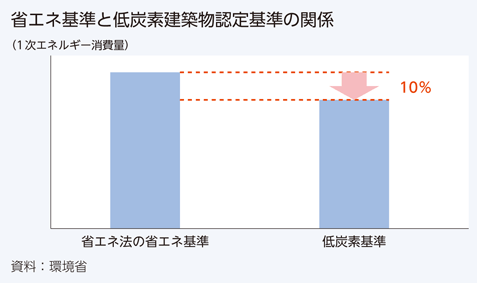
| 目次 | 次ページ |