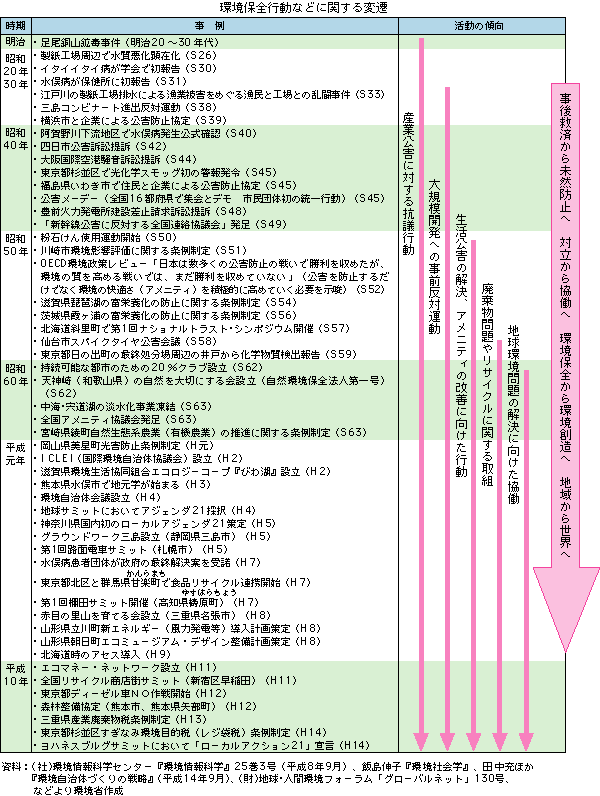1 地域で活発化する環境保全活動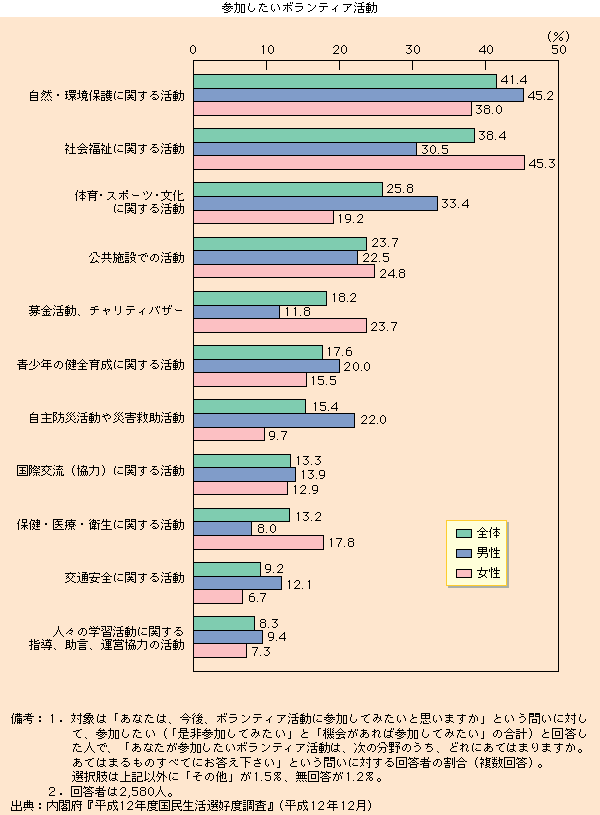
心の豊かさを重視し、社会に貢献したいという意識が高まる中、環境の分野でも、単に日常生活の中での行動を通じて環境の保全に取り組んでいくにとどまらず、ボランティア活動やNPOの活動への参加、町内会や自治会などによる活動への参加などを通じ、より積極的にさまざまな環境保全活動に取り組んでいこうとする動きが拡大の兆しを見せています。こうした環境保全活動は、まず、地域に根ざし自分の周りを良くしていこう、自分の周りで活動しようとする性格のものが多いと考えられます。
一方、事業者や事業者団体、生協、農協等の団体においても、地域社会への関心は高くなっており、自らの事業活動による環境負荷の低減を目指すことはもとより、社会的責任を果たすことが自らの社会的評価を高めることになるという観点などから、環境保全活動に自発的に取り組もうとする例が数多く見られるようになっています。
このように、近年、各主体が地域発の環境保全活動に取り組むことが多くなっています。2 地域における環境保全活動の歴史的変遷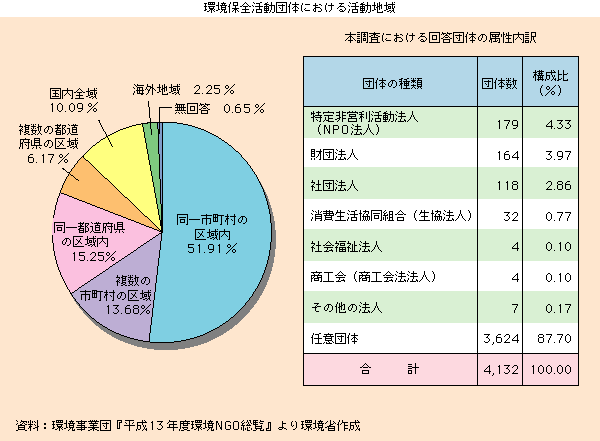
明治中期から昭和初期、鉱害問題などへの対応は、被害者との示談や和解、被害者側の移転等に限られ、限定された地域的な問題として扱われました。
昭和20~40年代、公害の全国的な広がりとともに、個々の地域の反対運動が連携することも見られるようになり、経済成長の一方で抜本的な公害対策が必要であることを日本全体が認識するようになりました。この時代、地方公共団体が国に先駆けて公害防止条例を制定するなど、地域における取組は公害対策における先導的役割を担いました。
都市・生活型公害が顕在化してきた昭和50年代、産業と地域住民の対立の構図が変化し、例えば、琵琶湖周辺における粉石けん使用運動のように、住民が自ら環境に与えている負荷を見直す運動が起こりました。この頃の日本の状況は、公害を防止するだけでなく、地域における環境の快適さ(アメニティ)を積極的に高めていく必要性があるとされました。
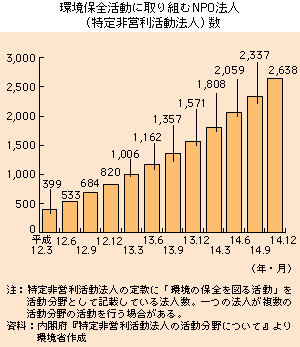 また、この時期、自然環境の破壊に対しては、募金活動等を通じ広く国民の参加を得て保護すべき土地を買い取るなどするイギリス起源のナショナルトラスト活動が行われるようになりました。廃棄物・リサイクル問題や地球環境問題に大きな関心が集まるようになった昭和60年代以降、環境問題の原因や解決策は一人ひとりの生活に直結するものであるため、地域に根ざした自主的な取組が重要との認識が高まるとともに、地域の各主体が一体となった廃棄物・リサイクルへの取組が急増しました。物質循環を媒介とした都市と農村の連携も生まれてきています。また、持続可能な社会の構築に向け、よりよい環境を積極的に打ち出そうとする取組も活発化してきています。
このように、わが国の地域における環境保全の取組の歴史を振り返ると、地域の取組は、わが国全体の環境保全の取組において重要な役割を果たしてきています。
また、この時期、自然環境の破壊に対しては、募金活動等を通じ広く国民の参加を得て保護すべき土地を買い取るなどするイギリス起源のナショナルトラスト活動が行われるようになりました。廃棄物・リサイクル問題や地球環境問題に大きな関心が集まるようになった昭和60年代以降、環境問題の原因や解決策は一人ひとりの生活に直結するものであるため、地域に根ざした自主的な取組が重要との認識が高まるとともに、地域の各主体が一体となった廃棄物・リサイクルへの取組が急増しました。物質循環を媒介とした都市と農村の連携も生まれてきています。また、持続可能な社会の構築に向け、よりよい環境を積極的に打ち出そうとする取組も活発化してきています。
このように、わが国の地域における環境保全の取組の歴史を振り返ると、地域の取組は、わが国全体の環境保全の取組において重要な役割を果たしてきています。
3 国際的にも求められる地域での取組(「ローカルアジェンダ」から「ローカルアクション」へ)
1992年(平成4年)の地球サミットで合意されたアジェンダ21は、地方公共団体に対し、持続可能な社会づくりのための行動計画としてローカルアジェンダ21の策定を求めています。2002年(平成14年)のヨハネスブルグサミットでは、このローカルアジェンダ21で進められてきた取組をより具体的な行動に移していくことなどを目的とする「ローカルアクション21」を推進していくことが宣言されました。このように、国際的にも、地域という、より一人ひとりに身近なレベルでの実際の行動を行っていくことの重要性が認識されています。