図で見る環境白書
序節 人口・経済社会活動の動向と物質・エネルギー循環にみる環境
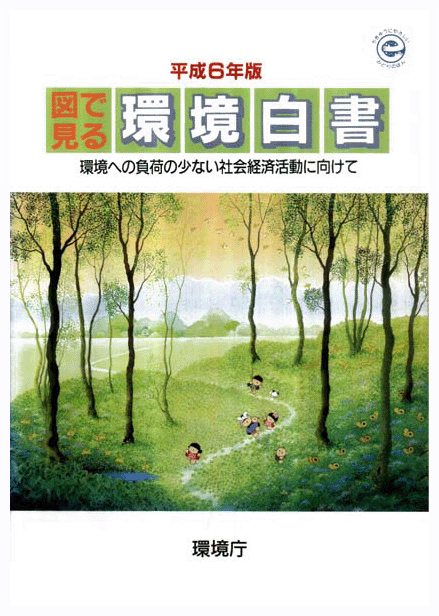
表紙の絵は、民話絵作家、池原昭治さんが環境月間のために描いた作品です。子供や動物たちが雑木林の中で躍動する風景に託して、生命の基盤である環境の大切さを訴えています。
読者の皆様へ
この小冊子は、去る5月31日に閣議決定の上公表された平成6年版環境白書の総説をもとにしています。その内容をやさしくかいつまみ、また、新しい出来事や写真なども加え、多くの方に親しんでいただけるよう、環境庁で新しく編集し直したものです。
毎年の白書は、主に前年度の出来事を報告していますが、平成5年度は、我が国の環境行政にとってまさに新たな出発の年となりました。地球化時代の新たな理念や政策を盛り込んだ環境基本法が同年11月に成立し施行されたのです。
人類が地球上に誕生してから百万年余が経過したといわれていますが、この長い歴史の中で見ると、今日の私達の生活様式や産業活動はけっしてありふれたものではなく、極めて特異な時代的特徴を持っています。それは、有史以来もっとも多量の資源やエネルギーなどの使用に支えられ、しかもその使用の増加の速さが歴史的に見て未曾有の水準にあり、限界が見えつつあること、そして何よりも、このような生活様式や産業活動によって地球規模での環境問題が引き起こされていることが明らかになってきていることです。
環境基本法では、環境への負荷の少ない接続的発展が可能な社会を構築することが理念の一つに掲げられています。このような現代の経済社会を私達はどのようにして実現していくことができるのでしょうか。
今年の白書では、このような問題意識に立って、今後の社会経済の変革の鍵となると考えられる私達の消費行動を中心とした生活文化とそれを支える産業界の動きについて焦点を当てて考察しています。また、環境投資と経済とが、長期的、短期的にどのような関係にあるかを分析しています。さらに、接続可能な経済社会の構築に向けた社会の様々な分野の努力を適切に噛み合わせるための様々な環境政策について述べています。
この冊子が読者の皆様一人ひとりの環境保全に向けた具体的な活動への一助となることを願っております。
序節 人口・経済社会活動の動向と物質・エネルギー循環にみる環境
1 人口・経済社会活動の趨勢
人類は、自然界から食べ物、薪、石油などの資源を採取して、それを消費し、ごみなどの不用になった物を自然界に排出してきました。自然の生態系には、食物連鎖に代表される循環の仕組みがあります。人間の活動が小さかった時代には、資源の採取も不用になった物の排出も、この自然の循環の営みへの影響はわずかでした。しかし、人類の活動が巨大になった今日では、資源の採取により森林などが減少し、不用となった物の排出として、大気中の二酸化炭素濃度が上昇するといった問題が起こり、地球の環境には、限りがあるということが明らかとなってきました。人口
環境問題に関連の深い人口と社会経済活動の長期的な動きを見てみると、いずれも今世紀に入って急激に増加しています。
これを地域的にみると、先進国では人口が安定し成熟化に向かいつつありますが、既に二酸化炭素などの環境への負荷は巨大な水準に逹しており、また、緩やかな伸びでも増加する負荷の量は大きなものとなる状況にあります。一方、開発途上国では、一人当たりの環境への負荷は低いものの、人口の爆発的増加を背景に環境への負荷の拡大が続いてます。
世界の人口は、今世紀に入って急激に増加し、1900年の16.5億人から1990年には53億人に増加しています。国連の中位推計によれば、2050年には100億人に達するものと考えられています。人口の増加率は貧しい国ほど高く、貧困による環境破壊を加速させる結果となっています。また、世界人口が増大する一方で、都市の人口が世界人口に占める割合が増加しており、21世紀の初めには世界人口の半分が都市に住むようになると考えられています。開発途上国の大都市においては、下水道や道路などの整備が進まないまま人口が爆発的に増大しており、その多くが深刻な環境問題を抱えています。
世界人口の推移と予測
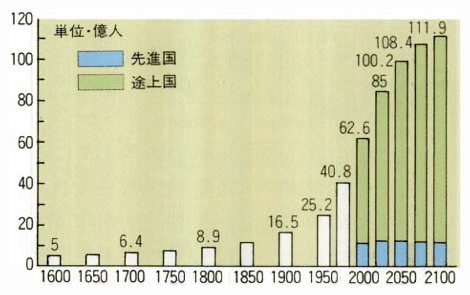
(備考)1. 国連「WORLD POPULATION PROJECTION(1992)」
厚生省「人口統計資料集」等より環境庁作成
2. 2000年以降の数値は中位推計
世界の都市人口比率の推移と将来予測
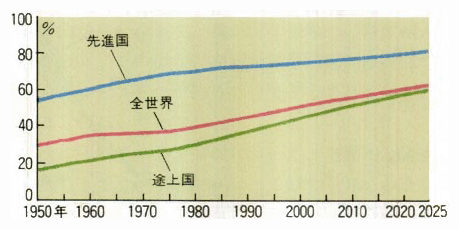
(備考)United Nations(1990) World Urbanization Prospects 1990
一人当たりGDPの推移と予測
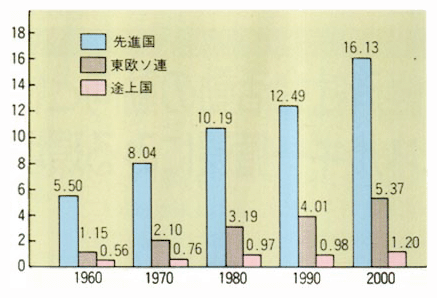
(備考)1.国連「2000年の世界」より環境庁作成
2.2000年の数値は基準シナリオに基づく予測値
3.1980年のドル価格と為替レートによる。
経済規模
世界の総生産は、1950年から1990年の間にほぼ5倍となりました。一人当たりで見てみると、人口増加が大きかったので、その間の伸びは2.3倍になります。一方、一人当たりの所得には世界的に大きな格差が存在しており、1990年には、先進国と途上国の間で12.7倍の開きが生じています。
長期の世界一次エネルギー供給の推移
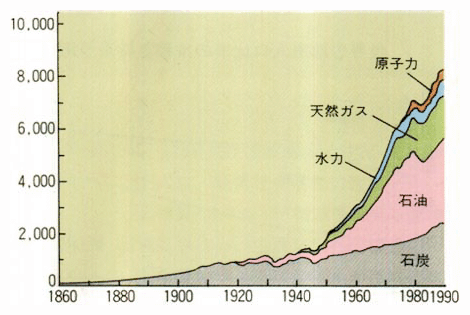
(備考)資源エネルギー庁「エネルギー政策の歩みと展望」
エネルギー
世界の一次エネルギー供給量は、第二次大戦後、中東における大油田の発見とそれに伴う石油価格の低下に支えられて急激に増加しましたが、石油危機による石油価格の高騰に伴って伸びが鈍化しました。しかし、近年再び価格が下がったため供給量が伸びています。また、一人当たりのエネルギー消費量については、1990年現在で先進国と開発途上国の間で9倍の格差があります。
我が国の一次エネルギー供給量の推移と目標
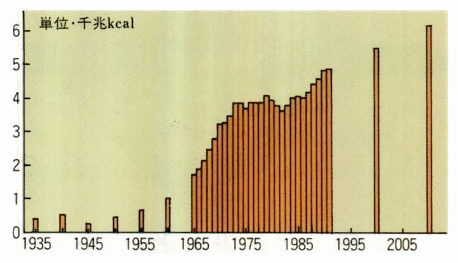
(備考)「日本の100年」、「日本国勢図会」及び「エネルギー需給見通し」より環境庁作成。
世界の肥料使用量の推移
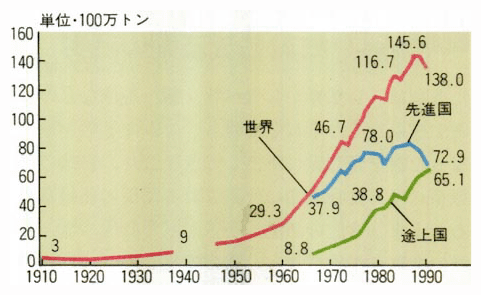
(備考)FAO「FERTILIZER(1961)」、「ANNUAL FERTILIZER REVIEW(1972)」、「yearbook FERTILIZER(1992)」より環境庁作成。
農林水産物
農林水産業は、人類の生存にとって最も重要な活動の一つですが、一方で、開墾や肥料の使用等により環境に対する負荷も与えています。
世界の農業生産が増加する一方で、肥料の使用量も、第二次大戦後急増しています。また、世界の森林面積は、開発途上国を中心に減少を続けています。海洋からの総漁獲量は1989年で頭を打っています。そして、FAOの予測によれば、今のままの漁業活動が続けば、大きな伸びは期待できないとされています。
世界の総漁獲量(1950~1992)海洋及び淡水
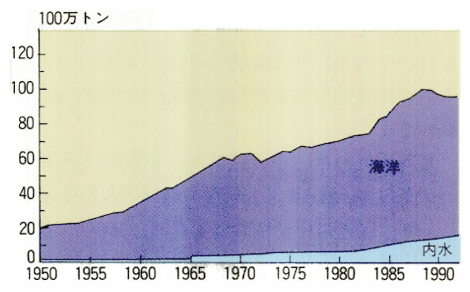
(備考)FAO「農業:2010年に向けて」
2 物質・エネルギー循環等に見る環境負荷の現状と課題
経済活動の進展と物質・エネルギー循環等の視角
我が国は、その経済活動に伴い、自然界から鉱物資源や生物資源などの資源を大量に採取し、利用した後、排水、排気ガス、ごみなどの不用物として再び自然界に排出しています。我が国の経済活動に係わる物質の流れを総合的に計算した物質収支(マテリアル・バランス)を見ると平成4年度には、合計で約23億3千万トンの物質が新たに我が国の経済活動に投入されました。この結果、約7億9千万トンの不用物が排出され、約9千万トンの製品が輸出され、残り約12億4千万トンは建築物や耐久消費財として蓄積されています。再生資源として再び投入に回されたのは約2億トンでした。
我の国の経済活動に伴う資源採取量と不用物排出量は一貫して増え続けており、これによる環境への負荷は増加し続けています。我が国の経済を環境への負荷の小さなものとしていくためには、資源の採取と不用物の排出の質を自然の生態系に適合したものとしていくとともに、それらの量そのものを減らすことが必要となっているのです。
我が国のマテリアル・バランス(物質収支)
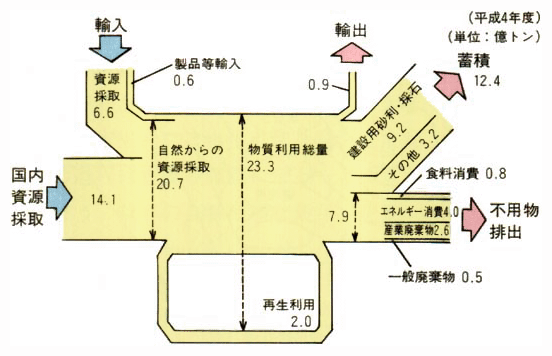
(備考)1.各種統計の更新に伴い、平成5年版環境白書に掲載したマテリアル・バランスから数値を更新している。
2.各種統計より環境庁試算。
窒素の循環等
窒素は、タンパク質などの構成元素の一つとして生命現象を支えていますが、その循環のシステムは自然界において長い時間をかけて成立したもので、人類もその延長上において生存が可能となっているのです。
地球を巡る窒素の存在量とフロー量
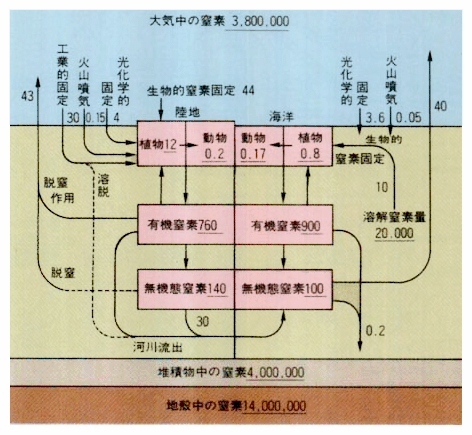
(備考)単位:百万tN/年、_は、10億tN/年:Delwiche, Scientific American, 1970より。
国家間での貿易を通しての窒素の移動を食料貿易に代表させて概観すると、アメリカ大陸から世界各国に向けてきわめて多くの窒素が移動している傾向が見られます。我が国は世界一の窒素輸入国であり、このように窒素循環を国家間の視点でとらえると、それが極めて片寄りのあるものであることがわかります。
次に国内での窒素循環について、先駆的な研究事例として、オランダにおける研究を見てみましょう。窒素は、工業固定(肥料)、飼料や食料の輸入及び河川等により国土に流入します。これに対して、食料等の輸出、河川・海への排出などにより国土から流出していると考えられます。1990年にオランダでは、差引で745百万キログラムが国土に蓄積されている勘定になります。
私達は、大気中の窒素を固定し肥料等として利用している他、化石燃料等の燃焼に伴って生じる窒素酸化物を環境中に放出していますが、これに伴い、種々の環境問題が引き起こされています。
例えば、化石燃料等の燃焼により、近年、特に大都市地域を中心とする窯素酸化物に係る大気汚染が引き起こされます。また、窒素酸化物は、硫黄酸化物とともに、最終的にはいわゆる酸性雨の原因物質となっています。土壌に負荷された窒素の一部は、下層に浸透し、地下水汚染の問題や湖沼、内湾といった閉鎖性水域等における富栄養化問題などの原因の一つとなっています。
オランダにおける窒素のフローチャート、1990年
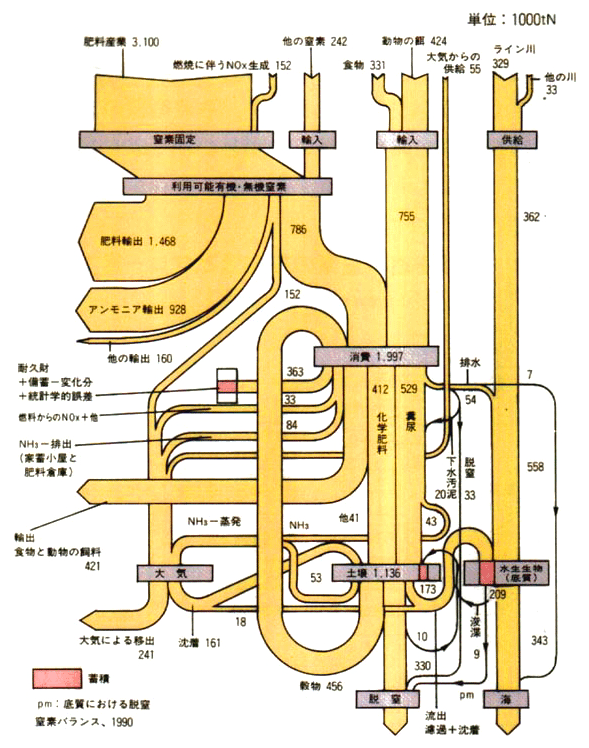
これまで、地球規模から国内にいたる窒素の循環をみましたが、様々な場面で著しい片寄りが生じ、各種の環境問題が引き起こされていることが示されました。窒素及びその化合物の局地的な遍在等に起因する環境負荷を低減するため、それらの循環全体を視野に入れた各種の対策を検討することが有効であるといえましょう。
エネルギーの循環等
図に見るように入射したエネルギーのうち30は雲などによって直接反射され、地表から放射されたエネルギーは、雲等によってとらえられ、その大部分が地表に向かって再放射されています。全世界で一年間に消費するエネルギーは、約7.13×1016キロカロリーであると言われていますが、このエネルギー消費は地球の複雑で精妙なメカニズムに作用しているのです。
地球のエネルギーバランス
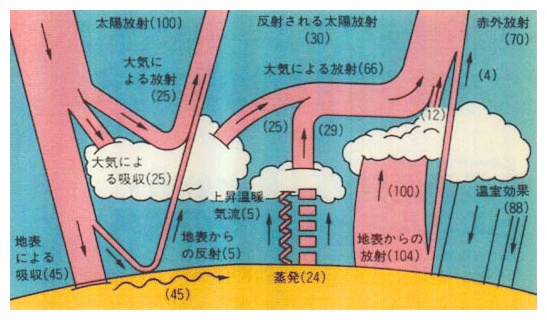
(備考)S. H. Schneider, Climate Modeling.Scientific American 256:5.72-80, 1987
世界の一次エネルギーの動向を見ると、例えば北米では、1906MTOE(石油換算百万トン)の一次エネルギーを生産し、2116MTOEの消費を行っています。人ロ一人当たりの消費量では、7.64TOE(石油換算トン)と群を抜いています。我が国は、69MTOEの生産に対して、428MTOEの消費と生産に比べ消費が圧倒的に大きく、人ロ一人当たりのエネルギー消費量は、3.45TOEと途上国と比べ高水準です。このように、エネルギーの生産と消費の間、また一人当たりの消費量には著しい片寄りがあることがわかります。
次に我が国のエネルギーの利用の状況をエネルギーフローで見てみましょう。エネルギーロスは、発電用では、62.5%、民生用では41.1%、運輸用では75%、産業用では40%となっています。一次投入エネルギーのうち有効に利用されているのは34%に過ぎず66%が排熱の形で直接環境中に捨てられています。
我が国におけるエネルギー供給・消費のフローチャート
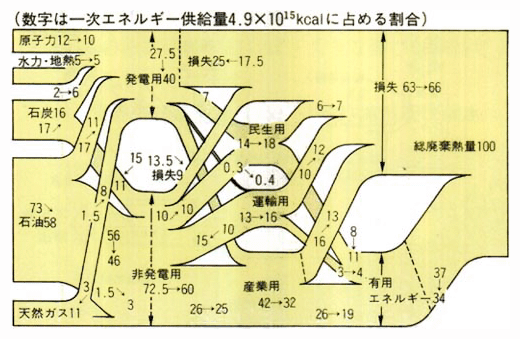
(備考)東京大学平田賢名誉教授作成 (1975年度)→(1992年度)
エネルギーの利用に伴って、各種の環境負荷が生じ、環境汚染問題を引き起こしています。石炭や石油の燃焼に伴い発生するばいじん(黒煙、すす)、高温燃焼等により発生する窒素酸化物、燃料の不完全燃焼に伴い発生する一酸化炭素、あるいは光化学オキシダント等による大気汚染などが考えられます。また、硫黄酸化物や窒素酸化物は、酸性雨の原因物質の一つとされています。地球温暖化との関係では、私達が排出する温室効果ガスの内、46%がエネルギー関連であるとの推計があります。
エネルギーを有効に活用するためには、熱を高温から低温まで効果的に利用することが必要です。高温の熱は熱機関で動力化し、温度を下げて排出された熱を熱として用いるといういわば直列的なエネルギーの利用が、熱エネルギーの合理的な使い方の第一歩といえます。
コージェネレーション・システムとは、燃焼により発生する熱の高温部から発電などに用いられる動力を、また動力がつくられる際の排熱等から熱を同時に取り出すものであり、一次エネルギーの70%から80%を利用することが可能といわれています。また、ごみ焼却余熱を有効に活用しうるものとしてごみ発電があります。特に他の熱機関を利用したごみ発電の高効率化のシステムを「スーパーごみ発電」と称しています。地方公共団体においてこのスーパーごみ発電を実施することにより一層の未利用エネルギーの有効活用を図ることが可能となるでしょう。
森林資源の循環等
森林資源は、地球上の熱収支、水収支に深い関わりを持ち、地球の環境を生物の生息に適した状態に保つとともに、野生生物に生息地を提供し、水源をかん養し、また、我々に木材を供給するなど多面的な価値を持つ自然資源といえます。森林資源は本来的には再生可能な資源ですが、この再生の過程は資源の循環になぞらえることができましょう。世界の森林面積は近年、先進国ではほとんど変化していないのに対し、途上国ではその減少が著しい状況にあります。特に、熱帯地域での森林減少の原因については、1)非伝統的な焼畑耕作、2)過度の薪炭材採取、3)不適切な商業伐採、4)過放牧等が指摘されています。木材に関する我が国と世界との関わりについて、我が国の用材供給の現状を見ると、約4分の3を外材に依存しています。
世界の森林面積の推移
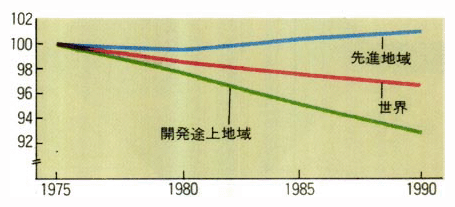
(備考)1.FAO「Yearbook Production」(1991)より作成。
2.森林面積には自然林、人工林の他植林予定の伐採跡地が含まれている。
我が国における木材供給の状況(平成4年)
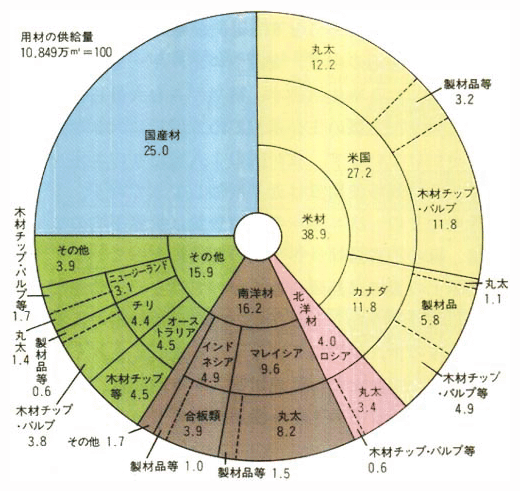
(備考)1.丸太以外については、丸太材積に換算したものである。
2.合計と内訳の計が一致しないのは、四捨五入による。
3.平成5年度「林業白書」より
森林の減少に伴って、地域レベルから地球レベルに至る環境への影響が懸念されています。まず、一地域の木材資源への過重な依存は、地域的な環境悪化を招く可能性もあります。また、地球規模での影響として、生態系への影響、土壌に対する劣化、地球温暖化への影響などが考えられます。この他、現在の木材の利用形態の中には、環境への影響が懸念される一面もあります。
森林資源の循環を確保するためには、まず、森林の保全と持続可能な経営が大切です。次に、木材の有効利用により、森林の循環の確保に貢献することもできましょう。
第1節 環境にやさしい生活文化への模索
1 今日のライフスタイルが環境に与える負荷
日本に住む私達の生活は、近年、大変便利で物質的に豊かなものになりました。その一方、私達は日々の生活の中で、資源やエネルギーを大量に消費し、ごみや生活排水、排気ガスを大量に排出しており、人類の生存基盤である環境に大きな負荷をかけています。我が国の1人当たりのエネルギーや物質の使用量は近年増加してきており、1人当たりの一次エネルギー消費量は世界平均の2倍、紙の消費量は世界平均の5倍に上っています。地球上の資源は無限にあるわけではなく、私達だけで使い尽くしてしまうと、世界の他の国の人々や将来の世代が利用できなくなってしまうおそれがあります。また、私達が購入する商品は、私達の手に届くまでの生産・流通段階でも、工場からの排水や輸送用トラックからの排気ガスなど様々な環境負荷を与えていますが、間接的にこうした負荷が増加する可能性もあります。さらに、私達の生活からも、直接的に様々な環境への負荷が生じています。まず、近年、照明や電気機器、自動車等のためのエネルギー使用の増加に伴って、二酸化炭素排出量が増加しています。この背景には、技術によってテレビや冷蔵庫などの電気製品等一台一台の省エネルギー化が進んでいるにも関わらず、私逹が大型、高級でエネルギー使用量の大きい電気製品や自動車を選択し、一家に複数保有し使用するなど消費形態が変化してきたことがあります。また、自動車利用が増加している背景には、買物やレジャーなどで自動車を利用する人が増えていることとともに、地価の高騰等で市街地がスプロール的に広がり、鉄道など公共輸送機関のサービス水準が低い郊外に居住する人が増加しているという変化があります。
ライフスタイルと環境負荷
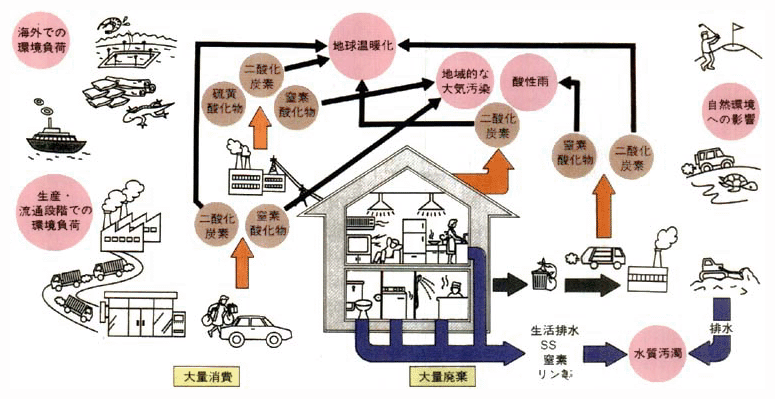
1人当たり物質、エネルギー等消費の推移
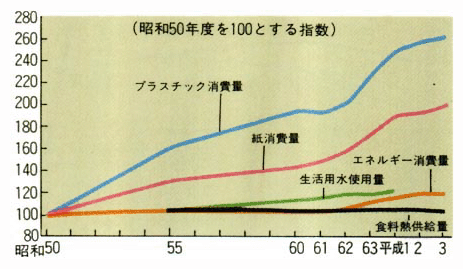
(備考)「総合エネルギー統計」、「日本の水資源」、「農業白書」、「紙・パルプ統計」、日本プラスチック工業連盟資料等より作成
家庭からの用途別二酸化炭素排出量
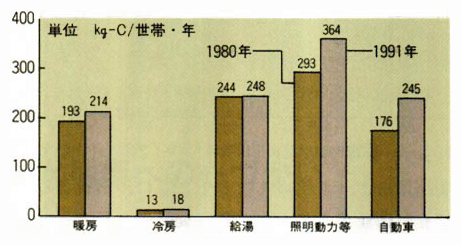
(備考)環境庁推計
家庭からのごみの排出量も近年増加の一途をたどっており、特に、私逹のライフスタイルの変化を反映して、時間と手間を節約できる使い捨て商品、容器・包装類、飽食の時代を象徴する食べ残しなどが増加しています。
水まわりに目を向けて見ると、台所で使用される調味料や油は水を汚す大きな要因となります。また、清潔志向が高まり、「朝シャン」する人が増えたり、洗濯回数が増加したりしていますが、洗剤やシャンプーも水を汚す要因の一つです。こうした家庭からの生活排水は、東京湾では、有機物による水質汚濁の原因の69%を占めています。
さらに、自由時間が増加し、レジャー活動が活発になってきていますが、環境に十分な配慮がなされない場合には、ゴルフ場などレジャー活動のための施設整備が自然環境に影響を与えることが心配されています。また、休暇の取りやすい時期に一部の有名観光地に観光客が集中することや、レジャー用の四輪駆動車やモーターボートの利用が自然環境に影響を及ぼすこともあります。
このように、私達のライフスタイルは環境に大きな負荷を与えており、多くの国民は現在のライフスタイルを環境にやさしいものへと変更していく必要性があると認識してきています。ところが、環境先進国と言われるドイツと比べてみると、例えば、自動車の排気ガスが環境に悪いことは分かっているものの実際に車の利用を控えている人は少ないなど、まだ認識と行動が一致していない傾向が見られます。さらに、我が国では、環境保護団体への参加や寄付といった積極的な行動については、まだためらう人が多いようです。
家庭ごみの組成(1人1日当たり排出量)
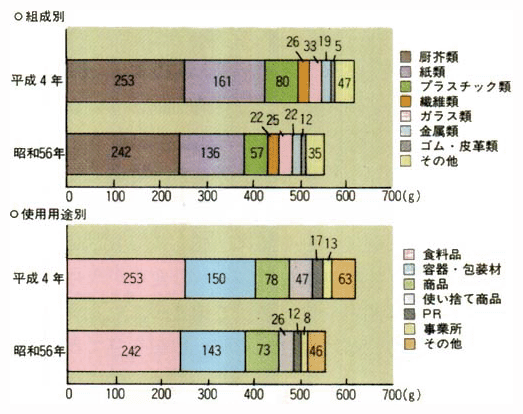
(備考)京都市清掃局資料より作成
自動車利用に関する認識と行動
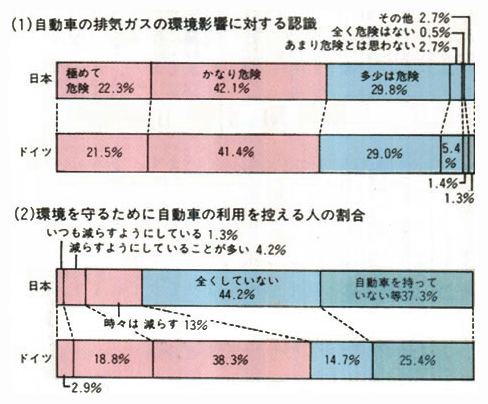
(備考)ISSP調査
環境保護団体への参加と寄付の状況
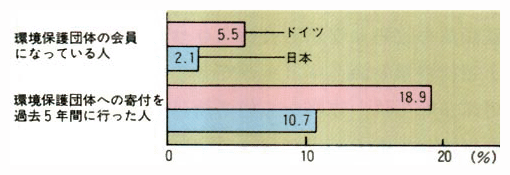
(備考)ISSP調査
2 ライフスタイルの新しい風
私達の生活が環境に大きな負荷をかけていることを見てきましたが、こうした生活を見直そうという取組が世界中で始まっています。特に、先進国の消費者は、大量消費、大量廃棄型の消費生活から、環境に配慮した商品を選び、長持ちさせて使うという「持続可能な消費」への変革が求められています。国内や世界各国で始まっているライフスタイルの変革に向けた新しい取組を見てみましょう。買い物の時の環境への心づかい
使い捨て商品を買わない、詰め替え可能商品やエコマーク商品を買うなど、環境に配慮した商品を選ぶ人が主婦を中心に増えてきており、メーカーの環境にやさしい商品づくりを支えています。また、消費者とメーカーが直結した有機農産物などの共同購入活動も活発化しています。さらに、先進国の消費者が、途上国の農産物や伝統工芸品を通常の国際取引価格より直接高く買い取り、途上国の人々の持続可能な開発を助ける「フェアトレード」が先進各国で盛んになってきています。
不用物の排出を減らす
不用物の排出量を減らすためには、まず要らないものの量を少なくすること(Reduce)、繰り返し再利用すること(Reuse)、さらに再生利用すること(Recycle)という3つの方法が重要です。例えば商品を修理しながら長持ちさせて使うことで、不用物の量を減らすことができます。また、再利用については、家庭からの不用品を交換するフリーマーケットが盛んになっています。昔からある飲料や食料品のビンの再利用システムも再評価され、欧州諸国では積極的に活用されています。さらに、缶、紙、ガラスビンなどのリサイクルは、地方公共団体の回収、住民の集団回収、事業者の回収などで活発化しています。
エネルギー消費を減らす
家庭でのエネルギー消費に伴う二酸化炭素排出量するための環境家計簿の作成といった取組が民間団体によって始められるとともに、消費者の間でも、消費電力の少ない電気製品や燃費のよい自動車を選びたいという意識の変化が見られます。国立環境研究所の試算によれば、家庭でのエネルギーや自動車の使用による二酸化炭素排出量は、何もしない場合には2010年に1990年の排出量(6460万t)の約1.4倍に増加してしまうと予想されますが、長期的な視点に立った断熱材やソーラーシステムの導入、より小型の車の選択など、次頁の下の図の全ての取組が行われた場合には1.1倍程度に押さえることができます。
商品購入における環境配慮
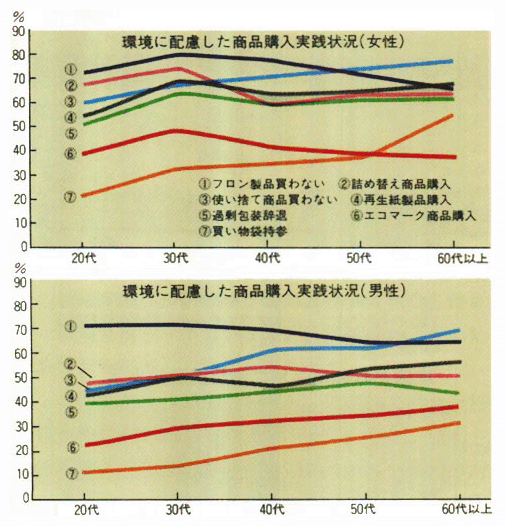
(備考)ニッセイ基礎研究所「都市生活者のエコライフ調査」(平成5年)
中古品・不要品の交換・売買利用意向
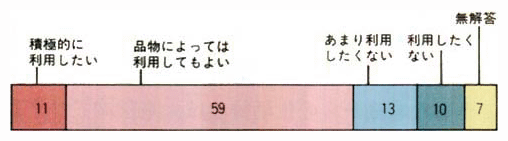
わが国のリサイクル率の推移
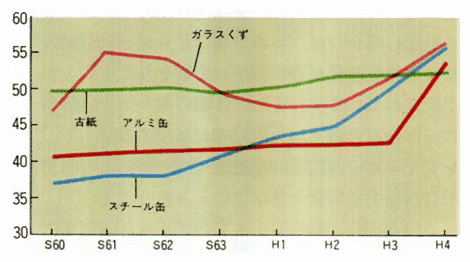
(備考)あき缶処理対策協会、アルミ缶リサイクリング協会
ガラスびんリサイクリング推進連合、古紙・パルプ統計より作成
家庭からの二酸化炭素排出量削減効果
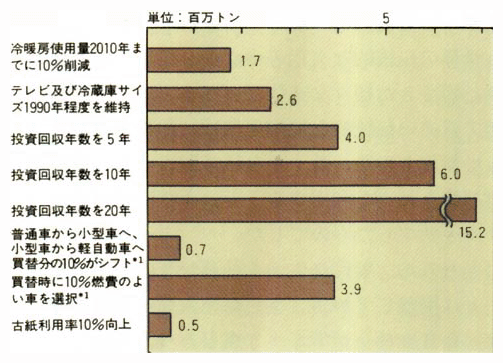
(備考)2010年における削減効果 *1平成7年から実施
国立環境研究所推計
水循環への心づかい
流しへの水切りゴミ袋の設置、廃食用油の適正処理、洗剤の適量使用など家庭内での工夫で、水質汚濁負荷を2割から3割、最大5割削減した例が地方公共団体から報告されています。また、煮汁の再利用など環境にやさしい「エコクッキング」の講習会も各地で行われています。
自然と共生したレジャー活動
レジャー活動は、スキー場やゴルフ場などの大規模な利用施設整備のために自然環境が改変される場合がありますが、クロスカントリースキーやネイチャーゲームなどこうした大規模な施設を必要としない自然のフィールドでのレジャーを楽しむ活動が行われています。また、環境への負荷が小さく、より深く自然とふれあう観光として「エコツーリズム」への関心が高まってきています。
行動を阻害している原因は?
このように環境にやさしいライフスタイルが徐々に広がってきていますが、環境を保全しようという気持ちはあっても行動に結びついていない人もまだ多いのです。その原因は何でしょうか。
環境にやさしい行動を阻害しているのは、第1に、一人ひとりが具体的に何をすればよいのか、自分一人の行動にどれだけ効果があるのかという点について情報が不足していることです。そこで消費者への普及啓発、環境保護商品の表示・広告の適正化、企業からの適切な情報提供、環境に配慮した商品を示すエコラベルの果たす役割が重要になっています。
環境に配慮した行動を行っている理由
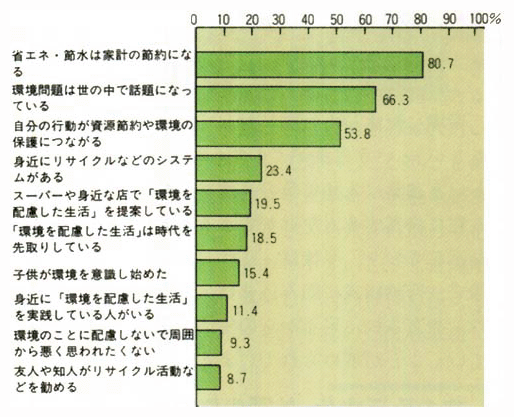
環境に配慮した行動を行っていない理由
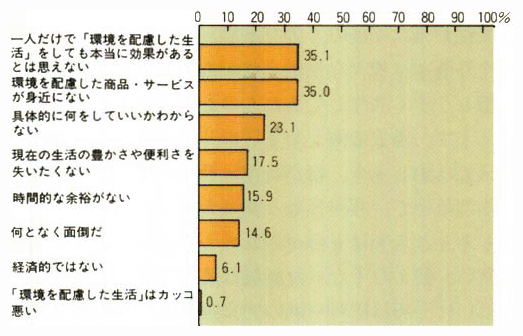
(備考)ニッセイ基礎研究所「都市生活者のエコライフ調査」(平成5年)
第2に、環境にやさしい商品やサービスが身近にない、あるいはリサイクルを行おうと思っても身近にそうした仕組みがないといった原因もあります。こうした要因については、消費者だけでなく、生産者たる企業や行政が協力していくことが重要です。
第3に、経済的に得になる行為は人々の行動を促しますが、逆に経済的でない行動はしたくないという人もいます。このため、ごみの排出量に応じた有料化や空き缶のデポジットシステム、ソーラーシステム導入のための融資制度など、環境にやさしい行動が経済的にも得になるようにして、人々の行動を促す仕組みが注目されています。
3 環境にやさしい生活文化への模索
環境に配慮した行動に対して、近年、「環境にやさしい」という言葉がよく使われます。「やさしい」という言葉は大和言葉の「痩す」が語源で、痩せる程に自省する人だけができる他者への思いやりを示しており、今後は、こうしたやさしさが生活様式、行動様式に組み込まれ、人々の間で伝播され、共有され、足下からの生活文化として定着していくことが求められています。昔の生活文化、外国の伝統的生活文化
私達は大量消費、大量廃棄型の現代日本の生活文化が当たり前のものだと思っていますが、過去や外国には様々な生活文化があり、その中には環境とうまく共生してきたものもあります。
まず、過去の例として江戸時代の生活の文化を見てみましょう。江戸時代は約230年に及ぶ鎖国体制の中で、利用できる資源も限られていたこともあり、人々はものが壊れても徹底的に修理して使い、使えなくなった紙屑は集めて漉返紙(再生紙)に、灰は肥料や酒のアク抜きに、糞尿を肥料に再生利用していました。熊やサケなどの生物資源については、繁殖期の捕獲をタブーとして禁じたり、神様からの授かりものとして捕り尽くしてしまわないよう守ってきた地域もありました。また、土地開発の際の環境配慮は今日でも重要な課題ですが、既に18世紀の沖縄の農業書「農務帳」には、農地を開墾する際に赤土を流出させないための工夫が記されるなど、山・川・海という一つながりの生態系への配慮がなされていました。
江戸および初期東京のエコシステム(概念図)
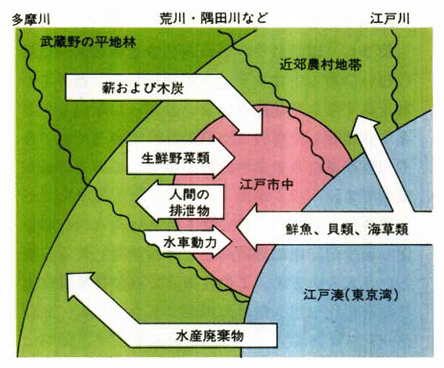
(備考)玉野井芳郎・室田 武・槌田 敦「永住する豊かさの条件」(S.クマール編『シュマッハーの学校』所収)
世界の伝統的な文化の中でも、環境との共生を成し得てきた様々な文化があります。例えば、東南アジアの伝統的な焼畑農業は、熱帯林を焼き払って耕作した後、数十年を経て回復した二次林を再び焼き払って利用する、という植物遷移のサイクルと共生したものでした。
もちろん、現代に生きる私達が昔の生活に戻ることは困難ですが、こうした先人達の知恵の中には、今日の社会が学ぶべき点もあります。
特に、人々が日々の経験と観察から、自然の循環や生態系のメカニズムをよく知り、環境を総合的に把握していた点、自然と共生しながら利用していく環境観を持っていた点です。先人達が守ってきた1)自然のサイクルに合わせた長い時間をかけて、2)適正に管理し、3)自然資源を使い尽くさないで、4)感謝の気持ちを込めて、5)必要なものを必要なだけ適切に使うという5つの共生の精神は、皆が環境の恵みを分かちあっていくために、改めて学ぶところが大きいと言えましょう。
また、地域の住民皆が環境保全に参加していた点も重要です。その土地の環境のことを最もよく知っている住民が、地域の環境管理に積極的に参加していくことは今日でも必要でしょう。
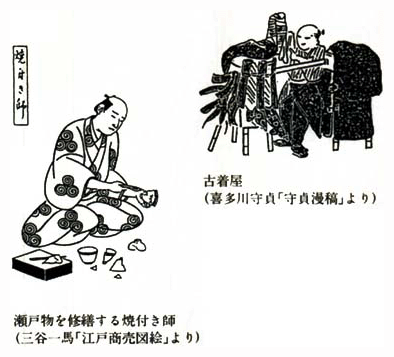
新たな環境観と規範の形成
現代の世界でも環境と共生する新しい環境観が生まれてきています。オゾン層の破壊や地球温暖化といった地球規模に広がり、将来の世代にも深刻な影響が及ぶ問題が明らかになる中で、国際社会では、将来世代の利益を確保しながら私達の世代のニーズを満たしていく「持続可能な開発」という考え方が打ち出され、これが1992年の「国連環境開発会議(地球サミット)」で全世界の行動原則となりました。
また、これまでの経済性、効率性といった価値判断の基準を環境の観点から再考し、環境と共に生きる人間活動の規範として「環境倫理」を構築しようという考え方が、アメリカの環境保全活動などの中から提唱され、議論が深められています。
こうした中我が国では平成5年11月、環境保全に関する新たな規範として環境基本法が成立しました。環境基本法では、環境の保全についての基本理念として、環境の恵沢の享受と継承、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進という3つを掲げるとともに、社会の各主体の責務を明らかにしています。そして、こうした理念を実現するために、環境基本計画の策定など多様な基本的施策を規定しています。
環境にやさしい生活文化の定着と発展に向けて
人々の環境観の変化と新しい規範の成立は、環境にやさしい生活文化の形成に向けた第一歩ですが、環境にやさしい生活文化が人々の間に定着していくためには、さらに、人々が容易に環境にやさしい行動をとることができるよう、様々な社会的経済的な条件を整備していくことが必要です。
クロスカントリースキーでの雪上観察会

環境にやさしい文化は、現在の大量消費、大量廃棄型の生活文化を見直し、物質的な制約はあるかも知れませんが、季節ごとに自然とのふれあいを楽しむような感性豊かな文化としていくことができます。また、地域のコミュニティ活動や企業と消費者のネットワークなど人と人との関わりをより豊かにするものでもあります。こうした環境にやさしい生活文化を構築し、次の世代に伝えていくことができるかどうか、私達の今後の取組にかかっているのです。
求められる社会的経済的条件
(1)環境についてよく知ること●環境の状況や経済社会活動の的確な把握
●環境指標の整備
●環境に関する学問、研究の充実
●環境保全技術の開発の振興、技術自体の環境にやさしい方向へ転換
(2)人々に知識を広め、活動の輪を広げること
●情報提供システムの構築
●環境教育の充実
●環境保全活動の支援
●政府施策への国民参加
(3)経済システムを変えること
●経済的インセンティブ、ディスインセンティブの活用
(4)社会システムや社会資本を整備すること
●社会ルールの形成
●社会資本の整備と都市構造の変革
熊本県環境センター(環境学習施設)
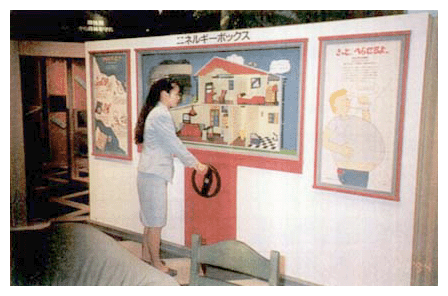
第2節 環境を守ってこそ健全に発展する経済
1 環境保全と経済活動
考え方の変化-対立から統合へ-
世界や日本の人々が、環境が限りあるものであること、そして、人類の存続の基盤である環境を守ることが重要であることに気づく前は、環境を守ろうとする努力は、経済の発展と対立するもの、相容れないものであると捉えがちでした。
しかし、今日、地球環境問題や都市・生活型公害などの環境問題が大きな問題となってきた中で、環境保全と経済成長の関係についての人々の考え方も変化してきました。すなわち環境を守ることなしに健全な経済の発展はありえず、環境への負荷の少ない持続可能な経済社会を作り上げることが大切であると考えるようになってきているのです。
こうした考え方の変化は、企業を中心とする産業界にも広がりつつあります。環境庁の調査(平成5年度環境にやさしい企業行動調査)によると、環境を守る努力を実施していくことを経営の基本方針に定めている企業は年を追って増えています。
環境に関する経営方針の有無
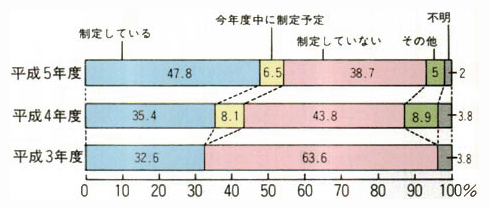
(備考)環境庁
環境への投資がもたらす経済的な効果
1)長期的な影響
環境保全と経済成長の関係についての考え方は、前項で見たように変化しつつありますが、依然として環境を守るために投資することは経済成長の負担であるとする考え方も根強いものがあります。国立環境研究所では、環境保全への投資が経済成長に長期的にどんな影響を与えるかを経済学的なモデルを使って分析してみました。その結集によると、まったく環境保全に投資しない場合は、21世紀半ばには工業生産は急激に落ち込んでしまうが、早いうちから継続的に環境保全へ投資すれば、21世紀後半になっても工業生産を比較的高い水準で安定化させることができることが分かりました。
結果1~環境保全に投資しない場合
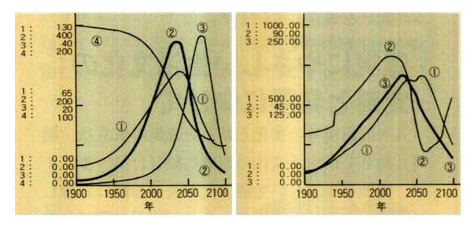
結果2~早いうちから継続的に環境保全へ投資した場合
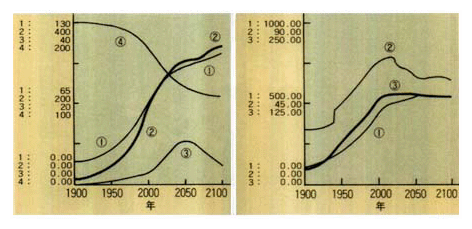
1):人口〔億人〕 1):1人当たりサービス生産〔ドル/年人〕
2):工業生産〔百億ドル/年〕 2):平均寿命〔年〕
3):汚染指数(1970年の汚染量を1とする) 3):1人当たり消費財〔ドル/年人〕
4):資源埋蔵量〔資源埋蔵単位〕
もちろん、この分析は現実の世界を大胆に単純化し、また、様々な前提条件をおいた上での結果であり、現実の世界をそのまま表したものではないことに注意する必要がありますが、将来にわたり環境の制約が考えられる場合には、持続可能な経済社会を作り上げるために、環境保全へ早いうちから投資することが大切であることが示されていると考えられます。
2)短期的な効果
環境保全対策と経済成長の関係については、1)の長期的な影響の他、様々な影響が考えられますが、環境庁では、環境への投資が短期的に経済全体でどれぐらいの生産を引き起こし、また、雇用を誘発するかという点につき、産業連関分析の考え方を用いて分析してみました。
分析結果は図のとおりですが、これによると、ここで取り上げた4つの環境保全事業はいずれも建設部門と同程度の生産や雇用の面での経済波及効果を持っていることが分かりました。さらに、こうした環境保全事業への投資は、近年台頭しつつあるエコビジネス(環境関連産業)の成長にも結びつき、長期的に見れば経済の活性化につながるものです。
環境保全対策の経済波及効果(産業連関)生産誘発額
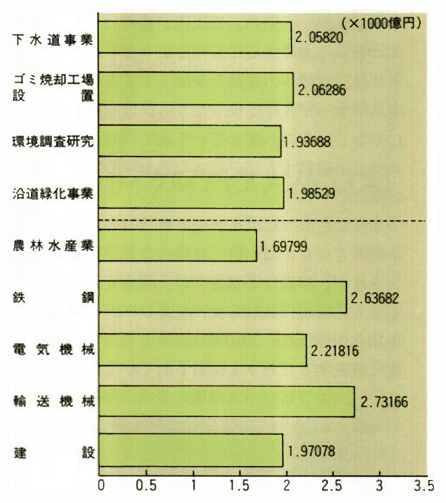
(備考)1.1990年産業連関表(速報)による
2.環境庁
以上のとおり、環境への投資は持続可能な経済社会の構築にとって重要な要素です。環境庁の調査によれば、環境保全予算の全体予算に占める割合が、平成4年度と5年度を比較して増加している企業は37.3%、ほぼ同じが41.0%、減少が12.7%となっています。これは、環境投資をコストアップ要因と位置づけて、長引く経済の低迷を受けて削減を図ろうとしている企業が見られる一方で、環境保全意識の高まりを受けて、現下の不況下でも積極的に環境保全へ投資しようとする企業があることを示しています。
環境保全予算の割合の動向
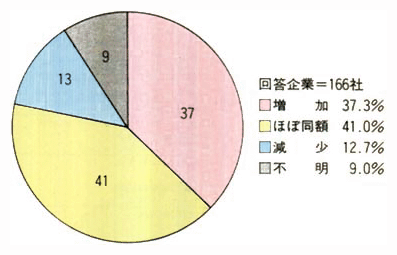
(備考)環境庁
環境保全対策の経済波及効果(産業連関)就業誘発人数
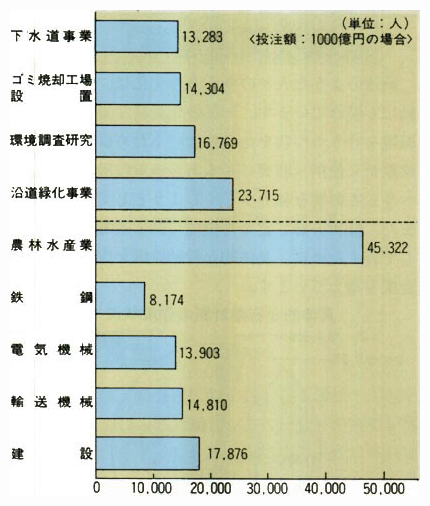
(備考)1.1990年産業連関表(速報)による
2.環境庁
3.但し、1985年産業連関表(雇用表)より推計した係数を利用
エコビジネス分類表
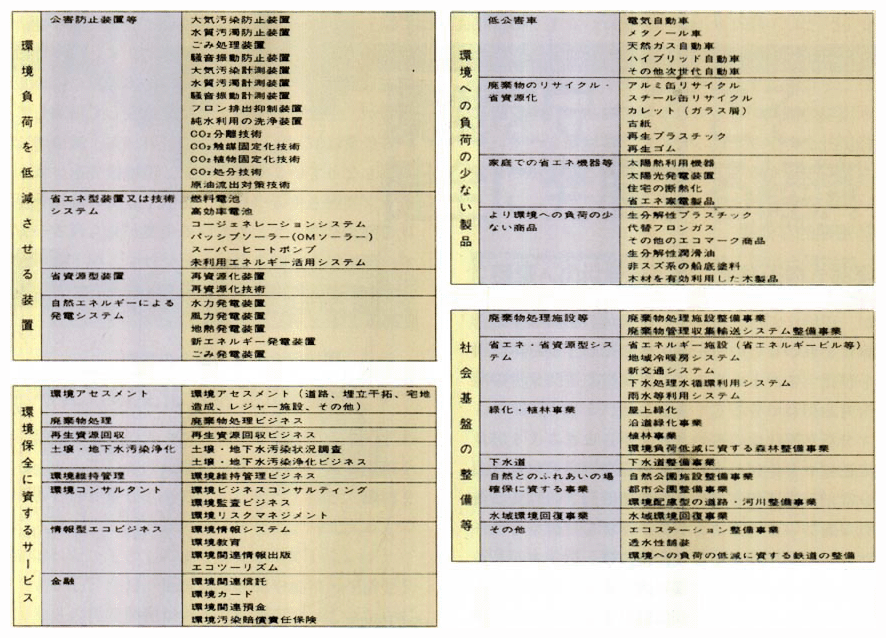
2 エコビジネス(環境関連産業)
前述のような人々の考え方の変化は、企業の行動にも現れています。一部の先進的な企業では、環境を守りつつ物を生産していくために、原料の採取から使用、廃棄に至るあらゆる段階で、環境へ与える影響を極力少なくしようとしています。また、経営方針で定めた環境に関する理念を実現して行くために、具体的な行動計画を作っている企業も増えています。具体的な行動計画の作成状況
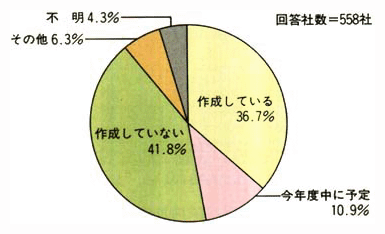
(備考)環境庁
こうした企業による自主的な取組は、建設業や製造業をはじめとして、様々な産業分野にわたっていますが、企業による取組が盛んになることは、エコビジネスの成長にもつながります。エコビジネスは、環境への負荷を少なくすることに役立つ商品やサービスを提供したり、経済や社会を環境にやさしいものへ変えていく上で役立つ技術やシステムを提供するビジネスなどを中心とする幅広い概念です。
こうしたエコビジネスがどれくらいの市場規模を持っているかについては様々な試算がなされていますが、環境庁の試算では、現在定量的に把握できる市場規模は約6兆円で、2000年にはほぼ倍の13兆円程度に、2010年にはさらに倍の26兆円程度に成長するだろうと推計されています。
エコビジネス市場の規模の推計
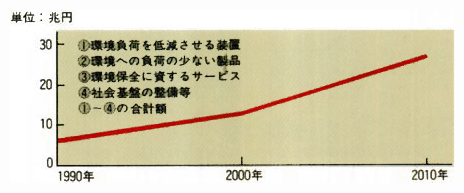
3 意識と行動の一致に向けて
今日の環境問題に対して、様々な立場の人たちがお互いに協力して対策を進めていくことができるよう全体的な枠組みが必要とされています。そうした枠組みのもと、企業や消費者はそれぞれの立場で取り組んでいく必要がありますが、ここでは、企業が今後取り組んで行くべき課題について見てみましょう。自主的な環境管理
企業の自主的な取組において、取り組んでいく体制を明確にし、目標の達成状況や計画の実施状況を定期的に点検しつつ、全体の取組状況を見直していく環境管理は、企業が環境対策を進めていく上で欠かせないものであり、国際的にも標準化に向けて作業が進められています。我が国でも、例えば環境庁から平成5年2月に「環境にやさしい企業行動指針」が公表されるなど企業の自主的な取組を促進するための施策が実施されています。環境管理に関しては、環境庁が実施した調査によれば、環境に関する取組を企業内で定期的に点検(内部監査)していると回答した企業は全体の27.8%を占めていました。また、欧米の一部の先進的な企業で見られる環境関連情報を積極的に開示する動きに関しては、同じく環境庁の調査によれば、報告書を作成し公表していると回答した企業は、全体の6.3%でした。
ライフ・サイクル・アセスメント(LCA)
企業がその活動を根本から環境へやさしいものへと変えて行くための一つの方法として、製品の環境への負荷を極力少なくすることが考えられますが、そのために製品の生産段階から消費、廃棄段階までの全ての段階において環境へ与える負荷を総合的に評価する手法(LCA)が必要となってきます。
LCAについては、国際的にも標準化が進められているところであり、今後、その手法が明確になるにつれて事業活動への適用が普及して行くものと期待されています。
海外進出企業の環境保全への取組
地球環境問題に対する人々の認識が高まりつつある中、海外に多数進出している日系企業の環境保全に向けた行動には、国際的にも国内的にも大きな関心が寄せられています。
環境庁では中国に進出している日系企業を対象として、立地段階での環境配慮、操業上の環境対策、環境対策を進める上での課題、環境対策関係の支出の負担感などについてアンケート調査を行いました。その結果によると、在外日系企業の環境保全に向けての取組は、現状の取組状況についてはある程度の自信を持っていて、また、合弁先との関係も順調ですが、今後の現地政府の取組への対応については、環境対策の負担が重くなることなどの点で若干の不安を持っていると考えられます。
環境対策の目標
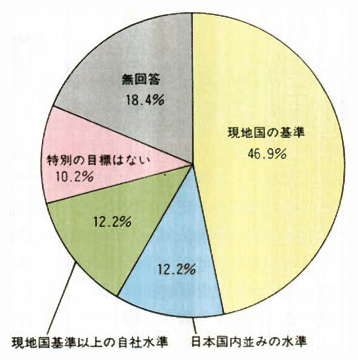
(備考)環境庁
社会貢献
企業には、社会市民の一員として国民一人ひとりに求められるのと同じように社会への貢献が求められています。しかし、環境庁の調査によれば、社会貢献について具体的な目標を設定している企業は多くはなく、企業の積極的な対応が必要となっています。
具体的な目標の内容
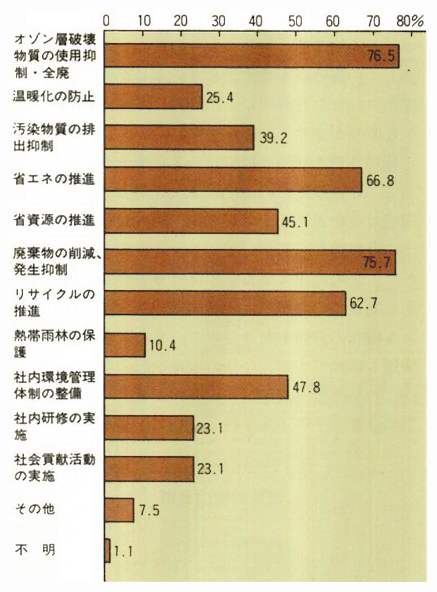
(備考)環境庁
環境保全経費
企業の中には、現下の不況下では環境対策へ投資する余力はないと主張する企業も見られます。企業が効率的に環境への配慮を事業活動に組み込んで行くためには、環境保全にかかる経費の把握は重要です。しかしながら、環境庁の調査によれば環境関連の費用や投資額を他と区別して集計している企業は回答全体企業のうち約3割しかなく、集計している費用の内容も公害防止投資関係及び廃棄物処理費が中心となっていて、環境保全経費の把握は十分なものとは言えない状況です。
この背景には、生産工程の環境への負荷を減らす努力などを含めた幅広い意味での環境保全経費については、集計の範囲や手法が企業にとって明確でないということが考えられます。環境保全のための経費をきちんと把握できてこそ、個々の企業にとっても、社会全体としても費用効果的な環境対策が実行できるわけですから、環境保全経費の把握に向けた今後一層の取組が求められています。
さらに、環境庁の調査によると、一般に企業の規模が小さいほど環境への取組が消極的な傾向がうかがわれます。我々の経済社会を環境への負荷の少ない持続可能な経済社会に変えていくためには、一部の企業だけでなくあらゆる企業が積極的に取り組んでいく必要があります。
具体的な目標の設定状況(売上規模別)
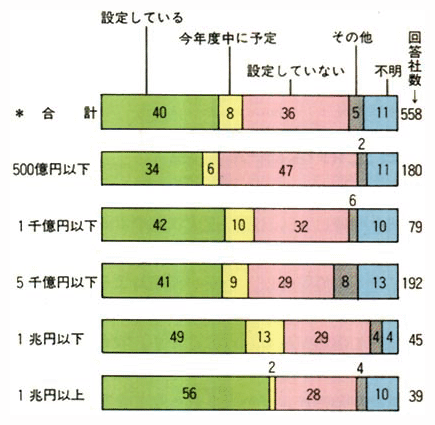
(備考)環境庁
以上のとおり、企業が今後取り組むべき課題は多いわけですが、こうした環境保全対策を実施していくことは、個々の企業にとって必ずしも負担の増加につながることばかりではありません。米国の研究では、生産工程を環境への負荷の少ないものに変える取組の181の例について分析していますが、多くの場合必要とされた費用は6カ月で回収された上、全体の約3分の1の事例の合計で年間約22億円もの利益が出ていました。これは、環境対策の実施が無駄を省く契機となって、企業にとって経済的な利益を生んでいたのです。
このように、個々の企業にとって環境対策を積極的に進めていくべき理由があっても、現実には多くの企業で環境対策が進んでいるとは言えません。そこには、個々の企業に消極的になってしまう事情があるほか、企業の取組を促進させる消費者の支援、社会的環境などが必ずしも整備されていないことがあります。環境への負荷の少ない持続可能な経済社会の構築に向けて、今後、こうした障害が克服される必要があるとともに、企業としても自主的な努力を積極的に推進していくことが望まれています。
第3節 持続可能な経済社会の構築に向けた日本の挑戦
1 国際社会からの期待と我が国の貢献
OECD環境保全成果審査
我が国の経済社会活動は、地球的な規模においても大きな影響を与えるまでになっています。こうした状況下で、我が国の環境政策はどのように位置付けられるのでしょうか。平成5年11月、OECD環境政策委員会により行われた我が国に対する環境保全成果審査(Environmental Performance Review)を見てみましょう。(18頁表参照)
「『アジェンダ21』行動計画」に見る我が国の貢献
「『アジェンダ21』行動計画」は、大気保全や砂漠化防止などの環境保全のほか、貧困の撲滅、人口問題など、アジェンダ21において掲げられた諸問題への我が国の行動計画を文書としてとりまとめたものです。本行動計画は地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定され、政府として一体となってその効果的かつ円滑な推進に努めていくこととなります。具体的には、
1) 地球環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築及び国民のライフ・スタイル自体を環境配慮型に変えるための普及、啓発等への努力
2) 地球環境保全に関する実効的な国際的枠組作りへの参加、貢献
3) 地球環境保全及び開発途上国の環境保全のための資金供与の制度に関する国際的取組
4) 環境上適正な技術移転の促進等の実施を通じた開発途上国の環境問題対処能力の向上への貢献
5) 地球環境保全に関する観測・監視と調査研究の国際的連携の確保及びその実施
6) 中央政府、地方公共団体、企業、非政府組織(NGO)等広範な社会構成員の効果的な連携の強化
の6項目の個々の施策について推進していくとともに、必要に応じ本行動計画の見直しを行う等、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に向け、一層の努力がなされることになります。
2 環境と経済を結ぶ新たな努力
環境基本計画
環境基本法は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進すべきことを規定するとともに、そのための中心的な仕組みとして環境基本計画を策定すべきことを規定しています。環境基本計画は、環境基本法に定められた広範多岐にわたる環境保全施策を有機的連携を保ちつつ、全ての主体の公平な役割分担のもと、長期的な観点から総合的計画的に推進するため、政府全体としての環境保全施策の基本的な方向を示すとともに、地方公共団体、事業者及び国民に期待される取組を記述するものです。平成6年1月16日には内閣総理大臣より、中央環境審議会に対し、「環境基本計画はいかにあるべきか」について諮問が行われました。中央環境審議会では、本年半ばに中間報告を、そして本年中に最終答申を行うことを目指しています。
OECD環境保全成果審査の概要
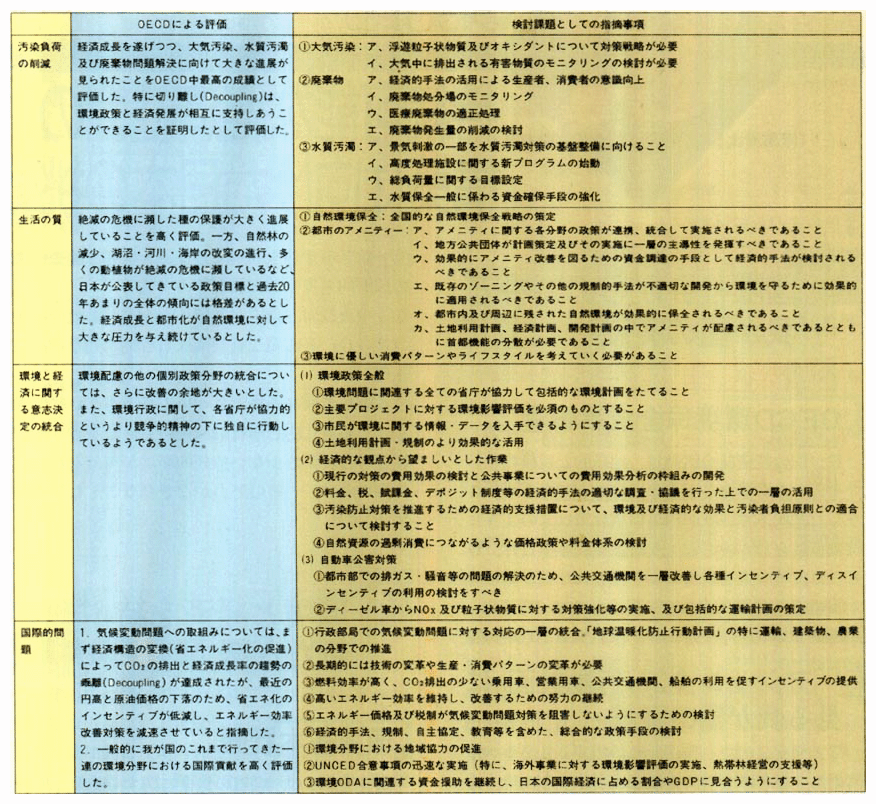
経済的手法
今日の環境問題は、時間的にも空間的にも広がっておりそのメカニズムも複雑化しています。
このため、従来の規制的手法のみでは対応が困難な課題も生じており、環境税のように環境への負荷に対し、経済的負担を課すことによって、自ら環境への負荷の低減に努めるよう誘導する施策の活用が有効です。
経済的手法は直接規制と比べ次の利点があります。第一に、広範な主体を対象とする場合、規制では、企業等に対する削減量の割当を定めることが困難であり、過大な削減コストを招きがちですが、経済的手法は、市場のメカニズムを通じて、それぞれの主体が最も経済的な行動を自主的に選択することにより、少ないコストで最適な努力の配分がなされると言えます。第二に、規制では、規制値以上に汚染量を削減するインセンティブが欠けるのですが、経済的手法は、汚染量の削減が経済的な利益に結びつくため継続的なインセンティブ効果があるものと考えられます。また、経済的手法は各主体に対し費用と便益に基づく自主的な判断を求めることになるため、より自己責任型社会の形成にも資するものといえましょう。
近年、環境税あるいは課徴金をはじめとする経済的手法の導入の議論が高まりを見せており、既に多くの国々で課徴金等の活用が見られます。
主要先進国環境総合計画の概要一覧
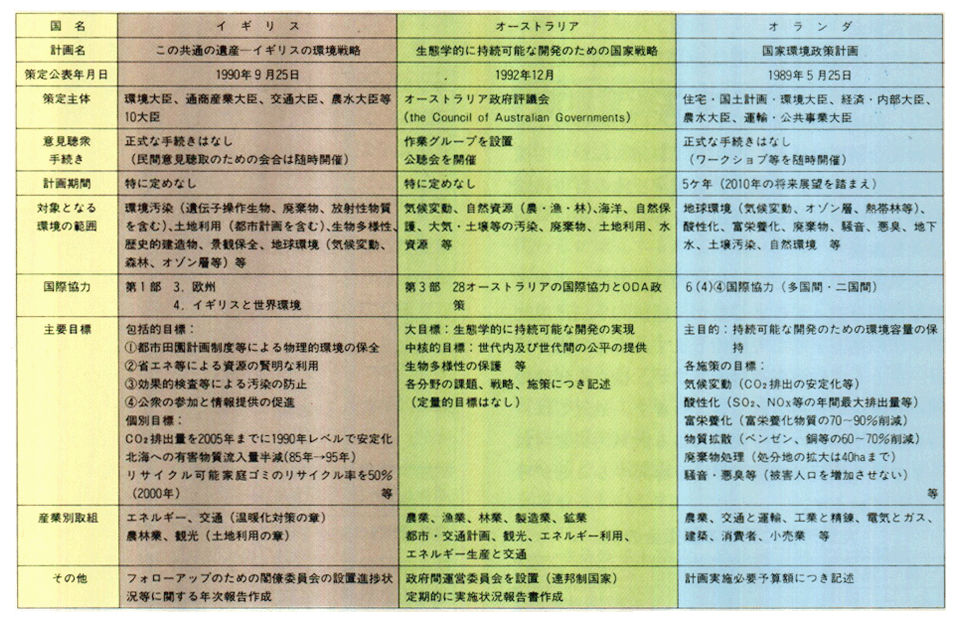
OECDでは、1991年(平成3年)に、「環境政策における経済的手法の利用に関するOECD理事会勧告」を採択し、承認し、経済的手法を、各国の社会経済的状況を考慮しつつ利用することを勧告しました。その後、OECDの「税制と環境に関する作業部会」は、1993年(平成5年)3月に環境税の導入に当たっての様々な論点を整理し、問題点への対応策を示す内容の報告書を公表しています。
また、我が国の政府税制調査会は、平成5年11月にその答申の中で、環境関連税制については、1)環境汚染抑制のための「経済的手法」としての税制の活用の側面と、2)国内外の環境対策のため「財源調達手段」としての税制の活用の側面の二つの議論があるが、内外での議論の進展を注視しつつ、更に調査及び研究を進めていく必要がある旨指摘しています。
このような状況の中で、昨年制定された環境基本法では、その第22条で新たに、経済的負担措置について規定しています。税・課徴金、デポジットなどの個別の措置の効果、経済に与える影響等を調査・研究し、国民の理解と協力を得るように努めるとしています。さらに、その措置が地球環境保全のためのものである時は、国際的な連携に配慮して行うこととしています。
次に世界の経済的手法活用の現状を見てみましょう。
各国毎の経済的手法の活用状況(1992年1月現在)
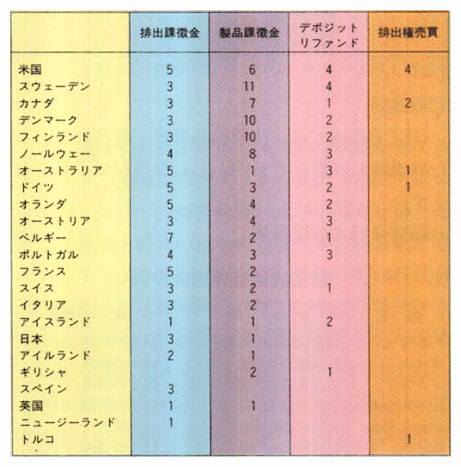
(備考)OECD調べによる
1)税・課徴金
a)水質保全
まず、水質保全の分野は、OECD諸国で従来から経済的手法が比較的重要な役割を演じてきた数少ない環境政策の分野です。排水の処理等のための課徴金制度はほとんどのOECD諸国において採用されています。窒素、重金属及び他の有害物質が多くの国々で共通の課題となっています。
b)大気保全
大気保全の分野では、伝統的に規制的手法が主要な役割を担ってきましたが、経済的手法は規制的手法の補完としても機能します。多くの国々では、主として財源調達目的ですが、様々な形態の燃料課徴金が適用されてきています。最近では、特に製品やエネルギー使用による大気汚染を対象としてより広範な経済的手法を導入することが考えられています。
大気汚染に係わる課徴金の例
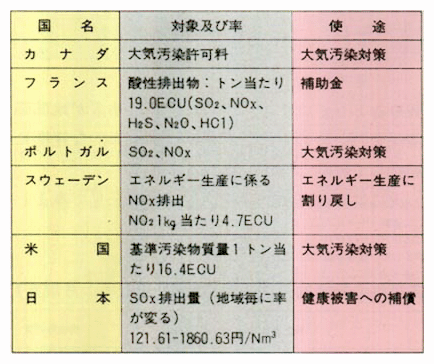
(備考)1 ECU≒¥120(1994年3月)OECD資料(1993年)より
c)廃棄物
OECD諸国では、使用後の容器・包装材といった廃棄物の減量化を目的とした課税が多く見られます。
d)騒音分野での活用例
航空機騒音課徴金の例
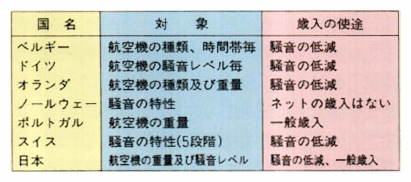
(備考)0ECD資料(1993年)より
容器・包装材等に係る課徴金の例
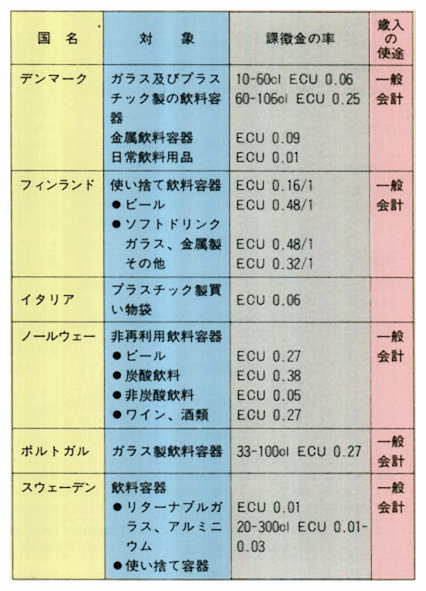
(備考)1 ECU≒¥120(1994年3月)OECD資料(1993年)より
e)エネルギー部門
エネルギーの分野では、これまでにも、エネルギー税、優遇措置、補助金などの適用例が見られます。1992年(平成4年)5月に炭素・エネルギー税導入に関するEC指令案がEC委員会で採択され、理事会で審査中です。また、スウェーデン、ノールウェー、フィンランド、デンマークの北欧諸国やオランダでは、地球温暖化の主因となっているCO2の削減を目的とした炭素税をはじめとする各種の環境税等を1990年代に導入しています。
炭素税の例
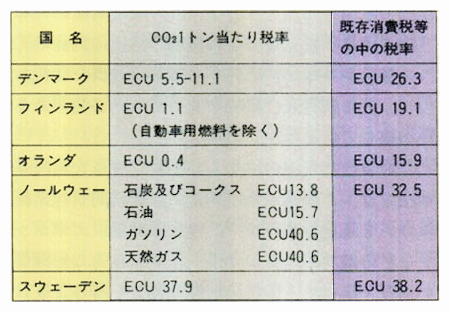
(備考)1 ECU≒¥120(1994年3月)OECD資料(1993年)より
f)農業部門
農業分野では、これまで環境保全目的を明らかにした経済的手法の活用は限られていました。OECD諸国では肥料や農薬に対して経済的手法を講ずる例が多く見られます。
2)排出権売買
排出権売買とは、個々の主体に定められた廃棄物の排出量等をあらかじめ割当て、その排出の権利の売買を許すものです。排出権売買にも様々なものがあります。
3)デポジット(預かり金)制度
デポジット・リファンド制度とは、潜在的に環境への負荷を有する製品などにデポジット(預かり金)を課し、当該製品ないしその廃棄物が適切に返却されたことにより環境への負荷が回避された時に払い戻し金を支払う制度です。OECD諸国の例では、飲料容器の分野が多く、この他にも使捨て電池やプラスチック、農薬など様々な導入例があります。
4)資金援助(補助金等)
環境基本法では、環境に対する負荷活動を行う者による公害防止のための施設の整備その他の自ら環境への負荷を低減するための措置に対し、経済的な助成を行うことを規定しています。
デポジット制度の例
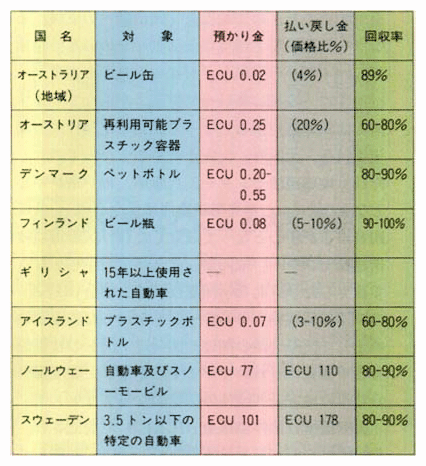
(備考)1 ECU≒¥120(1994年3月)OECD資料(1993年)より
環境資源勘定
従来の国民経済計算体系(SNA)は、生産活動や消費によって生じた環境汚染による国民生活の質の低下を反映しえないことなどから、これに代わるか補完する勘定体系の構築が必要とされています。環境資源勘定には、いくつかの種類があります。その第一は、森林や水などの自然資源について、そのストックと経済活動による採取・利用・廃棄等のフローを記帳するものです。第二は、環境汚染による被害や自然資源及びその減耗の経済的価値を評価し、これを現行のGNPやGDPから減じ、環境面から修正されたGNPやGDPを求めるものです。
サテライト勘定、自然資源勘定の相関図
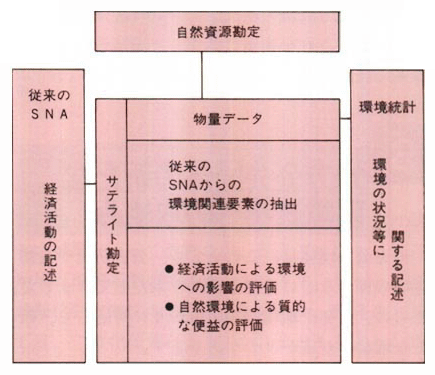
次に環境資源勘定を巡る国際的な状況を見てみましょう。先の地球サミットで採択されたアジェンダ21において、経済政策に環境の観点を盛り込むなど環境と経済の統合の重要性が記述されたところです。また、1993年に、国際連合では国民経済計算体系の改訂を行い、この改訂によりサテライト勘定が導入され、環境・経済統合勘定を含めることが決定されています。一方、OECDでは、今後、環境資源勘定をどのように政策決定に利用するかという側面からの討議が行われる予定です。米国においては、グリーンGDPの検討を進めるための予算が提案されています。ノールウェーでは、物理的な資源勘定のアプローチがとられています。自然資源と汚染物質の流れを捉え、これらの流れと経済活動の関係を分析することとしています。また、フランスでは、国家遺産勘定の研究が進められています。
メキシコに関するパイロットスタディ
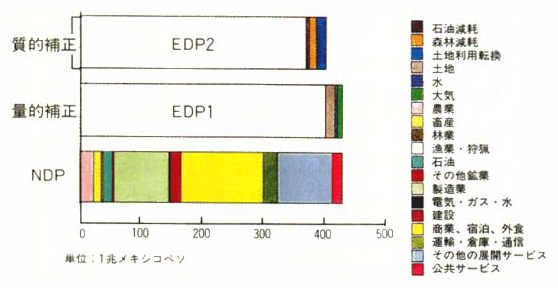
我が国では、環境基本法において、環境と経済との関わりを総合的に評価する新しい指標体系の開発が重要な課題であると規定しています。今後は、国際的な研究の動向をも踏まえ、環境資源勘定など環境と経済の状況を総合的に評価する手法を開発し、これを施策に活用し、環境政策と経済政策の統合を進めていくことが必要です。
3 地方公共団体の新たな環境対策への取組み
地方公共団体は、これまでも、公害防止や自然環境の保全などに重要な役割を果たしてきました。さらに、近年、環境問題の広がりに対応して、新たな取組みが広がりつつあります。その第1は、地球環境問題などを視野にいれた新しい総合的な条例づくりです。既に、熊本県、川崎市、大阪府で「環境基本条例」が制定され、神戸市でも、環境基本法の制定等を踏まえ、現行の「神戸市民の環境をまもる条例」を全面的に改正する条例が本年3月に制定されました。
その第2は、地球環境保全を目的に含めた計画や方針の策定です。計画としては、東京都「地球環境保全行動計画」、静岡県「地球にやさしい実践行動計画」、神奈川県「アジェンダ21かながわ」、広島県「エコネット21ひろしま」、千葉県「地球環境保全計画」等が制定されています。また、「地球環境問題への取組方針」等の方針が山梨県、愛知県、栃木県などで制定されています。また、従来から地方公共団体で策定が進められてきた地域環境管理計画に地球環境保全の観点を盛り込むことも、北海道、大阪府、大阪市等で既に行われています。さらに、地方公共団体の地球温暖化対策推進のための計画策定に対して、環境庁では補助を行っています。この補助を受けて、平成4年度に神戸市、大阪市、越谷市において策定された地球温暖化対策地域事業実施計画の概要は下表のとおりです。
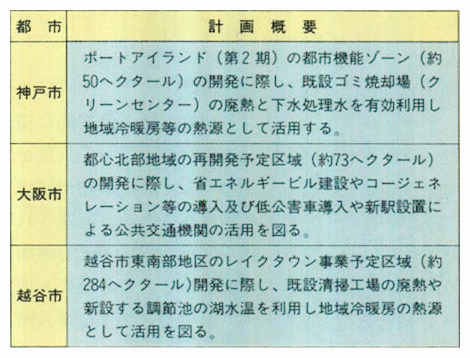
第3に、地域における環境教育施策が進んでいます。平成元年度に58都道府県政令指定都市に設置された「地域環境保全基金」により、環境副読本の作成などによる環境保全に関する知識の普及、自然観察会などの環境保全実践活動への支援、センターの設置など環境保全活動のための基盤整備、アドバイザーの委託などが進められています。
第4に、地域における国際協力が進んでいます。例えば滋賀県が中心となって設立した(財)国際湖沼委員会、大阪府、大阪市が中心となって設立した(財)地球環境センター、兵庫県、神戸市が中心となって設立した世界閉鎖性海域保全会議、三重県、四日市市が中心となって設立した(財)国際環境技術移転センター、福岡県、北九州市が中心となって設立した(財)北九州国際技術協力協会(KITA)のKITA環境協力センターなどを通じた協力を始めとして国際会議の開催や開発途上国への技術協力等が活発に行われています。さらに、環境保全のための地方公共団体の国際的な集まりとして、
「国際環境自治体協議会」(ICLEI)が設立され、我が国からも本年3月末現在で9団体が加盟しています。
第4節 環境の現状
現在の環境問題は、地域の特定の工場の活動や開発事業の結果生じる問題に加えて、大気、水、動植物などの様々な変化が互いに関係し、環境がその基礎から、そして広い範囲で悪化するような問題が重要になっています。
大気環境への負荷
わが国は、世界の各地域から大量の資源を輸入するとともに、環境への負荷となる物質を大量に排出しており、地球環境に大きな影響を与えています。また、交通や都市・地域構造、そしてライフスタイルなどに係る、私たちの日常生活からの負荷も大きくなってきています。
硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)排出量の推移
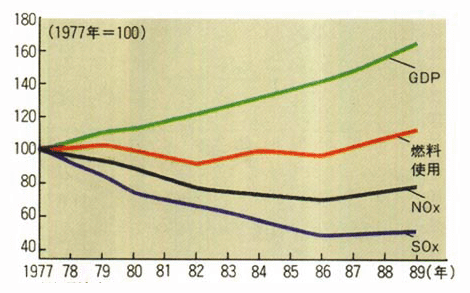
(資料)環境庁
窒素酸化物などによる大気汚染
人の活動に伴って、大量の、そして数多くの物質が大気の中に排出された結果、大気の成分や性質が変わって、人の健康や動植物などに悪影響を及ぼすおそれがあります。そのような大気汚染物質としては、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、浮遊粒子状物質ほか、新しい有害大気汚染物質などがあげられます。
二酸化窒素による大気汚染は、平成4年度においても相変わらず改善されておらず、環境基準(人準(人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準)を達成していない地域も少なくありません。この背景の一つには、自動車がますます多く使われるようになってきたことがあげられます。このため、工場からの排煙に対する規制に加えて、自動車1台ごとの排出ガスの規制を強めているほか、自動車から排出される窒素酸化物の総量を抑制するための様々な対策がとられています。
二酸化窒素年平均値の経年変化(継続測定局平均)
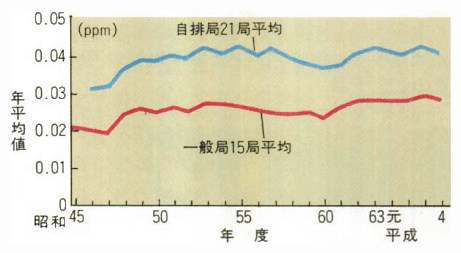
(備考)環境庁
二酸化硫黄による大気汚染は、工場などへの厳しい対策によって改善され、最近ではほとんどの地域で環境基準が達成されていきす。しかし、硫黄酸化物は酸性雨の原因となるほか、開発途上国では、二酸化硫黄による大気汚染は今も大きな問題となっています。
このほか、浮遊粒子状物質(大気中を漂う非常に細かい粒径10ミクロン以下の物質の総称)、特にその中でもディーゼル車から排出される微粒子
(DEP)あるいは光化学オキシダント(炭化水素や窒素酸化物に太陽の光が出たって生じる物質で非常に酸化力が強い)による大気汚染が問題となっているため、自動車に対する排出規制などの総合的な対策に取り組んでいるところです。また、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの、まだ規制されていない新しい大気汚染物質も問題となっています。
地球の温暖化
地球の大気中には二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・クロロフルオロカーボン(いわゆるフロンの一種)などの温室効果ガスがあり、地球から宇宙へ熱を逃しにくくし、地球を暖めています。
石炭や石油などが燃えると出る二酸化炭素は、産業革命の前には280ppm程度の濃度でありましたが、最近では350ppmまで高まり、さらに年々0.5%ずつ高まっています。この結果、何らかの対策が取られなければ、西暦2025年頃には気温が今より1℃、21世紀末頃には3℃ほど高くなると予測されています。3℃とは言えばわずかなようですが、東京と鹿児島の気温の差より大きく、地球全体の環境が変わってしまうことを意味しています。気温の上昇に伴い、海面が上昇し、雨の降り方も変わって、野生動植物の減少といった自然生態系の変化などのいろいろな影響が生じる場合があると予測されています。
地球温暖化に伴うアジア太平洋地域の河川の流出量の変化予測
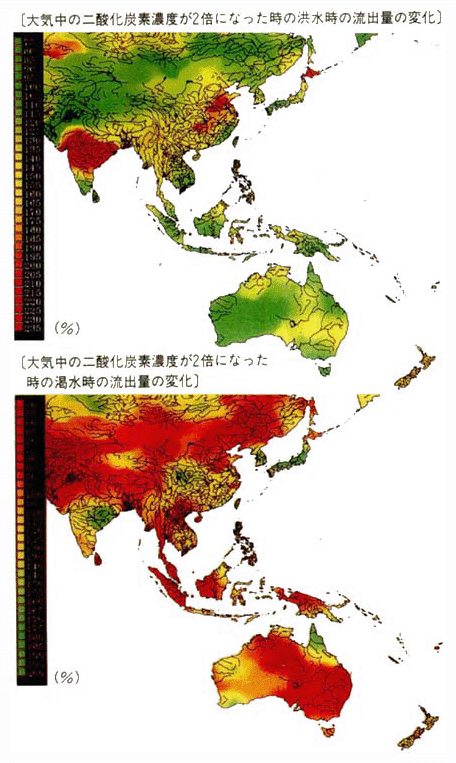
(備考)京都大学松岡譲助教授及び国立環境研究所が作成
地球の温暖化は、地球環境問題の中でも特に悪影響が心配される問題です。大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を日的とした気候変動枠組条約などの国際的取組の中で、我が国は温暖化防止対策を積極的に進めていく必要があります。
オゾン層の破壊
成層圏に存在するオゾン層が人工的に作られたクロロフルオロカーボンなどの物質により破壊されると、有害な紫外線が地表に届く量が増え、人に皮膚ガンや白内障が起きたり、生物の成長が妨げられたりする問題が起きます。
南極では、毎年春にオゾンが大変減ってしまう現象(オゾンホールという)が起きています。1989年(平成元年)から5年連続で、最大規模のオゾンホールが観測されています。
わが国では、モントリオール議定書という国際的な約束の改正などを受けて、オゾン層を破壊する物質を減らす対策をさらに進めるよう、オゾン層保護法改正などのオゾン層保護対策の強化を図っています。
南極のオゾンホール3要素の経年変化
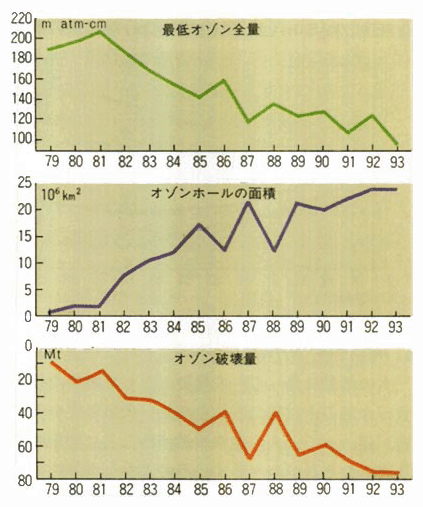
(備考)気象庁:オゾン層観測報告(1993年)
酸性雨
酸性雨は、先に説明した硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中を長い間漂ううちに酸化されて、雨に溶けて地上に降ってくる現象です。雨は自然の状態でも大気中の二酸化炭素を溶かしてやや酸性を示すしますが、それより酸性の強い雨(pH5.6以下)を一般に酸性雨と呼びます。
欧米では、酸性雨で湖が酸性化して魚が住めなくなったり、石造りの建造物が溶けたりするといった大きな被害が生じています。日本でも欧米とほぼ同じ程度の酸性雨が降っている状況にあり、今後酸性雨の影響が徐々に現れてくることが懸念されます。将来、酸性雨の被害が起こらないよう監視を強め、対策を考えておく必要があります。また、東アジア地域での酸性雨モニタリングネットワークの実施に向けた取組が進められています。
日本の酸性雨の状況
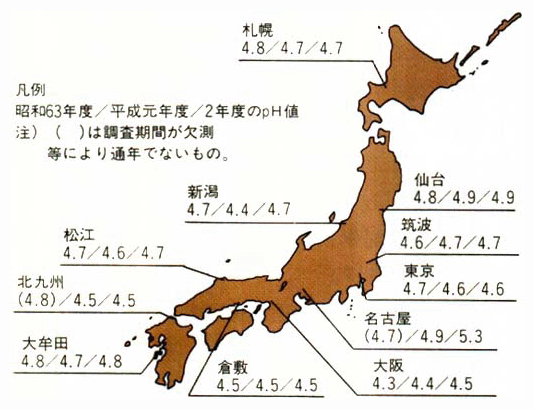
(備考)環境庁調べ
騒音、振動、悪臭
騒音は人の感覚に関わる身近な問題であり、苦情も最も多く、団らんや安眠を妨げ、精神的な苦痛をもたらします。騒音は工場や各種の交通機関などから生じますが、特に、自動車交通騒音が問題になっています。継続測定地点について見ると、環境基準を達成していない地点の割合は、依然として高い状況にあります。これまで自動車1台ごとの騒音の規制を強めてきましたが、さらに道路構造の改善などの総合的な対策が必要となっています。
騒音の継続測定地点(全国1,200ケ所)における環境基準達成状況の推移(%)
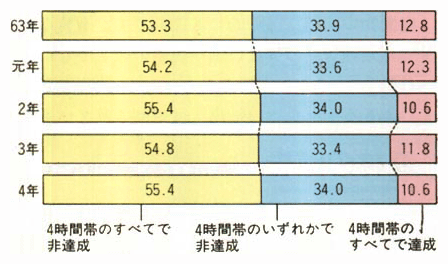
(備考)環境庁
建設作業や工場などからの騒音・振動や近隣騒音についての苦情も多く、発生源に対する規制のほか、意識の啓発等も行っています。
悪臭についても騒音についで多くの苦情が寄せられており、アンモニアなどの悪臭物質について、地域に応じた規制を行っています。
海、川、湖などの水質の汚濁
かつて、工場から排出されたメチル水銀により魚貝類が汚染され、それを食べた人々のうちに水俣病が発生しました。このような深刻な公害を踏まえて対策を進めた結果、今では、有害物質について水質環境基準のうちの健康項目をほぼ達成しています。我が国では、有害な化学物質による水質汚濁を未然に防止する必要から、環境基準や監視及び排水基準のそれぞれの項目の設定を行い、水質を常に守るための一層の対策を行っています。
BOD、COD(水の中の物質を酸化して分解するのに必要な酸素量)で表される有機物質による水盤汚濁では、環境基準の未達成率は25%もあります。特に、内湾や湖のような水の入れ替わりの遅い水域(閉鎖性水域)では、環境基準の達成率は依然として低い状況にあります。また、閉鎖性の海域では、流入した窒素や燐が蓄積し、赤潮が発生するなどの富栄養化という現象が問題となっています。このため、生活排水対策や産業排水の規制の強化などに努めています。
環境基準(BOD又はCOD)達成率の推移(水域別)
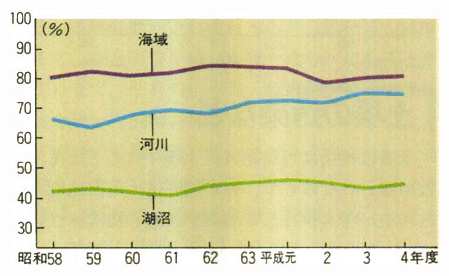
(備考)環境庁
また、発がん性が凝われているトリハロメタンが水道水中に含まれているという問題に対応するため、公共用水域の水質保全対策を進めています。このほか、近年飲料用の井戸などの地下水の汚染が問題となり、必要な対策が進められています。
一方、人々の生活や社会経済活動との係わりの深い水辺の環境では、河川水量の減少、埋立等による改変、それに伴う水辺の生物への影響など、良好な水辺環境が失われつつあります。
海洋の汚染
広大な海洋は、陸や空からの、また海上を航行する船からの汚染物質をそのまま受け入れています。例えば、陸地から遠く離れた海上で発泡スチロールが浮かんでいたり、し尿をはじめ各種の廃棄物も海洋へ投棄されています。海洋投棄は国際条約により厳しく制限されています。また、最近のタンカーからの大量の油流出事故に対しては、タンカー船体の二重化などの国際的な取組が進んでいます。
目視漂流物の個数と組成の水平分布
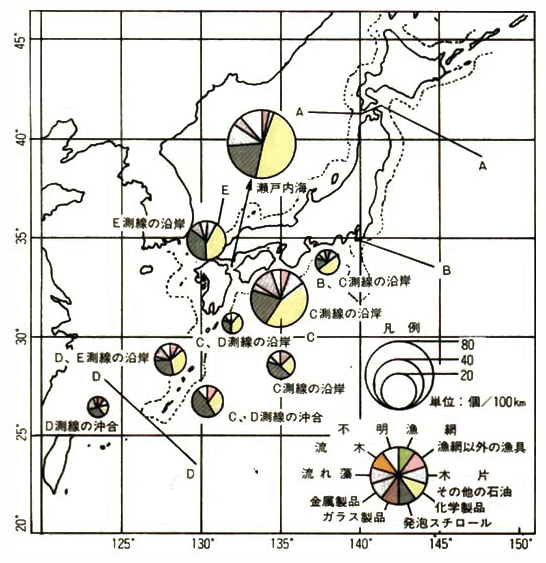
(備考)環境庁
土壌の汚染など
土壌の汚染は汚染物質が土壌中にとどまり、対策の難しいものです。わが国では、市街地の土壌の汚染が明らかになる事例が各地で相次いでいますし、農用地の汚染は7,140ヘクタールに達し、それぞれ対策が進められています。また、地盤の沈下はいったん生じると回復のできない問題です。
平成4年度の全国の地盤沈下の状況
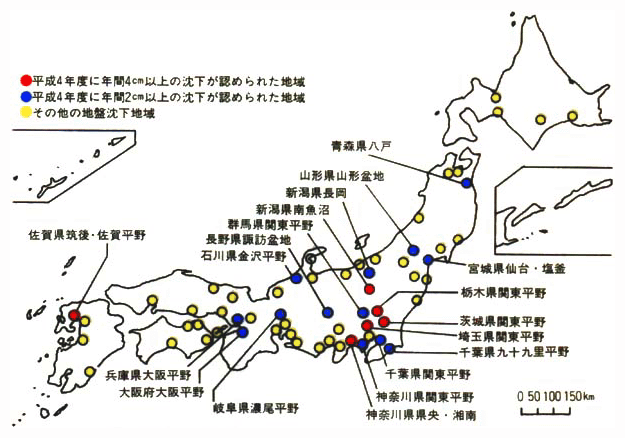
(備考)環境庁
廃棄物の増加
わが国のごみ排出量は年間5,077万トンであり、東京ドームの約136杯分にものぼっています。廃棄物は不適正に処理すれば汚染の原因となり、処理の過程で環境への負荷を与えるものです。また、最終的に埋め立てる際には自然の土地を処分場に変える必要があり、さらに処分場以外で不法に捨てられた産業廃棄物による水質汚染のおそれが問題となっています。
産業廃棄物排出量の推移(全国)
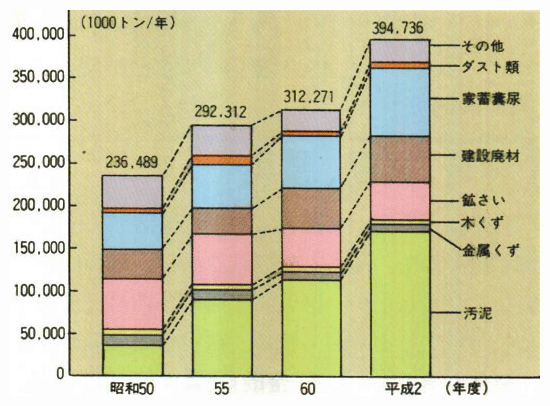
(備考)厚生省
廃棄物の問題は国際的にも深刻です。有害な廃棄物は処理費用の少ない国や規制の厳しくない国へ移動し、捨てられる例もあったため、国際条約などにより有害廃棄物の輸出入は規制されています。
森林の減少
森林は、地域の災害を防ぎ、水や各種の産物を提供し、多くの生物の生息地となっているとともに、二酸化炭素を吸収するなど地球全体の環境の安定化に役立っています。
わが国の国土は必ずしも広くはありませんが、日本の森林の割合は国土面積の約7割と世界的にも高くなっています。しかし、自然の状態を保った自然林などの割合は約18%にとどまり、特に大都市周辺の市街地などでは、森林のみならず、まとまった緑の少ない地域が広がっています。
植生自然度別の変化状況
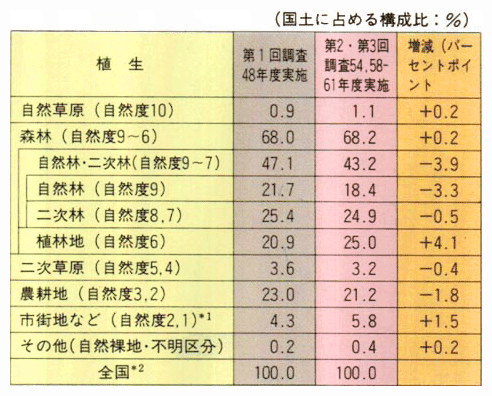
(備考)*1市街地などには緑の多い住宅地が含まれる。
*2開放水域を含まない。
環境庁 自然環境保全基礎調査 植生調査
世界では、約40億ヘクタールの森林があり、この約55%が開発途上国の森林で、その多くは熱帯林です。FAO(国連食糧農業機関)によると、熱帯林の減少はかつての予測以上に進み、調査対象の90力国の合計で年間1.540万ヘクタール、日本の国出面積の4割強に相当する熱帯林が減っています。内外で森林を守り育てるための取組が行われていますが、なお一層の努力が必要です。
地域ごとの森林面積と森林減少の見積もり
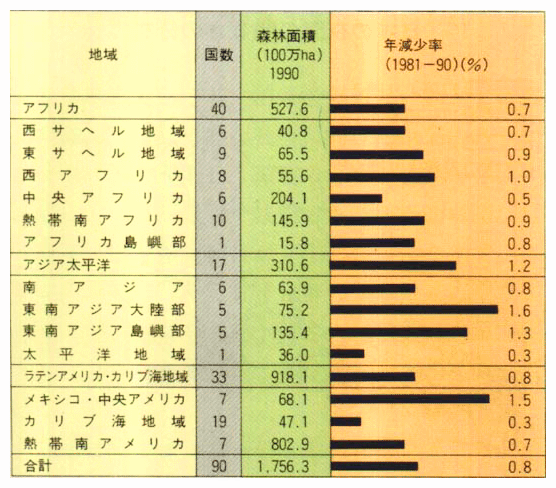
(備考)FAO1990年森林資源評価プロジェクト最終報告(平成5年)
砂漠化、土壌の劣化
UNEP(国連環境計画)によると、世界には森林を上回る約61億ヘクタール以上の乾燥地があり、このうち約36億ヘクタールの農地及び牧草地が砂漠化の影響を受けています。これは、耕作可能な乾燥地の約70%を占め、世界人口の6分の1が影響を受けています。このような砂漠化などの影響が最も深刻なのはアフリカであり、乾燥地の8割以上で土壌が脆弱になってきており、貧困問題と密接に関連した、いわゆる環境難民の問題が生じています。国連を中心として、砂漠化対策についての条約づくりなどの取組が行われていますが、日本も大いに役割を果していく必要があります。
脆弱な乾燥地域における土壌劣化
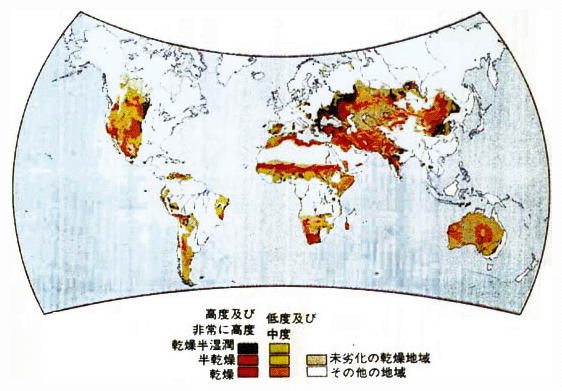
(備考)UNEP「WORLD ATLAS OF DESERTIFICATION」
野生生物種の減少
野生生物は、これまで人類とともに共存してきました。しかし、人間の活動に伴う生息地の破壊などにより、絶滅の危機に瀕しているものがあります。生物の種はいったん失われると、人間の手で再び作り出すことはできないものなのです。
これまでに確認された日本の野生動物について見ると、約3万5千種(亜種を含む)になるとされています。これらのうち、種の数が極めて多い昆虫を除いた動物各種では、その約15%に当たる種で絶滅の危機が追っていたり、そのおそれがあったり、あるいは極めて数が少なくなっています。日本産の植物でも約17%の種で絶滅のおそれがあるという調査結果が出ています。
野生生物の種が豊富なのは熱帯の諸国です。世界資源研究所(WRI)によると、熱帯林の減少により1990~2020年の間に全世界の5~15%の生物種が絶滅すると予測されています。こうした地球的規模の野生生物の種の減少に対して、世界が力を合わせて野生生物保護対策に取り組む必要があり、そうした国際的な取組も進められています。
我が国の絶滅のおそれのある野生動物の種の数
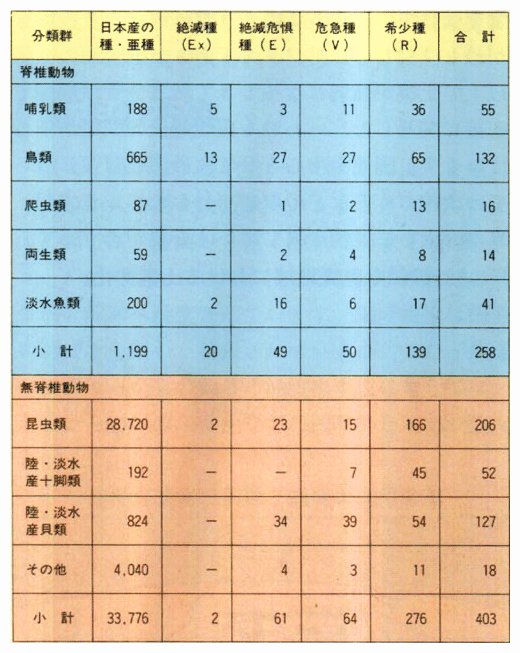
(備考)環境庁「緊急に保護を要する動植物の推定調査」
数字は種及び亜種を含む数。
日本産の種・亜種の数はこれまで学名が付されているものの数
絶滅種(Extinct)我が国ではすでに絶滅したと考えられる種または亜種
絶滅危惧種(Endangered)絶滅の危惧に瀕している種または亜種
危急種(Vulnerable)絶滅の危険が増大している種または亜種
希少種(Rare)存続基盤が脆弱な種または亜種
生物の汚染
生物は化学物質などを濃縮して蓄積することがあるため、その汚染は環境全体の汚染の指標となります。このため、化学物質の生物への蓄積状況を調査しています。化学物質の環境安全性を点検するため、今後とも、生物の汚染を含め環境全体にわたる化学物質の各種調査を行っていく必要があります。
自然とのふれあい
近年、余暇時間が増えたことや都市においての身近な自然が減っている中で、人と自然環境との絆を強める自然とのふれあいへのニーズが高まっています。自然公園や温泉地などのほか、身近な地域でのふれあいの場へ出かけたり、観察会等の活動に参加する人が増えています。
自然公園利用者数の推移
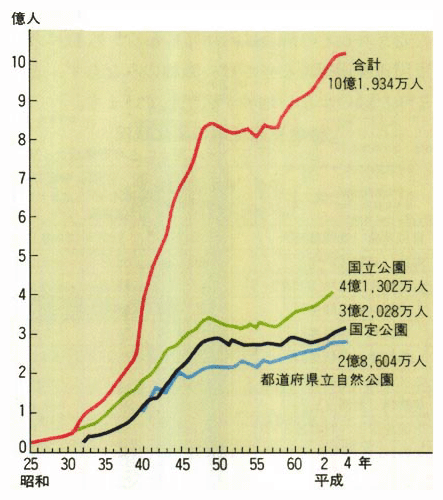
(備考)1.固定公園は昭和32年より、都道府県立自然公園は昭和40年より利用者統計を開始した。
2.環境庁
その他の環境
近年、私たちの身の回りには、人の健康に直接影響が及ぶほどではないものですが、いわゆる典型7公害に入らない新たな環境問題が起こっています。大都市圏においてのヒートアイランド現象や日照阻害、風害などがあげられます。また、過剰な光の氾濫により美しい星空を消失させる光害も問題となりつつあります。
日本の夜空の明るさの分布
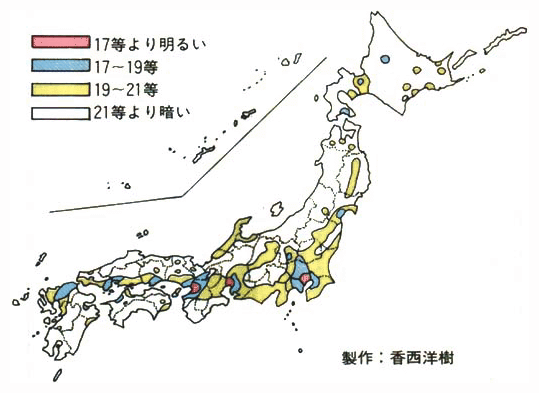
(備考)環境庁
むすび

人類共通の生存基盤であるただ一つの地球環境を壊さないためには、先進国と途上国とがそれぞれの責任を果たしつつ、協力して現在の社会経済を持続可能なものに変革していく必要があるとの認識が高まっています。
我が国においても、日常の消費行動が身の回りの環境のみならず地球環境に大きな負荷を与えているとの自覚の下に、持続可能な経済社会をめざした様々な試みが、消費者の間で始められています。
産業界においても、消費者の新しい動きを敏感に察知し、持続可能な社会に向けた企業のありかたを主体的に模索し、環境の保全と企業の存続・発展とを新たな発想や技術の下で積極的に結び付ける新たな企業家精神が芽生えつつあります。
そうは言っても、私達自身のものの見方や考え方を含め、現在の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会を変えていくことは決して容易なことではありません。
しかしながら消費者による新たなライフスタイルの模索と産業界による新たな生産様式の模索が噛み合ったとき、環境にやさしい生活文化に支えられ内容の変化を伴った持続可能で健全な経済の発展の道が開けてくるのではないでしょうか。
行政の役割は、行政の各局面で自ら環境保全面での配慮を徹底して行うとともに消費者や企業など各方面のそれぞれの努力を適切に噛み合わせる仕組みを作ることです。そのためには、これまで見てきたように、情報の整備や普及、経済システムの変革、計画的な環境投資、国際社会との協力などをはじめ多くの課題があります。現在策定が進められている環境基本計画はそのような多様な努力を一つにまとめ、持続可能な経済社会への具体的な行動を呼び起こすような道しるべの役割が期待されていると言えましょう。
持続可能な経済社会への道は決して平和なものではありませんが、社会のすべての人々が、それぞれの立場から地球的な視野に立って、自らの英知と行動によって選び育てていくとき、その社会での暮らしは、今日以上にに美しくまた心豊かなものとなるに違いありません。