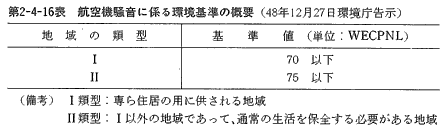
3 航空機騒音対策
航空機のジェット化の進展等は交通利便の飛躍的増大をもたらした反面、空港周辺地域において航空機騒音問題を引き起こした。特に周辺が市街化されている大阪国際空港及び福岡空港や、防衛施設である小松飛行場、横田飛行場、厚木飛行場及び嘉手納飛行場においては、夜間の発着禁止、損害賠償等を求める訴訟が提起された。これらの訴訟のうち、大阪国際空港訴訟については59年3月までに解決をみたが、その他の訴訟については現在も係争中である。なお、大阪国際空港については、公害等調整委員会に対し、周辺住民から損害賠償を求める調停申請がなされていたが、61年12月に同委員会の提示案に従い調停が成立し、解決をみるに至った。
(1) 環境基準の設定等
ア 環境基準
航空機騒音公害防止のための諸施策の目標となる「航空機騒音に係る環境基準」が48年12月27日に定められた。同基準は、地域類型の当てはめに従い、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)の値が70又は75以下になるようにするというものである(第2-4-16表)。
地域の類型の当てはめは、都道府県知事が行うこととしており、62年度末現在で、30都道府県51飛行場周辺において行われている。
イ 環境基準の達成状況等
58年12月末に環境基準の達成期限または10年改善目標の達成期限が到来した飛行場等の環境基準等の達成状況及び環境対策の実施状況は以下のとおりである。
? 一部の飛行場を除き環境基準が達成されるまでには至っていない。
? 東京、大阪、福岡等の空港周辺において、環境基準制定当時に比べて75WECPNL以上の騒音コンター面積は50%以上縮小するなど、公共用飛行場周辺の騒音の状況は全般的に改善の傾向にある。
? 75WECPNL以上の騒音区域については、移転補償(90WECPNL以上の区域)ないしは住宅防音工事等を行うことにより、環境基準が達成されたと同等の屋内環境が保持されるよう対策を講じており、特定飛行場においては、概ね完了した。
(2) 発生源対策
発生源対策は、航空機の騒音をその発生源である航空機そのものの段階で極力低減させるもので、騒音問題の解決に根本的な役割を果たすものといえる。今後も、発生源対策の強力な推進により、航空輸送量の増大にもかかわらず、騒音の及ぶ地域を縮小できるものと予想している。
ア 機材の改良
50年10月に制度化された「騒音基準適合証明制度」は、ジェット機について、その騒音が一定の基準以下でなければ飛行を禁止することを内容とするものであり、53年9月には、この基準を強化する措置がとられた。
これに基づきB-747、L-1011等の低騒音型機の導入が進められ、ジェット機の主力を占めるに至っているほか、最近では中小型機の分野でも、低騒音化の一段と進んだDC-9-81及びB-767が運航を開始している。この結果、従来の高騒音型機の退役が進み、62年12月末には在来型の主力機であったDC-8が完全に姿を消すに至った。
大阪国際空港においては、52年5月から低騒音型機が就航し、以後その発着回数は順次増加し、現在1日あたり200回のジェット便のうち190回前後を占めるに至っている。
イ 騒音軽減運航方式の推進
離着陸時の騒音を軽減させる運航方式として、急上昇方式、ディレイドフラップ進入方式及び低フラップ角着陸方式がほとんどのジェット化空港で実施されているほか、一部の空港では、立地条件にあわせて、優先飛行経路方式、優先滑走路方式、カットバック上昇方式等が行われている。
ウ 便数調整、時間規制等
大阪国際空港においては、47年4月から原則として、午後10時から翌朝7時までの発着を禁止してきたが、51年7月からは午後9時から翌朝7時までに発着するダイヤについても認めないこととしているほか、52年10月から発着回数枠を1日370回(うちジェット機200回以内)としている。
東京国際空港においては、ジェット機の発着禁止時間帯を原則として午後11時から翌朝6時までとするほか、夜間の発着を海上経由で行わせる措置を講じている。
新東京国際空港においては、航空機の発着禁止時間帯を午後11時から翌朝6時までとしている。
(3) 空港周辺対策
発生源対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及ぶ地域については、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」等に基づき周辺対策を行っている。同法に基づく対策が実施される特定飛行場としては、東京国際、大阪国際、福岡等16空港が指定されており、これらの空港周辺において、学校、病院、住宅等の防音工事及び共同利用施設整備の助成、建物の移転補償、緩衝緑地帯の整備、テレビ受信障害に対する受信料減額のための助成等が行われている(第2-4-18表)。
なお、大阪国際及び福岡空港は、同法に基づき周辺整備空港として指定され、関係府県知事が策定する空港周辺整備計画に基づき、国及び関係地方公共団体の共同出資で設立された空港周辺整備機構が上記施策に加えて再開発、代替地造成、共同住宅の各事業を実施している。
運輸省においてこれら施策に係る事業量の拡大及び事業内容の充実に努めてきた結果、住宅防音工事は、60年度に概ね完了し、「航空機騒音に係る環境基準」の改善目標に定める屋内環境が保持されることとなった。
一方、移転跡地を活用し、空港と周辺地域の調和ある発展を図る見地から、次の施策を講じている。?大阪国際空港周辺においては、周辺地域の低騒音化を踏まえ、騒音区域のうち第二種及び第三種区域を縮小することとし(62年1月5日告示、64年3月31日実施)、大阪府域の航空機騒音の特に激甚な地域における大規模緑地の整備についても62年2月に都市計画決定が、63年1月には計画区域のうち一部区域の事業承認・認可がなされるなど、空港周辺地域の計画的な整備が進められている。?緩衝緑地帯整備事業を61年度より従来の函館、仙台、大阪国際、福岡に加え、松山、高知、宮崎空港においても開始した。?大阪国際及び福岡空港においては、地方公共団体が移転跡地等を利用して公園等を整備する周辺環境基盤施設整備事業について国が助成を行うとともに、61年度より空港周辺整備機構が移転跡地の一時使用許可を受け、荷さばき場等の騒音斉合施設を設置する新しい形の再開発事業を開始した。また、63年度から、函館、仙台、松山、高知及び宮崎空港においても周辺環境基盤施設整備事業補助を開始することとしている。
また、「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき、新東京国際空港では、空港と調和のとれた周辺土地利用について、57年千葉県知事により航空機騒音対策基本方針が決定され、これに基づき航空機騒音障害防止地区等に関する都市計画の策定が進められている。
(4) 防衛施設周辺における航空機騒音対策
自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音については、自衛隊機等の本来の機能・目的からみて、エンジン音の軽減・低下を図ることは困難であるので、音源対策、運行対策としては、消音装置の使用、飛行方法の規制等についての配慮が中心となっている。この場合の駐留米軍における音源対策、運行対策については、日米合同委員会等の場を通じて協力を要請している。自衛隊等の使用する飛行場に係る周辺対策としては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、建物等の移転補償、土地の買入れ、緑地帯等の整備、テレビ受信料に対する助成等の各種施策が実施されている(第2-4-19表)。
なお、62年度末現在24飛行場周辺について同法に基づく第1種区域等が指定されており、住宅防音工事の助成等が実施されている。
以上のように自衛隊等が使用する飛行場周辺においては周辺対策の推進及び施策の充実が図られている。