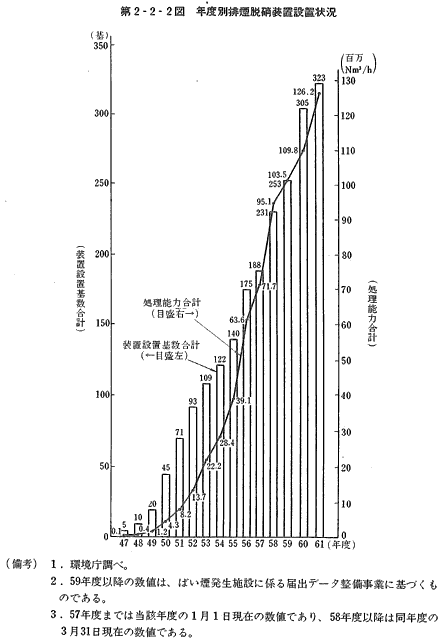
2 窒素酸化物対策
(1) 固定発生源対策
ア 全国一律の排出規制の実施
固定発生源に対する全国一律の窒素酸化物の排出規制については、48年8月の第1次規制以降、4次にわたり排出基準の強化及び対象施設の拡大を行ってきており、さらに、58年9月には、窒素酸化物の発生率が高い石炭等の固体燃料への燃料転換等のエネルギー情勢の変化に対応するため、固体燃焼ボイラーに係る排出基準の強化等を行った。また、60年6月には小型ボイラーを規制対象施設に追加したほか、62年10月にはガスタービン及びディーゼル機関を追加し、63年2月から新設の施設に対する規制を実施している。
イ 総量規制の実施
(ア) 総量規制の導入
工場、事業場が集合し、ばい煙発生施設ごとの排出規制では環境基準の確保が困難であると認められる地域については、56年6月、「大気汚染防止法施行令」の一部改正を行い、窒素酸化物に係る総量規制制度を導入することとし、環境基準を確保するために所要の削減対策を実施することが特に緊要であると認められた東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の三地域を総量規制地域として指定した。
総量規制の導入を保留した名古屋市等地域並びに検討を続けることとした北九州市等地域及び神戸市等地域については、地方公共団体が独自に要請等による窒素酸化物対策の推進を図っているところである。
(イ) 総量規制の実施等
56年6月に総量規制地域に指定された三地域においては、57年から総量規制が実施されており、60年3月末には、既設の工場、事業場にも、総量規制基準が適用された。
ウ 窒素酸化物排出低減技術の開発状況
固定発生源から排出される窒素酸化物の低減技術については、排煙脱硝技術、低NOx燃焼技術等があり、50年以来その開発状況等を継続して調査し、把握に努めている。
最近における低NOxバーナーの採用等により、相当程度の窒素酸化物排出低減効果を得る燃焼技術が既に普及している状況にある。
排煙脱硝装置の設置基数及び処理能力は、第2-2-2図にみるように着実に増加している。技術開発の状況についてみると、方式としては大半が乾式選択接触還元法であり、それ以外に無触媒還元法、湿式直接吸収法、湿式酸化吸収法がある。クリーン排ガスやセミダーティ排ガスについては、実機が順調に稼動している。石炭の燃焼排ガスのようなダーティ排ガスについても、従来の集じん装置と組み合わせた低ダスト脱硝方式のみならず、高ダスト脱硝方式についても実機の運転の段階に入っているなど、技術の信頼性が向上している。このように石炭の性状、集じん特性、経済性、用地等各施設の実情に応じた方式の選択が行えるようになりつつある。
(2) 自動車排出ガス対策等
自動車から排出される窒素酸化物については、逐次規制強化してきたところであるが、大都市等自動車交通量の多い地域においては、一層の排出量低減が必要となっており、自動車に対する個別発生源対策はもとより、交通管理、道路構造の改善等の諸対策についても一層の推進を図る必要がある(詳細は第4節参照)。
以上の対策のほかに、窒素酸化物等の大気汚染防止対策への新たな取組として、第5章で述べられているように「公害健康被害補償法」の改正により、新たに公害健康被害補償予防協会に置かれる基金を財源として、地域の大気環境改善に資する各種の事業が行われることとなった。これにより、地方公共団体等が行う電気自動車等の低公害車の普及、排出ガスのより少ない最新規制適合車等への代替促進、大気浄化能力を有する植栽の整備等の各種の事業を推進する。