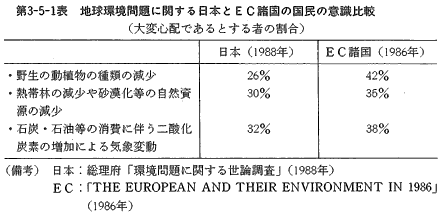
2 世界への積極的な貢献の方向
我が国の経済は、いうまでもなく、今日、世界経済の一割以上を占め、世界最大の債権国でもある。また、科学技術の面でも世界をリードする国でもある。このため、様々な観点から世界への貢献が求められる時代が到来している。
我が国は、貢献の可能性の大きさ、地球環境とのかかわりの大きさ等から、地球環境の保全に関し率先してリードすべく大きな役割が求められている。「世界へ貢献する日本」のベースとなる課題として、以下の方向に即して、政府、多様な主体、国民一人ひとりが積極的に地球環境の保全に取り組む必要がある。その際、我が国が世界的視点から地球環境の保全に貢献していくに当たり、アジア・太平洋地域の重要性は、ますます増大していることを認識する必要がある。
(1) 我が国政府の対応の方向
地球環境の保全のうち、現在我が国にとって早急に対応すべき課題になっている貴重な野生生物の保護やフロンガスの排出抑制については、関連の国内法の整備をはじめ諸般の対策が進められているが、今後とも強力な施策を講じていくとともに、広く国民や関連事業者の理解と協力を得ることが必要である。これらを含め、各種の環境関連の条約・協定の適正な履行等国際的な協調を図って取り組まなければならない課題については、国際的責任として、我が国の国際的地位にふさわしい行動や対応を行っていくことが必要であることはいうまでもない。
以上を前提として、地球環境の保全に向けての我が国の積極的な貢献の基本的方向を述べる。
ア 開発途上国の「持続的開発」への積極的貢献
水、土壌、森林など将来の発展の基盤である環境を損なうことなく開発を進めるという「持続的開発」の認識は、南北を問わず広がってきている。
開発途上国においても、近年、環境保全に開する法律、組織等が整備されてきているが、基本的なノウハウ、人材、資金等が十分ではない場合も多く、持続的開発には環境保全を組み込んだ先進国からの開発緩助等が大きな役割を果たす。
したがって、我が国が開発途上国の「持続的開発」に貢献する視点としては、?我が国の貴重な経験を踏まえつつ、開発途上国の環境の実状に応じた効果的な協力・支援をいかに行うか、?増大する開発援助や直接投資が現地の環境にいかに配慮し、持続的開発に寄与するか、という二点が中心課題となろう。
(ア) 環境協力の積極的展開
我が国の環境協力は、開発途上国の政府職員等の研修、専門家派遣等を中心にして緒についたばかりのものも多いが、世界への貢献の重要な課題の一つとして総合的な視点に立った環境協力を積極的に展開することが必要である。その際、環境協力を進めるに当たっては、次のような点に配慮する必要がある。
第一に、環境協力の拡大・質的改善のための要請主義の弾力的運用である。開発途上国では、環境問題の解決に必ずしも高いプライオリティーが置かれにくく、また、環境問題の解決のための適切な対応方策を見いだし得ない場合も多い。環境協力を拡大し、質的にも改善するためには、従来からの要請主義の枠組みを維持しつつも、要請主義を弾力的に運用し、開発途上国に対し環境分野の重要性について啓発するとともに、開発途上国のニーズを十分踏まえた協力プロジェクトの立案を支援するため、我が国から開発途上国に対する積極的な働きかけが必要である。
第二に、持続的開発に向けての開発途上国との政策交流・対話等の強化である。環境協力に際し、個別プロジェクトの協力のみならず、政策レベルでの交流・対話が必要であるとともに、開発援助一般の政策対話の中でも環境配慮について十分な指摘を行うことが必要である。また、持続的開発は、経済政策、地域開発政策の立案や個別の事業計画の作成段階での大きな課題である。このため、経済計画等のプランナーに対し当該計画への環境保全の組込みのための手法や個別事業計画を実施する際の環境配慮の方法等に関する協力を進めていくことが必要である。なお、持続的開発のための方策が組み込まれた事業計画に基づくプロジェクトへの援助も必要である。
第三に、これらの協力を総合的、効果的に実施していくため、開発途上国の実状を十分把握するとともに、国内における協力体制を整備することが必要である。例えば、効率的な人材の確保、環境に関する様々な協力案件の相互の連携、「持続的開発」の手法についての学際的な研究の推進等が必要であろう。
第四に、地方公共団体の国際協力の一環としての環境協力である。今日、地域レベルの国際交流・国際協力はその重要性を増している。我が国の地方公共団体には、世界に誇り得る環境行政、特に公害防止行政のノウハウ、人材が蓄積されており、専門家派遣等を通じて、これらの蓄積を地球環境保全の舞台で有効に活用することが重要である。
これらの視点から、閉発途上国の環境保全により一層積極的に協力していくことが、持続的な開発に寄与する我が国の貢献の第一の課題である。
(イ) 開発援助等国際活動における環境配慮の撤底
開発援助は、貧困を克服し、経済の持続的発展を推進する開発途上国の自助努力を支援していくうえで重要である。同時に、開発援助が被援助国の環境を損なわないよう、また、発展の基盤である環境の質を向上させるよう環境に配慮していくことは、開発援助そのものの長期的な実効性をあげるうえでも必要な要件である。こうした認識から、米国、イギリス、カナダ、西ドイツ等では、既に開発援助プロジェクトの環境アセスメントを実施している。また、既に述べたように、世界銀行等は開発援助プロジェクトの環境配慮を充実しつつあり、OECDにおいても開発援助プロジェクト等の環境アセスメントに関する理事会勧告を採択している。
我が国においては、これまでも環境問題に配慮した計画策定を行うよう努力してきているが、OECDの理事会勧告等を受け、我が国としての開発緩助における環境配慮の体系的な組入れのため、現在、基本的な事項をはじめ、配慮の方法、評価の方法などその方策についての具体的検討が進められている。
また、企業の海外における直接投資に際しての環境配慮については、OECDは、事業活動が行われる国の環境保護に関する方針に配慮すべきことを「多国籍企業の行動指針」において示し、現在検討中の「国連多国籍企業行動基準(案)」においても同様の趣旨が盛り込まれている。
また、例えば米国では、国家環境政策法により海外における特定の行為についても国内と同様の環境アセスメントを1979年から義務づけている。
我が国の開発援助や直接投資は、先にみたように近年急速に増大し、これらはいまや世界でもトップレベルの規模となっている。開発援助、直接投資を通じて開発途上国の持続的な発展に寄与するためには、その発展の基盤である環境への配慮を徹底していくことが基本的に重要である。
イ 地球環境保全に関する科学的知見の集積、技術開発分野における貢献
我が国の経済、科学技術の向上に伴い、我が国の科学技術に対する期待が非常に高まり、その国際的地位に即した役割を果たすことが必要になっている。地球環境保全に関する科学的知見の集積と技術開発について述べる。
(ア) 地球環境に関する科学的知見の集積
近年、地球環境に関する科学釣調査等は、直接的には生産活動に寄与しないものの、人類の長期的な生存と繁栄の基盤になる環境の保全に資するという意味で、「国際公共財」として各国政府や国際機関が協調的に取り組む必要があるとの認識が国際的に高まっている。
これまで、温室効果のシミュレーション、衛星による南極のオゾンホールの観側など地球環境に関する科学的調査や知見は、国際機関のほか米国の政府機関が実施し、蓄積してきたものがほとんどである。我が国は、昭和基地におけるオゾン層の観測のほか、地球科学に関する国際共同研究として、「気候変動国際協同研究計画(WCRP)」、「国際水文学計画(IHP)」、「海洋汚染モニタリング計画(GlPME/MARPOLMON)」等に参加し、主に地理的に近い西部太平洋域で調査研究を実施している。
我が国は、今後、産業技術面のみならず、地球環境に関する科学的調査や知見の集積のための国際的プロジェクトに積極的に参画し、また、世界に率先してこれらを推進することが強く求められている。このため、国立試験研究機関等を中心にして、大型プロジェクト等として学際的・国際的な調査研究を計画・実施するとともに、その成果を世界の共有財産として蓄積していくことが必要である。また、地球的規模での環境監視の技術的手段として、衛星等によるリモートセンシング等の技術開発を進め、地球環境の状況・変動を把握し、その成果を世界に提供していくことが重要な課題である。さらに、この分野での研究者の国際交流に積極的に取り組む必要もある。
(イ) 地球環境保全に関する技術開発
地球環境の保全は、技術開発に負うところも大きい。
まず、この分野で世界への貢献を進めるには、開発途上国の発展段階、風土、技術の習熟段階等に応じた技術を開発していくことが必要であろう。例えば、薪を採取することが砂漠化、熱帯林の減少等の一因になっている地域に向けてのエネルギー効率の高いかまどの開発、集落単位の太陽エネルギー等の利用技術の開発など現地の風土、生活様式、経済力に合致した「適正技術」の開発については、今後、こうした面での技術開発を積極的に進めるとともに、その普及を推進していく必要がある。こうした分野での開発途上国の研究機関、研究者に対する支援も強化する必要がある。
また、地球的規模の環境問題、自然資源の保全等のためには、エネルギーや水の効率的利用技術、廃棄物の再資源化技術、再生可能エネルギ一利用技術、フロンガスの回収・再利用技術や代替品開発技術等の環境保全型の技術を組み合せていくことも必要である。
さらに、熱帯地域、砂漠化地域等における生態学的知見を生かした植林技術、野生生物の保護・増殖技術、熱帯生態系における開発行為の環境影響評価技術など自然生態系に密接に関連する分野については、現地の自然環境に即した研究・技術開発を強力に推進する必要がある。
ウ 国際機関の具体的な活動との連携・協力
UNEPは、環境の保全に関する国際的調整機関の中核としての役割を果たすとともに、その触媒的機能を発揮して、各国政府の要請にこたえ、他の国連機関、国際機関、政府、民間団体と協力して様々なプログラムを実施している。
我が国は、財政面の貢献のみならず、UNEPに対し、アジア・太平洋地域における活動の強化を求めるとともに、各種の地域プログラム、クリアリング・ハウス等への技術的・人的側面等の連携・協力についての検討を進めることが必要である。
UNEPのみならず、UNESCO、FAO、WHO、WMO等においても各種の環境関連プログラムを実施しており、また、OECDは加盟国の環境の保全のほか、開発途上国の環境資源管理に関しての取組を進めつつあり、我が国としてもこれらの機関の活動と積極的に連携・協力を図っていくことが必要である。ITTOに対しては、我が国は、加盟国中最大の資金拠出を行っているところであり、今後とも積極的に協力していく必要がある。
さらに、世界銀行、アジア開発銀行等では、これまでの経験にかんがみ、環境担当セクション機能を拡充していくこととしており、我が国との環境分野での協力関係を強化することが求められている。
(2) 多様な主体の活動による環境協力ネットワークづくり
地球環境の保全、開発途上国との環境協力等には、国連等の国際機関や各国政府といった公的な機関のみならず、いわゆるNGOsが数多く携わっている。NGOsは、先進国、開発途上国を問わず環境に関する草の根レベルでの活動に貢献し、環境保全への行動を促進させるうえで大きな役割を果たしており、その数は年々増加している。こうした点を踏まえ、UNEP等の国際機関や欧米等の政府は、NGOsとの協力関係を重視している。例えば、UNEPでは、ラテンアメリカ、アフリカ、アジア・太平洋地域等のNGOsのネットワークづくりに協力し、あるいは協力のためのプロジェクトに財政援助を行っている。また、ナイロビに本部を置く「環境リエゾンセンター(ELC)」は、UNEPから財政援助を得て世界の6,000を超えるNGOsのネットワークを統括し、UNEPの情報を流し続けるとともに、様々な問い合わせに応じている。また、先に紹介した米国のNGO「コンサベーション・インターナショナル」が行っている「債務の自然保護払い」のようにユニークな活動も展開されるなどNGOsの役割はその重要度を高めている。
近年、我が国においても、地球環境の保全を目指したNGOsが公益法人を中心にしていくつか設立されている。「(財)世界自然保護基金日本委員会(WWF-JAPAN)」のように野生生物保護等の世界的組織の支部となっているもの、「(財)国際湖沼委員会(ILEC)」のように地方公共団体(滋賀県)が設立の母体となって世界の湖沼地域の環境保全に関する科学的調査、情報交換等を行っているものなど様々である。しかし、NGOsが十分社会的存在になっている欧米諸国と比較すると、一般的に我が国のNGOsは、比較的歴史が浅く、財政基盤が脆弱で専門家の確保が十分できない等の課題を抱えているのが現状であるといえる。
今後、我が国のNGOsがその活動のための基盤の整備を図りながら、地球環境の保全に「草の根環境協力」として積極的に貢献していくことが期待される。
一方、我が国の産業界においては、産業公害防止対策に関する世界のトップレベルの知見、技術が蓄積されている。今後とも、産業界において、開発途上国の企業関係者の研修等を通じて公害防止の技術移転を推進していくことが期待されている。
我が国が地球環境の保全の分野で世界に貢献するためには、こうした多様な主体による環境協力のネットワークが重要な位置を占めることになり、政府としてもこれらの主体による環境協力との連携を図っていくことが必要である。
(3) 国民一人ひとりの意識の変革と参加
環境問題は、生活排水、廃棄物等の身近な問題のみならず、地球環境問題に至るまで国民生活と深くかかわるようになってきた。
例えば、現在我が国で使用・消費されているフロンガスのうち10%強は各種のエアゾール製品の噴射剤として使われ、貴重な野生生物は、装飾品の材料、ペット等として幅広く利用されている。また、いまや地球にとっての貴重な生物資源となっているいわゆるラワン材は、建材、家具あるいは日用大工の材料として親しまれている。
我が国をはじめとする先進国の豊かな消費生活は、多くの場合、地球の環境を大量に利用することで成り立っている。
開発途上国の多くの地域では、例えば、焼畑農業が熱帯林の減少をもたらし、炊事のための薪の採取が砂漠化の一因となるなど生活を営むための最も基本的な活動それ自体が、地球環境問題の要因となっているのに対し、我が国をはじめとする先進国の豊かな消費生活は、リサイクリング等その方法を工夫したり、消費財の選択に配慮したりすることによって、消費生活そのものを環境への負荷が少なくなるように見直すことが可能である。
こうした観点から、豊かな消費生活のなかで、地球環境問題が国民一人ひとりの身近な問題であることを認識し、一人ひとりが地球環境に影響を及ぼす生活を見直すこと、すなわち、「地球人としてのライフスタイル」を追求することが必要である。また、地球環境の保全に寄与するNGOsの活動に参画したり、財政的援助をしたりすることにより、草の根レベルでの関心、知識を高め、あるいは我が国のみならず世界の人々との連携を図り、地球環境問題に積極的に取り組むことも必要である。
総理府が1988年に実施した「環境問題に関する世論調査」によれば、「あなたは、地球環境問題にどう対処するか」の問いに対し、「身のまわりの生活に注意する」、「活動に参加・協力したり、お金を出す」と回答した割合は、それぞれ44.2%、15.2%となっており、こうした意識は芽生えているとみられる。しかし、同調査による地球環境問題に対する我が国の国民の関心の程度とEC諸国の国民の関心の程度を比較する、我が国の国民の関心は低いことがわかる(第3-5-1表)。また、同調査によると、絶滅のおそれのある野生生物の輪入や取引が規制されていることを知らない人が26.8%あるとともに、その内容については、絶滅のおそれのある野生生物の規制等に関する知識・情報が少ないため、知らずに購入している可能性がある人もみられる。
したがって、国民一人ひとりが地球環境の問題を自らの問題でもあるとしてその対応を図るには、政府、NGOs等が、正確な知識や情報を普及することがその前提として必要である。
新たな知見や情報については、そのつど十分な普及を図っていくことはもちろん、子供のときから、環境と日常生活、資源、人口とのかかわり、地球環境の状況や背景等についての知識や認識を醸成していくことが必要である。このため、地球を視点の中心に据えた環境教育を展開し、地球環境とのかかわり、「持続的開発」の必要性等についてわかりやすい説明をしていくことが求められる。