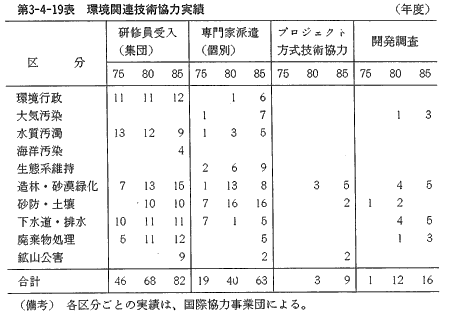
2 我が国の国際的環境協力ヘの取組の現状
国際社会における環境に関する認識の高まり等から、我が国においても国際的な環境保全への協力等が進められている。主な取組をみる。
(1) 地球環境保全に向けての国連への協力等
我が国は、UNEP基金に対し米国に次ぐ拠出をし、UNEPの諸活動に大きな財政的支援をしているとともに、1982年のナイロビ会議において、「環境と開発に関する世界委員会」の設置を提案した。一方、環境庁では、1981年から「地球的規模の環境問題に関する懇談会」を設置し各種の提言を行ってきた。1987年には、「環境と開発に関する世界委員会」の報告等を受けて、同懇談会に特別委員会を設け、我が国としての具体的取組を検討している。また、我が国の研究機関等では、二酸化炭素濃度の測定等地球環境の科学的調査等に着手しはじめている。
(2) 環境保全技術の移転等
我が国は公害防止等の経験や技術を有しており、これらを政府開発援助の技術協力等を通じて移転している。
二国間の政府開発援助は、被援助国からの要請に基づき実施され、環境関連分野においては大気汚染防止、水質汚濁防止、造林・砂漠緑化、下水道・排水、廃棄物処理等の事業が実施されている(第3-4-19表)。
まず、現在環境関連分野での協力の中心になっている技術協力についてみる。技術協力は、研修員受入、個別専門家派遣、プロジェクト方式技術協力、開発調査等に区分される。
研修員受入(集団)は1970年代はじめから逐次コースが充実され1985年は82人で1975年の約二倍となっている。
専門家派遣(個別)は、1985年は63人で1975年の三倍を超える。
プロジェクト方式技術協力は、研修員受入、専門家派遣及び機材貸与の三つの形態を有機的に組み合わせ数年間にわたって計画的に実施するものであり、1985年現在パンタバンガン林業開発技術協力(フィリピン、1976年〜92年)など9プロジェクトが実施されている。
開発調査は、調査団を派遣し、対策のための計画策定等を行うものであり、1985年には上海(中国)、アンカラ(トルコ)の大気汚染対策調査、ジャカルタ(インドネシア)、アレキサンドリア(エジプト)の都市廃棄物対策調査、シンガポールの石炭火力発電所及び一貫製鉄所環境影響調査、フィリピンの広域森林情報管理分析等が実施されている。
また、1985年のボンサミットにおいて、アフリカの砂漠化防止のための協力の強化がうたわれたことを受けて、我が国は、アフリカの砂漠化防止のため「アフリカ緑の革命構想」を提唱した。同構想の一環として、地域に根ざした植林の推進を図る国際的ボランティアによる「緑の平和部隊」運動を提唱しており、1986年より青年海外協力隊がセネガルとタンザニアにおいて住民自身の手による多目的共有林の造成に対する技術指導、普及活動等を実施している。そのほか、1985年からケニア林業育苗訓練プロジェクト等を実施している。
無償資金協力の分野においては、下水処理施設建設計画、造林研究訓練施設建設計画等に対し資金の協力が行われている。
また、有償資金協力の分野においても、下水処理場建設等の事業に対し資金の協力が行われている。
環境保全の分野の二国間政府開発援助は、緒についたばかりのものも多いが、協力の件数は全般的にみれば着実に増加している。
このほか、産業界においても、専門家の派遣、開発途上国の企業関係者の研修等を通じて、蓄積されている産業公害防止技術を移転している。例えば、先に述べた「環境管理に関する世界産業会議」のフォローアップとして、我が国の企業の環境担当者を開発途上国に派遣している。(財)日本生産性本部、(社)産業公害防止協会等は、開発途上国の企業関係者の研修を実施している。また、経済五団体による「発展途上国に対する投資行動の指針」(1973年)及びこれを改訂した1987年4月の「対外投資行動指針」においては、直接投資に際し、受入国の環境に配慮する旨を盛り込んでいる。
(3) 希少な野生生物の取引対策、フロンガス対策等への国内体制の整備
希少な野生生物の取引対策のため、我が国は、1980年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約、1973年採択、1975年発効)の60番目の締約国となった。しかし、加盟当初においては、不正に輸入されたものでも一旦国内に持ち込まれると規制の方法がないこと、水際規制が不十分であること、留保品目が多いこと、といった理由から、我が国の条約の履行は必ずしも十分でないとの国際的批判もあった。
このため、1987年には「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」を制定し国内取引を規制することとした。同年12月から施行された同法に基づく政令では、規制対象品目として、附属書?のうち我が国の留保品目及び我が国で生息が認められ、かつ、狩猟、漁撈等が行われているものなどを除く630種が指定され、これらの動植物については、環境庁長官の許可又は登録を受けたもの以外は国内譲渡が禁止された。また、水際規制については、1987年から、税関における通関時確認制の対象になっている対象動植物(附属書?、?)のうち輸出禁止措置を講じている国を原産国とする当該動植物の輸入については輸出国に対して確認を行うこと(事前確認制)とするなど条約加盟以来随時規制強化措置が講じられてきたところである。さらに、留保品目については、1987年10月にアオウミガメとサバクオオトカゲを撤回し、14品目から12品目とするとともに、1989年を目途にジャコウジカについても撤回することとしている。
一方、フロンガス対策については、ウィーン条約に基づきモントリオール議定書が1987年9月に作成され、我が国もこれに署名した。政府は、第112回国会にウィーン条約及びモントリオール議定書の締結について承認を求めるととともに、同条約及び同議定書に規定する義務を履行するための基本的な枠組みとして「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律案」を提出したところである。
このほか、我が国は、先に述べたラムサール条約を1980年に締結し、釧路湿原(北海道)、伊豆沼・内沼(宮城県)を登録するとともに、米国、オーストラリア、中国との間に渡り鳥の保護条約・協定を締結している。また、海洋汚染の防止のためのロンドン・ダンピング条約、MARPOL73/78条約を締結し、対策の充実強化を図っている。