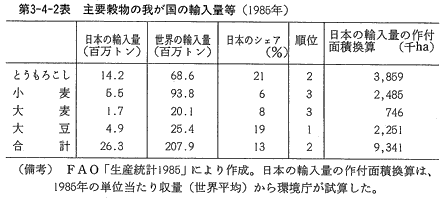
1 我が国の活動と地球環境とのかかわり
まず、我が国の様々な活動の動向を、資源輸入等の貿易活動、生産活動等、直接投資等の海外活動から概観し、それぞれの地球環境とのかかわりをみる。
(1) 資源輪入等の貿易の現状と地球環境とのかかわり
我が国の資源輸入の大宗を占める食料品、原材料、鉱物性燃料の輪入額は、1986年の総輸入額の58%となっている。これらには、農産物、木材、繊維原料等の自然の生産力に依拠する再生可能資源と、金属原料、石油等の非再生可能資源とがある。
まず、食料品の輸入をみる。食料品の輸入は逐年増加してきており、1986年の総輸入に占めるウェイト(金額)は15.2%となった。商品別(金額)にみると、エビ、とうもろこし、豚肉(臓器を除く。)、コーヒー、小麦等の順になっている。
このうち、近年著しい伸びを示し1986年には食料品の最大の輸入品目になったエビについてみる。エビの輸入量は、1985年には、世界の輸入量の3分の1を占めている。1986年の輸入量は22万t(我が国の生産量5万t)で、輪入先は台湾(金額構成比17.1%)、インド(同13.9%)、インドネシア(同13.7%)、中国(同8.8%)等となっている。エビは、東南アジア等の開発途上国の重要な輸出品の一つとなっており、養殖による生産の増大も図られている。
また、とうもろこし、小麦、大麦及び大豆の輸入の世界の輸入量に占める割合等は第3-4-2表の通りであり、これらの四品目の我が国の輸入量は作付面積に換算すると934万ha、我が国の畑の耕地面積243万haの3.8倍に相当する。
次に、原燃料等の輸入をみる。綿花、羊毛、木材、石油等の輸入については、我が国は世界最大の輸入国であるものが多い(第3-4-3表)。
このうち、原料品の輸入商品中最大のウェイトを占める木材の輸入をみる。1985年の我が国の木材の輸入は、世界の輸入数量の24%を占めている。丸太及びそま角と製材に分けて1986年の主な輪入先をみると、丸太及びそま角ではマレーシアと米国が、製材ではカナダと米国がそれぞれ大きな割合を占める(第3-4-4図)。このうち、熱帯地域からの木材(南洋材)の輸入は、近年減少しつつあるものの、1986年の我が国の木材輸入数量の42.0%、素材供給量の21.0%となっている。
世界全体の熱帯地域の木材(丸太及び製材)の主要な輸入国と輸出国をみると第3-4-5図のとおりである。
我が国の熱帯地域からの丸太(ラワン材といわれるフタバガキ科の樹木が中心)の輸入は、以前はフィリピン、インドネシアが中心であったが、これらの国々が資源保護、高付加価値化を目指し丸太輸出の制限等を行い、合板・製材輸出に転換したため、最近は、マレーシアのサバ州、サラワク州が中心となっている。
また、1986年の我が国の綿花の輸入は世界の輸入の15%を占め、輸入先は米国(数量構成比28.4%)、中国(同16.1%)、パキスタン(同13.5%)、オーストラリア(同13.4%)等となっている。
次に、野生生物の輸入をみる。
野生生物は、装飾品、医薬品等の原材料、ペット等として輸入されており、我が国は世界有数の輸入国である。絶滅のおそれがある野生生物としてワシントン条約でその取引が特に巌重に規制されているものについても、我が国は条約締約国のなかでも多くの留保品目を指定しており、輸入が行われている(第3-4-6図)(第3-4-7表)。
このように、我が国の資源輸入は、世界の資源輪入のなかでも大きなウェイトを占めるとともに、金属原料、石油等の非再生可能資源のみならず、農水産物、木材、繊椎原料等の自然の生産力に依拠する再生可能資源の輸入を通じて、地球環境と大きくかかわっていることがわかる。
一方、輸出面からの地球環境とのかかわりもある。ここでは、公害防止機器等の輸出についてみる。
我が国の公害防止機器の輸出額は、1986年度においては、580億円となった(第3-4-8図)。1986年度に大きく伸びたのは、主にアジア、大洋州地域への水質汚濁防止機器の輪出が増加したためである。地域別のシェアを最近5年間についてみると、東南アジア地域のシェアが高まっている(第3-4-9図)。1985年度のヨーロッパのシェアが大きくなったのは、酸性雨の被害が著しい西ドイツへの排煙脱硝装置の輸出のためである。
また、輸出品目のなかには、農薬、化学肥料等輸入国において適正に使用されるための措置が必要なものもある。
(2) 我が国の国内における諸活動と地球環境とのかかわり
我が国は、経済規模の大きな先進国として、国内の諸活動はいくつかの面で地球環境にかかわっている。
まず、我が国における諸活動をみる。
主要工業製品の生産活動をみると、その生産量、世界の生産量に占める割合等は、多くの分野で我が国の生産活動は世界のトップレベルの規模となっていることがわかる(第3-4-10表)。
また、これらの規模の大きな我が国の生産活動や、輸送活動、国民生活等を営むために必要なエネルギーの消費量は、1985年に3億1,000万t(石油換算)で世界の一次エネルギー消費量の4.9%を占め、米国、ソ連、中国に次いで4位となっている(国連エネルギー統計)。このうち、1985年の我が国の化石燃料の消費量の世界に占める消費量の割合(順位)をみると、石油7.2%(3位)、石炭3.5%(5位)天然ガス2.6%(5位)となっている(同統計)(第3-4-11表)。
これら国内における諸活動は、地球全体の環境に影響を及ぼすものもある。
ここでは、オゾン層の破壊、温室効果等の地球的規模の環境問題とかかわりのあるフロンガス、二酸化炭素、窒素酸化物等の我が国の排出量等についてみる。
まず、人の健康に係る物質でもあり、これまでこの面から削減対策が進められてきた硫黄酸化物、窒素酸化物について、OECD諸国との比較をすると、我が国の排出量は、主要先進国のなかではその経済規模に比し小さなものとなっている(第3-4-12図)。
次に、オゾン層の破壊の要因物質として排出削減対策が講じられることとなったフロンガスをみる。生産活動等のために使用・消費されるフロンガスの我が国の生産量をみると、1986年は約17万tであり、このうちモントリオール議定書により規制されるものは約12万tである。世界の規制対象のフロンガスの生産量は、1986年で約100万tであるといわれており、我が国の生産量の割合は一割強である。我が国におけるフロンガスの使用形態等は第3-4-13図のとおりである。
一方、温室効果をもたらす主要な気体であるとされ、その気侯変動等への影響について科学的調査等が実施されつつある二酸化炭素のうち化石燃料の消費に伴うものの排出量をみると、1985年の世界全体の排出量は193億8,000万t、我が国は8億4,200万tで世界の4.3%(4位)となっている(第3-4-14表)。化石燃料の消費に伴う二酸化炭素の排出量の年平均伸び率を1965年〜75年、1975年〜85年でみると、世界全体では、それぞれ3.9%、2.0%、我が国は、それぞれ7.9%、1.2%となっている。
(3) 我が国の海外活動と地球環境とのかかわり
我が国の海外直接投資、政府開発援助の動向から、我が国の海外活動と地球環境とのかかわりをみる。
ア 海外直接投資
我が国の海外直接投賛は、1980年代に入って急速に拡大を続けており、1986年度には、223億2,000万ドル(大蔵省届出ベース)となっている。1986年度末の累積(1951年度以降の累積額)も、1,059億7,000万ドルと1,000億ドルを超え、我が国は、世界有数の海外直接投資国となった。業種をみると1986年度末の累積で、商業・サービス60.4%、製造業26.6%、資源開発13.0%となっている。地域別にみると、商業・サービスは北米の割合が高く、製造業や資源開発ではアジアの割合が高い。アジア向けの製造業直接投資累計を1986年度末でみると、鉄・非鉄、化学、繊維、電機の順であり、電機、輸送機の割合の高い北米向けと比べると基礎素材産業の割合が高いことがわかる。また、近年、アジアが輸出生産拠点として見直され、そこでの生産による第三国輸出あるいは我が国への逆輸出が増加傾向にある。アジア諸国における我が国の直接投資の地位(累計ベース)についてみると、第3-4-15表のとおりであり、大きなウェイトを占めていることがわかる。
こうした海外直接投資、特に製造業の進出は、受入地の水、土壌、大気等といった環境とのかかわりを持つ。我が国からの進出企業の環境保全対策の状況を(財)日本在外企業協会が1983年に実施した調査でみると、環境保全対策の実施状況は第3-4-16図のとおりである。また、総投資額のうち環境保全対策費の割合は、平均して先進国へ進出した製造業で8.1%、開発途上国へ進出した製造業で6.7%となっている。
イ 政府開発援助
我が国は、これまで開発途上国に対する経済協力、とりわけ政府開発援助(ODA)の実施を我が国の国際社会において分担すべき最も重要な責務の一つとして認識し、その拡充に努めてきた。その結果、我が国の政府開発援助は、飛躍的に増大し、1986年における我が国のODA量は、56億3,400万ドルと米国(95億6,400万ドル)に次いで第2位の地位を占め、DAC諸国のODAに占める割合も約15%となっている。
政府開発援助は、二国間援助と多国間援助からなっており、我が国は、二国間援助の中の借款の割合が高い(1986年のDAC諸国全体の借款の41%は我が国が占める。)(第3-4-17図)。
二国間援助についてみると、地理的配分は、1986年においては、アジア64.8%、アフリカ10.9%、中近東8.8%、中南米8.2%等となっている。
対象分野としては、借款の割合が高いこともあって、発電所、通信、運輸といった経済インフラが高い比率を占めており、これらは1985年〜86年の平均でみても全体の37.3%(DAC諸国全体のこれらの分野の比率は16.5%)となっている(第3-4-18図)。
また、国際機関への出資・拠出等からなる多国間援助をみると、1986年においては国連等への国際機関贈与が21%、世界銀行等への国際機関融資等が79%となっている。
こうした我が国の政府開発援助、特に経済インフラや鉱工業、建設等の分野は、被援助国の環境とのかかわりが深い。