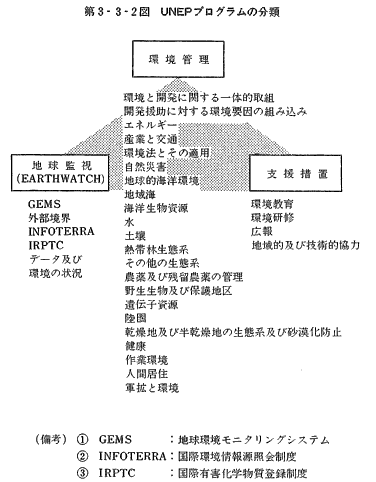
2 地球環境保全への国際的取組の進展
これまでみたような環境問題に関する国際的な認識の高まりを背景に、国際機関、関係国、非政府機関(NGOs)等では、様々な分野で地球環境保全に対する国際的な取組を行ってきている。主要な取組についてみる。
(1) 国連環境計画(UNEP)等国連関係機関等の取組
ストックホルムの国連人間環境会議を契機に、環境保全分野での活動を促進するため、国連総会の決議を経て、1972年UNEPが設置された(本部ナイロビ)。UNEPは既存の国連諸機関が行っている環境に関する諸活動を総合的に調整管理するとともに、広範な機関等の環境保全分野での活動を促進することを目的としており、各種の実施機関の間の触媒機能、調整機能の役割を担っている。
UNEPの活動のフレームワークは、地球監視(環境の現状及び将来の趨勢の把握・評価)、環境管理、支援措置の三つの柱からなっいる(第3-3-2図)。地球監視の分野では、地球環境モニタリング・システム(GEMS)によって各種の専門機関とのネットワークを通じて熱帯林等の再生可能資源、気侯変動、健康に関連する汚染物質(第3-3-3図)、酸性雨に関係する汚染物質の長距離移動、海洋環境等に関する監視、世界各地に測定地域を置いた人体暴露評価計画(HEALs)等を行うとともに、国際環境情報照会制度(INFOTERA)、国際有害化学物質登録制度(IRPTC)等を実施している。環境管理の分野では、様々な領域で環境プログラムの策定、各種ガイドラインの作成、パイロット・プロジェクト等に対し、技術的、財政的支援を行っている。また、支援措置の分野では、環境教育、環境研修のプログラム等に支援している。
また、UNEPは、1982年から、環境対策が早急に求められている開発途上国に対し、先進国や他の国連機関から有効な援助が得られるよう仲介者としての役割を果たすため「クリアリング・ハウス計画」を推進しており、西ドイツ、オランダ、スウェーデン、アルゼンチン等が財政的援助を行っている。これは、開発途上国の環境管理計画の策定や環境改善のための対策事業を実施すべき地域等についてUNEPがコンサルティングを行い、その結果をもとに当該対策事業等の具体的実施のための援助を先進国の援助機関等に照会するための仲介を行う仕組みである。
このような活動のフレームワークのもとで、UNEPは、地球環境問題の多くの分野で中心的な役割を果たしてきた。例えば、温室効果等に関する科学的知見の集積、熱帯林の減少、海洋汚染等の重要な環境問題に関し各国をはじめとする世界の関心の高揚、砂漠化、地域海汚染等の問題に関する行動計画や戦略づくりへの支援、オゾン層の保護に関する条約や海洋環境保全のための各種地域協定の制定等があげられる。また、現在では、これらの条約・協定を適正に運営するうえでの事務局としての役割も大きくなっている。
現在、UNEPでは、1990年代前半の国連における環境関係の活動の基本方針となる「システムワイド中期環境計画」(1990-95年)及び「UNEP中期計画」(1990-95年)の策定作業を行っており、これらのなかで「持続的開発」の理念を具体化することとしている。
UNEPのほか、国連教育科学文化機関(UNESCO)、FAO、WHO、WMO等が科学的調査等の諸活動を実施している。例えば、UNESCOは、「人間と生物圏計画」(MAB計画)を1971年から開始しており、「生物圏保存地域」として266地域を指定し、保護研究モニタリング等を行っている。また、FAOは、1985年に熱帯林の保全と適正な開発のため、「熱帯林生態系の保全」等の優先すべき五分野についての行動指針を示した「熱帯林行動計画」を採択した。現在、これに基づき各開発途上国別に行動計画が作成されており、当該計画は熱帯林の減少に対する効率的、効果的な対応を促進するものとして期待されている。さらに、UNEPと協力して、熱帯林の科学的調査を実施するなどのほか、農薬の不適切な使用等に伴う各種の環境間題に対処するため、1985年に「農薬の流通及び使用に関する国際行動規約」を採択し、農薬規制の法的措置がない国に対する自主基準の設定、農薬輸出国への協力要請等を行っている。なお、国際熱帯木材機関(ITTO:1986年に横浜に本部設置)は、熱帯木材経済(木材の貿易、流通等)に関する諸問題を解決するために設立されたものであるが、熱帯林の持続的利用と保全を目的の一つとしており、この分野での貢献も期待されている。
一方、国際開発金融機関については、世界銀行が1970年に環境保全に関する取組を開始しているが、1980年には、UNEP、世界銀行、アジア開発銀行等10の機関が「経済開発に係る環境政策及び手続きに関する宣言」を採択し、環境に配慮した責任ある開発の必要性を明らかにした。世界銀行は、1984年に融資に際しての環境保全上の配慮に関する基本方針を公表するなど、融資審査の様々な段階で環境保全のために配慮されるべき種々の技術的ガイドラインを作成してきている。また、世界銀行は、1985年に、アマゾンのボロノルエステ地方の開発援助プロジェクトに対する融資について、環境破壊を招くとして、ブラジル政府との合意のもと、このような環境破壊が是正されるまでは貸出しを停止する旨の決定を行った(現在までのところ貸出しは再開されていない。)。世界銀行は著しい環境破壊をもたらすようなプロジェクト、国民の健康と安全を著しく損なうようなプロジェクト等には融資を行わないとの考え方を示しており、1987年には環境政策のための体制を拡充・強化するなど環境保全に積極的な政策を採用している。このほか、アジア開発銀行等においても、環境保全への配慮等を重視して、その取組を進めている。
(2) 経済協力開発機構(OECD)等の取組
OECDでは、化学物質対策として既存化学物質の安全性の調査等を行うほか、酸性雨、有害廃棄物の移動等の国境を越える環境問題、開発途上国の持続的開発に対する環境協力等に関する取組が行われている。
酸性雨問題については、OECDは1972年に大規模モニタリング計画として大気汚染物質長距離移動計測共同技術計画(LRTAP)を発足させ、1977年には欧州における硫黄化合物の越境収支を明らかにした。酸性雨対策のための排出規制については、後述の「越境大気汚染条約」に基づく硫黄酸化物の30%削減措置が講じられているほか、ECは、自動車の排ガス規制値を強化し、新規制値は本年1月から順次適用されている。
有害廃棄物の越境移動の問題についてOECDは、「有害廃棄物の越境移動に関する決定及び勧告」(1984年)等を理事会において採択し、有害廃棄物の越境移動を管理するための協定を作成することを決定した。現在、協定作りの作業が進められている。
また、OECDにおいては、近年、開発途上国との環境協力の強化を図っている。OECD環境委員会は、1983年に「環境アセスメントと開発援助特別グループ」を設置し、OECD開発援助委員会(DAC)の協力を得て、1985年に「開発援助プロジェクト及びプログラムの環境アセスメントに関する理事会勧告」を採択し、環境に著しい影響を及ぼす可能性のある開発援助プロジェクト等については、可能な限り早い段階で適切な程度に環境の観点からアセスメントを行うべき旨勧告した。また、1986年には同じくDACの協力を得て「開発援助プロジェクト及びプログラムに係る環境アセスメントの促進に必要な施策に関する理事会勧告」を採択した。主要援助国が開発援助に環境配慮を行う必要性について合意した意義は大きい。
(3) 条約による取組
環境保全の分野でも1970年代から自然保護、海洋汚染防止、大気保全等の分野で各種の条約が締結され、着実に国際協力が進んでいる。
ア 多数国間条約
野生生物保護、海洋汚染防止、オゾン層の破壊等の地球的規模の環境問題に関する条約について、その代表的なものをみる。
まず自然保護の分野である。
水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を指定しその保全を進あることを目的とした「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)が1971年に採択されている。また、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)については、1973年に採択された。このほか、我が国は締結していないが、「世界の文化遺産及び自然遺産保護条約」(1972年)、「野生動物の移動性の種の保存に関する保護条約」(ボン条約、1978年)が採択されている。
次に、海洋汚染防止のための条約をみる。
海洋汚染の防止については、1972年11月陸上で発生した廃棄物の海洋投棄を規制する「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン・ダンピング条約)が採択され、さらに、船舶からの油や有害物質の排出の規制については「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)が1987年に採択された。
また、大気環境保全の世界的な条約として初めて「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が1985年に採択された。フロンガスによるオゾン層の破壊に伴う影響等については先に述べたが、1974年に米国学者が問題提起して社会問題化したことを受けて、UNEPが中心になってオゾン層保護のための国際条約の作成に向けて作業が進められてきたものである。同条約では、オゾン層の保護のために適切な施策をとるべきこと、調査・研究の推進を図ることなどが規定された。規制対象物質、規制スケジュール等具体的規制方法を定める議定書は、1987年9月にモントリオールにおいて採択された(「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」)。地球的規模の環境問題の予防的措置として、国際的合意が成立した意義は大きい。
イ 地域間、二国間条約
酸牲雨に関する物質の越境移動、地域海の汚染、国際河川の汚染など国境を越える環境問題について、地域的な条約が締結されている。
欧州等で問題となっている酸性雨については、国連欧州経済委員会(UNECE)において1979年に「越境大気汚染条約」が採択された。その後、1983年にオタワにおいて「酸性雨に関するカナダ・ヨーロッパ環境大臣会合」が開催され、関係国が硫黄酸化物の排出量を1993年までに1980年の30%減のレベルにまで削減することについて合意された。これを踏まえ、1985年にヘルシンキでの越境大気汚染条約執行委員会において硫黄酸化物の30%削減が同条約の議定書として採択され、署名国は現在21ヶ国に及んでいる。
また、地域海の保全のため、地中海における「地中海汚染防止条約」(バルセロナ条約)、南太平洋地域における「南太平洋地域の自然地域及び環境保全のための条約」等がUNEPの地域海プログラムの一環として採択されている。国際河川の水質汚濁対策のための条約も整備され、例えば、スイス、西ドイツ、フランス及びオランダを流れるライン川では、「ライン川塩化物汚染防止条約」「ライン川化学汚染防止条約」が締結されている。
一方、野生生物保護のための地域間、二国間の条約は、西半球条約、ベルン条約、アセアン条約等極めて多く締結されている。
(4) 非政府機関(NGOs)等の取組
地球環境の保全に関しては、NGOsあるいはそのネットワークが様々な取組を行っている。例えば、ローマクラブ、IUCN等は、地球環境の将来予測等を行い、米国の「世界資源研究所」(WRI)、「世界監視研究所」、イギリスの「国際環境・開発研究所」(IIED)等は、地球環境のデータ整備・評価等を行っている。また、IUCN、「世界自然保護基金」(WWF)、TRAFFIC等では、種の保全等に関する調査や支援を実施している。これらをはじめ、世界には数多くのNGOsが活動を展関しており、UNEPが情報提供しているものだけでも6,000団体を超えている。
こうしたNGOsの活動のなかで最近ユニークな取組として、1987年7月に米国の自然保護団体「コンサベーション・インターナショナル」がボリビア政府との間で、「対外債務の自然保護払い」に関する協定を結んだことが注目されている。これは、ボリビアの対外債務のうち65万ドルを「コンサベーション・インターナショナル」が引き受けるかわりにボリビア政府は約160万ha以上にわたる自然保護区域(UNESCO「MAB計画」によって生物圏保存地域として指定された「ベニ生物保存地域」を中心とする。)を創設し、これらの地域の保護管理のために、ボリビア政府は25方ドルの基金を設けることとしたものである。
一方、産業界においても取組が進められている。例えば、1984年「環境管理に関する世界産業会議」がUNEPと「国際商工会議所」(ICC)の共催で開催され、その際に採択された勧告に沿って先進国の民間企業の専門家を開発途上国の産業公害防止の協力のために派遣する等の活動が行われている。
このように、1970年代初頭から地球環境の保全に関し様々な主体が取組を行っている。1987年12月の「環境と開発に関する世界委員会報告に係る国連総会決議」は、国連機関の持続的開発への努力におけるUNEPの役割を強化することに同意するとともに、各国政府、NGOs、産業界等各レベルにおける持続的開発の努力を要請しており、各国政府等の責任はますます大きくなっている。