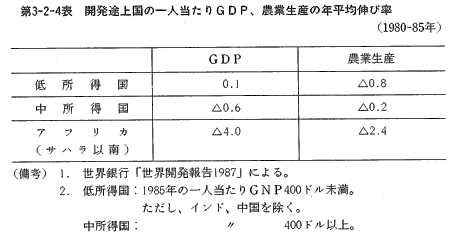
2 開発途上国の貧困と環境問題
開発途上国では、工業化、都市化の進展等によって大気汚染、水質汚濁等先進国型の公害問題が深刻化している地域がみられる一方で、多くの開発途上国、とりわけ低開発国(LDC)では、人口の増大、貧困といった国内的問題を抱えており、土壌、森林等に対する利用圧力が増大している。また、開発途上国の大部分は、なお一次産品やその低加工品の輸出に依存した経済構造を抱えているが、近年の一次産品価格の低迷、対外累積債務の増大等により、換金作物への作付転換等が行われ、これが国内の環境に対する利用圧力を一層高めている面がある。このように多くの開発途上国では、国内的にも、国際的にも自国の環境を収奪せざるを得ないような状況に追い込まれており、一部の地域では、自らの食糧生産等に支障が生じているばかりでなく、将来の成長や開発を支える潜在基盤までも損なわれつつある。環境は適切に利用すれば再生可能な資源であるが、人口、経済、開発、環境等の間の相互関連が強まる中で、環境の過度な利用が促進されるメカニズムが働き、環境問題を深刻化させているといえる。そこで、以下では、人口増加や貧困と環境問題及び一次産品貿易と環境問題に焦点を当てて具体的にみていくことにする。
(1) 人口の増加、貧困の深刻化と環境問題
1980年から85年の間の開発途上国の人当たりGDPの年平均伸び率をみると(第3-2-4表)、低所得国は0.1%、中所得国は△0.6%、特にサハラ以南のアフリカでは△4.0%となっている。また、同期中の一人当たり農業生産についても、低所得国では△0.8%、中所得国では△0.2%となっており、経済的困難が続いている。
こうした状況を背景として、開発途上国の一人当たり食糧カロリー供給量は先進国の72%(1983-85年)にとどまっており、なかでもアフリカは61%と低い(第3-2-5表)。栄養不足人口数は、1969-71年の4億6,000万人から1983-85年には5億1,000万人へと増加している。また、燃材不足に苦しむ人々は、1980年で開発途上国に約13億人も存在している。UNEPによれば、2000年に向かって開発途上国の農民一人当たり耕地面積は減少する一方、栄養・燃材不足といった貧困に苦しむ人々は引き続き増加するとしている。
こうした貧困の最大の要因は人口の急増である。すなわち、開発途上国の人口増加率は、70年代に入って伸びは鈍化したものの依然2%を超えており、3%を超える国もみられる。人口の急増は、食糧・燃料需要を増加させ、それが耕地や薪炭材需要の増大をもたらし、森林、土壌等の環境への圧力を強める。すなわち、熱帯林の農地への転換、薪炭材の過剰伐採、耕地・放牧地の酷使などが行われ、熱帯林の減少、砂漠化等につながっていく。こうした生活基盤である環境の破壊は、貧困を深刻化させるとともに、貧困に苦しむ人々が生存を維持するためにさらに環境を破壊するという「貧困と環境破壊の悪循環」が生じている。
そこで、環境破壊をもたらす具体的な活動についていくつかみてみる。
まず、熱帯林の最大の減少要因となっている焼畑移動耕作についてみる。焼畑移動耕作は、熱帯地方でみられる伝統的な農業生産形態であり、森林を伐採して火入れを行い、1〜3年はそこで耕作を行った後に別の森林に移動し、元の耕地は森林として回復するまで侍つという人口が少なければ維持可能な農業形態の一つである。しかし、農村人口は自然増がみられるとともに、地域によっては農地を求める人々の移住等によって耕地への需要は高まり、森林の焼畑農地への転換を促進している。木材運搬等のために開設された道路は、焼畑農民の森林への侵入を容易にし、その減少を加速している。また、既存の焼畑農地においても、休閑期の短縮等による過度な利用圧力が強まっており、土壌の悪化が起こり、最悪の場合には砂漠化に至ることもある。
次に、薪炭材の伐採についてみる。開発途上国の多くの国では、撚料のかなりの部分を薪炭材に依存しているため(第3-2-6図)、人口増加は薪炭材需要の増加につながり、森林の過剰な伐採が行われることになる。また、薪炭材不足を補うために、肥料として利用されてきた動物のふんや収穫残余物が燃料として利用され、それが地力の低下をもたらし、砂漠化などにつながることもある。
人口増加に起因する家畜の過放牧も、熱帯林、特に疎林の減少や土壌侵食等の大きな要因となっている。これは、家畜の増加によって新芽が食べ尽くされたり、過度に踏みつけられたりして草木の再生が妨げられるからである。
(2) 一次産品貿易と環境問題
一次産品貿易等の対外的要因も開発途上国の環境問題と深いかかわりを持っている。
開発途上国をとりまく対外的経済環境は、近年、厳しい状況にある(第3-2-7図)。1980年代に入り、世界的な需給の緩和を背景として一次産品価格は低迷しており、一次産品輸出に多くを依存しているサハラ以南のアフリカ、ラテンアメリカ諸国等の貿易収支は悪化している。また、累積債務問題についてもラテンアメリカ諸国を中心に深刻化しており、返済のための元利払いも増大している。こうした対外収支の悪化は、経済成長の阻害、生存のために必要な食糧等の輸入の制約等により貧困を悪化させる要因となる。
また、輸出用一次産品生産の際、再生可能限度を上回る過度な環境利用等により、貴重な資源が減少したり、環境破壊を招いている事例が世界各地で生じている。
まず。輸出用の商品作物等の生産のため、熱帯林が大規模に耕地・牧草地に転換され減少している地域がある。ブラジルのアマゾン地域及び中央アメリカでは、輸出用の牛の飼育が熱帯林を減少させる主な原因となっている。例えば、ブラジルのアマゾン地域では、1966〜78年の間に800万haの森林が336ヶ所の牧場に転換され、そこで600万頭の牛が飼育されるようになった。またアフリ力では、綿花等の輸出作物生産が大農場で経営される一方で、土地を失ったか、あるいは零細な自給農民が耕地を求めて熱帯林の減少や砂漠化を引き起こしている例もある。
一方、主にラワン材と呼ばれるフタバガキ科の樹木の世界最大の輸出地域である熱帯アジア地域における利用対象とされる樹木の資源量をみると、その量は減少しており、1980年末現在30億m
3
にすぎず、今後も減少すると見込まれている(UNEP/FAO前掲書)。例えば、フィリピンは、かつては熱帯木材の主要な輸出国であり我が国の輸入先としても重要な地位を占めていたが、資源量の減少により、丸太の輪出制限を行っている。また、マレーシア(サバ州、サラワク州)は、1985年において世界の木材輸出の約19%、特に広葉樹の輸出では世界の約66%を占めている現在世界最大の熱帯木材輸出国であり、同国の重要な外貨収入源となっているが、例えば輸出の中心であるサバ州の林業省によると、サバ州における天然林の丸太生産量は90年代中頃には地場消費を賄う程度に減少するとみられている。
さらに、国際取引により、開発途上国を中心にして、いくつかの野生生物が絶滅の危機に瀕していることがあげられる。野生動植物国際取引調査記録特別委員会(TRAFFIC)(USA)によると、現在ワシントン条約により国際取引が規制されている絶滅のおそれのある野生動物(製品を含む。)の合法的な取引額は50億ドルに、また、不正な取引額は10億ドルに達するものと推定されている。