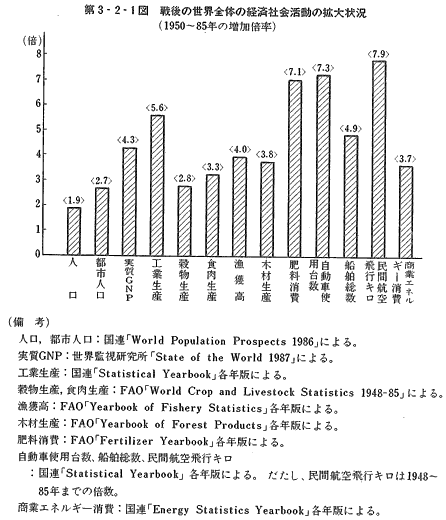
1 世界的な経済社会活動の拡大と環境負荷の増大
今世紀は、人類にとって飛躍的な発展を遂げた世紀として位置づけられるが、その発展の大部分は今世紀後半からのものである。ちなみに、1900年から85年までの間に人口は約3倍、実質GNPは約21倍、エネルギー消費は約15倍に増加したが、そのうち、人口増加の七割強、実質GNP及びエネルギー消費増加の八割強は1950年以降に生じたものである。このように、今世紀半ばからの地球上の人間活動は歴史上類例のない規模とスピードで拡大しているが、その反面で地球環境への負荷が増大し、局地的な問題にとどまらず地球生態系の維持能力、浄化能力にも影響を及ぼしつつある。そこで、まず今世紀半ば以降の世界的な経済社会活動の拡大(第3-2-1図)と環境問題のかかわりについてみてみよう。
(1) 経済社会活動の拡大
ア 人口
世界の人口は、1950年から85年までの35年間で25億人から48億人へと1.9倍となり、87年には2倍の50億人を超えた。近年、増加テンポは鈍化しているものの、現在の傾向が続けば2000年には60億人を超えるとみられる。なかでも、開発途上国における増加が著しく、2000年までの増加人口の90%以上はこの地域で生ずるとされている。
また、増加する人口の大部分は都市地域で発生している。世界全体でみた都市人口は、1950年から85年までの間に約3倍となり、地域別では、先進国では2倍であるのに対し、開発途上国では約4倍であり、増加のテンポが急速である。
イ 経済活動
世界全体の経済活動も著しく増大しており、実質GNPは1985年までの35年間で4.3倍となっている。
とりわけ工業生産は、技術革新、国際貿易の活発化等を背景に大きく増加し、同5.6倍となった。工業の中心は依然として先進国にあるが、近年の新興工業諸国(NICs)の高成長にみられるように、開発途上国でも工業化が進んでいる。
一次産業の生産も着実に増加している。農業生産は、機械化、品種改良、肥料・農薬の普及等から着実に増加し、穀物生産は1985年までの35年間で2.8倍、食肉生産は3.3倍となっている。また、漁獲高は4.0倍、木材生産も、産業用、燃料用のいずれも増加し3.8倍となってる。
経済活動の増大、都市化、モータリゼーションの進展等に伴い、人・物の国内・国際間の交流も飛躍的に増大している。自動車交通、航空機輸送の増加が著しく、近年は低迷しているもののオイル・タンカー等船舶輸送も含め、陸・海・空を通じた運輸活動は大きく増大している。
さらに、多国籍企業等による国境を越えた企業活動も活発化している。
ウ 資源・エネルギー消費
生産、消費、運輸活動等の増大を背景に、世界的な資源、エネルギー消費も著しく増加している。ここでは、エネルギー、水資源についてみてみる。
エネルギーについてみると、商業エネルギーの消費は、1970年代後半に入って、石油危機を契機とした経済成長の鈍化や省エネルギーの進展等から伸びが鈍化しているものの、1950年から85年までの間では、世界全体で3.7倍となっている。エネルギー供給源としては、先進国では石油、天然ガス、石炭などの化石燃料の消費への依存が大きく(1985年95%)、開発途上国では薪炭材等のバイオマスに依存する比率も高い(1984年の薪炭材依存度19%)。
また、水資源の消費も人口増加、工業・農業生産の増大等により増加している。先進国では工業用の消費のウェイトが大きいのに対し、開発途上国ではかんがい用のウェイトが大きく、世界全体(1975年)では、かんがい用73%、工業用22%、生活用5%と推定される。
エ 土地利用
人口、生産活動の増大は、農地、工業用地、都市用地等様々な用途のための土地資源への需要圧力を高めており、それに伴い世界の土地利用状況も大きく変化している。
このうち、世界の陸地の約3分の2を占める農地(耕地、樹園地、牧場・牧草地)及び森林面積の動向についてみると、1970年から85年までの間に、農地は年間425万ha増加(面積比率は0.4ポイント上昇し35.5%ヘ)しているのに対し、森林は農地への転換等により年間694万ha減少(同0.8ポイント低下し31.3%へ)している。農地の増加の約9割は耕地の増加によるもので、耕地の増加テンポは次第に低下しつつあるものの、年間378万ha増加している。
こうした変化は開発途上国でより大規模に発生しており、同期間中における開発途上国の農地の年間増加面積は世界全体を上回る479万ha、他方、森林の年間減少面積は世界全体を上回る767万haとなっている。なお、耕地面積については、世界全体の増加の90%以上を開発途上国が占めている。
(2) 環境負荷の増大
経済社会活動の拡大に伴い、様々な形での地球環境への負荷が増大している。ここでは、主として先進国で問題となっている化石燃料、化学物質、廃棄物の三点を取り上げ、環境問題とのかかわりをみていく。
ア 化石燃料消費の増大と環境問題
化石燃料消費の増大は、二酸化炭素、二酸化硫黄、窒素酸化物等の大気中への排出の増加を伴い、それが国内の環境問題にとどまらず、二酸化炭素濃度上昇による温室効果、酸性雨等の地球環境問題とかかわりがある。
大気中の二酸化炭素濃度の増加は、化石燃料の使用増大が主な原因となっているが、その排出を防止する技術は現時点では存在しない。化石燃料の消費による二酸化炭素の排出量は、戦後、大きく増加している(第3-2-2図?)。化石燃料の消費割合の高い先進国の排出割合が大きく、1985年時点では66%を占めている。また、化石燃料の燃焼に伴う二酸化炭素の排出量は化石燃料の種類によって異なるが、同年での全世界の燃料別の排出割合をみると、石炭39%、石油43%、天然ガス15%となっている。
二酸化硫黄の排出量も大きく増加している(第3-2-2図?)。先進国では、エネルギー転換部門、特に、発電所における化石燃料の燃焼が排出の最大の要因であり、工業活動による分も大きい。窒素酸化物の排出量についても、輸送部門、工業部門及びエネルギー転換部門における化石燃料の消費が主要な人為的要因であり、二酸化硫黄と同様に増加している。
イ 化学物質の利用の増大と環境問題
化学物質は、現在、世界で数万種類が生産され、その数は毎年1,000〜2,000種類ずつ増加しているといわれる。また、化学物質のうち有機化学物質の世界全体での生産量は、1950年に700万tであったものが85年には2億5,000万tへと約35倍になったと推定される。
化学物質の利用の増大は、工業・農業生産性の向上や我々の生活の向上に大きく寄与してきた。しかし、化学物質の中にはその性質上、生産、流通、使用、廃棄の過程を通じて環境中に広く拡散することは避けられないものが多い。また、製造過程等における事故によって、環境中に放出される場合もある。しかも、分解されにくく、環境残留性の高い物質もある。
近年、オゾン層破壊とのかかわりが問題となっているフロンガスは、1930年代に米国で開発され、その生産量は、戦後、特に1960年代に急速に増加した(第3-2-3図)。フロンガスは、化学的な安定性、不燃性、極低毒性等の優れた性質を持っており、エアゾール製品の噴射剤、冷媒、洗浄剤等に広く使用されている。その大部分は先進国で使用されており、用途としては、エアゾール製品向けは低下してきているものの、そのほかの用途は増加を続けている。フロンガスは、オゾン層を破壊するおそれのある物質として各国が協調して削減対策がとられることになったが、大気中に放出されると長期間にわたりオゾン層に影響を与える。そのため、被害が顕在化してから削減対策を講じても、その効果が現れるまでには時間がかかる。
また、我が国でもかつて環境影響が問題となったPCBは、耐熱性、化学的安定性、難分解性等の優れた性質から熱媒体、塗料等に広く使用されてきた。しかし、その後健康影響が明らかになり、現在は世界的にみて生産禁止又は縮小が行われているが、南極において検出される例もあるなど地球的規模での汚染の拡散がみられる。
農業生産にも化学肥料、農薬などの化学製品が大量に利用され、農業生産性向上に大きく貢献してきた。しかし、化学肥料は硝酸塩による地下水汚染や徴生物の減少等による土壌悪化、燐・窒素成分による富栄養化などの環境問題の一因となっており、農薬についても、一部の国々では残留性の高い種類のものが依然として使用されている。例えばDDTは、我が国では農薬としての販売が禁止されているが、開発途上国の中には使用を続けている国もあり汚染の拡散が懸念されている。
ウ 廃棄物の増大と環境問題
廃棄物の発生量も増大している。
都市生活から発生する廃棄物(都市ごみ)は、人口の増加、消費の拡大・高度化等によって増加している。都市ごみの形態は国ごとの生活様式等を反映して多様なものとなっているが、先進国では紙、ボール紙、包装用のプラスチック等の占める割合が大きい。また、一人当たりの排出量は先進国の都市の方が開発途上国の都市に比ベ大きいが、今後、開発途上国でも所得の上昇や都市化の進展等に伴い発生量が増大していくものとみられる。
産業活動に伴って発生する廃棄物(産業廃棄物)は、都市ごみに比べ量的に大きく、OECD諸国全体でみると、都市ごみ3億5,000万tに対し約3倍の10億t排出されている(1980年)。近年、工業生産の伸びの鈍化やリサイクルの進展等を反映して量的には伸びが鈍化しているが、有害廃棄物や処理困難な廃棄物の増加など、問題が複雑になってきている。
廃棄物の処理は、埋立てによる処理割合が大きいが、先進国では廃棄物量の増大に伴い埋立処分地の確保が困難となってきている。また、有害廃棄物については、米国ラブキャナル等でみられたような過去の不適正処分地、不法投棄等により地下水汚染等を引き起こしたり、国境を越えて移動する際に適切な管理が十分行われていないといった問題が生じている。さらに、開発途上国においては、都市ごみ等の廃棄物を処理するシステムの整備が遅れており、衛生的にも大きな問題となっている。