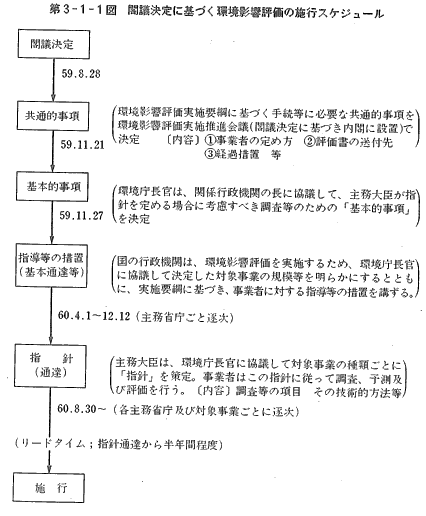
2 環境影響評価
悲惨な公害や自然環境の破壊を繰り返さないため、また、環境問題の根本的な解決のためには、一度起こった公害を除去するばかりでなく、環境汚染を未然に防止していくことが極めて重要である。
環境影響評価、いわゆる環境アセスメントは環境汚染を未然に防止するための有力な手段の一つである。すなわち、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、その環境影響について事前に十分に調査、予測及び評価を行うとともに、その結果を公表して、地域住民等の意見を聴き、十分な公害防止等の対策を講じようとするものであり、その必要性については広く認識が定着している。
国際的にみても、アメリカ、スウェーデン、オーストラリア、西ドイツ、フランスなどの欧米諸国のほか、韓国、タイ、フィリピン、中国等アジア諸国においても、それぞれの国情に応じ、環境影響評価の実施又は制度の確立をみている。また、経済協力開発機構(OECD)においては49年及び54年に環境影響評価の手続、手法等の確立についての理事会勧告が採択され、さらに、60年6月には、開発援助における環境アセスメントについての理事会勧告が採択された。
我が国においては、47年6月の閣議了解「各種公共事業に係る環境保全対策について」以来公有水面埋立法等の個別法や各省庁の行政指導により環境影響評価が行われてきた。また、地方公共団体においては、26の都道府県・政令指定都市において環境影響評価に係る条例・要綱等が制定され、残りのいくつかの都道府県・政令指定都市においても制度化の検討が進められている。
これらの環境影響評価は、その手続などがそれぞれ異なっており、また、評価手順等が十分整備されていないものもあり、制度として統一的な手続等の確立を図る必要がある。
このため、政府は、56年4月に環境影響評価法案を国会へ提出したが、この法案は58年11月衆議院解散に伴い廃案となった。そこで同法案の要綱をベースとして実効ある行政措置を早急に講ずることとし、59年8月28日に「環境影響評価の実施について」の閣議決定が行われた。
本閣議決定においては、国の関与する大規模な事業に係る環境影響評価の統一ルールとして「環境影響評価実施要綱」が定められている。この実施要綱において、対象事業は、規模が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるもので、国が実施し、又は免許等で関与するものとして、道路、ダム、鉄道、飛行場、埋立て、干拓及び土地区画整理事業などの面的開発事業等が定められている。事業者が行う手続の概要は、次のとおりである。
? 事業者は、対象事業の実施による影響について主務大臣が環境庁長官に協議して定める指針に従って事前に調査、予測、評価し、環境影響評価準備書を作成する。
? 事業者は準備書を公告・縦覧し、説明会を開催する。
? 事業者は、関係地域に住所を有する者の準備書についての意見の把握に努める。事業者は、都道府県知事に対し、市町村長の意見を聴いた上で、意見を述べるように求める。
? 事業者は、これらの意見を聴いて、環境影響評価書を作成し、評価書を公告・縦覧する。
このような環境影響評価の結果を国の行政に反映させるために行政庁は対象事業の免許等に際し、評価書をもとに環境影響に配慮し、また、その際、必要に応じ環境庁長官の意見が反映されるよう考慮されている。
この実施要綱に基づく環境影響評価は、国の行政機関(対象事業を所管する省庁:主務省庁)が事業者に対する指導等の行政措置を講ずることによって実施されるものであり、環境庁を始めとして関係省庁で連携を図りつつ準備作業が進められ、逐次実施に移行されているところである(第3-1-1図)。