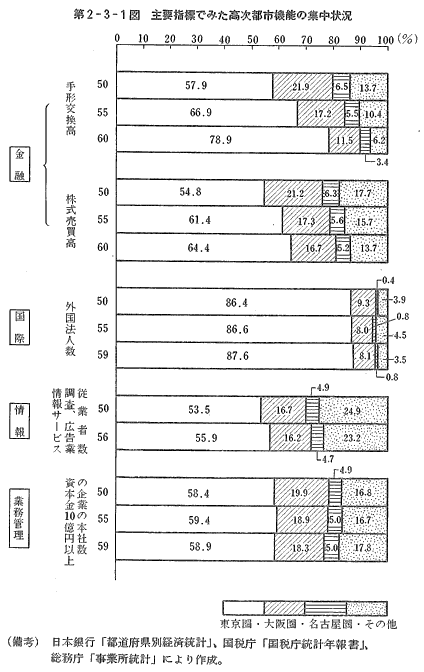
1 国土利用構造の新たな変化
(1) 大都市圏(東京圏)への新たな集中
第1節でみたように、大都市圏への人口の大量流入は、昭和40年代後半から減少に転じ、50年代に入るとほぼ均衡化するようになり、人口の地方定住が進んだ。しかしながら、50年代半ば以降再び大都市圏への流入超過に転じ、以後その数を増大させている(第2-1-2図)。これは、東京圏において流入超過が増大を続けているところが大きく、大阪圏、名古屋圏においても、50年代後半に比べ流出超過が減少している。また、工業出荷額については大都市圏のシェアは次第に低下してきているが、情報化、国際化の進展等に伴って、金融、国際、情報等の高次都市機能が大都市圏へ集中する傾向がみられる。第2-3-1図は、高次都市機能について、大都市圏と地方圏のシェアを経年的にみたものである。これによると、金融、国際及び情報機能については大都市圏のシェアが増大しつつある。特に、これらの機能が東京圏に集中しつつあることがことが注目される。また、業務管理機能については、大都市圏のシェアは若干低下しつつあるが、東京圏のシェアは高水準となっている。
以上のように、近年、大都市圏、特に東京圏への新たな人口と高次都市機能の集中傾向がみられる。東京圏への一極集中は、情報化、国際化等の進展に対応した社会的要請を背景としたものであると考えられるが、一方で国土の安全性等の面で脆弱性を強め、地方の活力を低下させるとの指摘がある。
環境保全の面からも、東京圏への一極集中は好ましくない面を有している。すなわち、東京圏では既に高密度な都市空間において活発な活動が行われており、二酸化窒素による大気汚染、自動車騒音、東京湾や都市内河川の水質汚濁等の環境基準の達成状況ははかばかしくなく、改善が遅れている。また、大量の廃棄物が発生しており、その処理が重要な課題となっている。このため、東京圏において、環境への適切な配慮をせずに更に高密度に空間が利用され、都市活動が増大することになると、こうした環境問題の解決を一層困難にするおそれがある。また、高次都市機能の集中を背景に都市再開発等の都市機能の更新が臨海部を中心に活発化の傾向をみせているが、その際には公害の防止など環境への影響に十分留意するとともに、快適な都市・生活空間の形成に積極的に役立てていく必要がある。さらに、内湾の利用に当たっては、高度成長以降の過程で海岸の改変が進み、東京湾に残された自然は今日貴重なものとなっているので、水面を確保するとともに、干潟などの水性生物の良好な生息環境が消滅したり、水質汚濁が生ずることのないよう十分配慮することが重要である。
なお、地方圏においても、近年、地方中核都市への人口、諸機能の集中傾向が顕著であり、こうした地域において新たに環境問題が発生することのないよう留意することも重要である。
(2) 産業立地の変化
経済が安定成長へ移行し、産業構造も素材型産業から加工組立産業に比重を移したことに伴い、産業立地にも変化がみられる。
第一次石油危機以降、新たな産業立地は低い水準にとどまっていたが、50年代半ば以降回復してきている。この背景としては、技術革新の急速な進展に伴い、先端産業の立地が増大していることがあげられる(第2-3-2図)。先端産業は、概して知識集約型・高付加価値型の産業であり、その製品は単位当たりの価格が著しく高いため、輸送コストの面で立地の自由度が高い。また、大規模な用地や港湾を必ずしも必要とせず、むしろ高速道路のインターチェンジやジェット機が就航している空港等に近接し、良好な用水が確保できること等が立地条件としてより重要視される。こうしたことから、先端産業の立地は全国に広がっており、その9割以上が内陸部である。
先端産業は、エネルギー消費量等が少なく、高度成長期において問題とされた硫黄酸化物等の汚染物質による公害問題を発生させる可能性は小さい。しかしながら、化学物質の利用拡大と使用形態の変化、廃棄物の性状変化をもたらすなど、新たな環境汚染の可能性を有している。このため、先端産業の立地に当たっては、環境汚染の未然防止の徹底に努めていく必要がある。なお、一部の先端産業には加工組立型産業としては地下水使用量が多いものもあるので、地盤沈下を生ずるおそれのある地域においてはその防止に配慮する必要がある。
(3) 高速交通体系の整備への要請
我が国の高速交通網は、50年代に入り急速に整備が進んできた。高速自動車国道の供用延長についてみると、50年度末には1,888kmであったが、59年度末には3,555kmにまで整備が進んでいる。新幹線については、50年3月に山陽新幹線岡山・博多間(443.6km)が開業し、東海道・山陽新幹線が全通したのをはじめ、57年6月には東北新幹線大宮・盛岡間(505.0km)、57年11月には上越新幹線(303.6km)が開業し、50年代には合計1,252.2kmの新幹線の整備が行われた。空港についても、50年5月に長崎空港がジェット機就航空港になったのをはじめ59年度までに37空港がジェット化され、ジェット化率は50年度の26%から59年度には52%へと著しい進展をみている。この結果、国土面積の8割程度の地域、人口でみれば9割程度がいずれかの高速交通機関のサービスを享受することが可能となっている(第2-3-3図)。
さらに近年は、技術革新、情報化、国際化等の進展に伴い、高速性、快適性、信頼性といった輸送サービスの質的向上が求められているとともに、地域内、地域間、国際間の交流の活発化を背景に高速交通体系の一層の整備への要請が高まってきている。高速交通網の整備は、国民生活の利便性を向上させ、経済社会活動の基盤として重要な役割を果たしてきたが、一部の交通施設周辺において深刻な公害問題を発生させた。これに対処するため、各般の施策が推進され、一定の成果を収めたものもあるが、未だ十分に改善されたといえる状況にはない。
交通公害は一度発生すると、その抜本的な解決のためには相当の期間と費用を必要とする。このため、高速交通体系を整備するに当たっては、新たに交通公害を発生させることがないよう未然防止に努めるとともに、既に交通公害が問題になっている地域においては自動車交通量の分散を図るなど地域の環境改善に資するものとなるよう配慮する必要がある。また、新たな技術を活用した低公害の輸送機関の積極的な導入に努めることも重要である。
(4) 国土管理主体の弱体化と自然に対するニーズの多様化
高度成長期以降の経済社会の変化に伴い、農地、森林等の管理主体が弱体化している地域がみられる。国土面積の約7割を占める森林についてみると、山村地域の過疎化、人口の高齢化、林業活動の停滞等に伴い、管理水準が低下している。61年8月に実施された「みどりと木に関する世論調査」(総理府)では、森林の現状についてどのような問題があるかを調査しているが、これをみても「山村で過疎化、高齢化が進んでおり、森林を守れなくなっている」、「林業の不振により、森林の手入れや管理面がおろそかになっている」とする回答が高い(第2-3-4図)。
農地、森林等は、経済的価値を有するだけでなく、環境保全機能の面でも重要な役割を果たしているため、今後、その多面的な機能を重視しつつ、適正な保全を図っていくことが望まれる。特に、森林については、国民の積極的な参加を得つつ保全していくことが重要になっている。
一方、都市化の進展等により身近な緑や水辺が失われるなかで、精神的なやすらぎや潤いを得るために自然とのふれあいを求めるニーズが増大している。また、レクリエーションについても、従来の観光型のレクリエーションに加え、長期滞在ができるようなリゾート型のレクリエーションのための地域開発を進める動きがみられる。
こうした変化は、今後、自然に対する開発や利用を増大させ、自然環境に対して新たなインパクトを与えることも考えられる。このため、開発行為等については、生態系維持の観点に立って十分な検討を行うとともに、優れた自然の保護や周囲の自然景観との調和を図るなど、自然環境の適正な保全に配慮していく必要がある。また、国土の14%を占める自然公園については、自然に対する多様なニーズに適切に対応しつつ、その機能を多元的に発揮するため、質の高い施設の整備に努めるとともに、一部の地域に利用が過度に集中し自然環境の悪化を招くことのないよう公園利用の分散化等を図っていく必要がある。