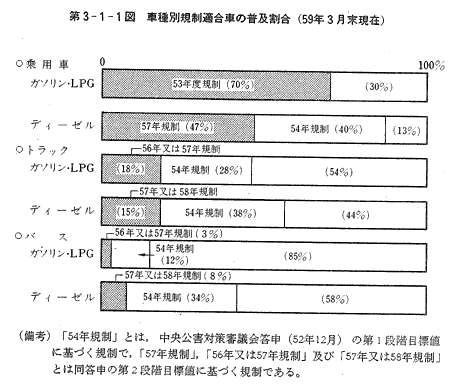
1 窒素酸化物対策
窒素酸化物については、二酸化窒素に係る環境基準を達成するため、これまで各種の施策が講じられてきたところであるが、大都市地域においては、達成期限である昭和60年度内に達成することは不可能であることが既に明らかとなっている。
窒素酸化物問題は、発生源が多岐にわたる上、対策技術も困難な側面を有するなどその対策は容易ではないが、二酸化窒素に係る環境基準を可能な限り早期に達成するため、総合的な展望の下、発生源ごとに計画的な対策を講じ、多角的な取組を行うことが必要である。
以下、窒素酸化物対策の経緯及び環境基準未達成の主な原因について概観したのち、今後の窒素酸化物対策の方向についてみていくこととする。
(1) 窒素酸化物対策の経緯
窒素酸化物については、46年に「大気汚染防止法」の改正により、同法の定める「ばい煙」の有害物質の一つとして追加され、48年には二酸化窒素に係る環境基準が設定(53年に改定)された。同年、大型ボイラー、加熱炉等の排出規制が開始され、規制対象施設の拡大及び規制基準の強化が順次行われ、58年までに5次に及んでいる。また、60年9月からは、新たに小型ボイラーについても規制が実施されている。さらに、工場等が集合して排出規制のみでは環境基準の確保が困難な地域では、工場、事業場ごとに排出総量を規制する総量規制を実施することとされているが、窒素酸化物については、56年に東京都特別区等地域、横浜市等地域、大阪市等地域の3地域が対象地域に指定され、総量規制が実施されてきている。
また、自動車から排出される窒素酸化物については、ガソリン、LPG車に対しては48年度から、ディーゼル車に対しては49年度から、それぞれ規制が開始され、その後、ガソリン、LPG乗用車にはいわゆる53年度規制が実施され、未規制時に比べ窒素酸化物の排出量が10分の1以下となっている。ディーゼル乗用車やトラック、バス等についてもそれぞれ規制が強化されてきている。
(2) 環境基準未達成の主な原因
以上のように、二酸化窒素に係る環境基準の達成に向け各種対策が講じられてきたところであるが、既に述べたように、大都市地域においては環境基準を達成できないことが明らかとなっている。大都市地域において環境基準が達成できなかった主な原因としては、次のようなことから、自動車からの排出量が当初計画していたほど減少しなかったことが考えられる。
? 自動車走行量の伸びが、普通貨物車など窒素酸化物の排出量の多い車種で大きかったこと。
? 車齢の伸びにより、より新しい規制適合車への代替が遅れ、代替による規制効果が現われにくかったこと(第3-1-1図、第3-1-2図)。
? 貨物車等を中心に、保有台数に占めるディーゼル車(ガソリン車に比べて窒素酸化物の排出量が多い)の割合が増加したこと(第3-1-3表)。
? ディーゼル車の中でも窒素酸化物の排出量の多い直噴式ディーゼル車の割合が、中型の貨物車やバスを中心に増加したこと。
(3) 今後の窒素酸化物対策の方向
今後、環境基準の達成に向けて、自動車単体対策、自動車交通対策及び固定発生源対策を総合的に推進していく必要がある。
ア 自動車単体対策
自動車排出ガスについては、自動車台数の増大、交通量の増加等により自動車交通量の多い地域においては一層の排出量低減が必要となっており、このため、自動車排出ガスの低減を今後さらに推進していくことが不可欠である。
自動車排出ガス低減に当たっては一層の技術開発が必要であるが、今後の自動車排出ガス低減対策のあり方については、60年11月に中央公害対策審議会の大気部会に自動車排出ガス専門委員会が設置され、技術的・専門的な事項について鋭意検討されることとなっており、自動車排出ガス低減技術の開発促進を図りつつ、目途の得られたものから対策の早期実施を図っていくこととしている。
また、電気自動車、メタノール自動車のようないわゆる低公害車を普及していくことはもとより、ディーゼル車の直噴式よりは副室式、また同一車種でもより新しい規制適合車というように、より低公害な自動車を普及していくことも重要である。
イ 自動車交通対策
最近の物流の動向をみると、国民のニーズの多様化や産業構造の変化等、社会経済情勢の変化に伴い、多品種、少量、多頻度の輸送形態へ変化している。このため、このような変化を踏まえて、輸送効率の改善、共同輸送の推進を図るとともに、公共トラックターミナル等大規模な物流施設を道路網の整備等との整合を図りつつ、環境保全に配慮して整備していく必要がある。
また、地下鉄、バス、新交通システム等の公共輸送機関を地域の状況に応じて有機的に整備し、乗継ターミナルの整備等によってその利便性を高めるとともに、通勤通学時の公共輸送機関利用の要請等によって乗用車利用の抑制を図ることも重要である。
さらに、都市部に集中する交通量の分散を図るための環境保全に配慮した環状道路等の整備、交差点構造の改良、交通信号処理の高度化等の交通流の円滑化を図るための対策についても一層の推進を図る必要がある。
ウ 固定発生源対策
固定発生源対策については、総量削減計画に基づき順調に成果を上げているが、窒素酸化物排出量のうち固定発生源によるものの割合は、地域によって違いがあるものの、かなりの割合を占めており、また、このままでは排出量が増加することも予想される。このため、引き続き固定発生源の排出量抑制に努めることが必要である。
ばい煙発生施設対策については、これまでの排出量低減の実績を踏まえ、排出規制の徹底を図るとともに、低減技術の開発等を推進し、窒素酸化物の排出抑制に努める必要がある。
また、群小発生源について環境影響の把握を行うとともに、地域冷暖房等対策の効果把握及び推進方策の検討を行う必要がある。