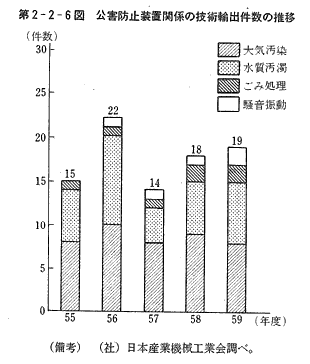
2 環境保全技術への要請の高まり
(1) 環境保全技術の多様な展開
これまでみてきたように、我が国の環境保全技術は、様々な環境保全上の要請にこたえて著しい発展を遂げてきている。今後とも環境問題の解決に環境保全技術の果たす役割がますます大きくなると見込まれており、環境保全技術の一層の向上を図っていく必要がある。このため、次のような点が重要と考えられる。
第1に、先端技術の活用等新しい技術を利用して新たな環境保全技術を生み出していくことが重要である。このような技術として、イオン交換膜や分離膜による処理等の新素材を利用した水処理技術、バイオテクノロジーを利用した汚水処理技術、人工衛星からのリモートセンシングによる環境監視測定技術等の開発が期待されている。
第2に、既に開発された環境保全技術について、一層の効率の改善、信頼性の向上、コストの低減等を図ることにより、その普及を推進することも重要である。このことは、特に中小企業における環境保全の推進に資するものと考えられる。
第3に、環境保全以外の分野の技術についても、環境保全の観点から見直すことにより、環境改善に大きな役割を果たすことが認識されてきている。例えば、省エネルギー・省資源の徹底や生産プロセスの見直しにより汚染物質の排出量及び排出濃度の抑制を図ることが可能であり、廃棄物の再資源化、有効利用は、環境負荷の削減に直結する。
また、多様化、複雑化する環境保全上の要請にこたえて、環境保全技術も様々なレベルにおいて多様に展開されていく必要がある。
例えば、生活排水の処理技術が農山漁村の特性に応じて開発されてきたように、地域の特性に適した技術を発展させていくことも重要である。
このほか、生態系を生かした技術の開発も重要な課題となっている。前述のとおり、湖沼の富栄養化の防止のために自然の浄化機能を活用した技術開発が望まれており、また、浸透性アスファルトによる舗装は、自然の水循環を通じて地下水のかん養、都市の浸水防止に資するものと考えられる。
以上みてきたように、環境保全のために科学技術の果たす役割は大きく、今後とも、公害の防止、自然環境の保全さらには快適な環境の創造に向けて、より一層の技術開発が期待されている。
(2) 環境保全技術の国際的展開
我が国の公害防止技術の開発は、外国からの技術導入によって促進されてきた面が大きかったが、その後、公害防止技術が急速に進歩し、我が国において独自に開発した技術も見られるようになり、今日、国際的にも有数の水準に達している。
一方、世界各国の環境の状況をみると、経済開発が進みつつある開発途上国においては、先進国が既に経験したような環境汚染に直面している。先進国においても、環境保全対策や防止技術の遅れ等から、環境問題が深刻化している国も見られる。こうしたことから、環境保全分野の国際協力について各国から寄せられる期待が大きくなっている。
本節においては、環境保全分野における二国間の政府ベースの技術協力、民間ベースの技術移転についてみることとする。
ア 政府ベースの技術協力
政府保全分野における政府ベースの技術協力は政府開発援助の枠組の中で行われており、技術協力の形態としては専門家派遣、研修員の受入れ、調査団の派遣、プロジェクト方式技術協力等がある。専門家派遣は、環境分野の専門家を相手国の環境行政機関(研究所等を含む。)へ派遣するものであり、これまでインドネシア、トルコ等へ専門家が派遣されている。研修員については、東南アジア、中近東、中南米から受け入れているが、受入人員は59年度69名となっている。調査団の派遣は、環境分野の諸計画を策定するための技術協力の形態であり、トルコのアンカラ市大気汚染対策計画調査等がある。プロジェクト方式技術協力は、専門家集団の派遣、機械供与、研修員の受入れを一体として有機的に運用する方式であり、通常相手国が提供する研究所等を拠点として、計画的・総合的な技術協力を行うものである。
例えば、シンガポールにおける石炭火力発電所及び一貫製鉄所の設立に関する協力をみよう。これは、シンガポール国の粉じんに係わる環境対策への資料を提供することを目的として国際協力事業団が協力を行っているものである。シンガポール国内20か所の観測地点において粉じん汚染の現況を調査し、得られたデータ並びに別に収集した発生源資料をもとに、同国が計画している石炭火力発電所及び一貫製鉄所から排出される粉じんの汚染予測を行うこととしている。59年度より、現地調査が行われており、データ収集と分析が実施されている。
イ 民間ベースの技術移転
近年、国際的にみて高い水準にある我が国の公害防止技術について、中国や東南アジア諸国から民間ベースでの技術移転への期待が高まってきている。
まず、最近5年間における我が国の公害防止装置関係の技術輸出をみると年間20件前後となっており、装置別には大気汚染防止装置関係が最も多い(第2-2-6図)。地域別では、開発途上国のほか、西ドイツなどの先進国へも移転が行われている。このほか、民間ベースでは、調査団の派遣、環境保全技術の普及、情報交換等が行われている。
また、ヨーロッパ等の先進国においても我が国の環境保全対策や環境保全技術について強い関心と期待がもたれるようになっており、技術協力が行われる事例がみられる。
例えば、オーストリア・デュールンロール石炭火力発電所への技術協力についてみよう。
オーストリアにおける電力供給は、水力が約7割、火力が約3割であり、火力の4分の3以上が石油火力発電である。同国では、オイルショック以降脱石油化を進めており、デュールンロール石炭火力発電所が61年に運転開始予定となっているが、酸性雨等にみられる厳しい環境の状況と都市に隣接した立地条件を考慮して、厳しい公害防止対策が計画されている。こうしたことから、同発電所の建設主体である州営電力会社等2社は、我が国の電源開発株式会社が自社の石炭火力発電で開発、実用化した脱硝技術を評価し、技術協力の申し入れをしてきたものである。現在、窒素酸化物を低減させるための燃焼改善及び脱硝装置の技術について協力が進められている。
ウ 技術協力等の一層の推進
開発途上国等に対する技術協力を有効かつ適切に行っていくためには、我が国とは環境の状況、自然条件が異なり、公害規制の方式等も異なる相手国の実情を十分に把握した上で、具体的な技術協力の方式を決定する必要がある。また、我が国においては技術協力のための人材が十分に確保されているとは言えないので、今後、専門家を積極的に育成し、プールするような体制を強化していくことが望まれる。さらに、開発途上国における環境の監視、測定体制を整備するとともに、環境保全に関する技術を積極的に活用できるような専門家の育成を援助することが重要であり、このための協力を推進していく必要がある。
以上の政府ベースでの技術協力に加えて、我が国の環境保全技術に対する国際的な要請の高まりに対応していくためには、民間ベースの技術移転を積極的に行っていくことが期待される。