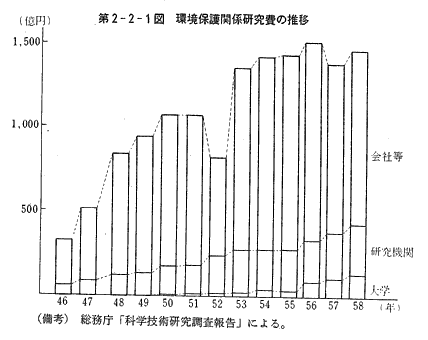
1 環境保全技術の発展
(1) 公害防止技術の発展
我が国における公害防止技術の発展をみると、公害防止に関する社会的要請を受けて研究開発や技術導入が行われ、環境基準や規制基準の設定に伴う対策のスケジュールの明示等により、技術の実用化及び普及が図られてきたと言えよう。
環境保全関係研究費全体の推移をみると、公害防止への要請が高まった昭和40年代後半に急速に増加している(第2-2-1図)。また、公害防止に関する外国技術の導入件数をみても、同様に40年代後半に増加がみられている(第2-2-2図)。
このような研究開発は技術導入により公害防止技術が発展してきているが、その普及の状況を、公害防止技術が具体化された公害防止装置の生産実績によりみていくことにしよう(第2-2-3図)。
まず、全体をみると、公害防止装置の生産額は、40年代を通じて急激に拡大し、41年度から51年度までの間に約20倍になっている。生産額のピークは51年度の6,900億円であり、その後およそ6,000億円のレベルで横ばいに推移している。種類別にみると、40年代から50年代初頭までは、大気汚染防止装置と水津汚濁防止装置が同程度の額で推移し、両者が全体の9割程度を占めていたが、それ以降は水質汚濁防止装置が5割以上を占め、大気汚染防止装置は全体の4分の1程度となっている。また、50年代後半には、ごみ処理装置も2割程度を占めるようになってきている。
これを、大気汚染防止装置と水質汚濁防止装置についてより詳しくみることにする。
まず大気汚染防止装置についてみると、すべての年代を通じて集じん装置が着実に普及している。また、重油脱硫装置は、43年の大気汚染防止法の制定を受けて生産が拡大し、40年代を通じて相当程度普及している。排煙脱硝装置は、49年から51年にかけて急速に生産が拡大している。さらに、50年代中頃には排煙脱硫装置の生産が拡大している。
次に水質汚濁防止装置についてみると、産業排水処理施設については、45年の水質汚濁防止法の制定とその後の規制対象の拡大を反映して、40年代後半から50年にかけて生産が拡大し、全体に占める割合が高まったが、その後普及の一巡から減少ないし横ばいの状況にある。一方、50年代に入ると、下水汚水処理装置の占める割合が高くなり、50年代半ばには公害防止機器全体の生産額の3割弱となってきている。
(2) 環境保全技術の現状
これまでみてきたように、技術開発の結果、公害防止装置の幅広い普及がみられるなど現在において我が国の環境保全技術は相当程度進展してきていると言えよう。ここでは、主要分野における環境保全技術の現状についてみていこう。
まず第1に、汚染物質の除去技術等直接的に公害を防止する技術についてみることにする。
大気汚染の分野においては、硫黄酸化物の除去のため、重油脱硫技術や排煙脱硫技術が広く普及しており、硫黄酸化物による大気汚染の改善に大きく寄与している。また、窒素酸化物による大気汚染の改善のため、固定発生源については燃焼方法の改善や排煙脱硝技術の実用化が行われており、移動発生源については、ガソリン車・LPG車に関して触媒、排気再循環装置等の採用が行われ、ディーゼル車に関して燃焼技術の改良等による窒素酸化物低減技術の採用が行われている。
水質汚濁の分野においては、重金属による水質汚濁については、処理技術の普及によりほぼ環境基準を満足する状況にあるが、有機物質による水質汚濁については、排水の一層の処理を図るため、処理施設の整備改善が必要である。また、富栄養化防止のため窒素、燐の除去技術の実用化が進んできている。さらに、高度な膜処理技術も実用化されてきており、バイオテクノロジーを応用した処理技術の開発についても着手されている。
騒音・振動の分野においては、自動車についてはエンジンルームの遮へい、エンジン構造の改良等の対策技術が普及し、乗用車等のほか大型トラックについても、60年規制に対応した騒音の低減が図られている。また、トンネル坑口部における吸音パネルの設置等道路構造上の防音対策技術の開発も進められている。さらに、新幹線については、鉄げた橋りょうの防音工事、バラストマットの敷設、逆L型防音壁、音波干渉を利用した新型防音壁、パンタグラフの改良等の対策技術が適用され、航空機についても低騒音の機材が外国で開発され導入が進められている。
廃棄物の分野においては、有機汚泥の肥料化、石炭灰の有効利用等の再資源化技術及び有害物質発生抑制のための燃焼技術の無害化処理技術について研究開発が進められている。
第2に公害の発生しにくい製法への転換や低公害製品の開発等公害の発生自体を低減する技術についてみることとする。
製法転換については、水俣病の発生を契機として水銀の危険性に対する社会的認識が高まったことを背景に、カセイソーダの製法が水銀法からイオン交換膜法に転換されたことが有名である。また、セメントの製造施設としてNSPキルン(ネオ・サスペンション・プレヒータ付きキルンの略称。ロータリーキルンとサイクロンプレヒータの中間にか焼炉を組み込んだセメント焼成施設)が開発されたことは、生産性の向上とともに窒素酸化物の低減等公害防止に役立っている。
また、公害の発生しにくい製品の開発も重要であり、例えば、湖沼の富栄養化を契機に無燐洗剤への転換が進んでおり、既に全体の9割以上の普及率となっている。
第3に、環境監視や予測手法等、環境保全施策の推進を支える技術についてみることとする。
環境汚染の監視測定の分野においては、自動測定技術やその測定結果を送信するためのテレメーター・システムが広く普及してきており、また、人工衛星や飛行機からのリモート・センシング技術も開発が進められている。
環境汚染の予測手法の分野においては、大気や水質のシミュレーション技術が普及し、環境アセスメントの実施に役立っている。また、赤潮発生予測モデルの開発も進められている。
このように環境保全技術は様々な分野で多様に開発が進められてきており、我が国の環境保全に大きく寄与している。
このほか、環境保全の分野において開発された技術が、他の分野において大きな役割を果たすことも少なくない。
自動車のエンジンの燃焼技術の改良が排出ガス低減と同時に燃焼効率の向上につながったことや、ろ過膜やイオン交換膜による水処理技術が排水処理だけでなくICの製造に必要な超純水の製造にも利用されていることなどは、その例である。こうした面からも環境保全技術の高度の発展が期待されている。
(3) 個別分野における技術開発の動向
これまで様々な分野における環境保全技術の開発状況についてみてきたが、ここでは環境改善が強く求められている窒素酸化物による大気汚染と閉鎖性水域の富栄養化の二つの分野についてその防止技術の開発動向をみていこう。
ア 窒素酸化物低減技術
窒素酸化物の低減技術は固定発生源に関する技術と移動発生源に関する技術に大別される。
第1に固定発生源についてみると、固定発生源に対する窒素酸化物の排出規制が48年8月から順次強化されてきたことに対応して、燃焼改善技術と排煙脱硝技術が発展してきている。
燃焼改善技術は、燃焼温度を低くする等窒素酸化物が発生しにくい条件で燃焼を行う技術であり、二段燃焼、低N0Xバーナー等が開発され広く普及している。二段燃焼法を例にとると、これは第1段階で完全燃焼に必要とされる空気の8〜9割程度を供給し、第2段階で不足する空気を補って全体として完全燃焼させる技術であり、燃焼温度と酸素濃度を低下させることにより窒素酸化物の発生を抑制するものである。
排煙脱硝技術は、排ガス中の窒素酸化物を除去する技術であるが、窒素酸化物は、硫黄酸化物に比べ化学反応性が低く、また、一般的に排ガス中の濃度レベルも低いため、従来、効率的な除去に困難な点があるとされてきた。しかしながら、近年の技術開発の進展により、効率的な排煙脱硝技術が実用化されてきている。脱硝の方法としては、還元剤を排ガスに加え、触媒により窒素酸化物(NOX)を窒素(N2)に還元する接触還元方式が大半となっている。
排煙脱硝装置の普及の状況をみると、47年度に設置数5基、総処理能力10.6万Nm
3
/hであったのが、59年度には設置数253基、総処理能力約1億Nm
3
/hへと飛躍的に拡大している(第2-2-4図)。
第2に移動発生源のうち自動車についてみると、窒素酸化物の規制がガソリン車、LPG車に対しては48年から、ディーゼル車に対しては49年から段階的に強化されてきており、これに合せて、技術開発が促進されている。
ガソリン車、LPG車のうち、乗用車については、窒素酸化物の排出量が10モード(都市内の一般走行を基礎にして定められた10過程の走行状態)で0.25g/km以下という53年度規制が実施された。これに対応するため、三元触媒(CO,HC,NOXを同時に除去することが可能な触媒)や酸化触媒、エンジン構造の変更により燃焼の際の窒素酸化物の発生を低減する技術、排気ガス再循環装置(EGR:排気ガスの一部をエンジンに戻すことにより酸素濃度及び燃焼温度を低下させ、窒素酸化物の発生を抑制する。)や電子制御式燃料噴射装置(空気と燃料の比率である空燃比を最適化することにより排ガスの低減を図る。)等様々な技術が組み合わされてきている(第2-2-5図)。
また、ガソリン車のうちトラック・バスについては、56年規制または57年規制に対応するため、様々な技術開発が行われており、低減技術は複雑なものとなってきている。
次に、ディーゼル車については、エンジンの原理が異なるため、ガソリン・エンジン車とは異なる排出ガス低減技術が用いられている。
すなわち、ディーゼル・エンジンは圧縮して高温、高圧となった空気中に燃料を噴射し、燃料の自己着火により燃焼を行うエンジンであり、全体として空気過剰の状態で運転される等のため、触媒による窒素酸化物の低減が困難である。また、NOXと黒煙の排出量に相反的な関係があり、黒煙を増加させずに,NOXの排出を低減させるための技術開発が求められている。低減技術としては、エンジン関係の改良が中心となっており、燃焼室・副燃焼室等の形状の改善、燃料噴射の噴射時期、噴射量、噴射角度等の改善、バルブ開閉時期の最適化等の技術を組み合わせることにより、排出ガスの低減を図っている(第2-2-5図)。
自動車排出ガス低減のための技術は、これまでの数次にわたる排出ガス規制の強化により複雑かつ高度なものとなってきており、更に低減を図るためには新技術を含め、より一層の技術開発が必要となっている。
さらに、メタノール自動車については、近年、環境保全対策の面から注目されてきており、ディーゼル車に比べ低NOX、低黒煙という特質を有しているため、その円滑な導入に向けて努力しているところである。
また、電気自動車については、排出ガスがないこと、低騒音であること等の特性があり、今後とも蓄電池の開発等を通じ走行距離等の点で更に改良を加え、電気自動車の特性をいかせる分野での普及促進が図られる必要がある。
窒素酸化物の低減のためには、以上みてきた個別の技術開発にあわせて、今後とも自動車交通量の増大が予想される中で、環境保全に配慮した効率的な交通体系の形成が求められてきている。
イ 富栄養化防止技術
湖沼、内海等の閉鎖性水域における富栄養化の防止を図るため、湖沼について窒素、燐の排水基準が設定されるとともに、瀬戸内海等の閉鎖性海域について栄養塩類の削減指導が行われており、これらの対策を反映して窒素、燐の抑制技術が発展してきている。その内容は発生源によって異なるため、?工場・事業場の排水、?生活排水及び?その他の負荷の三分野についてみることとする。
第1に工場・事業場の排水処理技術についてみると、燐の除去技術としては、凝集剤の添加により燐を沈殿除去する凝集沈殿法が普及している。また、生物学的処理において汚泥として燐を除去する技術や晶析現象(接触材の上に燐が化合物結晶として析出してくる現象)を利用して燐を除去する技術が開発されている。
窒素の除去技術は、燐の処理技術に比べ相対的に発展が遅れているといわれているものの、近年、生物学的処理法が開発、実用化されてきている。これは、様々な形態で存在する窒素を微生物により硝化、脱窒し、空気中に除去する方法である。また、コークス炉廃液等に含まれるアンモニウム態窒素については、アルカリ度が強くなるとアンモニアの形で気化するという性質があるため、これを利用して空気中に除去する方法(アンモニア・ストリッピング法)も実用化されている。
今後の技術的な課題としては、これらの方法について信頼性の向上を図っていく必要があるほか、特に燐の除去技術により汚泥の発生量が増加する場合があるため、汚泥の効率的な処理が求められている。
第2に生活排水の処理技術についてみると、窒素、燐の全体の負荷に占める生活排水の割合は一般に大きいことから、生活排水処理の推進が重要な課題となっている。大量の生活排水を処理する下水道等の施設においては、窒素、燐の削減のため、第1において述べた技術を採用することも可能であるが、人口密度が低い地域においても適正な排水処理を行うため、小規模な処理施設に適した技術開発が求められている。このため、最近では、トラック状のだ円形の汚水槽でばっ気を行いつつ汚水を周回させて嫌気・好気の状態を繰り返しながら処理を行う技術(オキシデイション・ディッチ法)、一つの汚水槽で順に流入、ばっ気、沈殿、排出の操作を繰返しながら処理を行う技術(回分式活性汚泥法)、汚水槽に浸した円板状の接触材を回転させながら接触材上の生物膜により処理を行う技術(回転円板法)、汚水槽に接触材を浸漬してばっ気を行い、接触材上の生物膜により処理を行う技術(接触ばっ気法)等の技術が発展してきている。これらの技術は、汚水の流量変動に対応することができ、かつ、維持管理が容易である等の特徴を持っている。今後は、従来の技術に併せて、地域特性に応じた小規模な技術を組み合わせて生活排水処理施設の整備を図っていく必要がある。
また、各家庭において合併浄化槽等の生活排水を処理することのできる処理施設を設置することの効果も大きい。合併浄化槽は、し尿と併せて生活雑排水も処理する浄化槽であり、従来は、水量の変動が大きい個別家庭用のものは安定的な処理効果を得にくいとされていたが、最近では、個別家庭用合併浄化槽が実用化されてきており、その普及が期待されている。
このような処理技術の開発・普及に加え、生活雑排水の負荷を低減させるために各家庭で実施される対策も重要であり、台所用ろ紙や網を用いて台所排水中の固型分を除去する等の対策も地域ぐるみで講じられた場合には、大きな意義を有する。
第3に富栄養化の原因として、市街地や農地等からの流出による面源負荷についても実態把握の上、適切な措置を講じる必要がある。これらの負荷については、従来のハードな機器による水質浄化技術だけでは対応することが困難であると考えられている。このため、例えば、営農の実情に即して農地における施肥法及び田面水の管理の適正化の徹底に努める等きめ細かな対策が要求されてくる。また、特に自然浄化機能を活用した技術の発展が期待されている分野でもある。自然浄化機能を活用した技術の例としては、ホテイアオイ等の水生生物により湖沼等の水質浄化を図る技術等があり、現在、研究開発が進められているところである。