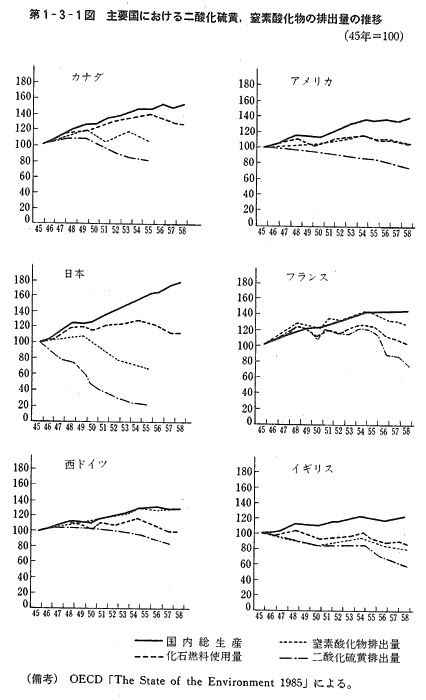
1 主要先進国における環境の状況
ここでは、昭和60年6月の第3回OECD(経済協力開発機構)環境大臣会議に報告された「1985年における環境の状況」により、主要先進国における大気汚染、水質汚濁等の環境の状況をみることとする。
(1) 大気汚染
大気汚染問題については、ここ20年間における防止技術と公害対策の進展の結果、従来から問題とされてきた一酸化炭素、二酸化硫黄、ばいじんについては効果が現われ排出量が減ってきている。特に北米や日本では、対策の強化と省エネルギーを主な要因として、早くから改善がみられ、40年代後半から50年代前半にかなり減少した。欧州OECD加盟国でも、これより遅れて50年代前半に改善をみている。その後、54年から59年の5年間は大部分のOECD諸国では、経済成長率の低下、化石燃料消費の低下、排出規制の実施から、総じて横ばいないし改善がみられる。
個別汚染因子についてみると、二酸化硫黄排出量は、低硫黄燃料の使用や、火力発電所の脱硫装置の使用といった対策面での成果も加わり、45年以来各国とも低下を示しており、経済成長を実現しながら、一方で二酸化硫黄排出量の削減に成功している。しかし、窒素酸化物の排出量は、概して、はかばかしい改善はみられず、悪化している国もあるが、近年は経済成長率の低下、窒素酸化物対策等により総じて改善傾向がみられる。
ここで我が国と他の主要先進諸国の二酸化硫黄と窒素酸化物の排出量の45年以降の推移をみると、我が国は他の主要国と比べ両因子とも低減しており、特に二酸化硫黄は著しく低減している(第1-3-1図)。次に、可住地面積当たりの排出量で比較してみると、我が国は、狭小な国土において高度な経済社会活動が営まれていることを反映して、45年頃は主要国の中で最も高い水準にあった。その後、排出削減努力が行われた結果、55年でみると、二酸化硫黄については中程度となったが、窒素酸化物は、西ドイツに次ぐ高水準となっている。なお、55年の生産額当たりの排出量は他国に比べ最も低くなっている(第1-3-2表)。
第1-3-2表 主要国にける経済活動、大気汚染因子排出量の比較(可住地面積1km
2
(2) 水質汚濁
河川の有機汚染の状況を代表的な指標であるBODの推移でみると、ミシシッピ川、ライン川、セーヌ川など顕著な改善を示している河川もあるが、改善を示していない河川もみられる(第1-3-3図)。なお、下水道の普及は河川の浄化に大きな役割を果たしているが、主要先進国の下水道の普及率は、58年において、西ドイツ84%、アメリカ70%、フランス64%と総じて50%を越えているが、我が国では59年度において34%にとどまっている。
また、湖沼等の富栄養化の要因となる窒素及び燐による汚濁は、長期間にわたり、対策を必要とする状況にあったが、全体的にはかばかしい進展はみていない。主な湖沼の全リン濃度の推移については第1-3-4図のとおりである。
(3) 廃棄物
廃棄物のうち、主なものは、都市ごみと産業廃棄物である。
都市ごみは、OECD加盟国全体で、55年において3.5億t排出されており、その8割が家庭からのものである。一人当たりの都市ごみの排出量は、生活様式の違いなどにより、国により開きがあり、我が国は先進国中では中程度である(第1-3-5図)。
産業廃棄物は、排出量が多く、有害な場合があるため、廃棄物問題において非常に重要である。特にその輸送と処理に注意が必要な状況にある。また、環境保全活動に伴い発生する下水汚泥等の増大が問題となっており、それらの処理技術の開発が必要である。さらに、過去に有害廃棄物が処分された場所の特定等が今後の大きな課題となっている。