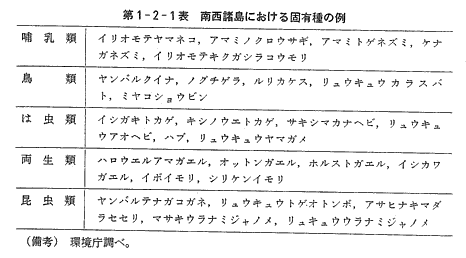
2 野生生物の現状
我が国の国土は南北に長く、自然条件も変化に富んでいることから、多様な動植物相がみられる。
動物についてみると、哺乳類130種、鳥類506種、両生類約50種、は虫類約80種、淡水魚類約180種、昆虫類等約10万種など数多くの種類が生息しており、植物についても、種子植物約5,500種、シダ植物約730種と多くの種類がある。また、我が国固有の野生生物種も数多い。例えば、南西諸島は、東洋のガラパゴスと呼ばれるほどに固有種が多く、野生生物の宝庫となっている(第1-2-1表)。
しかし、自然改変、乱獲あるいは外来種の移入などによって、特に、繁殖力が小さく生息域も限られているものについては、種あるいは地域個体群が絶滅の危機に瀕することが多い。
このような現象は地球的な規模で進行している。現在、全世界では微生物まで含めると3,000万種もの野生生物が生息しているものと推定されているが、IUCN(国際自然保護連合)の調査においては、2万5,000種以上の植物と1,000種以上の脊椎動物が絶滅の危機に瀕していると推定している。
我が国においてもトキ、イリオモテヤマネコを初めとして、脊椎動物から昆虫、植物に至るまで、様々な生物が生存を脅かされている。例えば、森林を生息地とするニホンザルについてみると、青森県下北半島が分布の北限で、世界のサルの中でも最も北に生息しているが、大正12年と昭和53年の分布を比較すると、人間の生活域の拡大等により、東北地方では点在していた分布域がさらに狭まり、九州地方でも分布域は、減少し、分断されてきている。(第1-2-2図)
以下、絶滅のおそれのある野生生物の現状について、57〜59年度に行われたイリオモテヤマネコ生息環境等保全対策調査及び59年度の小笠原固有植物保全対策緊急調査をもとにみていくこととする。
イリオモテヤマネコは、世界中で沖縄県の西表島にしか生息しておらず、骨格の進化度が著しく低いことから、「生きた化石」といわれている。調査の結果、イリオモテヤマネコは、内陸山岳地域に比べ沿岸低地地域に多く生息しており、餌は鳥類、は虫類、、哺乳類、イネ科植物、昆虫類等多種であることが分かった。活動は、完全な夜行性ではなく、行動圏の広さは、雄で平均3.2km
2
、雌は平均1.8km
2
であった。本調査による生息確認個体は24個体であったが、西表島全体でも100頭弱程度しか生息していないものと推測されている。
一方、小笠原諸島は、日本列島の南方1,000km以上離れた太平洋上に散在する島しょで数多くの固有動植物が生息、生育する学術的にも極めて重要な地域であり、47年国立公園に指定されている。しかし、同諸島では、43年までに、オガサワラマシコなど5種類の固有鳥類が絶滅しており、現在も数種の固有植物が絶滅の危機に瀕している。調査の結果、絶滅のおそれのある85種の植物のうち、特に、21種について個体数が極めて少ないか、自然状態での繁殖が困難であり、ムニンノボタン、オガサワラツツジ、シマホザキランの3種は極めて危険な状態にあることが確認された。
また、トキは、江戸時代には、北海道から中国地方までの広い範囲にその優雅な姿を見せていたと推測されているが、現在は新潟県のトキ保護センターに飼育されている3羽しかいない。
野生生物の保護に関しては、野生鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的として「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」が定められており、同法により、鳥獣の保護、繁殖を図るため、60年度末現在、国設鳥獣保護区137か所62万ha、都道府県設鳥獣保護区3,056か所253万ha(合計315万haで全国土面積の8.33%)が設定されている。
特に、絶滅のおそれのある鳥類については、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」に基づき特殊鳥類として指定し、その譲渡等に関し規制を行うことによって種の保存が図られている。60年度末現在における国産の特殊鳥類はアホウドリ、コウノトリ、トキ等の35種類となっている。
しかしながら、野生生物の分布状況、生態等については、これまでも各種の調査が行われてきたが、いまだ解明されてない点も多く、十分な情報が得られていないので、今後とも積極的に調査を実施していく必要がある。さらに、このような調査を踏まえ、特に絶滅のおそれのある種については、早急に適切な保全対策を講じていかなければならない。