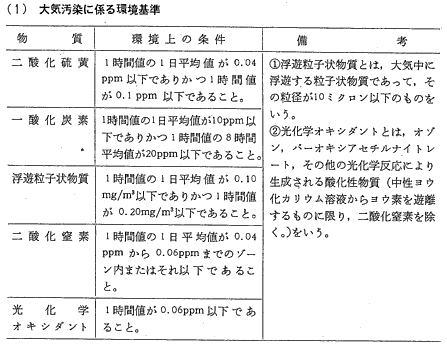
1 環境基準
大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件についてそれぞれ人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準
(1) 大気汚染に係る環境基準
(2) 水質汚濁に係る環境基準
(3) 騒音に係る環境基準(p270参照)
(4) 航空機騒音に係る環境基準(p290参照、単位:WECPNLについては、用語の解説6参照)
(5) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準(p297参照)
2 排出基準(排水基準)
ばい煙、汚水等を排出し、又は騒音、悪臭などの公害発生源となる一定の施設(工場・事業場)から排出される環境汚染物質等の許容限度。大気汚染防止法では排出基準、水質汚濁防止法では排水基準という。この許容限度を超える汚染状態のばい煙、排出水を排出し、又は騒音、悪臭等を発生させ又はそのおそれがあるときは、施設の改善命令や使用の一時停止命令等が行われ、更にばい煙や排出水については処罰の対象となる。
3 ppm
ごく微量の物質の濃度を表すのに使われ、%が100分の1をいうのに対し、ppmは100万分の1を意味する。例えば、空気1m
3
中に1cm
3
の物質が含まれているような場合、あるいは水1kg(約1リットル)中に1mgの物質が熔解しているような場合、この物質の濃度を1ppmという。ppmより微量の濃度を表す場合には、ppb(10億分の1)も用いられる。
4 K値規制
大気汚染防止法のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の規制方法である。K値規制による硫黄酸化物の排出基準は、地域ごとに定められたKの値を算式に代入して、ばい煙発生施設の排出口の高さに応じて算出された1時間当たりの硫黄酸化物の排出量として示される。(この規制方式は、硫黄酸化物の最大着地濃度を考慮して排出される硫黄酸化物の量を規制するものであり、Kの値が小さいほど規制が厳しい。)
昭和51年9月の基準改正により、この硫黄酸化物の排出基準は、120の政令特掲地域およびその他の地域(非特掲地域)について、K値3.0からK値17.5の範囲で16のランクに分け設定されている。
Q=K×10
−3
×He
2
Q:硫黄酸化物の許容排出量
K:地域ごとに定められる定数(3.0〜17.5の16のランク)
He:有効煙突高(煙突実高+煙上昇高)
5 総量規制
一定の地域内の汚染(濁)物質の排出総量を環境保全上許容できる限度にとどめるため、工場等に対し汚染(濁)物質許容排出量を配分し、この量をもって規制する方法をいう。大気汚染、水質汚濁に係る従来の規制方式は、個々の施設(工場・事業場)の排出ガスや排出水に含まれる汚染(濁)物質の濃度のみを対象としていたが、この個別規制では地域の望ましい環境を維持達成することが困難な場合に、その解決手段として総量規制が行われている。
6 WECPNL
Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Levelの頭文字で、直訳すると「加重等価平均感覚騒音レベル」となる。
1機ごとの騒音レベルに加え、機数や発生時間帯など加味した航空機騒音に係る単位で「うるささ指数」と呼ばれることもある。航空機騒音の特徴をよく取り入れた単位としてICAO(国際民間航空機関)が提案した国際単位である。
7 低周波空気振動
近年、人の耳には聞きとりにくい低い周波数の空気振動(低周波空気振動という。)が工場施設や道路橋等から発生し問題となっている。
苦情内容としては、ガラス窓や戸、障子等の建具ががたつきを生じ、これがうるさい、気になる、眠りが妨げられるといったものと、心理的・生理的苦情として圧迫感がある、眠りが妨げられる、頭痛がする、胃腸の具合が悪いといったものがある。
8 ばいじん・粉じん・浮遊粒子状物質
ばいじんは、燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用い伴い発生し、粉じんは物の破砕、選別その他の機械的処理又は鉱物等の堆積に伴い発生し、又は発散する物質である。
浮遊粒子物質は大気中に浮遊する粒子状の物質で、その粒径が10ミクロン以下ものもである。
9 赤潮
海中のプランクトンが大量増殖し、海水が赤褐色を呈する現象。
10 SS(浮遊物質)
水に溶けない懸濁性の物質をいう。水の濁りの原因となるもので魚類のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨げることによって水生植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機性浮遊物質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底質を悪化させる。
11 汚濁負荷量
大気や水などの環境に排出されるいおう酸化物、BOD等の汚濁物質の置量。一定期間における汚濁物質の濃度とこれを含む排出ガス量や排水量等との積で表される。
12 COD(化学的酸素要求量)
水中の有機物などは、溶存酸素を消費することなどにより、水中生物の成育を阻害する。このような有機物などによる水質汚濁の指標として、現在BOD及びCODが採用されている。これらの有機汚濁指標は、いずれもmg/lで表され、数値が高いほど汚濁が著しいことを示す。
CODは、水中の汚濁物質(主として有機物)を酸化剤で化学的に酸化するときに消費される酸素量をもって表し、環境基準では海域及び湖沼の汚濁指標として採用されている。
BODは、水中の汚濁物質(有機物)が微生物によって酸化分解されるときに必要とされる酸素量をもって表し、環境基準では河川の汚濁指標として採用されている。
13 PCB(ポリ塩化ビフェニル)
不燃性で熱に強く、絶縁性にすぐれ、化学的にも安定であるなど多くの特性を持った化学物質であり、このため用途も広範で、熱媒体、絶縁油、塗料等多岐にわたる。カネミ油症事件の原因物質で、皮膚障害や肝臓障害を引き起こすことが知られている。環境汚染物質として注目され、大きな社会問題となったため、現在我が国では製造は中止され、使用も限定されている。
14 pH(水素指数)
液体中の水素イオン濃度をあらわす値。水中の水素イオン濃度の逆数の常用対数であらわされる。7を中性とし、7より大きいものをアルカリ性、小さいものを酸性という。
15 pH(水素指数)
いわゆる淡水のプランクトンが増殖して呈色する現象をいう。このうち、藍藻類、緑藻類等により、緑色、青緑色、黄緑色を呈する場合をアオコといい、諏訪湖、霞ヶ浦等でみられる。一方、珪藻類、渦鞭毛藻類、黄緑色藻類等により、赤色、赤褐色、茶褐色、黒色を呈する場合を淡水赤潮といい、琵琶湖等でみられる。
16 上乗せ基準
ばい煙や排水等の排出の規制に関して、都道府県が条例で定める基準であって、国が定める基準より厳しいものをいう。
17 ザルツマン係数
二酸化窒素はザルツマン試薬を用いる吸光光度法により測定される。この方法は、二酸化窒素を吸収発色液(ザルツマン試薬)に吸収させ、生成した亜硝酸イオンが液中の試薬と反応してできたアゾ色素が発色するのを測定するものであるので、二酸化窒素と生成した亜硝酸イオンの比を示す係数が必要となり、これをザルツマン係数と呼んでいる。