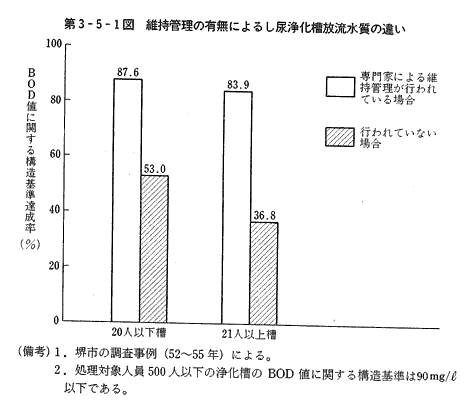
4 国民一人一人の手による環境保全
(1) 国民生活において必要な環境への配慮
国民生活の変化や向上に伴い、国民と環境の係わりも従来とは異なるものとなってきている。
すなわち、第2章第2節でみてきたとおり、消費の多様化、大量化が各種商品の使用後の廃棄物の増大と多様化をもたらし、都市における廃棄物の処理・処分が問題となってくるとともに、生活様式の多様化と都市化の進展による生活雑排水の増大が都市内河川、湖沼等の水質汚濁の大きな要因となるなど、国民生活に起因する環境問題が大きな課題となりつつある。このため、国、地方公共団体における排出規制、下水道整備等の施策の推進に加え、国民一人一人が日常生活においてできるだけ環境に与える影響を減少させるなど、環境保全に配慮した行動を心がけていくことが重要となってきている。
日常生活における国民の自主的な環境保全行動がどのような効果をもたらすかについて具体的にみてみよう。
たとえば、台所の流しの工夫により、水質汚濁を軽減することができる。
台所からの水質汚濁負荷は、生活排水(雑排水とし尿との合計)による負荷全体の約半分程度を占めると推計されており、これが無処理で公共水域に排出されると、水質に与える影響も大きい。この場合、台所の排水に含まれる食物の残りなどをこして排水中に混入させないようにすると、排水中の汚濁物質量が低下し、河川や湖沼の水質汚濁を軽減することに資する。たとえば、流しに設置するストレーナー(こし器)について、従来型では2〜5mmであった目の径をより細かいものに換えることにより排水中の汚濁物質が従来型のものより低下するとの実験結果もあり、下水道の整備等の施策とあいまってこのようなきめ細かな対策が期待される。なお、廃食用油は、台所から排出されるもののうちでも特に汚濁濃度が高い(BODで約32万mg/l)ものであり、排水中に混入しないようごみとして処理したり、別の形で再利用するなどの工夫が望まれる。
生活排水全体のうち、台所排水に次いで汚濁負荷量が大きいものは、し尿であり、生活排水全体の汚濁負荷の約3分の1を占めている。し尿は、下水道やくみ取りによりし尿処理場で処理されるもの以外は、主に浄化槽により処理された上、公共用水域に排出されることとなり、57年度の実績では、全人口の約24.5%に当たる約2,900万人分のし尿が浄化槽で処理されている。浄化槽は、その維持管理の状態によって、第3-5-1図の例のように、その放流水質が大きく変化することが知られており、水質汚濁の軽減のためには、浄化槽の適切な設置と併せて、使用者である国民が浄化槽の適切な維持管理を行うことも強く望まれている。
近年深刻化してきた近隣騒音問題も、家庭用機器の低騒音化や住居の遮音性能の向上などの施策が求められる一方で、自動車エンジンの空吹かし音、室内等の足音、話し声、扉の開閉音など、日常のちょっとした気配りで近隣に与える迷惑を軽減することができるものも多い。また、日常の心遣いだけでは音量の低減が難しい家庭用機器についても、機器の置き場所の工夫等で相当程度の改善が可能であり、使用者の側で周囲の状況に応じた防音対策、使用方法の工夫に努めることが望まれる。
沿道や海岸、山岳観光地等における空き缶の散乱も国民の努力で相当程度改善し得る問題である。いわゆる空き缶の「ポイ捨て」を行ったことがあるとする者に対してその理由をたずねた環境庁の調査の結果(第3-5-2図)によれば、空き缶回収容器の設置などの対策も必要であることがわかるが、基本的には、モラルの向上が重要であることが示されている。
公害の防止のほか、緑豊かなより良い環境を積極的につくっていく上でも国民の自主的努力は重要である。
たとえば、東京都の場合、58年度末現在、人により植栽されている樹木合計約1億本のうち、公園の樹木は1割にも満たない約900万本にすぎず、8割以上の約8,400万本が一般の住宅や事業所にある樹木である。このように、緑の少ない東京で都民が果たしている役割には大きいものがある。さらに、東京都は、「緑の倍増計画」をたてているが、この中でも、21世紀初頭までに新たに植えようとする約1億本のうちの6,300万本は都民が自分の庭等に植えるよう期待されているものである。
(2) 高まる自主的な環境保全の気運
近年、国民の暮しのあり方が環境に与える影響はますます大きくなってきているが、これに伴い、環境を自主的に保全しようとする国民の意識や行動も育ってきた。
すでに第2章第3節でみたように、環境保全活動一般に対する参加・協力意識を問う世論調査の結果でも、国民の約7割が積極的な態度を示している。
このような環境保全意識の高まりに応じて、環境を保全しようとする国民の自主的な活動も各地で盛んになってきている。
たとえば、滋賀県大津市においては、主婦グループを中心に「環境家計簿によるくらしの点検運動」が行われている。この運動では、洗濯、台所など身近な生活場面を幅広く取り上げ、洗剤の具体的な使用方法や雑排水の処理方法などに応じて、環境保全的であるかどうか、また、その程度を各自が詳細にチェックできるようなリストが作成されており、日常の暮し方を自然に環境に負荷を与えないような形に変えていく努力がなされている。
また、生活騒音問題についても、アパートやマンションの自治会や管理組合の申合せにより、住民自らが騒音の発生防止を図っていこうとする動きがみられる。
さらに、環境を積極的に美化していこうとする国民の意識も高まり、主体的な活動も活発になってきている。
愛知県豊橋市においては、登山道に空き缶等の散乱ゴミが多いことを憂慮したハイカーが「530(ゴミゼロ)運動」を始めたが、この運動が各地の清掃・美化運動の興隆に大きな刺激となったことは良く知られている。また、生け垣を増やそうとする「緑の垣根運動」(宮崎県高鍋町)などの各種の植樹・緑化運動を含め多種多様な創造的な環境美化活動が全国で行われるようになってきている。
(3) 国民一人一人の手による環境保全を進める施策
以上みてきたとおり、環境保全のための国民の自主的な行動は、相当の効果を持つようになってきており、また、積極的に環境に与える影響を減らし、環境を美化していこうとする活動も活発になってきている。こうしたことを踏まえ、今日では、環境改善に向けた国民の意識や努力を一層効果的に具体的な行動へと高めていくことにより、国民の活力を活用しつつ環境保全を進める施策を展開していくことが求められている。
国民の主体的な参加・協力を得て環境保全を進めていく上では、第一に、環境問題に関する理解や知識を増進し、環境を改善する国民の技量を灌養する環境教育や広報・啓発活動を充実していくことが、その前提として重要である。このため、学校教育の場においては、従来から社会科や理科を中心に指導が行われており、また、環境庁においては、各種の広報・啓発活動を行っているほか、6月5日の「世界環境デー」を初日とする「環境週間」を設け、関係省庁等の協力を得て環境問題に対する国民の関心を高めるための多様な行事を催している。さらに、自然公園内のビジターセンターや自然研究路等の整備を通じて環境教育の充実が図られているほか、関係団体等を通じた広報・啓発活動にも力が入れられている。
第二に、国民が環境保全のために行動するための機会を設けることが必要である。
環境庁では、厚生省とともに、58年度以来関係省庁、地方公共団体、事業者団体、各種民間公益団体等の協力を得て、「環境美化行動の日」を設定し、国民がこぞって環境美化に取り組むことを呼びかけている。この呼びかけに応え、59年度には45都道府県・政令市で統一実施日が設けられ、全国の市町村数の76%に当たる2,481市町村で環境美化運動が行われた。この結果、前年度を34万人上回る約750万人が参加し、約9万トン(前年比16千トン増)のごみを集めるなど全国各地で創意工夫を活かしつつ環境の美化に汗を流した。また、59年度には、「緑の国勢調査」の一環として国民が参加して行う「身近ないきもの調査」が行われた。このように、国民が積極的に参加できるような適切な機会や場を設定していくことは、国民の活力を活かして環境保全を進めていく上で重要な施策である。
第三に、一人一人の自主的な環境保全の努力の輪を国民的な規模に広げ、大きな力を発揮させていくための制度的な枠組を整備することも、国等の施策として必要なものである。
この点に関し、特に、60年度からは、広く国民から寄せられる資金によって豊かな自然の土地を買い取り、管理しようとする民間の運動である「国民環境基金(ナショナル・トラスト)活動」に関して新しい税制上の優遇措置が講じられることとなった。
ナショナル・トラストは、イギリスにおいて長い歴史を持つ民間団体であり、良好な自然の風景地や歴史的な環境の保全に大きな成果を収めている。我が国においても、これを範として、自然の風景地や歴史的な建造物等を国民が自主的に買い取って保護しようとする運動が近時盛んになってきた。国や地方の自然保護施策と連携をとりつつ、このような民間の自主的な自然保護活動を発展させていくことは、自然環境保全の一層の広がりを図る上で極めて重要である。このようなことから、国民環境基金活動を行う特定の法人に対する寄付金に関して所得税や法人税における課税の特例(寄附金控除又は損金算入)を認めることなどの措置がとられることとなったものである。
このほか、環境庁においては、国立公園等において利用道徳の高揚などを担当するボランティアの自然公園指導員の制度を設けているが、さらに、自然保護教育などを行う民間ボランティアを育成・活用する方策を具体的に検討していくこととしている。