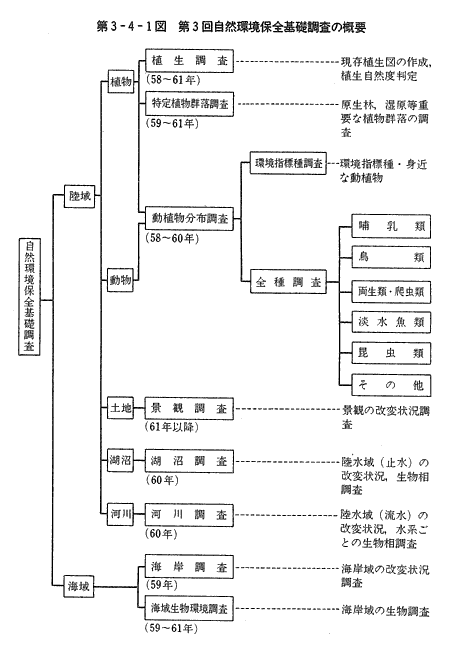
1 自然環境の保全
自然環境の保全を推進するに当たっては、自然環境が本来国民の共有的資源であるという認識に立ち、現在、破壊をまぬかれている自然を保護するというだけでなく、進んで自然環境を復元し、整備していくという施策を体系的に実施することが必要である。このため、原生的な自然やすぐれた風景地等の自然から農林業地域を含めた二次的な自然、都市地域の自然など、自然の質に応じて体系的に自然環境の保全を進める必要がある。
このような観点から、総合的な自然環境保全のための制度として、「自然環境保全法」が昭和47年に制定され、これを基本法とし、「自然公園法」、「都市緑地保全法」等関連する法体系に基づき、地域を指定して、各種の規制を行うとともに、保護及び利用のための施設の整備を行うなど、さまざまな施策が進められている。
また、都道府県においては、条例により、全国で約5万ヘクタールに及ぶ緑地環境保全地域等を指定するなど、市街地およびその周辺の自然環境を保全するための地道な努力が続けられている。
自然の重要な構成要素である野生鳥獣については、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」等に基づき、鳥獣保護区の設定、狩猟や取引きの規制等を行い、その保護が図られている。
このように、自然環境を体系的に保全していくための施策が進められているが、その展開に当たっては、以上の関係施策の充実を図るとともに次のことが重要である。
まず、第一に、自然環境の現状を正確に把握し、人間活動と自然との関係等を明らかにしていくための調査、研究の実施である。
環境庁では、「自然環境保全法」第5条に基づき、48年度から自然環境保全基礎調査として、植生、野生動物、地形地質などについて調査を行っており、現在、58年度を初年度とした第3回自然環境保全基礎調査を実施している(第3-4-1図)。このほか、原生自然環境保全地域については55年度から毎年、学術調査を行うなど、各種の調査を行っているところである。しかしながら、自然のメカニズムについてはいまだに解明されていない部分がきわめて多く、このため、人間活動と自然との関係、生態系等について明らかにしていくための調査、研究の充実を図り、その結果を活用することが肝要である。
第二に、国民の積極的な参加を得ながら自然環境の保全を進めることである。自然環境保全の活動に国民が自ら参加することは、国民一人一人が保護、保全の精神を身につけ、これを習性とすることにも結びつくと考えられるからである。このため、国民の自発的拠出をもとに自然環境や文化財の保全を図る国民環境基金(ナショナル・トラスト)活動の一層の発展が期待されている。
また、環境庁では第3回自然環境保全基礎調査の一環である「動植物分布調査」の実施に際し、広く一般ボランティアの参加を求めた。これに対し、約10万人もの参加があり、その内容も、家族、学校、自然保護団体その他年齢、職業とも広範にわたっており、国民の自然保護に寄せる関心が高いことを示している。
このように、広く国民の参加、協力を得て自然環境の調査を実施することは、少数の調査者だけでは困難な膨大な量の情報を収集することを可能にするとともに、国民の自然環境保全への意識の高揚にも役立つなど、種々の点において意義が高いと考えられる。