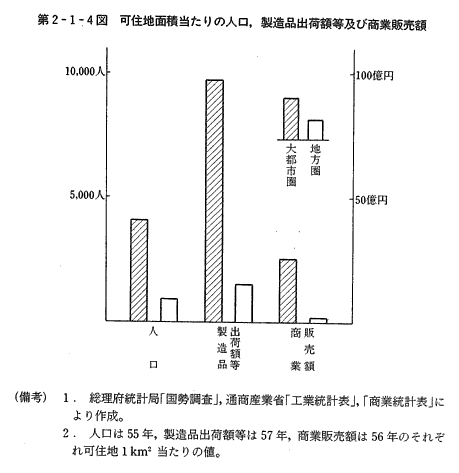
2 都市類型別の環境保全上の課題
都市と環境のかかわりは、都市の規模、都市の発展段階、都市の特性等によって異なる。ここでは、大都市圏と地方都市とに区分し、環境保全上の課題を整理することとする。
(1) 大都市圏
大都市圏の人口増加率は、一時に比べれば低くなったものの、依然、東京圏を中心に高い伸びを示している。
また、産業の集積度についてみると、工場の地方分散等により一般にその度合を減少させつつあるとはいえ、なお大都市圏は重要な地位を占めている。可住地面積当たりの人口、製造品出荷額等、商業販売額をみても、地方圏に比べれば極めて密度の高い都市活動が営なまれていることがわかる(第2-1-4図)。
このため、大都市圏においては、各種環境問題が顕在化している。
大気汚染についてみると、一般環境大気測定局の58年度の測定結果が二酸化窒素の環境基準のゾーンの上限(1時間値の1日平均値0.06ppm)を超える測定局は、すべて大都市圏にある。また、59年の全国の光化学オキシダント注意報の8割が東京湾地域(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)、大阪湾地域(大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県)で発令されている。水質汚濁については、排水規制、下水道の整備等により改善傾向にあるものの、なお汚濁の水準は高い。建設省が58年に調査した全国一級河川の測定結果によると、BODの年間平均値の上位5河川は、すべて大都市圏を貫流している。また、東京湾、伊勢湾、大阪湾のCODに係る環境基準の達成率は、他の海域よりも低い。
また、一部の幹線道路、飛行場、新幹線鉄道の周辺における交通公害問題、近隣騒音あるいは廃棄物の埋立処分地の確保も問題となっている。
以上のような問題に加え、大都市圏においては、都市化に伴い身近な緑、水辺などの自然とのふれあいの機会が失われてきており、住民の自然志向意識が高まっている。このため、大都市圏においては、このような環境問題に適切に対応していくことがまず基本である。
さらに、大都市圏の中心部と周辺都市とに分けて、環境保全上の課題をみると、次のとおりである。
大都市圏中心部においては、住工混在、ミニ開発、空家率の高い老朽木賃アパートなどがみられることや、緑地等のオープンスペースが不足していることなど居住環境が劣化しているところがある。一方、業務・サービス機能が集積しつつあり、都市機能更新等の観点から各種再開発も活発に行われるようになっている。このようなことから、総合的な公害対策を講じつつ、居住環境を改善し、快適な都市環境を積極的に創出していくことが課題となっている。
大都市圏の周辺都市においては、急激な人口増加に対し一般に公共施設等の生活基盤の整備があと追いになる傾向があり、特に、下水道整備が不十分な地域では、水質汚濁が問題となっている。また、就業、生活等の面で中心都市への依存度が高いことから、高次の都市的サービスが提供できず都市としての魅力に欠け、また、住民の地域に接する機会が少なく地元への愛着が育ちにくい状況にある。このようなことから、社会資本の計画的整備を進めつつ、地域住民が愛着を持てるような個性ある街づくりを行うことが大きな課題である。
(2) 地方都市
地方都市のうち、地方中枢・中核都市は、周辺市町村までを含めた都市圏を形成しつつ市街地の拡大が進み、中枢管理機能も集積しつつあるが、たとえば、自動車排出ガス測定局の58年度の測定結果をみると、地方中枢都市部の一部の測定局が二酸化窒素の環境基準のゾーンの上限(1時間値の1日平均値0.06ppm)を超えるなど、大都市圏において顕在化している環境汚染と同様の状況を示している地域もみられる。
地方中小都市においても、市街地の外延的拡大が進み、これに対し下水道等社会資本の整備が遅れがちとなっている。また、農家と非農家との混住化が進んだところでは、都市汚水による農業用水の汚濁等の問題が発生している。
しかしながら、地方都市は、大都市圏に比べれば自然環境に恵まれており、無秩序な開発が進行して環境が悪化する前に、計画的都市整備を進めつつ、このような地域特性を生かした快適な都市環境を形成することが課題である。