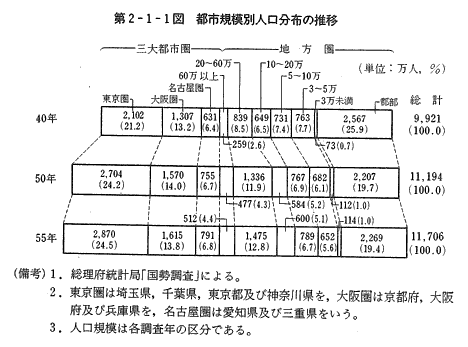
1 近年における都市化の動向
(1) 人口分布の動向
我が国の人口分布の動向をみると、一時の急激な都市への集中傾向は鎮静化したものの、全体としての都市化は依然として進行している。
都市化の動向を人口の集積度を示す指標として用いられるDID(人口集中地区:人口密度が1k?当たり4,000人以上の国勢調査区が互いに隣接して、当該隣接する国勢調査区の合計人口が5,000人以上となる地域)の尺度でみると、DID人口は、昭和35年には4,100万人であったのが、55年には約7,000万人、総人口の6割にも達している。今後もその増加が見込まれ、21世紀初頭には国民の7割がDIDに居住するとの予測もある。
人口分布の推移を地域別にみると、大都市圏においては、高度経済成長期に臨海型コンビナートを中心に生産活動が急速に拡大したことなどを背景に、地方圏から大量に人口が流入し、これが大都市圏における環境問題を深刻化させる要因ともなった。40年代後半以降は、大量に人口流入の傾向は鎮静化したが、自然増を中心に人口が増加し、周辺部への拡散的な市街化が進んでいる。
地方圏においては、産業の地方分散やサービス経済化が進み、これらが大きな雇用を創出したことなどを背景として、人口の定着化傾向が現われてきている。この中で、ブロックの中心である地方中枢都市及び県庁所在地等の地方中核都市の人口の増加率が相対的に高くなっている(第2-1-1図)。また、地方中小都市では、一般に低密度、拡散的な市街地が形成されつつあり、農家と非農家との混住化も進んでいる。
(2) 都市的生活様式の普及
都市においては、食料、衣料等の生活物資や各種サービスを市場から購入し、高度の消費活動を行うとともに、これに伴い排出されるごみ等の処理を公共サービスに依存するという生活が営まれている。このようないわゆる生活様式の都市化は、かつては大都市圏ほど進行していたが、近年においては、大都市圏と地方圏との所得格差の縮小や農家所得の上昇などを背景として消費生活の平準化が進み、地方都市のみならず、農村社会にまで都市的生活様式が普及しつつある。
たとえば、自家用自動車の保有台数をみると、地方圏においては圏域内の交通を道路に頼っているところが多く、また、自動車の持つ機動性を発揮させやすいこともあって、地方圏における増加率は大都市圏を上回っている(第2-1-2図)。また、1人当たりの生活用水使用量をみると、地方圏での使用量の増加が大きく、地域ごとの格差は縮小しつつある(第2-1-3図)。この背景としては、地方圏において水道普及率、水洗化率、洗濯機の普及率等が上昇したほか、核家族化が進行してきていること等が考えられる。
以上のような地方都市の人口増加や都市的生活様式の普及に伴い、道路交通公害問題、生活排水による水質汚濁、日常生活から排出されるごみの処理・処分等の問題が地方圏においてもさらに広がるおそれがある。