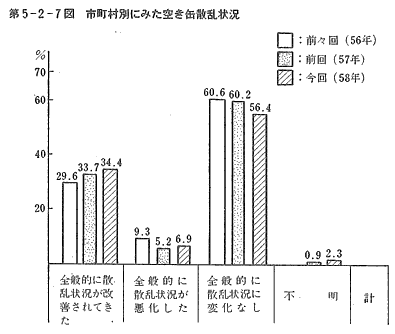
3 空き缶問題の現況と対策
缶飲料は、流通・消費段階における取扱いが容易であることに加え、消費生活の多様化、自動販売機の急速な普及とも相まって、その生産量は急速に増大した。昭和45年には8億缶程度であったものが、昭和56年には100億缶を超える状況にある。これら缶飲料の空き缶の一部が道路、公園、河川等に散乱し環境美化の観点から問題となっている。
環境庁が昭和58年度に全国の1,891市町村について実施したアンケート調査の結果によると、市町村別にみた散乱状況は第5-2-7図のとおりである。これによれば、「散乱状況が悪化した」と評価した市町村は6.9%であるが、「散乱状況が改善された」と評価した市町村は34.4%で、前年度に比べ僅かに増加している。
このように一部地域では問題が残されているものの全体的傾向としては徐々に改善されてきている。
空き缶散乱防止対策としては、大別して?投げ捨て防止と、?散乱空き缶の回収とがあり、各地方公共団体ではそれぞれの地域に応じた各種の対策を講じている。すなわち、空き缶散乱防止に関する条例や対策要網を定めた地方公共団体が増加しているほか、投げ捨て防止のためのキャンペーン等の実施あるいは回収を円滑にするための清掃の強化、住民団体の活動に対する助成等が行われている。
さらに、散乱空き缶の問題については当面、国、地方公共団体、事業者、消費者である住民等がそれぞれの立場において各種の取り組みを行ってきたが、なお国においても、空き缶散乱に対処するため、昭和56年1月関係11省庁からなる「空き缶問題連絡協議会」を設置し、同協議会における申し合せに基づき、昨年度に引き続き空き缶散乱防止のための普及啓発活動の充実を図っているほか、環境庁及び厚生省は新たに環境美化運動の一環として環境週間を中心とした「環境美化行動の日」の設定を都道府県及び市町村に呼びかけ、空き缶散乱防止の推進を図った。