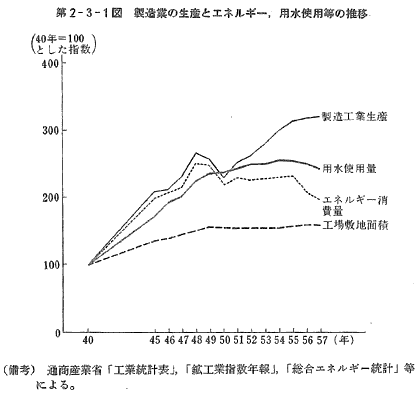
1 産業構造の高度化と環境
産業構造の高度化が進展している中で、環境と深い係わりをもつエネルギー消費や用水使用等の状況に変化がみられる。
まず、製造業全体について生産、エネルギー消費量、用水使用量及び工場敷地面積の推移をみると、それぞれ40年代前半までは、急速な伸びを示している。その後、50年代に入ってからは、いずれも伸びは低下しており、この中でエネルギー消費、用水使用は生産の伸びを大幅に下回っている(第2-3-1図)。
次に、これを産業構造の変化と関連づけてみるため、生産とエネルギー消費の動向を業種別にみると、40年代前半までは、すべての業種について生産、エネルギー消費とも大幅に増大しているが、50年以降については、エネルギー消費の小さな機械等加工組立型産業の生産が大幅に増加している一方、化学、鉄鋼などの素材型産業は伸びの鈍化が著しい。また、この間、素材型産業を中心としてエネルギー消費原単位の低下が顕著に進んでいる(第2-3-2図)。
硫黄酸化物の排出量は近年低減してきているとみられるが、この要因としては、公害対策の進展によるところが大きいが、それとともに上に述べたような産業構造の変化や省エネルギーの進展も寄与していると考えられる。仮に、50年から57年の間に、素材型産業と加工組立型産業の生産の構成比が変化しなかったとすると、57年のエネルギー消費量は約10%増大する計算になる。また、素材型産業のエネルギー消費原単位は50年から57年の間に約34%低下しており、これがなかったとすると57年のエネルギー消費量は約17%増大することになる。
このように製造業全体として、エネルギー消費がより少なくてすむ方向への体質転換が進んでいるとみられるものの、現在のエネルギー消費量自体は45年の水準からそれ程低下している訳ではなく、環境汚染防止のための対策は依然として重要である。
また、エネルギー供給源別にみると、今後、石炭、原子力等の比重が高まることが予想され、こうした変化に十分留意していく必要がある。たとえば、石炭は石油に比し、一般に硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん等の発生量が多く、貯蔵・運搬に伴い粉じんが飛散しやすいという問題がある。
用水使用量の伸びの低下についても、エネルギー消費と同様に、素材型産業から加工組立型産業への生産のシフトと化学を中心とした用水使用原単位の低下が寄与している(第2-3-3図)。
用水には淡水及び海水があるが、このうち淡水使用量には新たな水使用となる補給水量と、一度使用した水を再利用する回収水量が含まれる。淡水使用量に占める回収水の割合を示す回収利用率の推移をみると、40年の36.2%から56年の73.9%まで大幅な上昇を示しており、用水使用量の伸びの低下とあいまって補給水量は49年以降減少している(第2-3-4図)。
このように、40年代には大幅に増大した用水使用量も近年その増加が抑制されてきている。しかしながら、用水使用量の水準自体はかなり高く、今後とも水の回収利用を進めるなど、水の有効利用を図ることで、利水、排水に関連する環境影響を減少させることが望まれる。
次に、産業別の廃棄物の動向を50年度から55年度の間にみると、製造業の伸びは低かったものの、鉱業からの廃棄物の大幅な増加等があり廃棄物総量は23.0%増大している(第2-3-5図)。これを種類別にみると、汚でいの排出量が著しく増大し、55年度には総排出量の約30%を占め、次いで鉱さい、家畜糞尿、建設廃材の排出量が多い(第1-1-9図)。なお、汚でい排出量の増加は製造業における排水処理の強化によるものと推定される。
産業廃棄物の処理の状況をみると、再生利用の比率が増大し、55年度には43%に達したため、最終処分量は50年度から55年度の間に排出量の増加にもかかわらず12%の減少となっている。
以上、総じて、産業構造の変化と省資源、省エネルギーの進展は、公害対策ともあいまって環境に対する負荷の増大を抑制する効果をもたらしてきたといえる。しかしながら、エネルギー消費、用水使用、廃棄物いずれも絶対量としては高水準にあること等から、今後、経済活動の拡大に伴い、排出量が増大すること十分考えられる。こうしたことから、省資源・省エネルギーの一層の進展が期待される。
また、産業構造の高度化の進展の中で各分野で技術革新が進み、高度化した消費者のニーズに対応した多様な製品の生産、流通、消費が拡大している。今後、これらの動向も踏まえて、環境保全に引き続き努力していくことが重要である。
さらに近年ある種の化学物質による環境問題の可能性が指摘されている。たとえばトリクロロエチレン等による地下水の汚染などであり、また、現在のところ環境汚染の問題は生じていないがダイオキシンの問題も指摘されている。