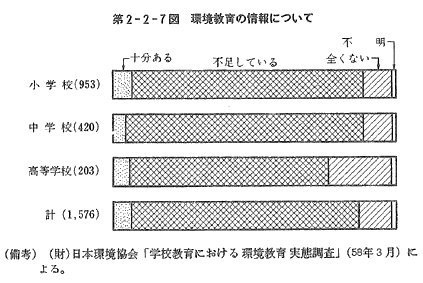
4 環境教育
環境問題を適性かつ円滑に解決し、よりよい環境を実現していくためには、行政的な対応や企業の努力のみにならず、国民一人一人が環境に配慮した生活行動を心がけていくことが大切である。そのためにも、環境教育を普及し、正しい環境の認識と環境保全のための積極的な行動の基盤を広げることが望まれる。
47年にストックホルムで開催された国連人間環境会議の勧告では、環境教育の目的について「自己を取り巻く環境を自己のできる範囲内で管理し、規制する行動を一歩ずつ確実にしていく人間を育成することにある」としている。
57年の国連環境計画(UNEP)管理理事会特別会合(ナイロビ会議)においても「広報、教育、研修を通じて環境の重要性に対する認識を高めること、環境を改善するために各人の責任ある行動と参加が不可欠であること」を改めて強調している。
アメリカではすでに、1970年に「環境教育法」が制定され、カリキュラムの開発、教師の現職教育、野外センターの設置などが各州で進められ、自然に親しませ、自然から感得させ、自然を理解させる教育が活発に行なわれるようになった。
また、イギリスでは1960年代の後半から各大学を中心に環境プロジェクトや環境学習研究が進められ、西ドイツでは環境学習が各邦の基礎学校でとり入れられることになった。
我が国でも学校における環境保全に関する教育については、その重要性にかんがみ、従来から社会科や理科を中心に指導が行なわれている.
また、学校以外の分野においても、たとえば、自然公園内のビジターセンター、自然研究路等の整備をつうじて環境教育の充実が図れている。さらに、公益法人等を通じた広報・啓発活動も行なわれている。
しかしながら、(財)日本環境協会が実施した「学校教育における環境教育実態調査」によれば、小・中・高等学校の教員の中で「環境教育という言葉」を「はじめて知った」と回答した者の比率が小学校24%、中学校29%、高等学校37%となっているこや、環境教育の情報について、情報が十分であると感じている学校は10%に満たず、大半の学校が不足していると感じていることなどから、環境教育が必ずしも十分浸透しているとは言えない状況にあることがうかがわれる(第2-2-7図)。
今後、環境教育の必要性について、より一層理解が深まるとともに、適切な教材の開発、自然と親しむ機会の確保などを通じて、更に充実した環境教育が行なわれることが望まれる。