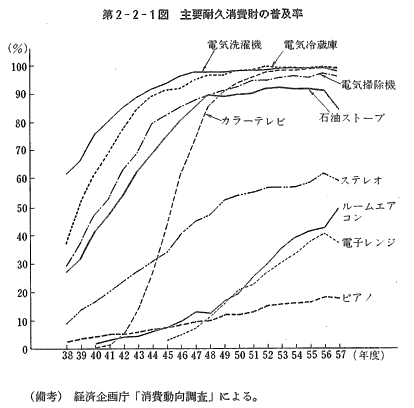
1 消費の多様化と環境
今日、国民の生活水準は向上し、所得水準や耐久消費財の保有に関しては、世界でも有数の水準に達している。大型家電製品を中心として、日常生活で消費される商品も多様化している。
ここ20年における主要耐久消費財の普及率と民生部門のエネルギー消費の推移は、第2-2-1図及び第2-2-2図にみるとおりである。電気冷蔵庫、カラーテレビ、石油ストーブ等のエネルギー消費機器はすでに90%以上普及しており、またルームエアコン、電子レンジ等も急速に普及しつつある。これに伴い、いわゆる民生部門におけるエネルギー消費は、他の産業・運輸部門を上回る伸びとなっている。また、その比重は相対的に高まっており、今後も一層比重が高まることが予測されている。
深夜営業店のカラオケなどの近隣騒音は近年公害苦情の中で大きな割合を占めており、また過密化した都市内においては一般家庭からの生活騒音も問題となっている。各種家庭用機器や音響機器には騒音の発生源となっているものがある。そのうち、騒音レベル、音の発生頻度、普及状況及び近隣居住者からの気になる音としての指摘状況からみると、特に問題になりやすいものには、エアコンディショナー等の空調機器、ピアノ、電気掃除機等があげられており、それらの使用台数は、第2-2-1図にみるとおり著しく増加している。
消費の多様化、大量化は、各種商品の使用過程において、エネルギー消費の拡大などの問題を生じるとともに、その使用後の廃棄物の増大と多様化をもたらす。乗用車を例にとると、保有台数は35年に約46万台であったものが、57年には2,554万台と56倍近くに増えており、またこの間の乗用車の累積廃棄台数は2,000万台近くにのぼると推計される(第2-2-3図)。
日常生活そのものからもたらされる廃棄物の増大は、各地で最終処分地の確保を困難にするという問題を生じている。また、ごみ処理のための費用も増大しており、東京都におけるトン当たり処理原価は47年に比べ56年には3.03倍(26,000円余)になり、年間約1,200億円が費されている。さらに、廃棄される製品が多様化し、製品に使われている物質が複雑化していることから、除去・無害化が困難な物質を含む廃棄物などその性状、排出量、排出形態等によっては、現行の処理施設・システムでは処理が困難なものが出現するなど廃棄物の適正な収集・処理のあり方に大きな課題を投げかけている。
今後とも便利で機能的な生活を求めて消費が多様化していくことが予測される。長期的に安定した国民生活の向上の基盤を確保していくためには、多様化した消費活動と環境との係わりにも目を向ける必要がある。