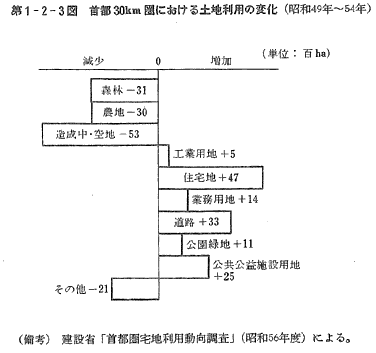
3 身近な自然の状況
地域住民が日常生活において身近に接する自然も大切なものといえる。このため、ここでは身近な自然の改変状況をみることとする。
我が国では、様々な形での土地利用の改変が行われた結果、国土庁の調べによると、40年から56年の16年間に全国で84万ヘクタールの農用地と、31万ヘクタールの原野が減少している。この間、森林が8万ヘクタールの増、水面・河川・水路が3万ヘクタールの増となっているので、単純に計算すれば差引き約100万ヘクタールに及ぶ自然地が改変されたということになる。これは関東平野にも匹敵する規模である。3大都市圏で見ると農用地が25万ヘクタールで28%、森林が7万ヘクタールで3%それぞれ減少している。農用地、森林、原野、水面・河川・水路が全面積に占める割合をみると、40年の81%が56年には72%となっている。これらの減少は、居住地周辺でとくに大きく進んでいると考えられる。
関東地方についてみると、戦後の急速な都市化の結果、身近な自然は失われてきたが、近年においてもその傾向が続いている。
第2回自然環境保全基礎調査によると、関東地方において、35年から50年にかけての15年間で森林、原野等の自然緑地が約75,800ヘクタール(関東地方の全面積の2.5%)、農地等の生産緑地が約81,800ヘクタール(同2.7%)も失われた。
また、建設省が実施した首都圏宅地利用動向調査によると、49年から54年までの5年間において、首都30キロメートル圏の2,700平方キロメートルの地域で、森林、農地がそれぞれ約3,000ヘクタール減少し、都市的な土地利用に転換している(第1-2-3図)。
さらに、首都圏の住民にとって身近な自然の代表的なものとして武蔵野の平地林面積についてみると、環境庁が実施した居住地周辺環境保全活用計画策定調査によると、第1-2-4図にみるとおり、明治43年を100とすれば昭和48年には46.0と半減し、その後、55年には、44.8まで減少している。このような状況の下で国民の意識を「自然保護に関する世論調査」(56年6月、総理府調べ)によりみると、居住地周辺の緑の自然について恵まれていないと思っている者が全国では17%であるのに対して、東京都区部では47%、10大都市では30%となっており、特に大都市で多くの人々が自然に恵まれていないと感じていることが分かる。