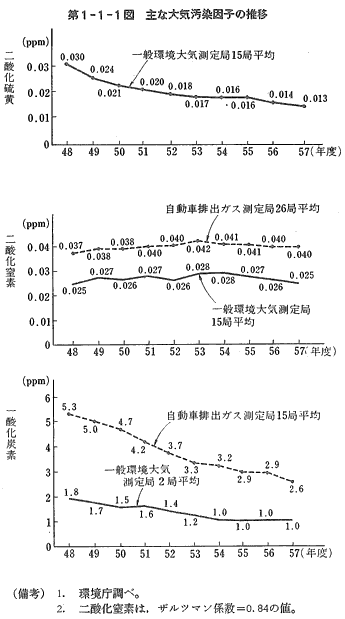
1 大気汚染
大気の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(環境基準)が、現在、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)、一酸化炭素(CO)、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質(SPM)について設定されている。以下においてはこれらの物質について環境基準の達成状況などをみることとする。
(1) 二酸化硫黄
大気中の硫黄酸化物は、主として石油、石炭などの化石燃料の燃焼に伴い発生するものであり、高度経済成長期に石油系燃料が大量に消費されたことにより、急速に汚染が拡大した。その後、排出基準の設定を基本としつつ、高汚染地域に対しては総量規制基準が導入されるなど諸対策が進められた結果、大気中の二酸化硫黄の濃度は、昭和43年度以降年々減少傾向を示してきた。
大気汚染の一般的状況を把握するため全国に設置されている一般環境大気測定局(以下「一般測定局」という。)のうち、二酸化硫黄濃度を40年度から継続している15局における年平均値をみると、42年度の0.059ppmをピークに減少し、56年度には、0.014ppm、57年度には0.013ppmとなっている(第1-1-1図)。
また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。)の達成状況をみると、長期的評価による環境基準を達成した一般測定局は年々増加しており、達成局数でみた達成率は56年度98.9%、57年度99.4%となっている。
(2) 二酸化窒素
大気中の窒素酸化物はその大部分が燃焼に伴って発生するものであり、発生源としては工場などの固定発生源に加えて、自動車などの移動発生源の占める割合も大きい。
二酸化窒素の濃度を45年度から継続して測定している15の一般測定局における年平均値でみると、49年度以降おおむね横ばいで推移してきたが、54年度以降やや減少傾向を示しており、56年度0.026ppm、57年度0.025ppmとなっている。(第1-1-1図)。
道路周辺における大気汚染を把握するため、沿道に設置されている自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の濃度を、46年度から継続して測定伊している26局の年平均値でみると、51年度以降横ばいの傾向にあり、57年度は0.040ppmとなっている(第1-1-1図)。
また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。)との対応状況をみると、一般測定局では、0.06ppmを超えた測定局の割合が56年度の3.2%から57年度には2.0%へ、0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内の測定局の割合が56年度24.0%から21.4%へとそれぞれ減少し、0.04ppm未満の測定局の割合が56年度の72.8%から76.6%へと増加している。0.06ppmを超えた測定局の割合は54年度以降減少傾向がみられる。
一方、自動車排出ガス測定局では、0.06ppmを超えた測定局の割合は56年度34.1%から57年度27.1%へと減少している(第1-1-2図)。
また、これらの測定局では、0.06ppmを超える高濃度測定局は、東京都、大阪府、神奈川県等の大都市地域に集中している。
(3) 一酸化炭素
大気中の一酸化炭素は不完全燃焼により発生するもので、主に自動車排出ガスによるものとみられている。自動車に対する規制が41年に開始され、逐次強化されてきた結果、自動車排出ガス測定局における一酸化炭素の濃度の推移を46年度から継続して測定している15局の年平均値でみると、48年度の5.3ppmから年々減少する傾向にあり、57年度は2.6ppmとなっている(第1-1-1図)。また、一般測定局における一酸化炭素の濃度の推移を43年度から測定している2局の年平均値の変化で見ると、43年度の4.9ppmから54年度1.0ppmまで低下し、その後横ばいとなっている(第1-1-1図)。
環境基準(1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。)の達成率の推移をみると、長期的評価では、自動車排出ガス測定局では56年度99.3%、57年度99.7%となっており、一般測定局では57年度100.0%となっている。
(4) 光化学オキシダント
光化学大気汚染は窒素酸化物と炭化水素類の光化学反応から二次的に生成される汚染物質によって発生するもので、その汚染状況は光化学オキシダント濃度を指標として把握されている。
光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令。)の全国発令延日数は、48年の328日をピークに49年以降減少傾向にあったが、気象条件の影響もあり、57年73日が58年131日へと増加した。
これを地域的にみると、東京湾地域(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県)と大阪湾地域(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)がほとんどを占めている。
また、光化学大気汚染による被害届出人数は50年の46,081人をピークに減少傾向にあったが、57年の446人から58年1,721人へと増加した(第1-1-3図)。
(5) 浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質は大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10ミクロン以下のもので、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度の場合には人の健康に与える影響が大きいものである。一般測定局について環境基準(1時間値の1日平均値が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートルであること。)の達成率をみると、長期的評価では56年度38.1%、57年度49.0%と達成率が向上しており、改善の兆しがみられるが、依然として低い状況にある。