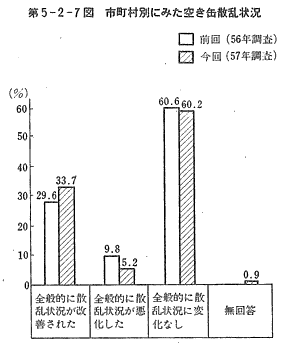
3 空き缶問題の現況と対策
缶飲料は、流通・消費段階における取扱いが容易であること等から自動販売機の急速な普及とも相まって、その生産量は急速に増大した。すなわち、昭和45年には飲料缶全体で8億缶程度であったものが昭和54年には92億缶と10倍を超える伸びを示している。しかし、その後昭和56年までは90億缶前後の横ばい状況で推移している。これら缶飲料の空き缶の一部が道路、公園、海岸、河川等において散乱し、地域の環境美化の観点から各所で問題となっている。また、空き缶の問題は、市町村における廃棄物処理行政上も無視できないものとなっている。
環境庁が昭和57年に全国1,891市町村(昭和55年調査で空き缶散乱が問題となっている場所があると答えた団体(東京都の特別区を含む。))について実施したアンケート調査の結果によると、市町村別にみた散乱状況は第5-2-7図のとおりである。これによれば、改善されたと評価した市町村の全体に対する比率は約34%で前回調査(56年)に比べ約4%程度増加している。一方、悪化したと評価したものの比率は約5%で前回に比べて5%程度減少している。
また、調査対象市町村における調査場所(8,062か所)ごとの空き缶散乱状況の1か年の変化をみると、?散乱が問題視されなくなった場所655か所(8.1%)、?散乱空き缶が少なくなった場所1,699か所(21.1%)であり、これら改善状況にあるとする場所全体では約29%となっている。一方、?散乱空き缶が多くなった場所404か所(5.0%)、?新たな散乱場所716か所(8.9%)であり、これら悪化状況にあるとする場所全体では約14%となっており、全体的には改善の傾向にあることがうかがえる。
空き缶散乱防止対策としては、大別して?投げ捨ての防止と、?散乱空き缶の回収とがあり、各地方公共団体ではそれぞれの地域に応じた各種の対策を講じている。すなわち、空き毎散乱防止に関する条例や対策要綱を定めた地方公共団体が増加しているほか、投げ捨て防止のためのキャンペーン等の実施あるいは回収を円滑にするための清掃の強化、住民団体の活動に対する助成等が行われている。
さらに、廃棄物の減量化等を図るため、空き缶の再資源化への努力も払われており、昭和57年に前述の散乱状況に関する調査と併せて行った調査の結果によると、調査対象市町村(1,891団体)のうち、約58%において、何らかの空き缶再資源化が行われており、前年度調査結果より5%程度増えている。
政府においても、昭和56年1月に設置された関係11省庁からなる「空き缶問題連絡協議会」の申合わせに基づき、地方公共団体、関係民間団体等とも協力しつつ昨年度に引き続き空き缶散乱防止のための普及啓発活動の充実を図った。