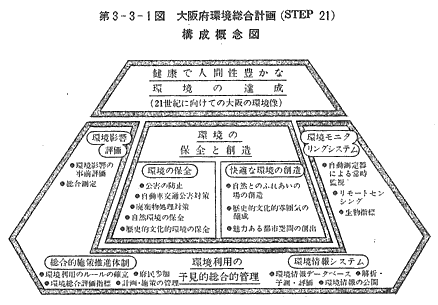
2 地方の特性に応じた創意と工夫
環境政策の推進に当たっては、それぞれの地域の環境上の特性を踏まえた施策を展開することが重要であり、「公害対策基本法」を始めとし、関連の法制度に基づきこれらのことに具体的に配慮している。
例えば、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」に基づき、都道府県ではその自然的、経済社会的諸条件からみて、全国一律の排出基準等だけでは、環境基準の確保が困難であると認められる場合に、条例でより厳しい排出基準等を設定しているほか、法律で定める環境汚染物質以外についても必要な規制を定めているものも多い。
また、「都市計画法」等に基づく土地利用に関する計画の作成、緑のマスタープランの作成など市町村の関与により地域特性を反映させているものも多い。 より良い環境の実現のためには、既存の法制度を十分に活用していくことは当然であるが、同時に地域の住民のニーズの高まりに対応した施策の新たな展開が必要であり、地域の環境の適切な保全と創造に向けて、国、地方公共団体等の密接な連携と積極的な努力が求められている。
(1) 快適環境づくり
ア 総合的な快適性の確保
我が国の国民生活は、高い経済成長を通じて、消費水準などの物的豊かさや利便性についてはかなりの水準に達した。他方、急速な都市化の下で、自然や歴史が失なわれ1.、やすらぎやうるおいが求められるようになってきている。物的なものから質的なものへとより高次の環境の質に対するニーズが強くなっている。このような要請にこたえて、既に各地で快適な環境づくりが始まっており、種々の形で模索されてきている。地域の住民、企業、地方公共団体等が地域における新しい役割を自覚し、環境資源を基にして快適性をつくり出す共同作業を始めている。
環境の快適性は、安全、衛生、利便等がその重要な要素となることはもちろんであるが、その他の要素として、静けさ、のびのびと歩ける空間、身近な水や緑などの自然、町並みの美しさ、あるいは歴史的なたたずまいなども含まれよう。このような素材は、かつてはほとんどの地域にあったものである。近年、大都市圏はもちろん、次第に地方都市、農山村でも失われようとしている。
したがって、今後の快適な環境づくりに当たっては、このような快適性の要素を生かしながら進めていくことが重要である。その際、地域の自然的、経済社会的、文化的、歴史的特性を踏まえ、地域住民の中から盛り上がってくる熱意とコンセンサスを基盤として、地方公共団体や国の施策と一体となって進められることが求められる。また、これまで続けられてきた公害防止や自然環境の保全の上に立って人々の生活と調和させながら進めることが必要である。
このことを快適環境づくりと大きな関係をもつ社会資本整備についてみてみよう。
社会資本はこれまで、例えば、廃棄物処理施設、道路、河川改修などについても、安全、衛生、利便の面を中心に整備が進められてきた。一方、より質の高いニ一ズである快適性という観点については、当時の経済社会状況からみればやむを得ない面があったが、従来ともすればみすごされていたことも多い。最近は、これらの社会資本の整備に際しても、快適性に配慮する動きがみられているが、今後とも住民のニーズの高次化に対応し、社会資本の整備に際し、地域の総合的な環境水準の向上にも資するよう快適性付与のための具体的方策について検討を推進していくことが求められる。例えば、道路については交通機能の面だけを考慮するのでなく、緑地帯を確保したり、人々がお互いに触れ合うことのできる空間を創造し、景観と合致した美観を形成するなど、街づくりと一体となった道路の体系的整備を図ることが必要である。
また、河川改修などの水辺環境に重要な係わりを持つ社会資本整備に際しても、人と水との触れ合いなどに配慮していくことが重要である。
イ 施策に関する経験の交流の促進等
快適環境づくりは、住民のニーズ、各地域の水や緑、歴史的遺産、建造物などの環境を構成する素材の状態などによって異なってくるものであり、全国一律に、画一的にその具体的な在り方を規定することは難しい。それだけに、快適環境づくりは、地方公共団体や地域住民が自主的に、あるいは、国の各種制度を生かしながら進めている。国は、そのような地域住民の活動を支援し、補完していくことが重要である。
このため、環境庁では、地方公共団体及び(財)日本環境協会との共催の下、55年度以来、地方公共団体の担当者等を対象に快適環境シンポジウムを開催し、学識経験者、住民団体の代表なども交えて各地の事例の紹介、将来展望などについて、幅広く経験、意見の交流の促進を図っており、これらを通じて、快適環境づくりが、次第に地域に定着してきつつある。
57年度は第3回快適環境シンポジウムが岩手県盛岡市において開催され、水と緑の復権をテーマに事例発表、講演などが行われた。また、国における快適環境創造への取組として自然環境保全、文化財保護、都市計画などの面についで快適環境づくりの観点から検討が行われた。
今後とも、国は環境の保全に資する法制度の整備とともに、快適でうるおいのある環境づくりに役立つ既存制度の活用方法等についての情報提供を行うなど快適な環境づくりの基盤となる施策の推進を図る必要がある。
ウ 快適環境づくりの試み
快適環境づくりについては、全国各地で多くの事例が報告されているが、ここでは埼玉県草加市の例をみよう。同市を流れる綾瀬川については、中川、綾瀬川総合治水対策特定河川事業及び河川激甚災害対策特別緊急事業が採択されている。草加市はこれを契機に、国、地方公共団体などから成る検討委員会を設け、総合的な河川再生計画の策定に取り組んでいる。
すなわち、?川に並行する旧奥州街道沿いの松並木を歴史的空間として位置付け、遊歩道として整備する、?緑地、空地を確保し、水の浸透性に配慮する、?河川整備に当たって、市民を水に近づける工夫をすることにより、水に対する関心を高め、河川保全への理解を深める、?河川を都市における水と緑の連続空間として位置付け、活用するなどである。
草加市の場合は、まだ緒についたばかりであるが、既に、水や緑を生かした例として宮城県仙台市では市の中央を流れる広瀬川を市民の心のふるさととし、この川のすぐれた自然環境を保全するための下水道の整備、周辺の開発の規制、緑地の保全などを通じて、環境の快適性を高めている。また、岡山市では緑化条例を基に都市における緑の保全を図るため、市と市民が一体となって緑化に取り組み、西川緑道公園を市のシンボルとして、緑と花、光と水にみちた清潔な街づくりを目指している。さらには鹿児島市の例など全国各地で水と緑を生かした快適環境づくりが進められている。このほか、歴史的、文化的遺産を生かした環境づくり、近代的景観美を生かした街づくりなどが進められている。
地域の水や緑、大気あるいは建築物などさまざまな環境を構成する素材を有機的に結び付け、環境の総合的管理を図る中で快適な環境づくりを進めていこうとする例もみられるようになっている。県民の参加と合意形成を図りながら快適な環境を追求し、県土の環境資源を十分に把握しながら環境に適合した地域社会の建設を目指している石川県の例などである。このような動きは市町村においてもみられてきている。
(2) 地域環境管理計画
多くの地方公共団体では、公害防止、自然保護の一層の充実に加えて、環境汚染の未然防止や快適な環境づくりをも含めた総合的な環境政策の体系を確立することを目的として地域環境管理計画の策定を試みている。
ア 地域環境管理計画策定の動き
環境管理計画策定の動きを振り返ると、まず48年9月に策定された大阪府環境管理計画(BIGPLAN)があげられる。これは京都市公害防止基本計画(49年7月策定)、神戸市の大気管理計画及び水質管理計画(49年5月策定)と並んで、地域における公害防止の総合的、計画的な実施の先がけとしての役割を果たした。
その後、52年3月には兵庫県が県の総合計画に基づく地域整備の環境上の指針となる計画を策定し、県下を自然的、社会的条件を基に9つの環境区に区分し、それぞれの環境区ごとに汚染物質の環境容量を示している。また、同年7月には川崎市が川崎市環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの技術指針として計画を策定している。
さらに、54年以降になると環境管理計画策定の動きは全国に及ぶようになり、石川県や宮城県で計画が策定され、県の総合計画の目標であるより良い環境づくりの具体化を目指している。これらの計画は、それぞれ地域の自然条件や土地利用の態様に応じた目標環境水準、自然環境を総合的に評価しうる自然環境質指教を設定するなど独自の工夫をこらしたものである。また、三重県では57年12月に中南勢地域環境管理計画を策定している。
このほか、特定の公共用水域の水質保全を目的とする管理計画として、鹿児島湾、愛媛県肱川、静岡県浜名湖、千葉県印旛沼及び手賀沼について各県で策定されている。
イ 地域環境管理の理念
地域環境管理計画は地域の実情やその時々の要請に応じて多様なものであるが、最近においては、多くの地方公共団体が21世紀に向かう長期的な環境政策の基本となる計画として検討してきている。
近年の環境政策を取り巻く状況をみると、依然として土地や水等の環境資源の利用が高密度化し、広域化している。このため、それぞれの利用者間の調整を図ることが重要になっている。また、生活水準の向上などに伴う地域住民の環境に対するニーズの高度化、多様化に配慮し、エネルギーや財政上の制約をも考慮することが重要となってきている。
環境資源の利用の調整に当たあっては、地域の自然的、社会的条件を考慮し、その利用を進めようとする各種の施策や計画について環境保全上の問題点をあらかじめ把握し、早い段階から調整を図っていくことが必要である。地域住民の環境に対するニーズにこたえるためには、地域の環境を総合的にとらえ、その望ましい環境像を明らかにするとともに、創意と工夫による快適な環境づくりの動きを助長し、支援していくことが求められている。エネルギーや財政上の制約に対しては、望ましい環境像の実現に必要な諸施策を総合的に調整し、個々の施策に効率的に資源を配分する経営的な政策体系が求められている。
地域環境管理計画は、このような要請にこたえるものとして、環境の総合的管理という理念に基づき検討が進められている。
ウ 最近の事例
57年12月に策定された大阪府環境総合計画(STEP21)は、大阪府が、庁内プロジェクトチームの作成した計画概案を57年2月に公表し、府民、学識経験者等の意見を反映させる手続を経て策定したものである。旧計画が公害の防止に関する総合的な計画であったのに対し、新計画では環境問題をより幅広くとらえており、21世紀に向けての望ましい環境像を描きつつ、健康で人間性豊かな環境の達成を目指している。計画の構成は第3-3-1図に示すとおりである。
新たな試みとして、環境の多様な側面を総合的に把握し評価するため、大気汚染、静けさ、緑、水辺への近づきやすさで代表させた環境の快適性と、通勤や買物の利便で代表された利便性について環境評価マップを作成している。
次に、58年2月に策定されたかながわ環境プランは、神奈川県の総合計画である「新神奈川計画」の理念の一つである」自然を守り、住みよい環境をつくる」ことを実現していくための環境面からの総合調整計画として策定された。この計画も大阪府と同様に計画の概要を公表し、広く県民の意見を求める手続を経て策定されたものである。本計画は、行政、事業者、県民に対して望ましい環境のための視点、目標及び指針をあらかじめ示すことにより、それぞれの行動の立案や実施の場において自主的に環境へ配慮することを求めるものであり、こうした性格付けの下に、自然環境の保全、都市環境の創造、公害の防止等についての基本方向を明らかにしている。
本計画では、県下を横浜、川崎、県央、湘南等の6地域に区分し、それぞれの地域を自然条件の特性により細区分した上で、自然の仕組に基づいた地域環境づくりの方向を示している。
例えば、県央地域のうち相模原台地地区は、農業生産性が高い土地であり、平担な土地条件や安定した地盤のため市街化しやすい条件を備えている。一方、この地区は見晴しがききやすいため景観保全上注意を必要とするとともに、浅い谷や台地は河川に対して影響を与えやすく、また、台地斜面地ではがけ崩れなどを起こしやすい条件を持っている。このような条件を考慮した上で、環境づくりの重点として?現存する農用地をまとまりのある形で保全、維持し、市街地の連続化を防止すること、?台地斜面地の連続する緑地を保全すること、?低地部の水田や樹林地を保全し、浅い谷における緑地、遊水地を整備すること、?下水道の整備による排水処理を推進することを掲げている。
また、土地利用、都市整備、産業政策等各種計画についてそれぞれ環境資源の利用に当たっての環境配慮指針を示している。
さらに、適切な施策の推進のため、各種環境情報の収集、蓄積、処理を行う環境情報管理システムを段階的に整備・充実することとしている。
エ 環境管理の総合的推進
このように、最近の地域環境管理計画の方向は、公害の防止、自然保護を始めとして、環境汚染の未然防止やより良い環境づくり等を含めた総合的な環境政策の推進を目指したものである。このため関連する部門の行政、事業者、地域住民が共同して、それぞれの活動を総合的、予見的に調整していく手段を模索したものとなっている。
こうした地域環境管理の推進に当たっては、環境庁においても、地方公共団体に提示しうる環境管理の指導理念や環境管理計画の策定手法等の検討を行っているところであるが、今後、国は全国的にみて重要な環境利用の調整、全国的な規模での事業や施策と地域環境管理計画との斉合性、地域間の調和等の問題に取り組んでいく必要がある。また、地域住民の意向に精通した市町村行政の役割も重要であり、都道府県と市町村の緊密な連携が必要である。そのためにも、今後の環境政策を総合的かつ計画的に推進していく上で国及び地方公共団体が環境管理計画の策定等地域環境管理の在り方について十分検討を進めていくことが必要である。