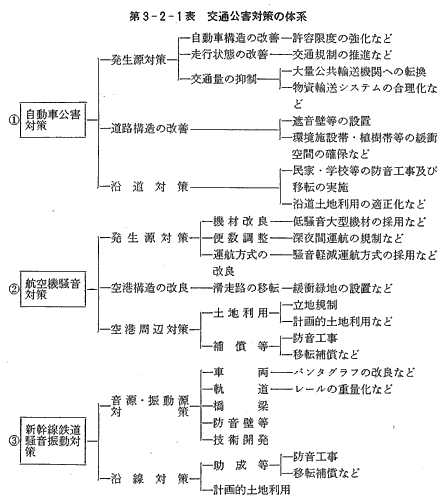
1 多角的な取組
近年、多角的な取組が必要とされる環境問題が増加している。ここでは、交通公害と閉鎖性水域の水質汚濁を例にとり多角的な取組の方向を検討することとする。
(1) 交通公害対策の総合的推進
我が国の交通機関は、戦後飛躍的に発展した反面、各地で公害問題を引き起こしている。このような交通公害を防止するため、これまで自動車等個々の交通機関の改良、交通機関の走行・運航方法の改善、交通施設の構造上の改善、周辺住宅等に対する障害防止対策等の対策が鋭意講じられている(第3-2-1表)。しかしながら、必ずしも十分な成果をみるに至っていないことから、更にこれらの対策の一層の拡充、強化を図るとともに、交通公害問題に多角的に取り組むことにより、総合的な施策を進めていくことが必要である。このため、環境庁では、交通公害の抜本的解決を図るため、55年6月26日に中央公害対策審議会に対し「今後の交通公害対策のあり方について」諮問を行い、57年12月24日には交通公害部会の物流専門委員会から現在、各地で深刻な問題となっているトラック公害問題を解決するため、物流体系のあり方を環境保全の観点から望ましいものに改善することが必要であるという基本的な考え方の下に、その実現のための方策について報告が行われた。また、同じく同部会の土地利用専門委員会から、交通公害の防止のためには、交通施設と周辺土地利用との整合性の確保が必要であるとの基本的考え方の下に、環境保全の観点から望ましい交通施設の構造及びその周辺の土地利用の実現のための方策について報告が行われた。
(2) 閉鎖性水域の汚濁対策
湖沼等の閉鎖性水域においては、富栄養化が急速に対策を要する問題となっている。このため57年12月25日には、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準が告示され、さらに、中央公害対策審議会は58年1月に環境庁長官から「窒素及びリンに係る排水基準の設定について」諮問を受け、湖沼の富栄養化の防止に係る窒素、リンの排水基準の設定について審議を行っている。このほか琵琶湖の富栄養化対策については、既に「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が、また、霞ヶ浦については「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」が制定され、各種の対策が進められている。
海域については、瀬戸内海において「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づくりん及びその化合物に係る削減指導が55年度から既に進められている。伊勢湾においては57年3月に、伊勢湾富栄養化対策連絡会での調整を踏まえ、各県別に、同年4月1日から富栄養化防止対策が行われているところである。
東京湾についても、57年6月に東京湾富栄養化対策連絡会での調整を踏まえ、各都県別に、同年7月1日から富栄養化防止対策が行われているところである。
ところで、水質汚濁の中で大きな割合を占めている生活排水対策は相対的に立ち遅れている。
生活排水対策の基本は下水道整備であるが、普及率は56年度末現在全国平均で31%と低い状況でにあり、多くの地域では、生活排水負荷(BOD)の約7割程度を占める家庭の台所、風呂、洗面所等からの生活雑排水が未処理のまま公共用水域に放流されている。
今後、下水道の整備は、大都市からその周辺部、あるいは中小都市の人口密度の相対的に低い地域へと拡大していくと考えられるが、現下の財政状況等を勘案すると、その整備にはまだかなりの年数を要すると考えられる状況にあり、今後とも効率的な執行を推進していく必要がある。
このため、今後は、下水道整備の推進を図りつつ、下水道の整備を勘案し、地域の特性に応じ、地域し尿処理施設、農業集落排水施設、合併浄化槽、生活雑排水単独処理施設等の整備等を的確に組み合わせ、生活排水対策を総合的に推進していくことが重要である。
生活排水処理施設のうち小規模なものは、集落単位や住宅単位での対策であり、施設単位にみれば、比較的少ない費用で効果が速やかに現われるとともに、地形上の困難や河川水量の保全についても適切に対応し得るので、その地域特性に応じた有効な活用が期待される。
今後、閉鎖性水域、特に湖沼の汚濁対策のためには、下水道の整備、生活雑排水処理対策等の生活排水対策、工場、事業上の排水対策、蓄・水産業等に係る対策、汚泥のしゅんせつ等の浄化事業及び湖沼の自然環境保全対策等を各湖沼の特性に応じ、総合的、計画的に推進していく必要がある。