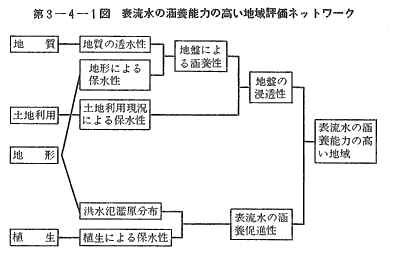
2 環境の総合的管理の推進
国民の環境に対するニーズの多様化に対応して、公害の防除、環境汚染の未然防止を第一義としつつ、積極的に良好な環境を確保し、創造することが求められている。
経済社会活動の展開に当たっては地域の自然的、社会的条件を踏まえて、環境の受容能力の範囲内で環境資源を浪費、枯渇させることなく、すぐれた環境を将来の世代に継承するという環境の持続的利用の観点に立ってこれを進めることが望まれる。このような要請に応えるためには、環境問題に対する幅広い政策指針として、環境管理計画の策定を始め環境管理のための体系を確立することが必要となってくる。
中央公害対策審議会においても、47年の防止計画部会の中間報告「公害の未然防止の徹底の方策について」を始め、54年4月の環境影響評価制度に関する答申、55年12月の「1980年代の環境政策を展開するための検討課題について」等で環境管理の必要性を強調している。環境管理計画は、長期的視点に立って地域環境の望ましいビジョンを明らかにし、その実現のための方策を示すことをねらいとするものであって、土地、水、生物等限りある環境資源を適切に保全、利用するという観点から、公害防除、環境汚染の未然防止、より良い環境づくり等総合的な環境管理のためのさまざまな施策を有機的に結合し、総合的計画的な方策を講じようとするものである。
従来、多くの地方公共団体で環境管理計画についての策定が試みられているが、これらの内容は、地域の実情や課題の相違等によりさまざまである。
48年に策定された大阪府環境管理計画は、地域ごとに、大気、水質についての環境容量を設定し、削減負荷量を明らかにする等公害防止のための総合的計画として位置づけられている。また、兵庫県環境管理計画(52年策定)、石川県環境管理基本計画(54年策定)、宮城県環境管理計画(55年策定)等は県の長期総合計画の環境編として位置づけられており、大気や水質等に関する環境容量を設定するとともに、緑の質指数等、自然環境保全上の指針として機能させようとするものである。更に、川崎市環境管理計画(52年策定)は、「川崎市環境影響評価条例」に基づき環境影響評価を実施するための技術指針として評価項目、標準的技法及び環境保全水準を定めたものである。
そのほか、環境情報の体系的整備を図ることによって計画段階において環境保全上の調整機能を働かせようとするもの、大規模事業について環境汚染や発生源のモニタリングを重視したもの等も検討されている。同時に土地利用に着目して、地域の自然条件や土地利用現況等から環境利用適性を明らかにするため、地域環境特性の解析、評価手法に関する検討も進んできている。
このように、地方公共団体における環境管理計画の内容はさまざまであるが、国においては、地方公共団体に提示しうる環境管理の指導理念や環境管理計画の策定手法等についての検討とともに全国的な規模での事業、施策と地域環境管理計画との斉合性、地域間の調和を図る等の配慮をしていくことが必要である。
次に環境管理計画の策定手法について、地方公共団体の例を参考としてみてみる。環境管理計画は地域環境の望ましいビジョンに基づく具体的な目標、環境利用が適正に行われるための指針及び目標達成のための施策から構成される。
地域環境の望ましいビジョンを明らかにするためには、地域環境特性の把握が重要であり、このため環境利用適性評価の手法が検討されている。すなわち、地域の自然条件に基づく生態学的手法による利用適性評価として、地形、地質、水文等自然条件に関する基本情報をもとに各種の自然作用の性質を地図に表示することにより、環境資源の利用に際しての環境保全上の制約条件等を明らかにしようとするものであり、既に多くの地方公共団体でその検討が行われている。第3-4-1図は、地質、水文等の基本図から、雨水の流出性、地盤の浸透性等の自然作用の評価図を作成し、これを重ね合わせて「表流水のかん養能力の高い地域」の評価図を作成することを目的としたネットワークの一例である。このような利用適性評価の手法については評価項目の取上げ方、自然作用の相対評価方法等、なお検討すべき課題は多いが、地域環境特性の把握による環境状況の診断のためにはもとより、環境管理を進めていくうえでの有効な指針として機能することが期待されている。
また、地域環境特性把握のための定量的手法として、従来の公害防止に係る総量規制手法を応用して、大気・水質に係る予測モデルを作成し、仮想煙源(又は汚濁源)を想定して汚染予測を行い、目標水準に関する寄与度の大小から、環境利用可能性を評価する手法も検討されている。第3-4-2図は、三重県の一部地域について水質(BOD)に係る地域環境特性の評価が試みられたものである。
この図は、流域範囲の区分別に水質保全上の制約性を評価しようとしたものであり、目標水準(環境基準)との対比において汚濁の寄与度が大きく、水質保全上からくる制約が大きい区域ほど評価ランクの小さい数字で表わしている。
環境管理の目標は環境についての明確なビジョンに基づくものであり、また具体的なものである必要がある。その際、環境基準等従来の公害対策の目標については、引続き環境の安全管理の具体的目標として位置づけられるべきであるが、これらに加えて兵庫県、石川県等では緑の質指数等の自然環境保全に関する目標水準を設定する試みが行われている。また、宮城県環境管理計画においても、植物、動物及び景観を総合化した自然環境質指数の考え方に基づき、意識調査による住民の緑に対する満足度を考慮のうえ、地域別に自然環境保全水準としてのグリーン・ミニマムを設定している。更に、大阪府では48年に策定された環境管理計画に続く新しい計画の検討の中で、公害の防止を始めとする生活環境の保全、自然環境の保全及び歴史的文化的環境の保全に関する目標等を示すほか、人間性豊かな環境の創造を目指して緑と水のふれあいの場の創造、歴史的文化的雰囲気の醸成及び魅力ある都市空間の形成を計画の基本的方向として掲げている。
環境管理の指針は、計画の目標を具体化し、環境への配慮の内容を明らかにするため、地域の特性に応じて環境利用に際しての条件や地域環境の保全又は整備の方針を具体的に提示するものであり、前述した環境利用適性評価の手法について検討が進んでいる。
環境管理の指針に沿って目標を達成するためには、規制、誘導事業等各分野にわたる各種施策を有機的に結びつけて効果的に実施することが必要である。規制の分野では、目標達成のための計画的な汚染物質削減のための施策のほか、目標を達成した地域においてこれを維持、管理していくための有効な方式の検討がなされており、また誘導の分野では、各種の政策決定段階で予め環境上の配慮を組込むための方策の検討が進められている。更に、自動車交通公害対策として経済的誘導手段の検討がなされている例もみられる。
事業の分野では、従来の公害防止事業や公園整備、レクリエーション施設整備事業などを積極的な環境創造という見地から推進することも必要であろう。このような環境づくりの例として、東京都では、清流を回復し、維持用水を確保するため、野火止用水等の用水路や中小河川に下水処理水を導入する事業や「武蔵野の森」復活のため、武蔵野台地に広がる緑地・公園を結び文化・スポーツ・レクリエーション施設を配置する計画など、豊かな水と緑に囲まれたうるおいのある環境づくりのための各種の施策が展開されつつある。
このように環境管理の考え方は、大気、水、土壌、生物や歴史的文化的環境資源を保全し、賢明な環境利用を進めるという基本的視点に立つものであるが、更に進んで近年国民のニーズが高まっている快適環境づくりを国民全体に浸透させ、展開していくためにも有効な方策となりうるものである。