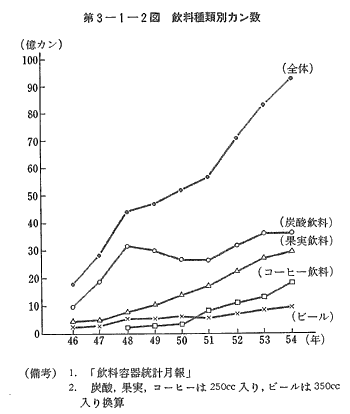
6 空きカン対策
カンは、?軽くて輸送や持ち運びに便利、?衝撃に強く、こわれにくい、?保管にスペースをとらない等、生産、流通、消費、それぞれの段階について、取扱いが容易であるため近年飲料カンを中心にその使用量が著しく増加している。45年には飲料カン全体で約8億カン程度であったが、54年には約92億カンと10年間で10倍を超す伸びとなっている(第3-1-2図)。
しかし、「近くにゴミ箱がなかったから」、「自動車に乗っていて始末に困ったから」等の理由で空きカンの投捨てが多く、各地で空きカンが散乱し、地域の環境美化の観点からも問題が生じている。
特に自然公園や、名所旧跡などでは観光客の投捨て等による空きカンの散乱のため著しく景観が損なわれている。京都市の試算によると、54年度1年間に京都市で販売又は持込まれたと推定されるカン入り飲料1億3,500万カンのうち、市の清掃工場へ回収されなかった空きカンの数は4,400万カン(この中には、スクラップ業者等市の清掃工場以外への回収量、市外への持出し等が含まれる。)と推定される。
環境庁が55年に実施した「空きカンに関する地方公共団体アンケート調査」によると、全国3,278市町村のうち空きカンの散乱が問題となっている場所があると答えた市町村が1,891団体(57.7%)あり、散乱する場所は、6,814か所であった。
散乱場所で最も多いのが「一般道路又はその周辺」で2,330か所(34.2%)、次いで「市街地の広場及び公園」の654か所(9.6%)であり、以下「海岸や湖沼の周辺」561か所(8.2%)、「大きな川の川原」517か所(7.6%)、「海水浴場」513か所(7.5%)等となっている。
空きカン問題は、?投捨てをどのように防止するか、?投捨てられた空きカンをどう回収するかが基本的な問題である。このような観点を踏まえて対策を推進する必要がある。
このため、地方公共団体では、条例の制定や、清掃事業の推進、広報活動等空きカン対策のための施策が活発化し、例えば収集かごの設置、投捨て禁止の呼びかけが行われている。また、民間においても活動が行われており、例えば、(財)クリーン・ジャパン・センターは空きカンの回収、再資源化等の事業を行っている。
なお、55年の調査で「空きカンの散乱する場所がある」と回答した市町村について、56年に追跡調査を行ったが、それによると、全体の42.9%に当たる2,909か所で散乱状態の改善がみられるとともに、前年より散乱箇所数は約6%の減少をみた。
また、ゴミの減量に役立ち、省資源・省エネルギーともなる空きカンの再資源化を行う市町村は990市町村(52.6%)となっている。
今後、空きカン問題の解決を図っていくためには、国、地方公共団体、消費者、関係業界、当該散乱場所の管理者、美化清掃活動へ参加するボランティア、住民等多数の空きカン問題の関係者が協力し合って問題の解決に取組む必要がある。
政府においては、関係省庁が、お互いに連絡調整を図りつつ、その対策を検討し、推進するため56年1月関係11省庁(総理府、警察庁、環境庁、国税庁、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省、自治省)からなる「空きカン問題連絡協議会」を設置した。56年4月には「空きカン散乱防止のための普及啓発活動の申し合せ」を行い、以後、統一美化マークの缶体への印刷等投捨て防止についてのPR、キャンペーンを夏期を中心として強化した。
なお、57年春の全国交通安全運動期間中においては、走行中における車両等からの空きカン等の投捨て防止の普及啓発活動を行うこととされた。また、日常の警察活動を通じて、路上等への不法な空きカンの投捨てについて警告、指導等が行われている。
以上、本節では、近年の産業構造の変化や都市化の進展の中で、環境基準の達成状況の悪い汚染因子や最近深刻化している問題を中心にその対策の方向をみてきた。従来から、個別発生源に対する排出規制や総量規制が講じられてきたが、これらの問題については、汚染発生源がますます多様化し、発生形態も地域ごとに異なってきていることが多く、また、石炭利用のように近年急速に拡大してきた結果生じているものもあり、その対策が十分ではなかったり、整合性を欠く面もみられる状態である。
したがって、今後、一層環境保全技術の向上に努めるとともに汚染発生源や発生形態の変化に即応し、それぞれの問題の自然的、経済的特性に応じつつ、必要な場合には法制定も含め、より総合的に対策を講じていくことが重要である。
同時に、本節でみてきたように最近公害現象が経済活動、社会活動、生活様式の変化の中で、複雑化していることを考えれば、国、地方公共団体、企業、消費者すべての者が環境資源を利用する立場にあることを考慮し、みずからそれに対応するための配慮を十分に行っていくことが肝要である。特に、国、地方公共団体の公共事業の実施に当たっては、環境をめぐる諸条件の変化を踏まえその執行に当たっていくことが必要である。