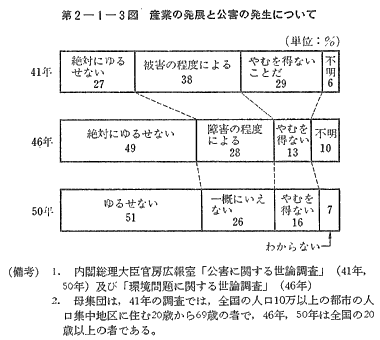
3 環境に対する意識の動向
環境汚染、自然改変の進行に伴い、環境問題に対する社会的関心は高まっていった。内閣総理大臣官房広報室では公害問題に関する世論調査を実施している。産業の発展と公害の発生について、41年には「被害の程度による」が全体の38%、「産業の発展のためには公害の発生は適当な補償さえあればある程度やむを得ない」が29%、「産業の発展のためといっても公害の発生は絶対にゆるせない」が27%であったが、46年には「絶対にゆるせない」が49%と大幅に増え、「障害の程度による」(28%)、「やむを得ない」(13%)の合計を上回ることとなった。この傾向は、50年の調査でも、「ゆるせない」が過半数の51%となった(第2-1-3図)。
次に公害による被害についての世論の動向をみると46年と48年には、「最近5年間で公害対策基本法で定める典型7公害について被害を受けた」がそれぞれ36%、45%であった。次いで50年、54年、56年には「この2〜3年間で被害を受けた」がそれぞれ35%、31%、33%であった。質問の内容が多少変化しているが、全体としては増減をくり返しつつも、「被害を受けた」は減少し、50年代は横ばいで推移しているといえよう。
被害を受けた者について公害の種類でみると、大気汚染の割合は48年から減少を続けており、56年には9%となっている。水質汚濁は50年以降ほぼ10%と横ばいで推移している。一方、最も多い騒音は56年には46%であり、また、騒音を始めとする振動、悪臭などのいわゆる感覚公害の割合は48年以降次第に増加してきている(第2-1-4図)。
公害による被害の発生源については、「交通機関(自動車、電車、航空機など)」が最も多く、50年には49%、54年、56年では44%と高い水準を示している。一方、「事業活動(事務所、工場、工事現場など)」は46年、48年には30%、32%、50年、54年では24%、28%となっている。56年には産業活動として事業活動とともに、「養豚場・養鶏場・牧畜など」及び「商店・飲食店」を加え調査しているが、「事業活動」は20%であり、「養豚場・養鶏場・牧畜など」、「商店・飲食店」はそれぞれ5%と3%である。また、「下水、ゴミなどの都市生活」、「近隣の私生活」は全般的には低いが、次第にその比重を高め、56年にはそれぞれ14%、8%となっており、交通機関や事業活動とともに、これらに起因する公害に対する意識が高まってきている(第2-1-5図)。
また、経済成長率の低下やエネルギー需給構造の変化の中で、環境保全をいかに図っていくかが今後の大きな課題となっている。まず環境保全と経済成長の関係については、「環境保全と経済成長は両立可能」が41%、「環境保全を優先」が28%であり、「経済成長を優先」は11%にとどまっている。
次に、環境保全とエネルギーの開発・導入との関係については、「両立が必要」が72%、「環境保全を優先」が15%で、エネルギーの開発・導入に当たっての環境への配慮が求められているといえる。
このように、今後、経済成長やエネルギーの開発・導入に当たっては、常に環境保全への努力を続けていくことを国民は期待していることが示されている。
次に、これからの環境行政に対するニーズをみることとする。まず公害の先行きについては、第2-1-6図に示されるように「将来公害がますますひどくなる」という意見が増加傾向を示している。このような中で政府に特に取組んでほしい国全体としての問題(複数回答)は「大気汚染」が最も多く、特に大都市になるほどその比率が高くなっている。次いで「水質汚濁防止」、「自然保護」となっている。また、国内の問題だけではなく地球的規模の環境問題に対する意識も高い(第2-1-7図)。
更に、環境へのニーズも変化してきている。所得の上昇や定住傾向の高まりを背景に次第に環境の質を重視し、快適な環境を求めるようになってきている。環境庁が55年に全国の自治体を対象として実施した「地域における快適な環境づくり事例調査」では、全国で約1,500の事例があがっている。それらの事例は地域的広がりとともに多様な活動内容をもっており、今や身の回りの生活環境を快適なものにしようという動きは、全国的に広がっている。
56年の「公害に関する世論調査」でみるとこのような快適な環境づくりを進める上で重要な要素(複数回答)として「豊かな緑」が42%と最も多く、次いで「さわやかな空気」40%、「のびのびと歩ける道や広場」39%、「静けさ」21%となっている。「さわやかな空気」については都市規模が大きくなるほど重要だと考えられており、東京都区部・政令指定都市では47%、その他の市では40%、町村では36%となっている。
今後は、このような国民の環境に対するニーズを的確に踏まえて環境対策を推進していく必要がある。