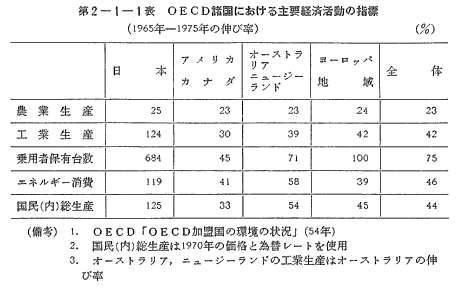
1 経済社会活動の拡大
人間のさまざまな活動は、環境資源の利用の上に成り立っている。人間活動は長きにわたり環境による制約を受け続けてきたが、環境をコントロールするための努力の積み重ねの結果、ようやく数世紀前にこの制約から解放されるようになった。
以後、技術の進歩などにより生産が増加し、今や先進諸国においては、人間の生存にとっての基礎的ニーズが満たされるだけでなく、これを上回る生活水準が可能となった。しかし、人間活動が環境により制約される度合が小さくなってからの生産活動の拡大は、環境に大きな影響を及ぼす結果をもたらした。
環境にはそれ自体を安定に保つ能力があるが、そのような機能には限界がある。このことが十分に認識されないまま人間活動が拡大・変化し、その結果不要となった汚染物が環境の受容能力の限界を超えて大量に放出されると、環境汚染が引起こされる。その結果、動植物への影響はもとより、人の生命、健康にまで影響を与えることになる。
以上のように人間活動に対する環境の制約を克服し、より豊かな生活を求めるための人間活動が、逆に環境問題という人間活動にとっての新たな制約を生み出すに至った。
我が国経済は、昭和30年代初めには、「もはや戦後ではない」といわれたように、ほぼ戦前の水準を回復した。それ以降、48年の石油危機に至るまで、ほぼ一貫して世界に類のない高度成長を続けた。例えば、35年から44年の間(1960年代)の経済成長率は年平均約11%と非常に高いものであった。しかし、この高度経済成長の過程で環境問題が深刻化し、また全国的な広がりをみせた。ここではこの時代の経済社会活動を環境問題との関係でみていくこととする。
我が国の国民総生産は35年から44年の間に約2.5倍になり、鉱工業生産は約3.2倍、農業生産は約1.3倍になった。その間、エネルギー消費は約2.7倍となった。また、乗用車保有台数は約15.3倍と著しい伸びを示した。
我が国の生産活動、消費活動を国際比較したのが第2-1-1表である。農業生産はOECD(経済協力開発機構)の他の諸国と比べほぼ同様の伸びであるが、工業生産、エネルギー消費、国民総生産については、いずれもOECD平均の2.6〜3.0倍の伸びを示している。特に、乗用車保有台数については、ヨーロッパ地域の約7倍、アメリカ・カナダの約15倍の増加率となっている。
また、35年から44年の間に我が国の1人当たり国民所得は、約2.2倍になった。消費生活の充実も顕著で、前述したように乗用車の保有台数が急増したほか、電気洗濯機や電気冷蔵庫などの耐久消費財も広範に普及し、45年には、それぞれ91%、89%もの世帯が所有するに至った。
当時の我が国の経済社会活動を可住地面積(国土全体から森林、不用地、水面を除いた部分)当たりでみると、国民総生産、乗用車保有台数、エネルギー消費は、45年時点で、それぞれアメリカのおよそ17倍、6倍、9倍となっており、我が国が極めて高密度な経済社会を形成していることを示している。このような高密度化の過程で、環境汚染及び自然改変が進行し、人の生命、健康にまで被害が生じるに至った例も多くみられた。
2次にわたる石油危機を契機に経済成長率は低下してきたが、依然約4%程度の成長を維持しており、現在、世界の約0.3%の国土で世界の国民総生産の約10%にのぼる生産活動が展開されている。これを可住地面積当たりの国民総生産でみると54年時点でアメリカの約21倍、乗用車保有台数、エネルギー消費は、それぞれ52年、55年時点で約10倍となっており、今後、環境への十分な配慮が必要となっている。