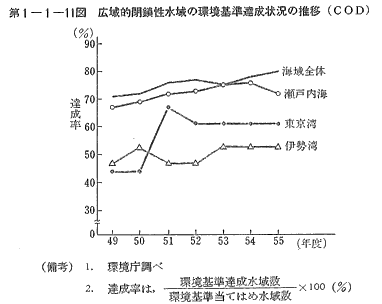
4 閉鎖性水域の状況
近年における我が国の公共用水域の水質汚濁の状況は、総体的には改善の傾向にあるものの未だ環境基準を達していない水域も多く残されている。特に水の交換が悪く汚濁物質が蓄積しやすい湖沼、内海、内湾等の閉鎖性水域では、依然として環境基準の達成状況が悪く、中でも後背地に大きな汚濁源を有する水域では汚濁負荷が大きいため、水質保全のための条件は厳しい。
湖沼について環境基準の達成状況をCODでみると、全体としては41.6%(54年41.8%)と、海域(COD)や河川(BOD)に比べ著しく低く、琵琶湖(滋賀県)、霞ヶ浦(茨城県)、宍道湖(島根県)など代表的な湖沼において未達成となっている。また、環境基準未達成湖沼の中には、手賀沼(千葉県)を始めとして環境基準を数倍以上も超えるような著しい汚濁状態にある湖沼もみられる。しかも周辺における開発の進行に伴って、これらの湖沼の水質汚濁が進行してきている。
海域について、広域閉鎖性水域における55年度の環境基準達成率をCODでみると、東京湾61%(54年度61%)、伊勢湾53%(同53%)、瀬戸内海72%(同76%)と横ばい又は低下しており、水質の改善傾向がみられない(第1-1-11図)。これらの3水域については、CODについて水質総量規制が導入されている。
更に、近年、湖沼や内海、内湾などの閉鎖性水域においては、生活排水や工場排水などに含まれる大量の窒素、リンなどの栄養塩類の流入により、プランクトンや藻類などの水生生物が増殖繁茂し、いわゆる富栄養化が進行している。このため、湖沼では水道原水の着臭や透明度の低下などがみられ、また、瀬戸内海、伊勢湾などの内海、内湾で、赤潮の発生などによって漁業被害や海水浴の利用障害、悪臭の発生、海辺の汚染、底層の貧酸素化など広く生活環境への被害が生じている。なお、瀬戸内海における赤潮の発生状況をみると、53年165件(うち被害を伴う件数15件)、54年216件(同17件)、55年212件(同12件)、56年198件(同8件)と依然としてかなり多い現状である。湖沼についても淡水赤潮やアオコの発生がみられるものも少なくない。
閉鎖性水域においては、一たび汚濁が進行すると水質の改善を図ることは容易なことではなく、自然の浄化能力に期待するだけでは将来的にも改善の見込みは薄いと考えられ、新たな施策を含め諸施策を総合的に講じることが必要となった。