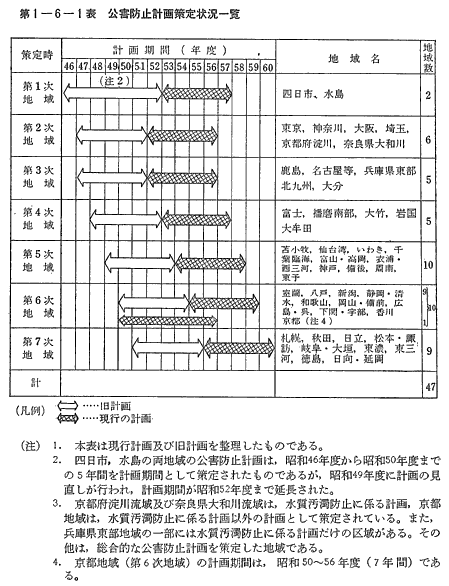
1 公害防止計画の策定状況
(1) 全国における策定状況
公害防止計画は、「公害対策基本法」第19条に基づいて、現に公害が著しいか、または人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域について策定される計画であり、第1-6-1表に示すとおり、昭和45年度に承認された第1次地域以降、51年度に承認された第7次地域までに順次策定され、計画の統廃合、見直し等を経て、現在、第1-6-2図に示すとおり全国47地域について策定されているところである。これらの計画の策定により、全国の主要な工業都市及び大都市地域が公害防止計画策定地域となっており(対全国比、面積で9%、人口で54%、製造品出荷額等で66%)、これらの地域における公害の防止に関する施策の推進が図られているところである。
(2) 第6次地域及び第7次地域公害防止計画の策定指示及び承認
54年度で計画期間が終了することとなっていた第6次地域(室蘭地域、八戸地域、新潟地域、静岡・清水地域、和歌山地域、岡山・備前地域、広島・呉地域、下関・宇部地域、香川地域)及び55年度で計画期間が終了することとなっていた第7次地域(札幌地域、秋田地域、日立地域、松本・諏訪地域、岐阜・大垣地域、東濃地域、東三河地域、徳島地域、日向・延岡地域)については、なお新たな公害防止計画策定の必要性が認められたためそれぞれ55年3月18日、55年9月9日に内閣総理大臣から関係道県知事に対して、基本方針を示して公害防止計画の策定が指示された。
関係道県においては、それぞれの地域に係る基本方針に基づいて公害防止計画の策定が進められ、「公害対策基本法」に定める手続に従い、第6次、第7次地域とも公害対策会議の議(56年3月20日)を経て同日付けを持ってそれぞれの公害防止計画について内閣総理大臣の承認が行われた。
これら18地域の概況は第1-6-3表に示すとおりであり、これらの地域の公害防止計画の内容はおおむね次のとおりである。
ア 地域の範囲
これら18地域の範囲は、それぞれ第1-6-4表に示すとおりである。
イ 計画の目標
計画の目標は第1-6-5表に示すとおりであり、各種防止施策の推進により、目標が全体として、第6次地域にあっては59年度を目途に、また第7次地域にあっては60年度を目途に、達成されるよう努めるものとしている。
ウ 計画の期間
計画の実施期間は、第6次地域にあっては55年度から59年度までの5年間、第7次地域にあっては56年度から60年度までの5年間としている。
エ 公害の防止に関する施策
事業者は、大気汚染、水質汚濁等の防止のための措置を講ずることとしており、また、地方公共団体等は、発生源等に対する各種規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化、中小企業対策等の施策を講ずるとともに、下水道の整備、緩衝緑地等の設置、廃棄物処理施設の整備、学校等環境整備、河川・港湾しゅんせつ、導水、農用地土壌汚染対策等、監視測定体制の整備等の公害対策事業を実施することとしている(第1-6-6表及び第1-6-7表)。また、公園緑地等の整備、交通対策、地盤沈下関連対策等の公害関連事業も併せて実施することにより、計画の総合的な推進を図ることとしている。
以上の公害の防止に関する施策を実施するために、計画期間内にそれぞれの地域で必要とする経費の見込額は、第1-6-8表のとおりであり、第6次地域にあっては事業者が講ずる措置については、2、078億円、地方公共団体等が講ずる施策については、公害対策事業について7、042億円、公害関連事業について1、459億円、合計10、579億円と見込まれている。また、第7次地域にあっては事業者が講ずる措置については、664億円、地方公共団体等が講ずる施策については、公害対策事業について6、698億円、公害関連事業について3、250億円、合計10、610億円と見込まれている。
(3) 公害防止計画策定地域における環境質の改善状況
公害防止計画策定地域(第1次地域〜第7次地域)における環境質は、この間の公害の防止に関する各種施策の推進により、環境基準の達成状況等から見て、次のような改善状況にある。
? 大気質
二酸化硫黄については、環境基準の長期的評価による達成測定局数の割合(達成測定局数/有効測定局数)を見ると、48年度39%、49年度65%、50年度77%、51年度86%、52年度92%、53年度93%、54年度97%と各年度とも、年々着実な改善が認められている。
一方、二酸化炭素については54年度の測定結果について、環境基準(1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ―ンの内又はそれ以下)との対応状況を見ると、一般環境大気測定局のうち、ゾ―ンの上限を超える高濃度測定局が6%、ゾ―ン内の測定局が32%、ゾ―ンの下限を下回る測定局が62%となっており、全国の一般環境大気測定局のうち、ゾ―ンの上限を超える高濃度測定局の全局が公害防止計画策定地域内にある状況である。
また、浮遊粒子状物質についても、環境基準の長期的評価で見て、達成測定局数の割合が13%と低く、オキシダントについても、注意報発令濃度(1時間値0.12ppm)以上の濃度を観測している測定局が多く、これらについては今後も改善努力が必要である。
? 水質
河川、湖沼及び海域について、BODまたhCODの環境基準達成状況を達成水域数の割合(達成水域数/水域数)で見ると次のとおりである。
まず、河川(BOD)については、48年度35%、49年度44%、50年度51%、51年度47%、52年度48%、53年度50%、54年度55%と48年度当時と比べると改善傾向にある。湖沼(COD)については、48年度10%、49年度10%、50年度9%、51年度15%、52年度19%、53年度13%、54年度31%と達成水域数の割合は全体的に低い傾向にある。また、海域(COD)については、48年度57%、49年度57%、50年度62%、51年度65%、52年度66%、53年度67%、54年度70%と全体的は改善傾向がある。
これら54年度の達成水域数の割合を全国平均と比較すると、いずれも全国平均を下回っており、更に一層の改善努力を要する状況にある。