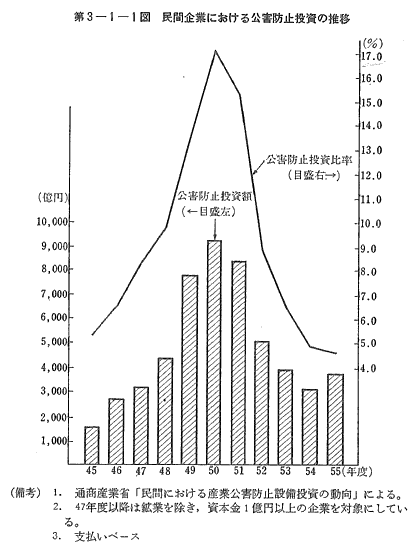
1 排出規制等
既に見たように、経済社会活動の拡大に伴う物質・エネルギ―の流れの拡大は、生産活動、流通活動、消費活動の各過程で各種汚染物質を環境中に排出し、環境汚染を引き起こしてきた。化学工場の排水中に排出された水俣湾を汚染し、魚介類を経由して多くの犠牲者を発生した有機水銀、金属鉱山の排水中から土壌に蓄積し農作物を汚染したカドミウム、石油、石炭等化石燃料の燃焼時に発生する硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんなどの大気汚染、自動車による大気汚染、騒音及び振動、工場、事業場、家庭からの排水による水質汚濁、工場、建設作業等による騒音、振動、さらに各種事業活動による悪臭などがそれである。
このような経済社会活動に伴う環境への負荷を管理し環境汚染を防止するため、公害対策は事業所などの発生源において汚染物質の排出を抑制する排出規制を中心に整備されてきた。特に、我々の生命、健康に重大な影響を与える汚染物質については、発生源における徹底した排出規制が課せられると同時に、環境中への排出の防止が困難なものや環境中での挙動について十分な知見のない化学物質などについては、第2章第3節で見たPCB、DDTなどの例に見られるような使用規制の措置と事前の監視体制がとられている。この排出規制には、工場など事業所に対する固定発生源対策と自動車の排出ガス規制のようにその生産者に対し生産段階で製品の排出性能を規制する移動発生源対策がある。
(1) 固定発生源対策
高度成長期には、重化学工業を中心とした第2次産業の急速な拡大によって、生産活動を通じた汚染物質の排出が増大し、特に、工場など事業所が集中した地域においては公害が発生し、環境汚染が我々の生命、健康を脅かすまでに深刻化した。このため産業公害という言葉が一般化し、産業公害の防止を図ることが、環境政策への緊急の課題となった。我が国の環境政策は産業公害対策から始まったともいえる。
固定発生源対策においては、汚染物質を確定した上で、主要な発生源である施設等を指定し、そこから排出される汚染物質の濃度あるいは量を排出基準によって規制する排出規制が講じられた。これによって、事業者の責任において公害の防止が行われることとなった。現在までに固定発生源に対しては「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」などに基づいて規制対象業種と指定施設の拡大が行われたほか、著しく汚染が進行した地域における大気汚染、水質汚濁については総量規制が導入されるなど厳しい規制が行われてきている。さらに国による排出規制に加え、都道府県、市町村においてはそれらの事業活動の集中の程度などに応じて上乗せ基準の設定、事業者との公害防止協定の締結を行っているところも多い。
このような排出規制の強化・拡充により、事業者による公害防止対策は進展をみており、公害防止の費用の内部化が進んでいると見ることができる。第3-1-1図は大企業における公害防止投資額並びに公害防止投資比率の推移を見たものであるが、45年度には全業種で1、600億円程度であった投資額が、排出規制の強化になどによって50年度にはその約6倍に当たる9、300億円に拡大するとともに、公害防止投資額は、既設生産設備に対する公害防止施設の設置がほぼ一巡したと見られることや生産活動の低滞などによって減少を続けているが、55年度(実績見込)においてはわずかながら増加に転じている。
また、企業における公害防止の進展は公害防止技術の現状に表れており、排煙脱硫装置や排煙脱硝装置といった生産の最終プロセスにおける排出汚染物質の防除技術から、カ性ソ―ダ製造工程の水銀法から隔膜法への転換のような生産工程の変更・転換を伴った技術に至るまで、高度化、多様化している。
このように生産活動に伴う環境汚染は、排出規制による発生源対策の強化によって、全体としては改善の傾向にあると見られるが、環境基準の維持・達成のためには今後ともなお一層の公害防止努力を要する汚染物質も多い。
また、第2章第4節で見たとおり、2次にわたる石油危機により、石油需給はひっ迫し、中長期的にもこの傾向は強まるものと予測され、その結果石炭等の石油代替エネルギ―への転換が必要となっている。
石油代替エネルギ―のうち石炭については適切な対策を講じなければ石油と比較して環境への負荷が大きくなる可能性があり、その開発利用に当たっては環境基準の維持・達成を基本とし環境の保全に十分配慮しなければならない。このため、石炭利用工場の立地等に当たっては環境保全に留意しつつ所要の公害防止措置の実施等が必要である。
石炭灰の処理については、その有効利用の推進に努めるとともに、埋立処分を行うにあたっては、所要の環境保全対策を講ずる等十分な配慮が必要である。
さらに、石油についても今後輸入原油の重質化が進むものと見込まれる。このため、石油燃焼における環境保全対策についても従来以上に努めなければならない。それとともに石油価格の高騰に伴って我が国の産業構造及びエネルギ―消費構造が省エネルギ―型へと転換してきているが、今後とも環境への負荷を軽減するため、この省エネルギ―の動向をより確実なものにして行くことが是非とも必要である。
(2) 移動発生源対策
経済社会活動の拡大に伴う貨物輸送量、旅客輸送量の増大の中で、自動車、航空機、新幹線鉄道など移動発生源による大気汚染、騒音、振動が都市域を中心に大きな問題となっている。我が国では狭あいな国土の中で都市化が急速に進展し、このため都市域においては高密度な環境利用が行われているが、その中で物流、人流の交通輸送需要の増大は特に顕著である。このため全国各地で交通公害が問題とされている。
このような交通公害を防止するため、各々の交通機関別に発生源対策として排出ガス、騒音の許容限度等の設定を行うとともに、特に交通量の集中する地域では利用段階において利用時間帯規制や走行車線の規制等により騒音の低下、交通量の抑制等を図っているほか、騒音に対しては、遮音壁の設置や緩衝緑地を設けることなども行われている。
自動車に関しては、ガソリン、LPGを燃焼とする乗用車について、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物に対する厳しい排出ガス規制が行われており、それぞれ未規制時に比べ90%以上の削減が行われるとともに、バス、トラック等大型車両についても規制の強化が進められている。また、自動車騒音を防止するため自動車騒音の規制が行われている。さらに、航空機による騒音を防止するため、騒音基準に適合しない航空機の飛行を禁止するとともに、離発着の時間の制限などの利用規制が講じられているほか、空港周辺の土地利用規制についても「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づく措置が講じられることなっている。新幹線鉄道については防音壁の設置等の音源対策、振動減対策等の実施に努めている。
しかし、自動車保有台数は毎年200万台程度の割合で増加し、道路網や新幹線鉄道網、空港の整備・充実が求められている今日、地域的に集中する大気汚染、騒音を始めとする交通公害を早急に解決することは困難なことが多い。このため、現在講じられている発生源対策を強化・充実するとともに、交通施設周辺の土地利用及び交通・物流システムの再検討等のより総合的、構造的な対策が求められているといえる。
(3) 日常生活に伴う汚染防止
所得の上昇に伴って都市的な生活様式が定着し、都市人口が増大して都市域が拡大する中で、個々の発生源の規模は小さいが家庭やサ―ビス業など多種多様で広く分散した発生源を持った汚染が都市域に集中して、それが最近における環境汚染の一つの大きな要因となっている。家庭雑廃水、し尿、ごみ、合成洗剤、プラスチック、空缶、近隣騒音など日常生活に近いところで消費段階の物質・エネルギ―の静脈流から排出されるものである。
このような日常の生活に起因する環境汚染に対しては、カラオケ騒音の規制等が一部の地方公共団体で行われているが、個々の発生源としては小さく、しかも広く分散しているとともに、個々人の生活に深く係っているだけに排出規制等を行うことは困難である。このため、静脈流の最下流で廃棄物の集中処理や下水道等の整備が行われているほか、合成洗剤や空缶のように上流の生産段階あるいは購買段階での協力や規制が必要な場合もある。また、サ―ビス業や消費者に対し環境問題に対する理解を求め、高密度な都市生活の中で環境保全のための自律的なル―ルを確立していくことも有効であろう。