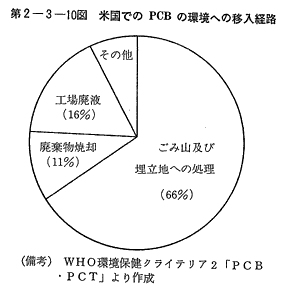
2 化学物質
科学技術、特に化学工業技術の発展により、人間は従来自然界になかったか、あるいはあったとしてもごく微量にしか存在しなかった様々な化学物質を生産することができるようになった。この人間によってつくり出された新たな物質変化の過程で製品として、あるいは副次的な余剰物として生まれる化学物質の数は今や数万点にのぼると考えられている。このような化学物質が原因となった環境問題として例えば水俣病があげられよう。
水俣病は、化学工場におけるアセチレンからアセトアルデヒドを製造する工程(現在、化学工業技術の進展等によりこのような工程は姿を消している。)からの排水中に含まれていたメチル水銀が環境に排出され、それが生物に対する毒性とともに環境中で比較的変化しにくくかつ生物体内に吸収され残留する性状を持っていたため、水俣湾中の魚介類に蓄積し、さらにそれを人々が食物として摂取したために起こった。このような環境中で容易に分解変化せず、かつ水、食物の摂取を通じ生物体内に高密度に濃縮されるような化学物質は人間活動に伴って環境中に排出される物質のなかでも特に注意を必要としている。
(1) PCBの経験
水俣病におけるメチル水銀は、それを製造することが目的ではなく、その環境中への漏出も工場排水という形でのみ行われたため、その環境中への拡散、魚介類への蓄積、濃縮、人による摂取と被害の発生というメカニズムは比較的狭い地域内で行われた。これに対し、その使用を前提として製造される化学物質は、その生産、流通、消費、廃棄の過程で様々な形で広く環境中で拡散する。このような物質のなかで、その毒性、環境中での安定性及び生物への蓄積性から環境汚染物質として早くから注目されたのがDDT、BHCなどの有機塩素系農薬とPCB(ポリ塩化ビフェニ―ル)であった。
PCBは、かつて絶縁油、熱媒体、可塑剤、複写紙等の材料として、トランス、コンデンサ―、冷却・加熱機器、複写紙などに広く使用された。PCBの生産が開始されたのは1930年であり、生産がピ―クに達した1970年前後にはその累積生産量は全世界で100万トンに達したと考えられている(我が国では1971年までに輸入量を含め57、920トン)。これらのPCBは極めて分解しにくいため、生産過程からの漏出、様々なPCB使用製品からの揮発、漏出及びその製品の廃棄に伴い環境中に蓄積されていった。このようなPCBの環境への移入経路としては廃棄物としての環境移入が最も大きいと考えられている(第2-3-10図)。
このようにして環境中に拡散したPCBによる環境汚染の可能性が問題となったのは、1960年代半ばにスウェ―デンにおいてPCBが野生生物の体内に蓄積されていることが発見されてからであり、さらに我が国におけるカネミ油症事件などの直接食物に混入したPCBを大量に摂取した事例によってPCBの毒性が明らかになったこと等により、PCBについての環境中及び人体中の存在についての研究が世界各国で行われることになった。
各国で行われたこれらの調査は、PCBが広く拡散していること及びそれらPCBが水の摂取や食物の摂取を通じ生態系のなかで魚介類に濃縮されていることを示した。さらにPCBが人体にも蓄積していることも各地から報告された。また母乳中からもPCBが検出され大きな社会問題となった。
このような背景のもとに、世界各国でPCBの製造禁止等の措置がとられ、我が国においても次に示すように、46年から47年にかけて次々とPCBの生産、使用、輸入等が中止された。
昭和46年2月 感圧紙(複写紙)へのPCBの使用禁止
46年12月 開放系用途(塗料、インキ等)への出荷禁止
47年3月及び6月 国内生産メ―カ―(2社)生産中止
47年6月 熱交換器について、回収に万全を期することのできるもの以外生産中止
47年8月 コンデンサ―等電気機械器具について、回収に万全を期することの出来るの以外生産中止
47年9月 PCB使用機器に対し原則として輸入禁止
このようは措置とともに、既に使用されているPCBについても、それが環境中に漏出、拡散するのを防ぐため、回収措置がとられたが、広く分散したPCBの回収は困難であった。
PCBは、その環境汚染物質としての危険性が明らかになり生産等が中止になった後もPCBを使用、含有する機械機具、再生紙の廃棄に伴い環境中へ移入していったものもあると考えられる。PCBは現在でもなお、環境中や生物体内から検出されている。第2-3-11表は環境庁が53年度及び54年度に実施した生物指標環境汚染測定調査結果のなかから、日本列島周辺及び特定水域の汚染レベルを調査する目的で採取された魚体内のPCB濃度を示したものである。
(2) 化学物質の安全対策
今日、環境汚染物質のなかでも、環境中で容易に変質せず、生態系内の物質・エネルギ―循環を通じ生物体内に蓄積されるような化学物質の環境中への排出について、極めて厳しい規制が課されている。例えば、水俣病の原因となったメチル水銀などのアルキル水銀については、事後的対応ではあったが水質汚濁防止法に基づき、排水中から検出されてはならないこととされている。この水俣病の事例は、化学物質が環境中に排出されたのち、生態系を通じて食物連鎖によって生物体内に蓄積され、人間を含めた生物全体にもたらされる測り知れない危険が顕在化したものである。水俣病の発生が我々に示した最大の教訓は、このような化学物質の環境中の安全対策において事後的対応には大きな限界があり、事前の対応が不可欠であるということである。
一たん広く環境中に大量の物質が拡散されてから、その毒性が判明しても、その後に取り得る対策は極めて限られたものでしかない。当該物質の生産が中止された後も汚染及び生体内への蓄積が進行する可能性が高く、かつ回収はほとんど不可能といってよいからである。すなわち生態系を通じて生物体内に蓄積されるような化学物質による環境汚染は、環境中の自浄作用を期待できず、不可逆的に進行するので、環境汚染のなかでも特に厳密な未然防止対策がとられる必要がある。
このため、新たに製造または輸入される化学物質について、環境汚染の観点から事前にその安全性を審査するため、48年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化学物質審査規制法」という。)が制定された。同法においては原則としてすべての新規に製造又は輸入される化学物質が、?自然条件下での分解性、?生物体内への蓄積性、?慢性毒性の三つの観点からのチェックを受け、これら三点の性状をすべて有する化学物質については、これを特定化学物質として指定し、その生産、使用等について様々な規制を行うこととしている(第2-3-12表)。
一方「化学物質審査規制法」においては審査の対象外とされている膨大な数にのぼる既存の化学物質についても、分解性、生物濃縮性等の環境中での挙動と生態系への影響及び人の健康への影響に着目した安全性の点検作業が行われている。しかしながら数万点にのぼる既存化学物質のすべてについて詳細な点検を行うことは実態上不可能であり、また環境汚染の観点から着目する必要のない物質も極めて多い。そのため現在は、既存の資料、情報を基礎に生産量や使用形態を加味して当面安全性の点検を行うべき物質を選び出し、リスト・アップされた物質を中心に点検作業が進められている。
このように化学物質の分解性、生物濃縮性等の環境中での挙動に関する知見の集積が図られているが、なお未解明の部分が残されており、さらにこのような安全性の点検を積極的に展開して行く必要がある。
再びPCBの経験をふりかえれば、PCBによる環境汚染の具体的被害が出る前に生産中止等が行われた直接の契機は、スウェ―デンの学者が野生動物の体内に蓄積されている未知の有機塩素系化学物質がPCBであることをつきとめたことにある。また、水俣病においては、環境中に魚介類等にメチル水銀という特異な物質が蓄積していたことが発見できなかったことが早期の対策が講じ得なかった一因となったと考えられる。このことを考えるならば、環境モニタリングを実施することにより化学物質の環境残留性の検討を進め、化学物質の安全性点検を補完して行くことが望まれていると言える。既にこのような環境試料中の残留化学物質を検索するシステムについては、ガスクロマトグラフ―質量分析計による検索の技術開発及び実施が行われはじめているが、今後この試みを充実して行く努力が必要である。さらに、化学物質の人のみならず生態系の動植物及び系の働きに対する影響についても、今後調査研究を行うべきものと考えられる。
また、化学物質のなかには、厳重な管理を前提とした上で生産、使用されているものも多い。これらが不適切に排出・廃棄された場合の危険性については十二分の配慮が必要である。このような化学物質の不適切な廃棄によって生じた被害の例が、近年アメリカのニュ―ヨ―ク州のナイアガラ滝の近くにラブキャナル地区で起こっている。ラブキャナル地区はかつて運河として堀削され、それが途中で放棄された地区である。この地区は運河計画の廃止ののち近在の化学工場が約20年にわたり多種多量の化学物質を含む廃棄物を投棄し、その後覆土された上でそれ以降住宅地となった。その後1970年代に入り、豪雨により当該地区内の地表、住宅地下室に様々な化学物質の漏出が起こるに及んで、この地区における住民の健康調査が行われ、流産率等に異常が生じている可能性が示され、ついには大統領による緊急事態宣言と住民の一時移転にまで事態が進展した。このような化学物質の不適切な投棄に伴う問題は化学物質の排出・廃棄等の管理の重要性を示すものといえよう。
従来、生産活動等においては、生産工程における物質の流れを示すものとしてフロ―シ―トというものが工夫されてきた。しかしながらそのフロ―シ―トとはあくまで一定の製品をつくり出すために必要な物質の流れのみに着目したものであった。しかしながら近年化学工業等においては、公害防止等の視点から生産工程のクロ―ズド・システム化と関連して、生産工程で漏出、蒸発、廃棄される物質の流れを表わすようなフロ―シ―ト(ネガティブ・フロ―シ―ト)の必要性が言われている。化学物質の安全管理においては、このネガティブ・フロ―シ―トの考え方をさらに進め、生産、流通、消費、廃棄そしてその後の環境中の挙動(運命)に至るまでの調査研究を推進していくことが重要であろう。