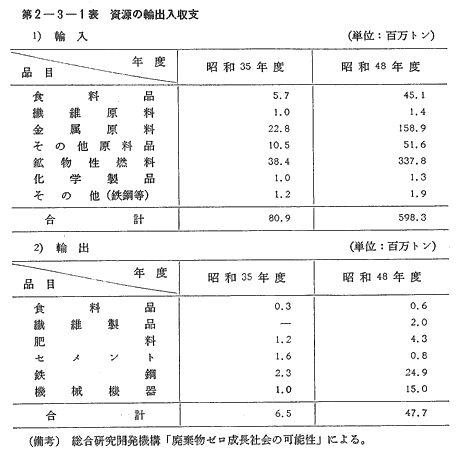
1 廃棄物
(1) 廃棄物の処理
廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に従って、処理されることとされており、事業活動に伴って生ずる燃えがら、汚でい、廃油、廃酸等の産業廃棄物及びその他事業活動に伴って生ずる廃棄物は事業者が自らの責任において適正に処理することが義務づけられている。一方、日常生活から排出されるごみやし尿などからなる。一般廃棄物については、市町村が計画的にその処理を行うこととなっている。
廃棄物は生産、流通、消費活動に伴い必然的に発生するものであり、しかもこれらの活動水準が高まり、そこに、投入される物質・エネルギ―が大きくなるとともに廃棄物も増大傾向にある。第2-3-1表は資源の輸出入重量の推移を示したものであるが、海外からの輸入資源の量的大きさは、海外資源が国内の生産、流通、消費に投入されることによって生み出される人工の物質・エネルギ―の流れの量的大きさを示している。これから輸出量を差引くことによって国内で処理しなければならない海外資源を源泉とする人工の物質・エネルギ―の静脈流の大きさの変化をみることができる。
国内資源の乏しい我が国は、海外資源を大量に輸入することにより、経済成長が可能であったといっても過言ではなく、昭和35年度には約81百万トンの輸入に対し輸出は7百万トンで純計74百万トン、48年度で約600百万トンの輸入に対し、輸出は48百万トンと純計約550百万トンの物質が国内に蓄積され、13年間に海外資源を源泉とする物質の量は実に7倍強になっている。人工の物質・エネルギ―の流れの拡大に伴って、その静脈流から、硫黄酸化合物、窒素酸化合物、二酸化炭素などが大気中に排出され、騒音が発生し、汚濁物質を含む排水も行われる。残りの物質は生産、流通過程で産業廃棄物及び一般廃棄物になるとともに、最終消費財となったものも家庭等を通じての一般廃棄物あるいは事業者の下取り等を通じて産業廃棄物となっている。
このような人工の物質・エネルギーの流れの拡大に伴う膨大な量の廃棄物の発生によって、その処理・処分が大都市を中心に大きな問題となってきている。廃棄物問題の現状を東京都の資料を中心に最終処分場の確保並びに廃棄物処理費用の面から見てみよう。
廃棄物の増大に対してその有効利用を進めるとともに中間処理による焼却、脱水、乾燥を行い減量化の努力が行われているが、それにもかかわらず最終処分場に回る廃棄物は増大しており、最終処分場の確保が極めて大きな問題となってきている。第2-3-2図は東京都における埋立処分場の2年からの推移をみたものである。東京都においては、2年以降37年まで8号地を中心に面積では36万?、埋立ごみ量では370万トンが埋立処分された。次いで32年からは14号地が埋め立てられ、さらに40年からは15号地で埋立が開始されそれぞれ43年、48年に終了したが、埋立面積、処理ごみ量とも急増していることがわかる。48年からは新たに中央防波堤内側処分場での処分が開始されるとともに、52年からは併せて8号地の約9倍の面積に当たる中央防波堤内側処分場での処分が行われており、埋立面積、所理量が大きく増大しているにもかかわらず、60年には早くも満ぱいになる予定である。60年中に、中央防波堤外側の埋立が予定地までに完了すれば、面積にして東京都23区の中で一番小さな台東区の半分以上の面積がごみの埋立でつぶれる計算になる。
廃棄物の問題は、有効利用や減量化のための中間処理を進めても最終処分に回ってくる量の問題が第1に大きな問題である。東京都の場合内陸部に埋立て処分適地がないためこのような巨大な海浜埋立てを必要にしているといえる。このような埋立用地と並んで、廃棄物処理費用の増大も顕著である。
第2-3-3図は東京都における一般廃棄物処理費用の推移と構成をごみについて見たものであるが、ごみについては収集量が45年度の360万トンから52年度には、その約1.4倍に当たる520万トンへと増加するとともに、トン当たりの処理原価も同じ7年間に3.1倍と大幅な上昇を示しており、この間の物価の上昇を考慮してもかなり大幅なものであることがわかる。これは、都市域の拡大と高密度化に伴って廃棄物の発生量が増大するとともに、最終処分場が遠隔化することもあって収集、運搬に多くの人員を要するうえ、中間処理、施設整備あるいは環境保全に多くの経費を要することを示しているといえる。
(2) 廃棄物の現状
? 産業廃棄物
産業廃棄物は全国で50年度約2億4,000万トンと推計されているが、この内訳は鉱さい25.8%、家畜ふん尿17.4%、汚でい15.9%、建設廃材14.4%が主要なものである。産業廃棄物のうち5、100万トン(22%)は有効利用され、1億2、500万トン(53%)は脱水、乾燥、焼却等の中間処理が行われ、4,700万トン(20%)にまで減量化された後、一部はさらに再利用されている。中間処理された後再利用されなかった2,400万トンと中間処理されなかった6、000万トンと合わせて8、400万トンは最終処分に廻されている。これを種類別に見ると、汚でいは中間処理の過程で水分が取り除かれ、最終処分される割合は排出量の10.6%まで軽減量化されるが、一方中間処理のむずかしい建設廃材は排出量の72%が最終処分に廻されているため産業廃棄物の最終処分量に占める割合は36%と大きくなっている。金属くず、紙くず、動物のふん尿等は再利用される割合が高く、廃油、廃酸等は中間処理による減量化が大きい。
これを東京都について詳しく見ると、全国と比べ鉱さい、家畜ふん尿を発生する金属工業、養豚、養鶏が少なく、人口と工業出荷額の全国ウェイトはそれぞれ10.4%、8.6%となっており、産業廃棄物の排出量は汚でいの定義が全国ベ―スのそれと異なるが、52年度において3、300万トンで全国に占める割合は1割強とみられる。その処理・処分では5.5%に当たる180万トンが有効利用され、85%に当たる2、800万トンが中間処理された上で約400万トンが最終処分に回っている。最終処分量の内訳は建設廃材50%、汚でい38%、廃プラスチック2%となっており、建設廃材と汚でいを合わせて9割近くを占めている。
また、東京都における産業廃棄物の排出量を業種別、種類別に見たのが第2-3-4図である。建設工事業から排出する建設廃材と上下水道業から出てくる汚でいが最終処分量の大宗を占めているが、建設工事業からはその他に廃油、金属くず等が排出され、また、製造業では金属くず・紙・木・繊維くず、鉱さい、ガラス・陶磁器くず等多様な廃棄物が多量に排出されている。その他の業種では鉄道・道路運送を除き、百貨店・ス―パ―の廃油、廃プラスチック、電気・ガスの廃アルカリ、洗たく・公衆浴場の廃アルカリのように特定の廃棄物が排出されている。
次にこのような産業廃棄物がどのような過程を経て最終処分されているかを見てみよう。第2-3-5図は産業廃棄物の排出から最終処分までの流れを東京都について示したものである。産業廃棄物の排出量3,300万トンのうち上で見たように180万トン(5.5%)は有効利用され、残る3,100万トンの内2,800万トン(90%)は脱水、乾燥、焼却等の中間処理が行われ、1,300万トン(46%)にまで減量化された後、一部は有効利用されている。中間処理された後有効利用されなかった100万トンと中間処理されなかった約300万トンと合わせて400万トンは最終処分されることになるが、最終処分量の94%は埋立処分されている。
廃棄物の処理の流れを種類別にみたのが第2-3-6図である。汚でいは中間処理の過程で水分が取り除かれ、最終処分される割合は排出量の5.5%にすぎないが、排出量そのものが他の廃棄物に比べ大きいため最終処分量も160万トン(33%)と大きい。一方、建設廃材は汚でいとは異なり中間処理がほとんど行われず、排出量の98%がそのまま最終処分に廻されているため、廃棄物の最終処分量に占める割合(35%)が最も大きくなっている。金属くず、紙・木・繊維くず、鉱さい、動植物残さい等は有効利用される割合が高く、廃油、廃酸、廃アルカリ等は中間処理による減量化が大きい。また、廃プラスチックは30%程度有効利用されているが、最終処分に廻される量の割合(64%)もかなり大きい。
産業廃棄物は量的にも一般廃棄物に比べはるかに大きく、質的にも広範な事業活動から多様な物質が排出されている。しかも有害物質を含有していることが少ないため、適切な処理が行われない場合には大きな問題を引き起こすことは、アメリカのラブキャナル地区事件に限らず過去の多くの例が示すところである。廃棄物処理法に違反する例も多く、54年度における公害事犯検挙5、855件のうち4、778件が廃棄物関係で81.6%を占めている現状にある。
これらは、廃棄物が十分に処理されないまま不法に投棄されることなどによりひき起こされており、このことは、生産段階における公害防止とともに産業廃棄物の処理・処分の重要性を示している。すなわち発生源における環境汚染物質排出規制によって事業所段階での公害防止を通じて排気、排水中から汚染物質が除去されても、これら物質は一部有効利用されるほか中間処理による無害化、減量化が行われているものの最終的に環境中に廃棄される場合が多く、公害防止を完全に進めていくためには、廃棄物の処理・処分段階での環境保全が極めて重要であることを示している。
? ごみ
日常生活に伴って生じるごみは国民所得の増加、都市的生活様式の一般化に伴い増加し、1人年間排出量は48年度には325キログラムとなったが、48年度に発生した石油危機は国民所得の伸びを一時的に停滞させまた、資源の有限性が一般的に認識された結果、省資源が生活の中に定着し、49年度には279キログラムと前年度に比べ約14%の減少を示した。しかしその後国民所得の増加とともに再びごみは増加してきており、52年度では年間1人当たり289キログラム、全国で4、153万トンが排出されている。特に人口や産業の集中した都市においては住民のごみに加え事務所、商店等からのごみが大量に排出されているためその量は大きくなっている。東京都は全国平均年間1人当たり295キログラムに対し、468キログラムとなっている。東京都のごみの量だけでも年間540万トンと20万トンタンカ―で27杯分の量が排出されている。この大量のごみの処理・処分の現状を見てみよう。
外国の主要都市では、我が国の都市と比べ土地利用に余裕があるため、直接埋立の比率が高く、ロンドン92.0%、モスクワ93.0%(いずれも1971年)、ニュ―ヨ―ク83.0%(1973年)となっている。我が国では第2-3-7図にみるように、53年度においては4、053万トン収集されたうち、59%の2、387万トンが焼却処理されて388万トンに減量化され、最終処分量は1、990万トンと収集量の49%となっている。そして、全収集量の39%が埋立処分されている。
特に、大都市部では、埋立処分の比率は低く、川崎市0%、京都市6.2%、北九州市19.8%などであり、大都市部では、最終処分のための埋立適地が限られているため焼却による減量化が進んでいることを示している。
? し尿
第2-3-8図は、53年度におけるし尿処理の流れを示したものである。計画処理区域内人口のうち41%が水洗化され、公共下水道とし尿浄化槽で処理されているが、残る59%はいまだ汲み取りによる非水洗化部分である。し尿浄化槽、し尿処理施設で処理された水は河川等に排出され、残った汚でいは、し尿浄化槽では汲み取られてし尿処理施設に廻されるほか、一部は海洋投棄、農村還元などにより、下水道、し尿処理施設では埋立てなどにより最終処分されている。現在下水道あるいはし尿浄化槽の整備が進められているが、このような処理によって発生する大量の汚でいは、東京都の例で見たように年間2、700万トンの汚でい(20万トンタンカ―135杯分の計算になる。)を生み、このため最終処分場の確保が難しくなってきている。一方、非水洗化人口の分は一部し尿処理施設と下水道投入が行われ、最終的には海洋投棄、農村還元等により処理・処分されており、し尿浄化槽汚でいと合わせその収集のための人件費は大きなものである(第2-3-9図)。