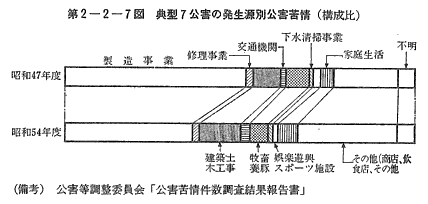
3 環境汚染と多様化と拡散
この10年あまりの懸命の環境保全努力の結果、環境汚染は一時の危機的状況を脱し、生命・健康を脅かすような深刻な汚染については事後的な対応という側面は有しているが、防止体制が整備されてきた。しかし我々は依然として種々の汚染発生源の中で生活をしているのが現状である。
第1章第1節の公害苦情で見たように、公害等調整委員会「公害苦情件数調査」による全国の苦情件数は、深刻な公害を中心に防止が進められてきたこともあって、47年度以降では「典型7公害」全体としてかなりの減少を示したが、51年度以降最近では横ばいの傾向にある。「騒音・振動」については顕著な減少傾向が見られず、また、「廃棄物」などの比重が高い「典型7公害以外の公害」は増加を続けている。このように全国的に見ると、公害の地域的拡散と発生源の多様化が進んでいるといえる。
公害等調査委員会調べによる「公害苦情件数調査」によって、公害問題の所在を詳しくみて見よう。
第1章で見たように、公害苦情の総件数は47年度を100とした指数で、51年度79.8、54年度79.1となっている。「典型7公害」は54年度74.3となっているが、他方「典型7公害以外の公害」は途中年度における増減はあるものの54年度126.5と件数自体が増加しており、公害苦情全体に占める構成比では47年度9.2%から54年度14.6%と上昇している。「典型7公害」について苦情の種類別に構成の変化を見ると、「大気汚染」、「土壌汚染」、「地盤沈下」の構成比は大きな変化はないが、「水質汚濁」は47年度17.8%から54年度14.7%へ、「悪臭」は同じく27.1%から24.6%へと低下を示し、「騒音・振動」は47年度の35.6%から54年度は42.2%へと構成比率を高めている。
このように公害の種類により苦情内容は変化してきているが、発生源別にみても大きな変化が認められる(第2-2-7図)。
公害苦情の発生源は「修理工場」、「牧畜・養豚・養鶏場」、「下水清掃事業」、「娯楽・遊興・スポ―ツ施設」で減少しているが、「建築、土木工事」、「交通機関」、「家庭生活」で増加しており、特に、都市活動と密着した「その他」に含まれる「商店・飲食店」での苦情の増加が目立っており、建設、交通、消費段階で苦情が増加し、発生源が多様化していることを示している。
一方、47年度では公害苦情件数のほぼ半数を占めていた「製造事業所」は規制の強化を通じる公害防止努力もあって47年度を100とした指数で52.5に減少するとともに、構成比も3分の1に低下している。しかし、47年度を100とした指数で食料品は76.2、と改善がはかばかしくなく、また、個別の業種ごとに苦情の種類をみると、ほとんどすべての業種で騒音が高い割合を示しているほか、食料品では「悪臭」、「水質汚濁」、パルプ、紙、ゴム皮製品化学工業、石油石炭製品では、「悪臭」、「大気汚染」、木材・木製品、鉄鋼非鉄金属製品、機械・器具では、「大気汚染」、窯業、土石製品では「大気汚染」、「水質汚濁」が大きな割合を占めている。このことは、業種により区々ではあるが、製造業においても依然として種々の公害をかかえていることを示している。
「典型7公害」に関し、苦情を用途地域別にみると、「都市計画区域内」の苦情はその構成比を高めているのに対し、「都市計画区域以外の地域」では低くなっている。また「都市計画区域内」では「住居地域」が比率を高め「商業及び準工業地域」も若干その比率を高めているが、「工業地域」では低下している。
以上、環境汚染を公害の種類別、発生源別、用途地域別の苦情により見てきたが、全体としては改善傾向にあるものの、近年その改善傾向は足ぶみの状態にあり、発生源が多様化する中で住居地域を中心に都市域に集中化するとともに全国的な拡散の傾向にあるといえる。
このように公害苦情は減少してきているが、公害発生源の多様化と苦情の都市集中を伴った地域的拡散が顕著になってきている環境汚染の背景として、産業化と都市化の進展がある。
産業化は第2次産業と第3次産業の拡大を通じて進んでいくが、これは大量の埋蔵資源を利用して人工の物質・エネルギーの膨大な流れを作り出すことによって、その動脈流ともいえる部分で物的豊かさと利便を生み出している。それと同時に静脈流ともいえる部分で、大気、水、土壌などの環境中へ大量の排出・廃棄物を生み出している。しかも産業化は地域的な集中を伴って進展し、それが人口の都市集中と同時進行していくため、環境汚染、汚濁の地域集中と都市域における環境問題を大きなものにしている。
都市的地域としての特性を端的に表わす人口集中地区の人口及び面積の推移を見ると、35年の全国の人口集中地区は、人口約4、100万人、面積約3、900平方キロメ―トルで、全国のそれぞれ437.%、1.0%であったが、50年には約6、400万人、約8、300平方キロメ―トルで全国のそれぞれ57.0%及び2.2%に増加し、この15年間に人口集中地区人口は1.56倍、人口集中地区面積は2.14倍になっている、またこれを3大都市圏と地方圏に分けて見ると(第2-2-8図)、3大都市圏への人口集中のテンポは極めて高いが、40年以降地方圏での人口集中地区への人口の集中のテンポも急速に上昇していることがわかる。