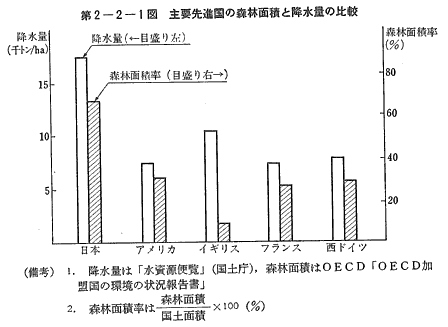
1 高密度な経済社会活動
我が国の環境問題の基本的な背景には、我が国のおかれた狭小な国土条件の下で、急速に高密度な経済社会が形成されてきたという事実がある。
昭和30年代、40年代の我が国の経済成長は目覚ましいものであった。この20年間にGNPは年平均8.8%の成長が見られ、5.4倍に拡大し、鉱工業生産は8.3倍になっている。日本を除くOECD(経済協力開発機構)加盟国23カ国の1970年から1979年にかけてのGNP成長率が3.2%であるのに対し、我が国は5.4%と1.7倍になっている。
このように国際的にみても急速な経済の拡大に伴って、30年代においては主として東京、大阪、名古屋の3大都市圏中心に産業と人口の集中が進み、その後40年代に入ると3大都市圏とともに地方圏においても産業と人口集中が進み、我が国の経済社会活動の拡大は産業と人口の地域的集中と全国的な拡散という2つの動向の中で進展してきている。これによって我が国の都市域を中心とした生産・生活空間の利用は極度に高密度なものとなった。
OECDの統計によると、全国土に対する可住地面積(国土全体から森林、不用地、水面を除いた部分)の比率はイギリス91%、フランス69%、アメリカ52%に対し、日本はわずか22%となっており、可住地の狭小な我が国の国土条件が経済社会の高密度化を加速化してきた大きな要因となっていると考えられる。それと同時に我が国が国土の豊かな自然が高密度化を可能にしてきたという条件も見逃すことができない。
我が国の約38万平方キロメ―トルの国土は、温暖多雨地帯に属しており、年間降水量は世界平均の973ミリメ―トルに対し、1,788ミリメ―トル(いずれも1975年)と極めて高い水準にあり、主要先進国と比べても降水量、森林面積ともに恵まれている(第2-2-1図)。このような自然条件は、我が国の環境を単位面積当たりでいえば、浄化力の高いものとしており、経済社会活動の高密度化を可能にしてきたといえる。
経済社会活動密度を生産、物流、人流を例にとって国際比較してみよう。可住地面積当たりの国民(県民)総生産額によって生産密度を比較すると、日本は、欧米主要国で一番高い西ドイツの約4倍の水準となっている。これをさらに我が国のいくつかの都道府県の生産密度と比較すると、日本で一番生産密度の低い北海道で1平方キロメ―トル当たり3.4百万円となっており西ドイツと同じ水準にある。その他はいずれも西ドイツより高く、東京都は西ドイツ平均の約63倍、大阪府は約33倍に達している(第2-2-2図)。
可住地面積当たりの自動車保有台数から見た交通密度によって物流と人流の密度の国際比較を行うと、日本はアメリカの約14倍で西ドイツと比べても3倍に近いものになっており、自動車を乗用者とバス、トラックに分けると、日本はバス、トラックのウェイトが特に高く、我が国の高い交通密度がバス、トラックによって加速されていることが分かる(第2-2-3図)。
このように先進諸国の比較しても、ずばぬけて高い経済社会活動密度は、我が国の高い水準の生産、流通、消費が生み出す人工の物質・エネルギ―の大きな流れが地域的に過度に集中し環境への大きな負荷を生み、これが高度経済成長の下で深刻な環境汚染と自然改変の激化をもたらしたことを示している。