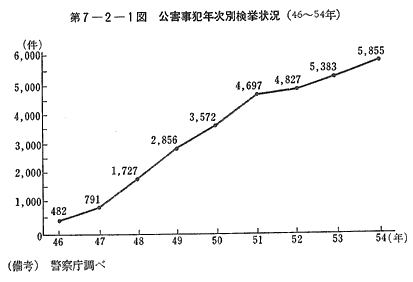
2 取締りの状況
(1) 増加を続ける公害事犯
公害事犯の検挙件数は、第7-2-1図のとおりで、逐年増加を続けており、54年中の総検挙件数は5,855件で、前年に比べ472件(8.7%)の増加となっている。
(2) 態様別及び法令別検挙状況
検挙した公害事犯を態様別にみると第7-2-2表のとおりで、廃棄物が4,778件(81.6%)とその大部分を占め、次いで水質汚濁860件(14.7%)、悪臭139件(2.4%)の順であり、この三態様で全体の98%を占めている。
また、公害事犯の検挙に適用した法令についてみると第7-2-3表のとおりで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が5,103件(87.1%)で大部分を占め、次いで「水質汚濁防止法」312件(5.3%)、「河川法」113件(1.9%)の順となっている。
(3) 検察庁における公害関係法令違反事件の受理・処理状況
最近5年間において全国の検察庁で取扱った公害関係法令違反事件の受理・処理状況は、第7-2-4表のとおりである。54年中の受理人数は、6,605人で前年より306人増加している。
次に、54年中における受理人数を罪名別に前年と対比してみると、第7-2-5表のとおりで廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の4,358人が最も多く、受理総数の66%を占め、以下海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反、水質汚濁防止法違反、港則法違反の順となっている。前年に比較して受理人数が増加した主な罪種は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(286人増)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反(79人増)、港則法違反(48人増)であり、反面、減少したのは、水質汚濁防止法違反(61人減)、下水道法違反(30人減)である。
54年中における公害関係法令違反事件の処理状況は、第7-2-6表のとおりで起訴人員は4,410人、不起訴人員は1,765人、起訴率は71.4%となっている。起訴人員のうち、公判請求されたものは、84人で、前年(78人)よりやや増加しており、罪名別にみると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反が63人で最も多い。略式命令を請求されたのは4,326人で起訴総数の98.1%を占めている。
良好な環境を保全するためには、まずもって適正な行政施策による公害の未然防止が必要であり、刑事司法の関与する分野はおのずから限界があるのみならず、この種事犯の検挙には、種々の法律的な困難があることも否定できないところである。公害関係法規の罰則の適正な活用がこの種事犯の防止のために有効な一つの手段であることにかんがみるとき、今後ともこの種事犯に対する実効ある取締りが期待される。
(4) 公害事犯の傾向
警察の取締りを通じて見られた事犯の特徴的な傾向は次のとおりである。警察としては、今後とも悪質事犯の取締りを強化して違反者の責任を追求するとともに、違反の動機や背景の解明に努め行政措置に反映させることとしている。
? 公害防止に対する事業者の自覚が不十分な事犯が多い
産業廃棄物、汚水の処理経費を節減するために産業廃棄物の不法投棄や無許可業者への処理委託事犯及び汚水処理施設の不使用や未設置、処理薬品の投入懈怠による汚水の排出事犯などが多く、公害防止に対する事業者の自覚が不十分な事犯がみられた。
? 産業廃棄物の不法投棄事犯が増加した。
産業廃棄物の不法投棄事犯は3,829件で前年に比べ442件(13.0%)増加した。これら事犯は、水質汚濁、悪臭等の二次公害を各地で発生させたほか、バキュームカー1台をもった無許可処理業者らがグループをつくり、広域にわたって建設業者等から大量のベントナイト汚でいの処理を受託して下水道、農業用水路、海洋等にこれを不法投棄していた事犯など大規模、組織的な事犯が目立った。
? 犯行を隠ぺいする悪質手段が多い
廃油を不法投棄するに当たり発覚を免れるためドラム缶につめて山中に埋立てる事犯、他人名義の産業廃棄物処理業の許可証をコピーしてこれを改ざんし、排出源事業者を信用させてその処理を受託する事犯、届出以外の隠し排水口の設置や夜間、早朝時を狙っての汚水たれ流し事犯、その他排水量を虚偽に過少の届出をして汚水をたれ流していた事犯など警察取締りや行政監視を免れる悪質な手口の違反が多くみられた。
なお、海上保安庁が実施した海上における公害事犯の取締りの状況については、第3章第4節3、海洋汚染の監視取締り状況で述べたとおりである。