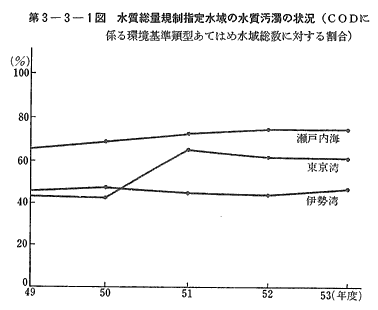
2 水質総量規制の制度化
第84回国会において成立した「瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が昭和54年6月12日に所要の改正法令等とともに施行された。これにより汚濁の著しい広域的な閉鎖性水域を対象に、水質環境基準の確保を図ることを目途とし、当該水域に流入する上流県等内陸部からの負荷、生活排水等を含めた汚濁発生源について、汚濁負荷量の総量を統一的かつ効果的に削減することを目的とした水質総量規制が導入されることとなった。
? 水質総量規制制度の背景
後背地に大きな汚濁源を有する湖沼、内湾等においては、そこに流入する汚濁負荷量が大きいことに加え水の交換が悪く、ひとたび汚濁が進行すると水質の改善を図ることは容易なことではない。
このような広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るためには、その水域の水質に影響を及ぼす汚濁負荷量を全体的に削減することが肝要であるが、水質汚濁防止法による従来の規制方式では、
ア その水域の水質に関係する汚濁発生源の全体(臨海県だけでなく上流県を含めて)を捉えることができないこと。
イ 特定施設を設置する工場や事業場だけを対象としているため、下水道整備などの遅れた現状では、大きな負荷量をもつ生活排水への配慮が十分でないこと。
ウ 濃度規制であるため、特定施設の新増設や稀釈排水による汚濁負荷量の増大に有効に対処できないこと。
等の制度的限界があり、これらの問題を解決し、広域的な閉鎖性水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法の改正により水質総量規制を制度化したものである。
? 水質総量規制の仕組み
ア 指定水域、指定地域、指定項目
水質総量規制は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性水域(湖沼や内湾、内海)で都道府県のいわゆる上乗せ基準を含む排水基準では水質環境基準の確保が困難な水域を対象とする。このような水域(指定水域)として、今回、瀬戸内海環境保全特別措置法によって法律上指定水域となる瀬戸内海のほか、東京湾及び伊勢湾が政令により指定された。
汚濁負荷量削減対策が実施される地域は、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域(指定地域)であり、瀬戸内海については臨海の大阪府等の11府県のほか京都府及び奈良県、東京湾については埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県、伊勢湾については岐阜県、愛知県及び三重県のそれぞれ関係地域が政令により指定された。
削減の対象となる水質汚濁項目(指定項目)としては、海域における有機汚濁の代表的な指標である化学的酸素要求量(COD)が政令により指定された。
イ 総量削減基本方針
指定水域に流入する水の汚濁負荷量を削減するためには削減の目標、目標年度等を定める必要があり、これらについては、内閣総理大臣が公害対策会議の議を経て定める総量削減基本方針において示される。削減の目標は、水質環境基準を確保することを目途とし、指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量が目標年度において人口及び産業の動向、汚水又は廃液の処理技術の水準下水道の整備の見通し等を勘案して実施可能な限度内において削減を図ることとした場合における総量となるように指定地域において公共用水域に排出される水の汚濁負荷量についての削減目標として定められる。総量削減基本方針においては、この削減目標量は、各々の水域について発生源別(生活排水、産業排水、その他の別)及び都道府県別に定められる。
今回の東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海についての化学的酸素要求量に係る総量削減基本方針は、昭和59年度を目標年度(昭和56年度を中間目標年度)として、昭和54年6月22日に公害対策会議の議を経て、第3-3-4表のように定められ、関係都府県知事に通知された。
? 総量削減計画
汚濁負荷量を削減し、削減目標量を達成するため、都道府県知事は総量削減基本方針に基づいて総量削減計画を定めることとなっており、総量削減計画においては、各都道府県内の発生源別の削減目標量、下水道等の整備の目標や総量規制基準設定の基本的方針等削減目標量達成のための方途のほか底質汚泥の除去等の汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項について定める。
これらの事項は国の諸施策とも密接な関連があるため、総量削減計画を定めるときには内閣総理大臣の承認を受けることとなっており、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の関係都府県の化学的酸素要求量に係る総量削減計画は、55年3月18日に公害対策会議の議を経て内閣総理大臣の承認を受け、定められた。
? 汚濁負荷量の削減対策
削減目標量達成のため、下水道等の整備、総量規制基準による規制、その他未規制事業場や小規模生活排水に対する指導等の汚濁負荷量の削減対策が総量削減計画に基づいて実施される。
生活排水対策の中心となる下水道の整備については、現在事業費総額75,000億円の第4次下水道整備五箇年計画(51〜55年度)が実施されており、また総人口普及率を昭和60年度に約55%とすることを目標とする新経社会七箇年計画が54年8月10日に閣議決定されており、総量削減計画においては、これらとの整合性を図り、水質総量規則の対象となる指定地域においては、重点的に整備することになる。
総量規制基準は、指定地域内の特定事業場で日平均排水量が50立方メートル以上のもの(指定地域内事業場)から排出される排出水のうち工程内で汚濁負荷の加わるもの(特定排出水)に適用される当該指定地域内事業場から排出される汚濁負荷量についての許容限度であり、都道府県知事が指定地域内事業場ごとに定める。なお、特定事業場の排水口における排水基準は、指定地域内事業場にあっても従来どおり適用される。
総量規制基準の適用されない工場等からの排水、一般家庭からの雑排水等を含めた小規模の生活排水等からの汚濁負荷については、その汚濁負荷量の総量に占める割合が相当程度あることから、関係都道府県知事は適正な汚水の処理方法等について総量削減計画を達成するため必要な指導等を行うことになる。また、この指導等を的確に実施するため、関係都道府県知事は、特定事業場を設置する者以外の一定のものについて汚水等の処理の方法等に関し報告を求めることができる。
(5) 汚濁負荷量の監視測定
水質総量規制制度を的確に実施していくためには、汚濁負荷量の測定を確実に行うことが不可欠であり、「水質汚濁防止法」においては、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は汚濁負荷量を測定し、その結果を記録することが義務付けられている。(第3-3-5表)
汚濁負荷量の測定に当たっては、事業場の規模、排出水の特性等に適合した測定方法を選定する必要がある。このため環境庁では、54年度において、CODに係る各種自動計測器の選定方法等の検討、簡易COD計の有効性の検討を行った。
また、関係の地方公共団体においては、環境庁の補助金の交付を受けて水質テレメータ監視システムを整備しており、54年度において、三重県及び兵庫県に対し助成を行った。