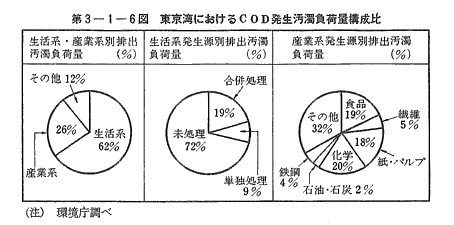
2 要因
最近における公共用水域の水質汚濁の特徴は、有害物質による汚濁が排水規制の強化により、工場からの排水に起因すると考えられるものを中心に改善されつつあること、及び有機物による汚濁の程度が、大都市圏内の中小河川や内湾、内海、湖沼等の閉鎖性水域で依然として高いことである。とりわけ、これらの閉鎖性水域においては、窒素、燐等を含む物質が流入し、藻類その他の水生生物が増殖繁茂することに伴い、その水質が累進的に悪化するという、いわゆる富栄養化の進行がみられる。
こうした汚濁の状況の背景としては、工場、事業場排水については、排水規制の強化等の措置が効果を現わし始めていること、これに反し、家庭排水等については、下水道整備の立ち遅れ、し尿浄化槽の設置及び維持管理等の問題が依然として大きいことが一般に考えられるが、それらに加え、特に内湾、内海、湖沼等については、水の交換が悪く、沈降した汚濁物質による底質の悪化に伴って水質の悪化も生じやすいという、閉鎖性水域特有の物理的条件も関与していることが考えられる。また、内湾や内海等の臨海部には、人口や産業が集中しているという社会経済的条件が加わっていることも重要である。
例えば、東京湾に流入するCOD負荷量(51年度)を発生源別にみてみると、環境庁の推定によれば、生活系負荷が62%、産業系負荷が26%、その他負荷が12%となっており、生活系負荷の占める割合が高い。さらに、それぞれの内訳をみると、生活系負荷では、未処理の雑排水による負荷がその約7割を占め、産業系負荷では、化学、食品、紙・パルプの3業種の排水による負荷がその約6割に達している(第3-1-6図)。
また、水利用上重要な琵琶湖、霞ヶ浦等の湖沼について、富栄養化の要因物質の一つである燐の発生源別負荷量をみてみると、いずれの場合も家庭排水によるリン負荷が比較的大きなウェイトを占めている。そのうち琵琶湖についてみると、滋賀県の調査によれば、家庭排水が48.0%と約半分を占め、その内訳は、し尿が39.0%、合成洗剤が37.9%、雑排水が23.1%となっている。(第3-1-7表)。
以上述べたように、近年、一般的には有機物による汚濁を中心として、生活系排水対策の緊要性が高まっており、特にそれが閉鎖性水域で顕著となっている状況があるが、この他に、面としての広がりをもつ市街地、土地造成現場などの発生源から、通常、降雨に伴って流出するいわゆる「非特定汚染源(nonpointsources)」による汚濁についても、公共用水域の水質保全の観点から、その実態を把握して適切な措置を講ずる必要があること、及びフローとしての汚濁負荷の対策に加え、底泥等のストックとしての汚濁負荷の対策が、特に汚濁の進行した水域で課題となっていることを加えておく必要があろう。
また、富栄養化の進行に伴い、水道におけるろ過障害や異臭味問題、水産における魚種の変化等の種々の障害が生じている。特に赤潮による漁業被害等が問題となっている。赤潮は、日照、降雨、窒素、燐、微量金属等が相互に関連しあって発生するものと考えられるが、その発生機構の解明には一層の努力が必要である。